車を所有していれば、定期的に必ず行わなければならないのが車検です。
「定期的に」とは言っても、新車と中古車では次回車検までの年数が異なります。また、車種の違いによってもさまざまな決まりがあります。
これから車を購入する方や車に乗り始めて間もない方は、車検自体がどういうものか分からないかもしれません。
そこで、この記事では車検について詳しく解説していきます。次回の車検までの年数の違いや、車検にかかる費用などもあわせて説明するので、ぜひ参考にしてください。
そもそも車検とは?
車検とは、対象となる車が道路運送車両法にのっとった保安基準をクリアしているか、チェックすることです。正式には「自動車検査登録制度」といい、国が検査を行います。
検査によって車全体を点検し、異常箇所があれば修理を行います。そうして合格した車に車検証が発行される仕組みになっているため、公道を走る車なら必ず受けなければなりません。
もしも、車検が切れたままの車で公道を走っているのが見つかると、罰金や罰則の対象となります。
車検を定期的に受けることは義務なので、自分が乗っている車の車検日をしっかり把握しておくことが大切です。
車検と定期点検の違い

車には車検の他にも定期点検というものがあります。
「車検」「定期点検」という名称から、どちらも車のチェックをするという漠然としたイメージはできるかもしれません。しかし、どのような違いがあるのか具体的には分からない方もいるでしょう。
定期点検には「12か月点検」と「24か月点検」の2種類があります。ここでは、それぞれの内容や特徴を解説します。
定期点検は受けなくても罰則がありません。そのため、12か月点検の実施率はとても低くなっています。
しかし、定期点検も法律で義務付けられた点検です。罰則がないからと言って受けなくてもいいわけではなく、安全のために受けましょう。
点検項目は全部で26項目あります。具体的にはベルトのゆるみやオイル漏れがないかといった細かな点検です。他にもブレーキの効き具合、タイヤの状態の確認などが行われます。
また、12か月点検を受けておけば、万が一故障した場合でもメーカー保証が受けられるというメリットがあります。
保障内容にもよりますが、故障や不具合による車の修理代は思いがけず高額になりやすいので、メーカー保証が受けられることは節約にもつながるでしょう。
24か月点検は、点検の項目数が56項目あります。12か月点検で行う26項目に加えて車全体やハンドル操作の点検などがプラスされます。
この点検は車検の時に一緒に行われることが多く、意識せずとも点検が済んでいるケースがほとんどです。
ただし、自分で運輸局に車を持ち込んで車検を行うユーザー車検の場合は、24か月点検が行われないため注意しましょう。
故障を未然に防ぎ、長く愛車に乗るためにも24か月点検は必要です。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
車検の有効年数を確認する方法とは?

車検は一般的な乗用車であれば2年おきに行われます。2年前の車検日を正確に覚えているというのは難しいため、次の車検がいつなのか確認する方法を覚えておくと便利です。
次の車検日を確認したい場合は、車検証かフロントの上部に貼られているステッカー(検査標章)を見てください。どちらも車検満了日が記載されています。
検査標章は、外から見ると年月までしか記載されていませんが、車内側から見ると正確な日にちを確認することができます。
しっかり車検満了日を把握して、余裕のある車検スケジュールを立てましょう。
車検はいつから受けられる?

車検は、車検満了日の前であればいつでも受けることができます。
極端に言うと、車検を受けてから1か月後でも可能です。しかし、せっかく2年という有効期限があるのに早めに車検を受けるのは、もったいないです。
そのため、車検満了日から1か月を切ったあたりで検査を行うのがベストだとされています。
あまりに早いと損をし、ギリギリすぎると車検が切れてしまう可能性があるので注意しましょう。
車検の期限延長は可能?
車検の有効期限は決められています。では、その期限は延長することが可能なのでしょうか?
結論から言うと、車検は原則延長することができません。急な入院や海外出張などのやむを得ない事情であっても、認められることはありません。
ただし、これまで救済措置が取られた特殊な事例もあります。
例えば、2019年に台風19号が大きな被害をもたらした時です。被害が大きかった宮城県全域を含め、あわせて12都県で車検延長の救済措置が取られました。
また、最近では新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、2021年3月までに4回車検の延長が行われました。
このように、天災やウイルスなどの被害が大きく、国土交通大臣が認めた場合のみ車検の有効期限の延長がされます。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
車種によって変わる?車検の有効年数の違い
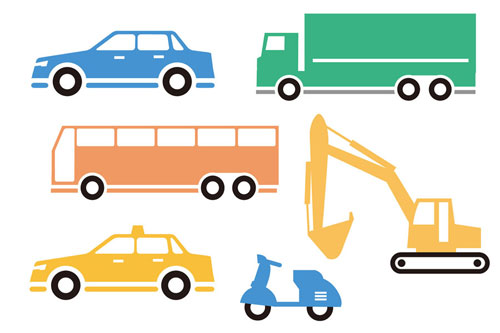
車検は車種によって有効年数が変わります。ここでは、普段の生活に関連がありそうな車種をピックアップして、それぞれの年数を説明します。
これから車を買う方もすでに車を所有している方も、ぜひ参考にしてください。
自家用乗用車とは、大型のセダンやミニバン、SUV、小型であっても排気量2,000ccを超えるエンジンを搭載している、「3ナンバー車」と呼ばれる車です。その他に、3ナンバー車よりも小型、小排気量エンジンを搭載した「5ナンバー車」も含まれます。
自家用乗用軽自動車は、人が乗ることを目的とした軽自動車です。座席よりも荷物を置くスペースが広い軽自動車は、また違う車種に分類されます。
自家用乗用車と自家用乗用軽自動車を新車で購入した場合、最初の車検までの有効年数は3年間です。その後の車検は2年おきとなります。
小型自動二輪車とは、簡単に言うとバイクです。自動二輪車にも排気量の違いによって、さまざまな種類があります。
車検が必要なのは、普通自動二輪車(250cc超)です。新車登録の場合、最初の車検までの有効年数は3年間で、その後は2年おきとなります。
ちなみに同じバイクでも、原付(125cc以下)や軽二輪(125cc超から250cc以下)と呼ばれるものは、車検を受ける必要がありません。しかし、日ごろからこまめな点検を行い、より長く安全に乗れるようにする心がけが大切です。
貨物自動車とは、荷物を積んで運ぶことを目的とした車です。主にトラックやバン型の車が該当します。
貨物自動車の場合は、8トン以上と8トン未満で車検の有効年数が違います。
8トン以上の貨物自動車の有効年数は、新車登録から最初の車検までが1年間です。その後も1年ごとに車検を受けなければなりません。
8トン未満の貨物自動車の有効年数は、新車登録から最初の車検までは2年間です。その後は1年おきに車検を受けます。
どちらも自家用乗用車などとは違い、短めの有効年数なので注意が必要です。
特種車とは、キャンピングカーなどの車です。いわゆる「8ナンバー車」と呼ばれる車で、ベースとなる車体にそれぞれの用途に合わせた特殊な改造を施した仕様になっています。
新車で購入した場合は、最初の車検まで2年の有効年数があります。その後の車検も同じく2年おきです。
ただし、車体の形状などによっては年数が異なる場合があるため、確認が必要となります。
レンタカーは、普通自動車と軽自動車で車検の年数が異なります。
普通自動車をレンタカーにした場合は、新車登録から最初の車検までは2年間です。その後は1年おきに車検を受けます。
軽自動車をレンタカーにした場合は、新車登録から最初の車検までは2年間です。その後も同じく2年おきに車検を受けます。
また、中古車をレンタカーに登録したい場合は、車検の残りの日数によって次の車検までの期間が変わります。
中古車のナンバー登録をした時点で残存期間が1年以上ある場合、車検は登録した日から1年後です。残存期間が1年未満の場合は、もともと残っている車検期間内に行います。
中古車レンタカーの車検は、他の車種の車検とは異なるので確認が必要です。
ここで紹介した車種の他にも、クレーン車やフォークリフトなどの大型特殊自動車、幼児専用車、バス・タクシーなど、さまざまな車があります。さらに、自家用か事業用かによっても車検の有効年数は違います。
車を購入する際は、車検の年数について一度確認してみると良いでしょう。
中古車の車検はいつ?

車を購入する際は、すべて新車というわけではありません。車の購入を考えている方の中には、中古車を購入することを考えている方もいるでしょう。
中古車を購入する際は、前の持ち主が行った車検が残っている場合と、そうでない場合があります。
ここでは、中古の自家用乗用車・自家用乗用軽自動車を購入すると考えた時に、車検ありと車検なしでは年数がどう違うのかを説明します。
車検が残っている中古車の場合は、残存期間にあわせて車検を受けることとなります。その後は2年おきです。
例えば、車検が5か月残っている中古車を購入したとします。この場合は、購入してからまず5か月までの間に車検を受けなければなりません。
タイミングはその中古車によって違うので、しっかり確認してから購入しましょう。
車検がついていない中古車を購入する場合は、購入と同時に車検を受ける必要があります。
中古車販売店が販売した車を納車する際、納車前に点検が行われます。通常は、その点検の時に中古車販売店のほうで車検を行ってくれることがほとんどです。
その後の車検については、2年おきとなります。
車検費用の内訳を見てみよう

車検の費用は何千円でおさまるような額ではなく、ある程度まとまったお金が必要となります。高額ゆえに、その内訳が知りたいという方もいるでしょう。
車検にかかる費用は、以下の3つに分けられます。
- 法定費用
- 車検基本料
- 部品交換代金
ここからは、この3つの費用について詳しく解説します。
法定費用は、「自動車重量税」「自動車損害賠償責任保険料」「検査手数料(印紙代)」の3種類から成り立ちます。
自動車重量税とは、車の総重量ごとに課税されるものです。普通車の場合はおおよそ20,000~40,000円です。
環境に優しい車であればエコカー減税が適用となるので、自動車重量税が減税されます。
自動車損害賠償責任保険料とは、交通事故の被害者を救済するための保険で、必ず加入しなければなりません。「自賠責保険」とも呼ばれています。
検査手数料(印紙代)とは、車検の際に使用する自動車検査票に貼り付ける印紙代のことです。
この3つの合計が法定費用となります。
法定費用は車検をするうえで必要な経費であると同時に、どの業者に頼んでも一律の金額です。
車検基本料は、「24か月法定点検料」「測定検査料」「車検代行手数料」の3種類から成り立ちます。
24か月法定点検とは、上記でも触れた通り法律で定められている定期点検のことです。その点検にかかる費用が、24か月法定点検料と呼ばれます。
測定検査料とは、車が安全に走れるように細かい所まで検査をするための費用です。これは検査自体に費用がかかります。
車検代行手数料とは、所有者の代わりに車検を行うことで発生する費用です。
この3つを合計したのが車検基本料になります。
車検代行手数料に関しては、車検を行う業者によって金額の差があるので注意しましょう。
部品交換代金は、新車登録から年数が経つにつれて高額になる傾向があります。部品を交換するということは、それだけ部品が消耗され、交換を余儀なくされているためです。
新車登録から数えて2回目くらいの車検まではあまり気にならないかもしれませんが、それ以降の車検では徐々に金額が上がることが予想されます。
車検費用が高くなるのはいつから?

車検には、費用が高額になりやすいとされる年数があります。
それは以下の3つです。
- 5年目以降の車
- 11年目のディーゼル車
- 13年目のガソリン車
ここからは、費用が上がる時期を上記の3つに分けて、理由も一緒に解説します。
新車登録から5年目以降は、車検費用が高額になりやすい傾向があります。その理由の一つとして考えられるのが「消耗品の交換」です。
新車の場合は全てが新品なので不良品でない限り部品の交換は必要ありません。
しかし、日々車を使用していれば、雨風にさらされることはもちろん走行距離も増えていくので、自然と部品が消耗していきます。
新車登録から5年目は、一般的に部品の消耗時期と言われています。さらに年月が経過すれば、もっと大きな部品が故障することも考えられるため、交換するのにかかる費用がだんだん高額になっていくでしょう。
また、5年目はメーカー保証が切れるころでもあります。今までは無料で修理できていたのが、メーカー保証が切れると修理にかかった費用は全て自費となります。
さらに、エコカー減税の適用期間が終了するなど、さまざまな要因が考えられます。
ディーゼル車は軽油を燃料として走行します。軽油1リットルあたりの金額は、ガソリンよりも10~30円ほど安いため、燃料代を抑えられることがメリットです。
しかし、ガソリン車より環境への影響が大きいと言われています。年式が古ければ古いほど、その影響は大きい傾向にあります。そのため、ディーゼル車はガソリン車よりも早い11年目から増税されます。
上乗せになる金額は、乗用車であれば元の金額の約15パーセント、トラックやバスであれば約10パーセントです。
ガソリン車の場合は、13年目から増税になります。車検費用に含まれる自動車重量税をはじめ、毎年4月1日時点での所有者にかかる自動車税(軽自動車税)が対象です。
例えば、1,000cc~1,500ccのコンパクトカーは、13年未満であれば30,500円(令和元年9月30日以前に初回新規登録を受けた自家用乗用車は34,500円)だったのに対し、13年を過ぎている車だと約40,000円近くまで跳ね上がります。さらに、18年を過ぎるとまた一段階増税され、元の税額の約1.5倍ほどの金額となります。
その他にも、消耗品の交換箇所が増えてくるでしょう。税金だけではなく、そのような費用がかかることは目に見えています。
徐々に高額になっていく車検費用やメンテナンス代を支払う負担は、とても大きなものです。
乗れるまで乗るということも選択肢の一つですが、比較的新しい車にすることで税金や燃料代が安く済むというメリットがあります。そのようなことも、「車検を受けるのか」「車を変えるのか」どっちにするか考える判断材料にしてみてください。








