車を購入する際に支払う必要があるリサイクル預託金は非課税ですが、廃車の際には消費税が課されることをご存じでしょうか。売却する際はかからない消費税が、廃車する場合は発生するため混乱してしまう方も多いでしょう。
この記事では、リサイクル預託金とは何かを明らかにし、どのような場合に消費税がかかるのかを解説します。
さらに、自動車リサイクル法の概要や成立の背景などにも焦点を当て、多くの方が感じるであろう疑問を解消します。
廃車時はリサイクル預託金に消費税が発生する

車の購入時にリサイクル預託金を支払うことは知っていても、廃車時に消費税が課税されることはあまり知られていないかもしれません。
リサイクル預託金は、廃車の際に発生する廃棄物処理や各種部品のリサイクルのための費用を前払いしているものだと考えてください。
従って、車が廃車になりリサイクルや廃棄物処理が実際に行われる段階で、課税取引として計上されることになるのです。
消費税の計上については、個人だけでなく法人も注意が必要です。税務報告を確実にするためにも、リサイクル預託金と消費税について把握しておきましょう。
自動車リサイクル預託金とは?

自動車リサイクル預託金とは、自動車リサイクル法の規定に基づき、新車を購入する際に支払う必要のある料金です。通常、自動車の購入価格に含まれています。
リサイクル預託金は、廃車の際に車の部品を廃棄したり、リサイクルしたりするために使われる費用であるため、車が廃車になるまでは消費税が課税されません。
ただし、リサイクル預託金の中に含まれる「資金管理料金」は、リサイクル料金の運用・管理に必要なサービス料として位置付けられます。そのため、資金管理料金だけは廃車時ではなく購入時に課税仕入れとして計上されることを押さえておきましょう。
自動車リサイクル預託金は、すべての自動車が対象となるのではなく、その例外となる車種もあります。
対象外となる具体的な車種は、以下になります。
- 被けん引車(動力を持たず、けん引されることで貨物・乗客を輸送する車両)
- 二輪車(原動機付自転車、側車付きのものを含む)
- 大型特殊自動車(ブルドーザー、ショベルカー、クレーンなど)
- 小型特殊自動車(農業用運搬車、フォークリフトなど)
上記以外にも、スノーモービル、公道を走行しないレースカー、自衛隊の装甲車、無人搬送者、ホイール付き高所作業車などは対象外となります。
自動車リサイクル預託金を構成する各種料金について
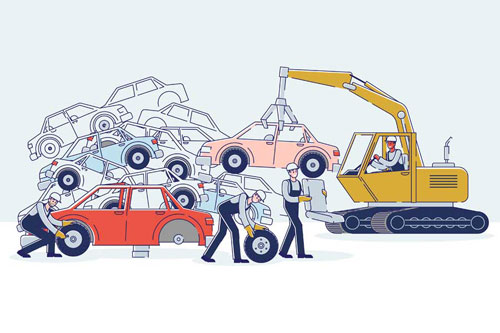
ひとことで「自動車リサイクル預託金」と言っても単一の料金ではなく、目的に応じて細かく項目が分かれています。
ここからは、リサイクル預託金を構成する各種料金について、それぞれ詳しく解説します。
シュレッダー料金は、自動車を解体しリサイクルする過程において、シュレッダーによって分解された車の破片や金属を適切に回収し処理するためにかかる料金です。
自動車の部品に含まれる金属やゴム、ガラス、プラスチックなどを細かく粉砕してリサイクルする、環境に配慮した廃棄物処理のために必要な費用です。
一般的には新車購入の際に支払う料金に含まれますが、車種や排気量、車両の重量によって金額が変動します。
エアバッグ類料金は、自動車に搭載されたエアバッグやプリテンショナー(事故時にシートベルトを締め付けて身体をシートに固定させる装置)など、特定の安全装置のリサイクルに必要なコストです。
エアバッグ類の部品は、エアバッグインフレータやエアバッグモジュールなど、危険物に該当する場合があるため、自動車が解体される際に別個で取り扱われます。
そして、専用の処理施設でリサイクルする必要があり、そのためにエアバッグ類料金が必要なのです。
フロン類料金は、自動車のエアコンなどに使用されているフロンガスを適切に処理するためにかかる料金です。
フロンガスは冷媒としてカーエアコンに利用されていますが、大気中に放出されるとオゾン層の破壊や地球温暖化など、環境への悪影響が懸念されます。そのため、環境省の規定に従って高熱で分解し、地球環境へ影響がないよう無害化しなければなりません。
地球環境保全のためにも、フロン類料金は必要不可欠な費用と言えます。
情報管理料金は、自動車のリサイクル過程における情報を管理するための料金を意味しています。
具体的には、リサイクル預託金の運用や対応窓口の運営資金、各種コンピューターの維持管理などにかかる費用が中心です。また、窓口業務や実務にあたっている人々の人件費としても使われています。
実際に1人のユーザーが支払う情報管理料金の金額は130円ですが、リサイクル過程の透明性を確保し、情報管理の効率化を図るために非常に重要な費用です。
資金管理料金は、プールされたリサイクル預託金を適切に管理するための業務全般に利用される費用です。
シュレッダー料金、エアバッグ類料金、フロン類料金、情報管理料金の4つは、自動車が廃車になった場合の費用を前払いするという形のため、実際に廃車するまで消費税はかかりません。
しかし、資金管理料金はリサイクル預託金の管理・運用のためのサービス料という形を取るため、自動車購入時の支払いに課税仕入れとして計上されています。
自動車リサイクル法とは?

自動車リサイクル預託金の制度は、自動車リサイクル法に基づいて定められています。
では、そもそも自動車リサイクル法とはどのような法律なのでしょうか?
ここからは、自動車リサイクル法の概要と、同法が施行された背景について解説します。
自動車リサイクル法は2005年に施行された法律で、自動車の所有者、自動車メーカー、輸入業者、関連事業者の果たすべき役割を規定しています。
自動車リサイクル法が定める、それぞれの主な役割は以下のとおりです。
リサイクル料金を支払い、廃車時には登録された引取業者に車を引き渡すこと
自社で製造または輸入した車が廃車になった際は、リサイクル可能な部品を回収し、適切に処理する責任を負うこと
廃車を引き取って解体し、リサイクル処理に至るまでのプロセスを適切に管理すること
自動車リサイクル法が施行された背景にあるのは、環境保全と資源の有効活用への声が高まっていることです。
現在、日本で廃車になる自動車は年間約350万台にのぼり、その約8割がリサイクルされていますが、残りの2割はゴミとして埋め立て処分されています。
ところが近年、処分場のキャパシティ不足と、それにともなう処分費用の高騰が問題となりました。
さらに、フロンガスの不適切な大気放出によるオゾン層破壊や地球温暖化、専門的な解体処理が必要なエアバッグ類の処理負担など、多くの問題への対処も必要です。
こうした行き詰まった状況を改善するために、自動車リサイクル法が施行されました。
自動車リサイクル預託金の目的

自動車リサイクル預託金の制度について解説してきましたが、どうして預託金という制度があるのか、その具体的な目的は何でしょうか?
ここからは、自動車リサイクル預託金が必要な理由、その役割と目的について詳しく解説します。
自動車リサイクル預託金の制度が設けられた背景には、自動車リサイクル法成立の背景と同様に、環境保全と資源の有効利用が大きく関係しています。
自動車の大部分は鉄などの有用な金属で作られており、リサイクルは資源の無駄遣いを避けるためにも非常に重要なプロセスです。
しかし、解体した部品をリサイクルし、フロンガスの無害化、エアバッグ類の処理、一連の情報管理などを行うためには、多大な費用を捻出しなければなりません。
そのような自動車のリサイクルにかかる費用を、車の購入者から前払いという形で回収するのがリサイクル預託金です。
リサイクル預託金に消費税が発生するのは本当?

新車を購入する際に支払うリサイクル預託金は、廃車する際にも必要となります。このリサイクル預託金には消費税が発生する場合があるため注意が必要です。
ここからは、どのような場面で、リサイクル預託金に消費税が発生するのかを詳しく解説します。
新車を購入する際は、リサイクル預託金に消費税は課税されません。
リサイクル預託金は支払われると、自動車リサイクル促進センターに委託されます。この時点では、具体的なサービスを利用したわけではないため非課税です。
また、中古車購入の場合はリサイクル預託金が「金銭債権の譲渡」と考えられるため非課税取引となり、消費税は課税されません。
形式上は、「車を買った側が売った側にリサイクル預託金を払う」という形になるのです。つまり、新車購入時も中古車購入時にも、リサイクル預託金に消費税は課税されません。
車を売却する際もリサイクル預託金に消費税はかかりません。
車を売却する場合は、上記の例における中古車購入の逆と考えれば分かりやすいでしょう。この場合も、形式的なリサイクル預託金の支払いは金銭債権の譲渡とされ、消費税の対象とはなりません。
ただし、2014年に法改正があり、課税売り上げの割合を計算する際には、リサイクル預託金の譲渡代金の5%だけを分母に入れて計算するように変更されました。
この点は消費税の計算やその他の税務処理に影響を与える可能性がありますが、リサイクル預託金自体の譲渡に消費税がかかるわけではありません。
車を購入または売却する際は、リサイクル預託金に消費税はかかりませんでした。しかし、車を廃車する場合は消費税が課税されます。
廃車すると、車のリサイクルに付随する様々なサービスを受けることになり、税制上の区分が「課税仕入」に分類されるためです。
また、どのタイミングの消費税率が適用されるのかという問題に注意しておきましょう。
リサイクル預託金に消費税が課税される場合、車を購入した当時の税率ではなく、リサイクルを行う時点の税率が適用されます。
廃車の際には課税のタイミングを理解し、会計処理に誤りが生じないよう注意が必要です。
法人の場合は仕訳に注意が必要

リサイクル預託金や資金管理料金の会計処理は、一般的な資産の取り扱いとは異なるため、より正確な会計処理が求められます。そのため、法人の場合は仕訳に注意が必要です。
ここからは、車の売却と廃車の際の具体例をもとに、リサイクル預託金の仕訳について解説します。
自動車を売却する際には、リサイクル預託金の譲渡も行われるケースが一般的です。
例えば、帳簿価額1,980,000円(税抜1,800,000円)で、売却額が2,310,000円、リサイクル券を20,000円で譲渡した場合、売却益は以下のよう計算します。
この場合のリサイクル券の譲渡は消費税法上、「金銭債権の譲渡」とされるため非課税売り上げです。
また、課税売上割合の計算上、リサイクル預託金の5%すなわち1,000円を課税売上の分母に加える必要があるため、会計処理では見落とさないよう注意しましょう。
自動車を廃車にする場合は、リサイクル預託金を取り崩して廃棄費用として処理します。
例えば、帳簿価額1,760,000円(税抜1,600,000円)で、18,500円をリサイクル預託金としてプールしていた場合を見ていきましょう。
この預託金18,500円は、自動車の廃棄処分サービスの対価として「課税仕入」に計上されます。つまり、この場合のリサイクル預託金には消費税が課税されるため、注意が必要です。
廃車時の帳簿価額は固定資産廃棄損(車を廃車にして生じた損失)として計上され、消費税法上の扱いは不課税取引となります。
リサイクル預託金の金額はいくらぐらい?

リサイクル預託金は複数の要素に基づいて設定され、車種やメーカー、装備品によっても異なります。
例えば、軽自動車でエアバッグ4個とエアコンが装備されている場合のリサイクル料は7,000円〜16,000円が一般的です。
普通乗用車でエアバッグ4個とエアコン付きの場合、1万円〜1万8,000円程度かかります。
また、大型バスでは、エアバッグ2個とエアコン付きで、4万円〜6万5,000円程度と、車の種類だけでも価格に大きな開きがあると言えるでしょう。
リサイクル預託金の消費税に悩みたくない場合は売却がおすすめ

車を廃車にする場合、リサイクル預託金の消費税についてあれこれと悩むことが多いかもしれません。
そのような場合には目先のことも変えて、自動車の売却という選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
ここからは、自動車売却のメリットと注意点について解説していきます。
売却を選択する最大のメリットは、リサイクル預託金にかかる消費税とその仕訳について気にする必要がなくなる点です。
値段のつく状態や年式の車であれば、思い切って売ってしまうことで負担軽減につながるだけでなく、売却によって得た利益を次の自動車購入に回せるメリットも生まれます。
先述したとおり、売却による金銭債権の譲渡には消費税が課税されないため、廃車よりも精神的な負担を軽減できるでしょう。 売却の際にはリサイクル券が必要となるため、なくさないようにしっかりと保管しておく必要があります。
リサイクル預託金に消費税がかからないことは確かに利点ですが、売却の際の注意点も忘れてはいけません。
自動車の売却を検討する際は、複数の業者に見積もりを依頼するのがおすすめです。
ひとつの業者だけに依頼する場合、その業者が提示する価格に疑いを持たず、市場価格よりも安い金額を提示されても気づかないリスクが高まります。
一方で、複数の業者から見積もりを取ることで市場価格の相場が把握でき、自分が納得できる金額で売却できる可能性が高まるでしょう。
安い金額で売却してしまうと、次の車の購入資金に影響してしまうため、売却の際は業者と価格を慎重に見極めなければなりません。





