軽自動車をユーザー車検に出す場合、準備しておくべき書類がいくつかあります。それらの中には、前もって準備できるものや当日準備するもの、さらに必要に応じて用意する特殊なものなどがあります。
準備段階で不備があれば、二度手間になるかもしれません。ユーザー車検で準備しなければならない必要書類を詳しく説明します。
また、ユーザー車検のメリットとデメリットもあわせて紹介しますので、車検の時期が近い方は参考にしてください。
ユーザー車検は準備をしっかりと
軽自動車のユーザー車検は、予約方法や必要書類などが普通自動車の場合と違うのでしっかり確認して準備しましょう。
車の検査にはいくつかの種類がありますが、ここではいわゆる「車検」と呼ばれている「継続検査」の内容を説明します。
軽自動車の定義

車検証の一番上にある「自動車の種別」の項目を見ると、その車が軽自動車であるとすぐに分かります。
軽自動車の定義は、排気量が660cc以下で車体の長さは3.40m以下、幅は1.48m以下のものとなっています。
1998年10月に車体の大きさが改定される前は、長さ3.30m以下、幅1.40m以下が軽自動車の定義でした。改定によって車体が大きくなったことが分かります。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車のユーザー車検の予約方法

軽自動車のユーザー車検を受ける場合、車検場所である「軽自動車検査協会」に予約を入れておかなければなりません。
受検2週間前から予約手続きが可能で、同協会の「軽自動車検査予約システム」というWebサイトを通して行います。
手続きは決められた内容を入力するだけなので簡単ですが、インターネットに慣れていない方は電話でも予約することができます。
軽自動車検査協会のホームページに全国の事務所や支所の一覧が載ってるので、最寄りのところを調べて直接電話しましょう。
軽自動車のユーザー車検で必要になる書類・物品

軽自動車のユーザー車検で必要となる書類や物品には「事前準備するもの」「当日準備するもの」「場合によって準備するもの」の3種類があります。
普通自動車のユーザー車検を受ける場合とは用意するものが異なります。普通自動車の場合と混同したり、不備や忘れ物があったりすると二度手間になってしまいます。
事前にここで確認しておきましょう。
事前に準備するもの

以下では、ユーザー車検を受けるために軽自動車検査協会に直接車を持ち込む時に、事前に準備しておく書類と物品を説明します。
紛失している場合は、再発行が可能なものと難しいものとがありますので注意しましょう!
車検証(自動車検査証)は、用意する書類の中でもっとも重要なものです。コピーは認められていないため、必ず原本を用意してください。
基本的に、車検証は車を運転する時に車内で保管することが義務付けられています。そのため、他の書類と一緒にダッシュボードの中などに収納されていることが多いでしょう。
万が一紛失してしまった場合は、地域を管轄している「軽自動車検査協会」に連絡します。
普通自動車の場合、車検証を紛失したら管轄の運輸支局に問い合わせることになりますので、この点が軽自動車と普通自動車とで違う点です。注意しましょう。
車検の際、参考資料として「点検整備記録簿」提出を求められます。
点検整備記録簿は、普通自動車か軽自動車かに関わらず準備が必要です。車検証などと同様に、車内に備え付けて一定期間保存するよう定められていますので、車内のダッシュボート内を確認してみるといいでしょう。
紛失してしまった場合は、当該車を新車として販売していたお店に問い合わせて再発行してもらわなければなりません。ただし、データが残っていないこともあるので難しい場合もあります。
軽自動車納税証明書は、金融機関窓口などで税金を納めた時に受け取れます。
もしも紛失した場合は、納税した市町村の窓口に問い合わせて再発行してもらいましょう。再発行は簡単な手続きで済むので、直接窓口に赴いてもいいですし、郵送で済ませることもできます。
車検で提出する時はコピーは不可なので、注意してください。
自動車損害賠償責任保険証明書も、コピーではなく原本で用意しましょう。
紛失した場合は加入している保険会社か、あるいは加入時に手続きをしたディーラーや自動車販売店に問い合わせて再発行手続きを行ってください。
注意しなければいけないのは、個人間の取り引きで購入した車で、自賠責保険の名義変更が行われていない場合です。こうなるとどの保険会社に問い合わせるべきか分からないこともあり、各会社にしらみつぶしに聞いてみるしかありません。
認印は、継続検査申請書の「使用者」欄に押印する場合に使うことになり、シャチハタ以外のものを用意します。
現在は基本的にサインのみで済ませられますが、業者によっては印鑑を必須としていることもあるので注意しましょう。
印紙を購入して自動車重量税分の支払いを行うので、その分の費用を用意しましょう。
税額は当該車両の年式などによって異なるので、軽自動車検査協会の「次回自動車重量税額照会サービス」などを活用すると間違いありません。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
当日準備するもの

ここからは当日準備する書類について説明します。
「自動車重量税納付書」「軽自動車検査票」「継続検査申請書」の3つは車検当日に協会窓口でもらうことになります。中には、前もってダウンロードして入手できるものもあります。
まず、自動車重量税を納めるための納付書が必要になります。
軽自動車は普通自動車と比べて税額としては安く済むでしょう。また、普通車と違って軽自動車には重量による金額の差がありません。
例えば、重量が1トンの場合、普通車なら6,600円ですが軽自動車なら新規登録から12年目までは1年につき3,300円です。
ただし、自家用と事業用の違いや、車の使用年数によっては税額が変わります。
新車登録から12年間の間は重量税が6,600円で、13年目からは8,200円、18年目からは8,800円となります。
新車登録から12年間の間は重量税が5,200円で、13年目からは5,400円、18年目からは5,600円となります。
車検は、検査によって車が道路運送車両法の保安基準に達していることが最終的に認められた時点で合格となります。これがいわゆる「車検に通った」ということで、軽自動車検査票にはこの検査の結果が項目ごとに記録されます。
この検査票は、車検当日に軽自動車検査協会で受け取ることが可能です。そして車検が完了すると、窓口で車検証をもらえます。
不合格だった場合は、2週間以内に再検査を受けなければなりません。ユーザー車検では、事前に専門の業者による整備が行われないので無事に合格できるようしっかり事前に点検や整備をしておきましょう。
軽自動車のユーザー車検では、継続検査申請書も必要です。これは車検証を発行するために電子機器で読み取らせて使う書類です。
車検の完了後にこの申請書を運輸支局内のコンピュータに通すことで車検証が交付される仕組みになっており、「OCR申請書」という名称でも呼ばれています。
継続検査申請書は、車検当日に軽自動車検協会で受け取るか、事前に同協会のホームページからダウンロードして入手しておきましょう。
機械で読み取るので、ダウンロード印刷する場合は白色度80%以上の紙を使い、しわや汚れができないように気を付けてください。
さらに準備するものが増える5つのケース
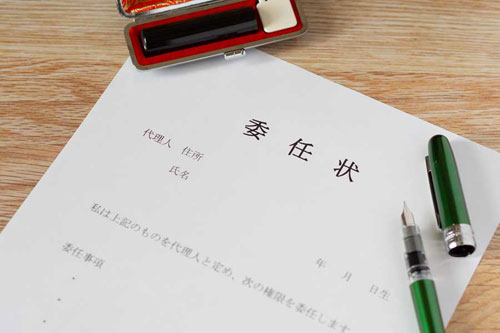
以下の内容に該当する場合は、別途準備しなければならない書類や物品があります。
- 放置違反金を滞納していた
- リコール整備が行われていない車を使っていた
- 手続きを代理人に頼んでいる
- ロックナットを使っている
- 発炎筒が使用期限を過ぎている
自分が該当するかどうか不安な場合は、あらかじめ確認しておくといいでしょう。
委任状は、通常ですと普通自動車の検査や移転登録などの手続きを代理人が行う場合に必要になります。
それが軽自動車の場合はなぜか「申請書」という名称の書類になっており、ディーラー車検を代行してもらう場合はこれを提出することになります。
ちなみに、ディーラーや整備工場に依頼する場合も委任状が必要と思われがちですが、必要書類さえ準備できれば委任状は不要です。
放置違反金の納付を滞納している車は車検を通すことができないという「車検拒否制度」というルールがあります。
滞納があるかどうかは、オンラインでナンバー照会するとすぐ判明するので、ごまかすことはできないでしょう。
当該車両は違反金を納付しない限り車検を受けられず、さらに放置すれば有効期間が満了となって公道で運転することができなくなります。よって、放置違反金はすみやかに納め、車検時には納付の証明として領収書を提示しなければなりません。
領収書は、金融機関の窓口で違反金を納めるとその場で半券の形で受け取ることができます。多くの場合、違反金を納めてから1~2週間で、車検拒否の対象から外されます。
2004年以降に外国で発生したタカタ製エアバッグの異常破裂による死亡事故を受けて、国内外において対象のエアバッグをリコールによる無償の改修が行われています。
しかし、未だに改修されていない車両もあり、そうした車は車検が通りません。これは国土交通省が取った措置で、リコール対象車のうち改修が行われておらず特に危険とされる車両がこれに該当します。
自分の乗っている車が該当するかどうかは国土交通省のホームページで確認することができるので、当てはまる場合はすみやかに修理しましょう。
改修が済むと「改善措置済証」が発行されますので、車検時に提出します。面倒ではありますが、安全のためですのできちんと手続きを行いましょう。
タイヤホイールにロックナットが使われていると普通の六角レンチなどでは外せないので、車検時には専用の「キーアダプター(キーソケット)」を持参しましょう。
ロックナットは防犯用なので、整備業者でも簡単には外せません。整備する時にはタイヤを外す必要があるので、ロックナットを装着したままでは車検を受けられませんので、注意してください。
道路運送車両法保安基準43条により、車には「非常信号用具」の常備が義務付けられています。こうした用具の一種で、他の車に危険を知らせるのに役立つのが発炎筒です。
発炎筒と同じ読み方の道具に「発煙筒」がありますが、非常信号用具として認められているのは、あくまでも煙ではなく「炎」で危険を知らせる「発炎筒」の方です。
発炎筒には使用期限があり、JIS(日本工業規格)によって4年と定められています。有効期限が切れそうな場合や、あるいは手持ちの発炎筒がすでに使用済みの場合は、新品に交換しましょう。
ユーザ車検当日の流れ

ユーザー車検当日は、以下の流れで手続きが進みます。
- 軽自動車検査協会の予約確認窓口で、予約されていることを確認します。
- 手数料取扱窓口で検査手数料と自動車重量税を支払います。
- 検査コースへ行き、検査を受けます。
- 検査の項目は普通自動車と同じで、全ての項目に合格のハンコが押されれば、いわゆる「車検に通った」ことになります。
- 申請書受付窓口に、用意した書類を全て提出します。
- 新しい車検証と検査標章を受け取ります。
- 車検証の内容を確認して、問題がなければ検査標章をフロントガラスに貼り付けます。
ユーザー車検のメリットとデメリット
費用が安く済むという点がユーザー車検の大きなメリットですが、一方でデメリットも存在します。
メリットとデメリットを比較した場合、人によってはユーザー車検はやめた方がいいこともありますのでよく確認しておきましょう。

ユーザー車検の最大のメリットは、車検費用を最小限に抑えることができる点です。
ディーラー車検などはどうしても費用が高くなりがちですが、ユーザー車検なら業者に払う分は浮くことになります。
また、車に関する知識を得られるというメリットもあります。愛車を車検に通すためには車の構造を詳しく知っておかなければなりません。
また、場合によっては自力で整備することも必要です。車の知識があれば、トラブルに遭遇しても自力での対処ができます。
車に関する知識や経験を深めたい方は、ユーザー車検向きだと言えるでしょう。

ユーザー車検のデメリットは、土日祝日や夜は検査を受けることができないという点です。車検場がこの日時には稼働していないため、平日に仕事がある方はスケジュール調整が必要になります。
また、ユーザー車検では必ずしも車がパーフェクトな状態で車検を通るとは限りません。公道を走るのに最低限必要な機能があれば多少の不具合があっても合格するため、車検を通してから不具合が発覚することもあります。
そういう場合も車に詳しい方なら対処が可能ですが、素人だと車の不調そのものに気付かないこともあるでしょう。後のトラブルを防止するためにも、車に関する知識や経験がない方は、専門の業者に依頼したほうが賢明です。
ユーザー車検には「代行」という選択肢もある

ユーザー車検には、費用が節約できるなどのメリットがあります。
しかし、点検整備を自力で済ませるのはいいけれど、手続きや車検場に持ち込むための時間が作れない…という場合はどうすればいいのでしょう?
そんなときは、車検代行業者に依頼するという選択肢があります。車の持ち主に代わって、車検の手続きを請け負ってくれるサービスです。
車検代行業者は、車検場の予約や車の持ち込みなどを行ってくれます。これを利用する最大のメリットは、なんと言っても時間を節約できることです!
さらに、業者によっては代車の手配や、点検整備のアドバイスをしてくれることもあります。ひとくちに代行業者と言っても、そのサービス内容や料金はさまざまです。
デメリットとしては、代行業者に頼んでも必ずしも車検に通るとは限らないという点です。
もし不合格になれば、業者に依頼して時間を節約したつもりだったのに、かえって二度手間になり費用も余計にかさむ結果になるでしょう。
点検整備については、代行業者に期待することはできません。業者にできるのはあくまでも「手続きの代行」やアドバイス程度で、細かい点検整備をすることは禁止されているからです。
また、車検代行は通常なら車検と同時に行う法定24ヶ月点検にも対応していません。よって、車検とは別に行う必要が出てきます。








