誰しも燃費が良くて維持費がかさまない車に乗りたいでしょう。軽自動車は、普通自動車に比べて燃費がいいと言われています。
軽自動車の燃費がいいのは事実ですが、それは車種や乗り方次第です。軽自動車とはいえ、車の種類や運転状況によっては「燃費の良さ」というメリットが活かされないこともあります。
ここでは、軽自動車の燃費がいい理由と、反対に燃費がかさんでしまうケースについて詳しく説明します。
また、車を購入する場合に押さえておきたい費用面のポイントも紹介するので、参考にしてください。
本当に軽自動車は燃費がいい

軽自動車は、車体のコンパクトさや排気量の低さなど、普通自動車と比べて劣る面がいくつかあります。そのかわり、燃料がいいのが特長です。
燃費の良さを重視する方は軽自動車を選ぶことも多いです。
ただし、どんな場合でも絶対的に燃費がいいわけではありません。場合によっては軽自動車の燃費の良さが全く活かされないような運転例もありますし、逆に普通自動車の中にも燃費のいいものがあります。
普通車と軽自動車の燃費を比較

普通自動車と軽自動車を比較した場合、軽自動車の方が低燃費です。
軽自動車は、車体の大きさや排気量に制限があるため全体的に軽く作られており、走る時に使うエネルギーが少なめで済みます。
とはいえ普通自動車も、例えばハイブリッドモデルとしてアクアやプリウスなどがありますし、中には40km/Lを超える低燃費のグレードも存在します。
こうして見ると、必ずしも軽自動車の方が絶対に燃費がいいとは言い切れません。
また、両者の間では安全性や性能の差も縮まりつつあります。軽自動車にもターボ付きエンジンが搭載されて走行性が向上しているものもあったりと、普通・軽ともにそれぞれの弱点をカバーする装備も増えています。
そんな中、今でも差があるのは、自動車税(軽自動車税)や自賠責保険料の金額です。特に税金の金額を比較すると、最も安く済む普通車でも軽自動車の2倍以上になることがありますし、車が大きければ大きいほど金額は増します。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車の燃費がいい理由は?

普通自動車と比べて軽自動車の燃費がいいのは確かですが、その理由はなんでしょう?
答えは、車体のコンパクトさ、それに伴う車体の軽さ、そしてエンジンの小ささなどにあります。これらの条件が合わさった結果、軽自動車は燃費も含めた全体的な維持費の安さを実現しているのです。
以下でさらに詳しく説明しましょう。
どんな軽自動車でも、長さ3.4m以下、幅1.48m以下、高さ2m以下と規格は一律に決まっています。
少しでもこの規格を超えてしまうと、軽自動車ではなく普通車ということになります。
この、軽自動車全般に共通の「小ささ」が燃費の良さを実現しています。
小さいということは空気抵抗が少ないことを意味し、走行時に馬力を必要としません。力を出すためのエネルギー、すなわちガソリンも比較的少なめで済みます。
軽自動車の「小ささ」ともつながる話ですが、軽自動車はコンパクトゆえに車体に使われる金属の量も少なく、普通自動車よりも軽くできています。
これも走行時にエネルギーを浪費せずに済む理由のひとつです。
車体が小さくて軽いものほど燃費の良さは圧倒的と言えるでしょう。
軽自動車の定義として「排気量660cc以下」というのがあり、これは一般的な普通自動車の半分です。
つまり、軽自動車はエンジンも小型ということで、その分だけガソリンの消費量も少ないことになります。
もちろんエンジンが小さければ、出せるパワーもその範囲内に限られてきます。とはいえ、それも軽自動車の小ささと軽さゆえの長所と考えるべきで、無理にパワーを出そうとすればかえって燃費が悪くなり元も子もありません。
動力源が2つある車が「ハイブリッドカー」と呼ばれています。モーターとエンジンの双方が状況に応じて自動で使い分けられるものです。
モーター使用時は、ガソリンの代わりに電気を使うので燃費が良くなります。軽自動車にもこうしたハイブリッドカーに分類されるものがあります。
ガソリンを多く消費してしまいそうなシーンでは、エンジンからモーターに動力源を切り替え、燃料の無駄な消費を抑えてくれます。
ただし、軽自動車の場合はハイブリッドシステムを採用するとどうしても高値になりがちです。
もともと軽自動車ならではの燃費の良さもあるので、軽自動車のハイブリッドカーはあまり量産するメリットがないことからさほど生産されていないのが現状です。
燃費が悪い軽自動車はある?

軽自動車の中にも、燃費の良いものもあれば普通自動車とさほど違いがないものもあります。
「軽自動車なら絶対的に燃費がいいだろう」と思い込んで、充分吟味せずに買ってしまうと後悔する事態になるかもしれません。
以下では、軽自動車でも燃費が悪くなるタイプのものを紹介します。購入の際は注意しましょう。
燃費が悪くなりやすい軽自動車の代表格が、車体が大きいタイプのものです。
軽自動車はもともとコンパクトなつくりのため車内が狭くなります。
しかし、例えば家族の人数が多いとできれば車内がゆったりしたタイプのものを…と希望することもあるかもしれません。
ただ、これは普通自動車にも言えることですが、大きい車はそれだけ燃費が悪いと考えるべきでしょう。
走行時の風圧は大きくなりますし、車内が広いだけに人数・荷物ともに多めになることが考えられるので、どうしてもそうした面が燃費に影響してくることになります。
次に、軽自動車の中でも燃費が悪くなるタイプのものとして「パワーがあるもの」が挙げられます。
軽自動車はもともとパワーがないため、無理をするとエンジンが高回転しガソリンの消費が早くなるのです。
軽自動車は車体の小ささ・軽さに合わせてエンジンも小型になっており、だからこその低価格と燃費の良さを実現しています。よって、エンジンに負担がかかるようなタイプのものは、やはり燃費への影響は避けられません。
こうした難点をクリアしようと、ターボ搭載のものや四輪駆動の車も開発されています。しかし、こうした車もパワーを必要とすることに違いはなく、状況によっては普通自動車とあまり燃費が変わらなくなることも考えられます。
燃費が悪くなるのはどんなとき?

軽自動車の特長である燃費の良さを最大限に活かすためにも、適切な利用シーンを覚えておくことをおすすめします。
軽自動車に適した場所なら燃費はいいですし、そうでない場所では燃料を多く消費してしまうことになります。
次に挙げる3つのパターンでは、いずれも燃費が悪くなりがちです。軽自動車よりも普通自動車のほうが向いているでしょう。
軽自動車はそもそも街乗り用に設計されており、スピードを出して走ることを想定していないので高速走行時は燃費が悪くなります。そのため、高速道路での走行は、軽自動車の燃費が悪くなる走り方の典型と言えるでしょう。
軽自動車は基本的に加速することが苦手で、高速道路での合流や長時間の走行をするとエンジンにも負担がかかってしまいます。
また、車体が軽いことから高速道路では風にあおられやすく、コンパクトな車体に対して空気抵抗が大きくなるため、やはりガソリンの浪費は否めません。
そして、軽自動車は強い横風を受けたり、大型車に追い越されたりすると風圧でハンドルを取られやすく、高速道路の走行は運転手に大きなストレスがかかります。
軽自動車のシートも長時間走行向けの作りではないため、疲労がたまりやすくなります。
高速道路でガソリンを多く消費するメカニズムと同じになりますが、軽自動車はあくまでも街乗り用のため、山などでずっと坂道を走っていると燃費が悪くなります。
坂道ではアクセルを大きく踏み込んでパワーを出すことが多いです。本来、軽自動車が想定しているよりも無理な力がかかり、結果としてガソリンの消費につながります。
燃費のことを考慮すると、軽自動車一台の乗車人数は1人か2人が適当です。
軽自動車は車体を軽くすることで燃費をよくしているので、重量が増せばそれだけガソリンを食います。
また、荷物をたくさん載せてもやはり燃費が悪くなります。
最近の軽自動車には車内の広さが普通車に引けを取らないものもありますが、それも大人数・大荷物の搭乗を許すことで燃費を犠牲にしていると言えるでしょう。
日常的に、3人以上の人数や荷物をたくさん乗せて走ることが多いなら、軽自動車よりも普通自動車が適しています。今から車を購入する方は参考にしてください。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
燃費の良し悪しで車を選ぶ場合の注意点

最近は、普通自動車でも軽自動車と同じくらいに燃費がいいものが販売されています。燃費の良し悪しという観点で車を選ぶなら、普通自動車を選択肢の中に入れてもいいでしょう。
また、車の燃費を示す数字には「カタログ燃費」と「実燃費」の2種類があります。燃費の良さを重視するならこの2つを比べるのがおすすめです。
軽自動車の燃費は現在でも向上していますが、最近の普通自動車の性能の良さも軽自動車に引けを取りません。燃費については、絶対に軽自動車の方がいいとは言い切れないところがあります。
前述しましたが、軽自動車が低燃費を実現できているのは、車体をコンパクトにして軽量化しているからです。そのため、普通自動車でもコンパクトカーなどであれば、軽自動車と同じくらいの燃費になっているものもあります。
また、燃費に限らず安全面についても、今の軽自動車と普通車はさほど差がありません。さまざまな面で両者の差はなくなりつつあります。
車の燃費をメーカーのホームページなどで調べてみると、「カタログ燃費」と言ってガソリン1リットルあたりの走行可能距離が示されています。
車の購入時にこれを参考にする方も多いかもしれません。しかし、カタログ燃費はあまり当てにならないところがあります。
燃費が良くなったり悪くなったりするのは走行時の状況によるからで、カタログ燃費はそうした細かい状況を考慮していません。
カタログ燃費は、条件の一番いい状況で走り続けてどのくらいの燃費になるかを示したものです。決して鵜呑みにしないようにしましょう。
購入したい車の燃費を調べる場合は、カタログ燃費と一緒に「実燃費」も確かめておくのがおすすめです。
実燃費は、実際に走行することでどれくらいの燃費になるかを算出したもので、カタログ燃費よりも現実的なものと言えます。
最近の車の場合、メーカーHPやカタログに「WTLCモード」と記載された燃費情報が記載されています。この数値が街乗りに限りなく近い状態での燃費数値とも言われています。
ただ、これはあくまでも実例のひとつです。実際の燃費は走行する状況によって異なってきます。
自分が走行するパターンに最も近い実例を探すか、多くの実例を集めて平均的な数値を算出するといいでしょう。
軽自動車の維持費にも注意
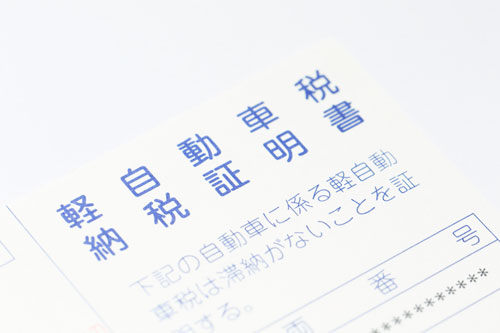
普通自動車・軽自動車を問わず、車の維持費は燃費の他にも「税金」「保険料」「走行費用」「メンテナンス費用」などに大別することができます。
車を購入する際は、これらの要素もあわせて考慮した方がいいでしょう。以下では、各項目について説明します。
意外と見落としがちなものもあるので、車の購入前に確かめておいてください。
軽自動車の場合は、市町村税にあたる「軽自動車税」を毎年春に支払うことになります。これは4月1日時点の車の所有者に課されます。
他にも、軽自動車にかかる税金として「自動車重量税」があります。これは軽自動車の場合6,600円と一律で定められています。また、新車登録から13年経過すると8,200円、18年経過すると8,800円となります。(エコカーは除く)
軽自動車に限りませんが、車を買う時に一括払いにすれば車一台分の代金が必要ですし、ローンを組んだ場合でも頭金が必要です。
また、購入に伴う手続きの費用もかかることから、初期費用としてまとまったお金を準備することになります。
- 法定費用
- 登録諸費用
- 車庫証明発行費用
- 検査登録手続き費用
- 納車費用 など
また、これら以外に業者などに手続き代行を依頼すれば、「代行手数料」もかかるでしょう。
購入時にかかる税金としてよく知られていた自動車取得税は、廃止されました。それに変わるものとして2019(令和元)年10月に「環境性能割」が導入されました。車を購入した際にかかる税金で、燃費の良さに応じて減税されていきます。

車を入手すると自動車保険に入ることになります。
自動車保険は2つの種類があります。法律によって強制的に加入することになる「自賠責保険」と、任意で保険会社と契約して加入する「任意保険」です。いずれも一定の料金体系に基づいて金額は決まります。
自賠責保険の金額は、車種と地域によって異なりますが、軽自動車で沖縄と離島を除く地域の場合、保険料は以下の通りです。(2021年11月現在)
- 12ヶ月…12,550円
- 13ヶ月…13,150円
- 24ヶ月…19,730円
- 25ヶ月…20,310円
- 36ヶ月…26,760円
- 37ヶ月…27,330円
自賠責保険の支払い方法は、車検時に次回の車検までの分の掛金を前払いする形になります。
任意保険の金額は、具体的な補償内容や普段運転する方の年齢などによって変動します。また、支払い方法も加入する保険会社によるので確認しておきましょう。
車の維持費の中でも、金額に最も個人差が表れるのが走行費用で、これには「ガソリン代」「パーキングエリアの利用料」「有料道路の通行料金」などが含まれます。年間を通して意外と大きな支出になりがちです。
特にガソリン代は、車の利用者が多い地方部などでは家計への影響が大きいです。大都市と小都市の年間のガソリン消費量を比較すると、その差が最大で約2倍以上になるという統計結果もあります。
メンテナンス費用としては、オイル類の交換、車検、故障の修理代、消耗品の交換にかかる代金が挙げられます。
オイルやタイヤの交換費用は年間平均でおよそ20,000円、整備費用はおよそ30,000円~35,000円というのが一般的です。
車検代の内訳は「整備代」や「代行手数料」となり、あわせて支払う「重量税」や「自賠責保険料」といった法定費用を差し引いても数万円かかります。
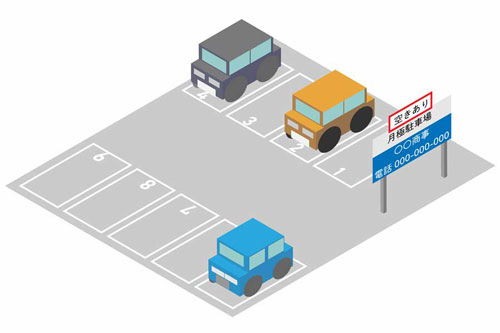
車の維持費として、駐車場代も挙げられます。車を購入すると車庫証明の提出が必須となるので、自宅や自分の敷地に駐車スペースが確保できない場合は、どうしても場所を借りなければならず利用料金がかかります。
駐車場代は、一年にかかる車の維持費の中でも1、2を争うほど高くつきます。
既に借りている場合は、駐車場が無料や安価で使える物件に引っ越すか、屋根のない露天駐車場に変えるだけでも費用の節減になるでしょう。
車を買う場合はまとまった初期費用が必要で、一括払いで支払えるなら問題ありませんが、そうでない場合はローンを組んで返済していくケースがほとんどです。
ローンを組むと金利が発生します。金利により、結果的に車の購入金額以上の分を支払うことになるので家計が圧迫されることも多いです。
高価な車や支払期間が長期間になると金利分も比例して高額になるので、ローン返済額と維持費のバランスを見ながら少しでも低金利のローンを選びましょう。








