テレビの車のCMでもしばしば見かける「自動ブレーキ機能」に関して、言及している宣伝は近ごろ増えてきました。
自動ブレーキは今では普通自動車だけでなく、軽自動車でも搭載されているモデルも多くなってきていますが、どのようなものかきちんと理解しているという方は少ないかもしれません。
ここでは、軽自動車の自動ブレーキ機能について詳しく見ていきます。その上で、購入する際にどのようなポイントに注意すればいいかをまとめました。
自動ブレーキの基礎知識
自動ブレーキという名前は知っているけれども、具体的にどのようなシステムか知らないという方も多いかもしれません。
そこで、ここではまず自動ブレーキとは何かについて見ていきます。
自動ブレーキと似たような機能としてブレーキアシストもありますが、両者には違いがあります。ブレーキアシストとどこが異なるかも見ていきましょう。
正式名称は「衝突被害軽減ブレーキ」

自動ブレーキの正式名称は「衝突被害軽減ブレーキ」と言います。その英語表記の頭文字をとって「AEBS」と呼ばれることもあります。
自動ブレーキの機能は、車の中に搭載されているカメラもしくはセンサーが、歩行者や車両を検知するシステムで、最初のうちは警告音などで衝突の危機をドライバーに知らせます。それでもドライバーが有効な対応を取らなかったら、車両の方で自動的にブレーキをかける仕組みです。こうして衝突を回避します。
衝突を回避できなかったとしても、ブレーキをかけることで少しでもダメージを軽減できます。車両や搭乗者のダメージをできるだけ低減するために、有効な機能です。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
ブレーキアシストとの違いとは?

似たような安全性能として、ブレーキアシストを搭載している自動車も少なくありません。ブレーキアシストと自動ブレーキは若干違いがあります。
自動ブレーキは、最悪の場面で車がブレーキをかけることで衝突回避するのが目的の機能です。
ブレーキアシストは、ブレーキの力を増幅する機能になります。ドライバーが急ブレーキをかけようとしているけれども、踏み込む力が少ない時に働きます。そのため、ドライバーがブレーキを踏み込むことが前提の機能です。
自動ブレーキは、ドライバーが全くブレーキに足が行っていなくてもセンサーなどで衝突の危険性が増したと検知した時に、文字通り自動的にブレーキがかかります。
軽自動車も自動ブレーキの義務化が始まる
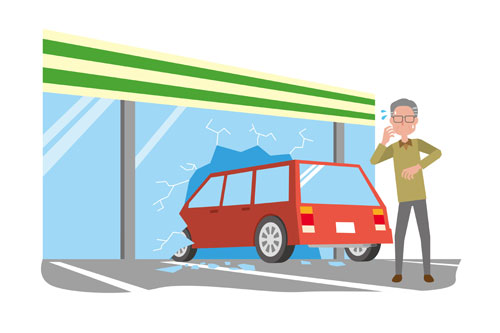
今後、自動ブレーキ機能を搭載した軽自動車は増えると見込まれています。なぜなら、2021年11月以降に発売される新型の国産車を対象に、自動ブレーキの搭載が義務化されるからです。
新型の国産車ですから、軽自動車も対象になります。ここでは自動ブレーキの義務化について、詳しく見ていきましょう。
自動ブレーキ搭載の義務化の背景には、事故の増加が関係しています。
事業用車両の居眠り運転を原因とした重大事故は、少なくありません。また、高齢者ドライバーによる事故頻度が増加していることも背景としてあります。
いずれも共通しているのは、ドライバーの運転ミスによるものです。特に高齢者の起こす死亡事故で、運転ミスを原因としたものが全体の3割を占めています。
自動ブレーキ搭載の車が増えれば、このような重大事故を回避できる可能性が高まるでしょう。
もし安全運転を重視して車を選ぶのであれば、自動ブレーキを含めた安全をサポートする車両を購入するのがおすすめです。
自動ブレーキ義務化の開始時期は、車の種類によって異なります。
国産車は、新型車の場合2021年11月です。輸入車は、若干後倒しになり、2024年7月から義務化が開始されます。
ここで勘違いしてほしくないのは、新型車とは新車ではない点です。新しく市場に投入するモデルを指します。従来から生産されているモデルは、継続生産車になります。
国産の継続生産車が義務化の対象になるのは2025年12月からです。輸入車の継続生産車はさらに1年遅れの2026年7月から義務化が開始となっています。
国産車の中でも、軽トラックは若干他のタイプとは異なります。軽トラックの継続生産車は、2027年9月が義務化の開始月です。
自動ブレーキをただ搭載すればいいかというと、そうではありません。国土交通省の認定を受ける必要があり、そのためには国が定める基準をクリアする必要があります。
まず、静止している車両に時速40kmで衝突しないことという条件です。
次に、時速20kmで走行している車両に対して、時速60kmで走行し衝突しないこと。
さらに、歩行者に対する試験があります。高さ115cm、6歳児相当のダミーを使った試験です。車両がブレーキ作動しなかった場合、4秒後には衝突するタイミングでダミーが動きます。その状況下で、時速30kmで走行して衝突しないこと。
この3つの条件をクリアして初めて、自動ブレーキとして認められます。
自動ブレーキ搭載義務化で心配している方も多いでしょう。軽自動車の所有者の中には、現在の車両に自動ブレーキが搭載されていない方も多いはずです。
義務化された以降も自動ブレーキが搭載されていない車両を運転しても、ペナルティの対象にはなりません。また、自動ブレーキがついていなくても、車検を通すことはできます。
そのため、自動ブレーキ義務化が始まったら、自動ブレーキが搭載されている車に速やかに買い替える必要はありません。
ただし、自動ブレーキが搭載されていると事故回避の確率は高まります。今後、軽自動車の買い替えを検討するタイミングが来たら、自動ブレーキがついているものに買い替えるのも一考です。
自動ブレーキで安全性を高めたいと思っている方は、車を買い替えないといけないかというとそうでもありません。自動ブレーキをはじめとした安全装置の中には後付づけできるものもあります。
例えば、「ペダル踏み間違い急発進抑制装置」があります。アクセルとブレーキの踏み間違いによる事故を回避するための装置です。
高齢者ドライバーの事故を見てみると、踏み間違いが原因というケースも少なくありません。高齢者自身が車につけるのもいいですし、高齢の両親にプレゼントするのも一考です。
ペダル踏み間違い急発進抑制装置は、厳密には自動ブレーキではないかもしれません。しかし操作ミスによる事故を回避できるので、取り付けを検討してみるのもいいでしょう。
自動ブレーキの性能について紹介
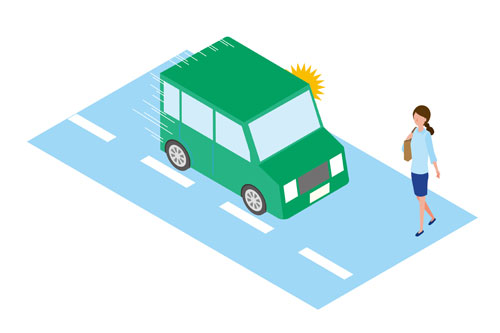
自動ブレーキといわれると、いつでも自動的にブレーキがかかるイメージを持っている方もいるでしょう。しかし、厳密には違います。
自動ブレーキは何段階かに分けて事故を回避する機能です。ここでは、自動ブレーキとはどのような役割を果たす機能かについて、詳しく見ていきます。
自動ブレーキ機能の搭載された軽自動車には、カメラもしくはセンサーがどこかについています。カメラやセンサーで歩行者や車両、障害物などを検知します。
一定範囲内に何らかの物体が見つかると、衝突の危険性がどの程度か判定が可能です。軽自動車1台当たり、複数のセンサーやカメラが設けられています。
また、車種によってはレーザーを搭載しているものも少なくありません。赤外線レーザーを放射できれば、夜間の暗い状況でも障害物との距離を正確に測定できます。
このセンサーの精度がどれくらいかによって、自動ブレーキ機能の良し悪しも変わってきます。センサーの精度が高いかどうか、購入する際にチェックしてみましょう。
センサーで障害物を検知し、衝突の危険性が高いと判断されるとまずは警告音を発します。ドライバーに危険の近づいていることを認知させるためです。
警告の内容はさまざまです。前の車両への衝突や歩行者の接近、さらにはドアを開閉する際に別の車両が接近しているなどが考えられます。
通常は音で警告する車種が多いです。
中にはサイドミラーにLEDライトが内蔵されていて、これが点滅することでドライバーに知らせるモデルも見受けられます。
LEDライトが作動するのはバックしている時に別の車両が接近してきた、死角に車両や歩行者が入り込んだ場合などです。サイドミラーを見ている時に点滅するという仕組みとなっています。
最初は警告音や点滅でドライバーに知らせます。ドライバーがこれを確認して、ブレーキをかけるなどの適切な操作をすれば、それ以上のシステムは作動しません。
しかし、中には警告音を発してもドライバーが認識しない、操作が間に合わないこともあるでしょう。その結果、車がどこかに衝突するのを回避できなければ、自動ブレーキが作動します。
自動的にブレーキがかかることで、衝突を回避するわけです。たとえ衝突してしまったとしても、ブレーキがかかればダメージは最小限に食い止められます。
このようにセンサーやカメラが事故の危険性を検知し分析することで、できる限り事故による被害を軽減するための装置です。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
自動ブレーキと補助金

軽自動車の中には、自動ブレーキを搭載しているモデルも少なくありません。
新規購入する、軽自動車に買い替えようと思っている方の中には、自動ブレーキのついた車種が欲しいと思っている方もいるでしょう。
自動ブレーキ搭載の軽自動車を購入する前に、補助金情報を確認してください。一定の条件を満たせば、車購入に対して補助金が交付される可能性があります。
サポカー補助金という言葉を、コマーシャルなどで見かけたことのある方も多いでしょう。2020年3月から申請受付している制度で、安全装置搭載車購入支援のための国の政策です。
これは高齢者向けの補助金で、2021年度に65歳以上の方を対象にした制度となります。補助金が出るのは、2つの条件のうちのいずれかを満たした場合です。
①対歩行者衝突被害軽減ブレーキ、もしくはペダル踏み間違い急発進抑制装置の付いた軽自動車を購入すること。
②所持中の車にペダル踏み間違い急発進抑制装置を後づけすること。
高齢者のペダルの踏み間違いに伴う事故を回避するためにも、この制度をどんどん活用しましょう。
サポカー補助金で補助される金額ですが、条件によっていくつかのパターンが考えられます。
まず新規購入する際、対歩行者衝突被害軽減ブレーキだけか、ペダル踏み間違い急発進抑制装置もついているかで変わってきます。
対歩行者衝突被害軽減ブレーキだけの場合、軽自動車は新車で30,000円です。中古車の場合には補助金は20,000円となります。
ペダル踏み間違い急発進抑制装置もついている軽自動車だと、新車で補助金は70,000円です。ただし中古車を購入するのであれば、40,000円となります。
ペダル踏み間違い急発進抑制装置を後づけすることでも、補助金がおります。この場合、どのような機能の搭載された装置を後付けするかによって補助金額は変わってきます。
ポイントになるのは「障害物検知機能」がついているかどうかです。現在販売されている装置を見てみると、検知機能のついているものとそうでないものが販売されています。
障害物検知機能がついているのであれば、40,000円が上限です。障害物検知機能がついていないのであれば、20,000円が上限となります。
ペダル踏み間違い急発進抑制装置を後づけする場合は障害物検知機能がついているかどうか必ず確認しましょう。そして、販売価格ともらえる補助金額のバランスを考えて、どうするか検討することをおすすめします。
軽自動車を保有している方で、自動車保険に加入している方も多いでしょう。いざというときに幅広い補償が受けられるので、安心して運転できます。
自動車保険に加入するにあたって、やはり気になるのは保険料です。
自動ブレーキ搭載の軽自動車で保険に入ると「ASV割引」が適用されます。
しかし、ASV割引には条件があります。ASV割引が適用されるのは、発売後3年以内の車両です。具体的には、保有する車両の型式が発売された年度の3年後の12月までが適用されます。
3年で割引きが終了するのは、型式別料率クラスに基づき保険料が算出されるためです。型式別料率クラスでは事故リスクの低さも保険料算定に反映されます。
つまり、割引きなしでも自動ブレーキ搭載車は事故リスクが低いと判断されるため、保険料は安くなるわけです。
自動ブレーキ以外の軽自動車の安全装置とは?

自動ブレーキのほかにも安全に運転ができるようなサポート機能が搭載されている軽自動車も見られます。
どのような安全装置が搭載されているか、主要なものについて見ていきます。
今後軽自動車を購入する際に、チェックしてみてください。
軽自動車の中には、ACCの搭載されているモデルも見られます。
ACCは、オートクルーズコントロールの略称です。高速道路を走行している時に、主に機能する装置です。
ACCを作動させると、高速道路を運転している時にドライバーがアクセルペダルから足を離しても一定速度で走行します。
ドライバーにとっては高速道路を運転している時に、ペダルをずっと踏み込む必要がありません。その分負担を軽減できるわけです。
ACCの歴史は古く、登場したのは1980年代です。最初は高級車を中心としていたのですが、今では軽自動車でも採用されている車種があります。
事故防止のための安全装置は他にもあります。それは標識認識機能です。
標識認識機能は、カメラなどで標識を検知すると、メーターパネルにそのメッセージが表示される機能です。
運転している時に、ついつい標識を見落としてしまう場合もあるでしょう。しかしメーターパネルに標識が表示されれば、見落とすこともなくなります。
進入禁止や一時停止などの標識がメーターパネルに出てくれば、違反するリスクも低減されます。また、制限速度も表示されるので、知らないうちにスピード違反してしまうこともないでしょう。
誤発進抑制機能が搭載されている軽自動車もあります。
高齢者ドライバーの事故で多いのが、ブレーキとアクセルの踏み間違いです。この踏み間違いに伴う事故リスクを低減するのが、この装置です。アクセルを思いっきり踏み込んでも急発進しないようなシステムになっています。
具体的には障害物があって、アクセルを踏み込むと音もしくは表示で警告してくれます。それと同時に、エンジン出力を抑制する仕組みです。その結果、スピードが急に上がるのを防ぎ、飛び出しを抑制してくれます。
レーダーもしくはカメラなどで障害物を検知することで、システムが作動し、急加速を防いでくれます。








