「コンパクトサイズで小回りが利く」「メンテナンスコストが安い」ということで、自家用車として軽自動車を買い求める方は少なくありません。
そこで、各メーカーとしても軽自動車の製造・販売には結構な力を入れています。
軽自動車というジャンルに分類されるためには、一定のルールの中で製造しなければなりません。軽自動車には一定の規格が設けられているからです。
この記事では、軽自動車の長さ、車幅、車高などの大きさの規格について詳しく見ていきます。
軽自動車の規格
軽自動車として販売するためには、国の定めた一定の規格をクリアしなければなりません。ここでは軽自動車の規格について解説していきます。
軽自動車の規格は、過去何度か見直されてきました。また軽自動車というと黄色いナンバーが特徴ですが、なぜ普通自動車とは別のナンバーが用意されているかについても見ていきます。
2022年現在の軽自動車の規格について

- 全長…3.4メートル
- 全幅…1.48メートル
- 全高…2.0メートル 以下
- 全長…4.7メートル
- 全幅…1.7メートル
- 全高…2.0メートル 以下
軽自動車のほうが小型自動車よりも車高以外は一回り小さなサイズであることが分かります。
また、規格にはもう一つ「エンジン排気量」もあります。
- 軽自動車のエンジン排気量…660cc
- 小型自動車のエンジン排気量…2,000cc
軽自動車と小型自動車のエンジン排気量にはかなりの差があることが分かるでしょう。
ちなみに軽自動車では馬力が64psまでという取り決めもあります。しかし、これは規格ではなくメーカー内の自主規制となります。
軽自動車の規格について「2022年現在」としたのは、過去に何度か変遷を経ているからです。
まず、軽自動車というジャンルが作られたのは1949年7月のことです。
当初の規格だとサイズは以下のように決められていました。
- 全長…2.8メートル
- 全幅…1.0メートル
- 全高…2.0メートル 以下
今のサイズよりも小さいことが分かります。
また、1949年当時は「排気量が150ccまで」と決められていました。これも現行の660cc以下と比較すると、かなり制限されているでしょう。
その後、1954年に軽自動車の規格が見直され「排気量が360ccまで」になりました。さらに1976年には「排気量が550ccまで」となりました。
1990年には排気量が現行の660cc以下になり、全長は3.3メートルまでとなります。
1998年には全長3.4メートルになり現在に至っています。
軽自動車と普通自動車を見分けるポイントとして、ナンバープレートがあります。
普通自動車の場合、白ベースのナンバープレートが装着されるのに対して、軽自動車の場合、黄色ベースのナンバープレートです。
これは、高速道路の料金所が関係しています。高速道路の通行料金は普通車と軽自動車とでは異なります。
料金所の人がナンバーを見て普通車か軽自動車か、簡単に区別するためにナンバーの色を変えました。
しかし、近年では軽自動車でも白ベースのナンバープレートを装着しているケースも増えています。ETCの普及によって、見分ける必要性が失われつつあるためです。
軽自動車にはサイズなどの規格が設けられています。では、実際に販売されている軽自動車のサイズはどうなっているのでしょう?
主要な軽自動車の全長や全幅を見てみると、ほぼ全て同じと言っても過言ではありません。全長と全幅は、規格で定められた上限ギリギリのサイズに設定されています。
軽自動車の弱点の一つに、車内空間の狭さがしばしば挙げられます。少しでも車内スペースを確保するために、全長と全幅を上限ギリギリにしているわけです。
車高については、同じ軽自動車でも車種によってまちまちです。1.2メートル弱のものもあれば1.9メートル超のものもあります。
かつては全長2.7メートル、全幅1.5メートル程度の規格よりもさらにコンパクトサイズの車種もありました。しかし、現在は全高に違いはあるものの、全長と全幅はどの軽自動車でも横並びと考えていいでしょう。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車に細かな規格が設けられている理由
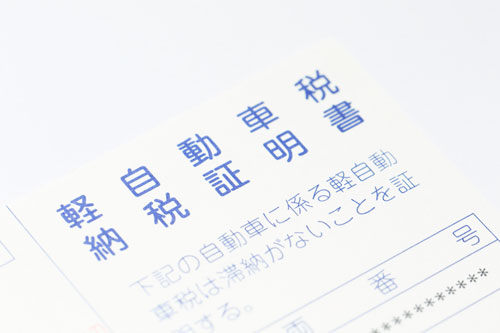
普通自動車と比較して、軽自動車は車のサイズやエンジン排気量などかなり細かな決まりがあります。
なぜこのような詳細な規格が設けられているのか、これはメンテナンスコストによるものです。
まず、自動車税は軽自動車のほうがかなり優遇されています。軽自動車は3年間で32,400円です。これに対し1.5リッタークラスの普通車の場合、103,500円です。3倍以上の税負担を強いられます。
また自動車重量税についても、軽自動車と普通車には差があります。乗用車の継続車検の場合、軽自動車は6,600円ですが、1.5tの普通車だと24,600円なので、かなり差があります。
このように、軽自動車は税金などで様々な恩恵を受けられるため、サイズなどに細かな制約を設けているわけです。
軽自動車を購入すると駐車場など、どこかに車を保管できるスペースが必要です。
駐車場に安全に車を停めるためには「全長+0.2~0.8メートル」「全幅+0.5~1.2メートル」というように余裕があったほうがいいとされています。
軽自動車のサイズを見てみると、全長3.4メートル・全幅1.48メートルが上限です。ほとんどの車種がこの上限ギリギリに設計されています。
軽自動車を停めるためには、「長さは3.6~4.2メートル」「幅は2.0~2.7メートル」のスペースは確保しておきたいところです。
もし自宅の敷地内に駐車するのであれば、これだけのスペースがあるかどうか確認しておきましょう。
ショッピングセンターなどには軽自動車専用の駐車場を設けているところもありますが、こちらの駐車スペースは上で紹介したサイズは確保されているはずなので、駐車できないということはまずありません。
軽自動車の種類について解説

地方に住んでいる方は、公共交通機関が手薄なので、交通の足として軽自動車を買い求めることが多いです。
そこで現在では、多種多様な軽自動車を各メーカー製造しています。
軽自動車は大きく分けて5種類に分類できると言われています。それぞれどのような特徴があるかについてまとめましたので、購入する際の参考にしてみてください。
軽自動車の中でもベーシックなタイプと言われているのが「セダン系」です。
昔から製造されていて、ロングセラー商品も少なくありません。
セダン系の主要な車種のサイズを見てみると、全長3.4メートル・全幅1.47メートル・全高1.5メートルのものが主流です。軽自動車の中では標準的なサイズと言えます。
標準的なスペックのため、価格もリーズナブルなものが多いです。
しかし近年、サイズを大きくして車内スペースを確保し、プラスアルファの価値をつけているモデルも登場しつつあります。
軽自動車のデメリットと言われてきたのは、コンパクトサイズがゆえの車内スペースの狭さでした。その問題を克服した画期的なジャンルとされたのが、この「ハイトワゴン系」です。
「トールワゴン」とも呼ばれる軽自動車の特徴は、車高の高さにあります。車の高さを従来モデルよりも引き上げることで、上部スペースの圧迫感をなくしました。
主要なハイトワゴン系の車高を見てみると、おおむね1.62~1.65メートルのものが主流です。従来のセダン系の1.5メートルと比較して、高い設計になっています。
少しでもゆとりのある軽自動車を購入したければ、トールワゴンの中から候補を絞り込むといいでしょう。
ハイトワゴンよりもさらに車の高さを出しているのが、「スーパーハイトワゴン系」と言われる軽自動車です。
ハイトワゴン系と比較すると、プラス100mm以上さらに高くなっています。そのため、かなり広大な車内スペースを確保できています。
スーパーハイトワゴン系の軽自動車は、ファミリーカーとしても人気です。夫婦と子供1~2人乗る車としては十分なスペースがあるため、ファミリーユースを意識した機能も導入しています。
例えばスライドドアです。子供や大きな荷物を抱えている時にでも、車の開け閉めができるように設計されています。
「ワンボックスタイプ」の軽自動車も、安定した人気があります。
かつて「軽バン」と呼ばれていたジャンルを、自家用車バージョンにしたものです。
ハイトワゴン系やスーパーハイトワゴン系と比較すると、もともと商用車仕様なので快適性は若干劣るかもしれません。しかし商用車をベースとしているので、積載性には優れています。
アウトドアが趣味の方は、レジャー仕様の車として愛用しているケースも多いです。キャンピングカーのベース車両として購入する方も少なくありません。
このタイプの軽自動車は、車高もかなり高いです。1.8~1.9メートルと、規格ギリギリのサイズで設計されているものもあります。
「SUV系」の軽自動車を取り扱っているメーカーも見受けられます。従来のSUV車同様、オフロードの走破性に優れているのが特徴の一つです。
かつてはいろいろなメーカーで取り扱っていたのですが、近年ではバリエーションもかなり絞られています。しかし、現行のSUV系軽自動車の中には、根強い人気のある車種もあります。
SUV系の軽自動車も、車高を高くしているモデルが少なくありません。主要なブランドを見てみると、1.6~1.7メートル程度に設計されているものが主流のようです。
キャンプやスキーなど、レジャー目的で軽自動車を探しているのであれば、SUV系を購入するのも一考です。
軽自動車のメリットとは?

自家用車として、軽自動車を買い求める方は少なくありません。軽自動車の普及率も年々高まっています。
なぜ軽自動車が人気なのか、それは普通自動車にはないメリットがあるからです。
主にどのようなメリットがあるのか、ここで紹介しましょう。
軽自動車は広く普及しています。
一世帯当たりに換算した場合の軽自動車の普及率は、近年50%を超えると言われています。年間に販売される新車台数で見ても、軽自動車が4割を占めるほどです。
そのため、各メーカーとも軽自動車の開発にかなりのウエイトを置いていると言われています。
特に近畿から西に行くと、軽自動車が広く普及しています。2020年の軽自動車の比率を都道府県別で見ると、高知県がトップで55.4%を占めています。近畿以西の中でも、四国と九州地方の普及率は高いです。
共通しているのは、公共交通機関が未発達なことで日常の足として欠かせない存在になっているからです。
軽自動車が高い人気を誇る理由はいくつかありますが、その中でも大きいのは使い勝手の良さでしょう。
普通自動車と比較して一回りコンパクトサイズに設計されているため、小回りが利くので狭い路地でもスイスイ走行できますし、狭い駐車スペースにもストレスなく停められます。家族の送迎や近所への買い物をする日常使いには、とても適しています。
また、最近は企業努力によって、コンパクトサイズでありながら車内スペースが広々な車種も少なくありません。ファミリーカーとしても重宝します。
ラゲッジスペースが広めのモデルも見られます。キャンプ用品なども問題なく積載できるモデルもあり、レジャーユースの車としても人気が高いです。
軽自動車が人気の理由として、燃費の良さを挙げる方も多いです。
普通自動車と比較してコンパクトサイズなので重量も軽く、余計なガソリンを消費する心配もありません。
流れのスムーズな一般道を走行する場合、走り方によってはかなり優れた燃費をたたき出すこともあります。普通車と比較して、2~3倍走行することも可能です。
投機マネーの流入などで、時にガソリンの価格が急騰することもあります。近年ではコロナ禍の影響で、産油国が生産を絞ったことで価格が高騰したこともありました。
このようにガソリン代が値上がりすることは、今後十分考えられるため、ガソリン代の節約の見込める軽自動車は魅力的でしょう。
マイカーを購入する際には車両価格だけでなく、維持費用のことも頭に入れておかないといけません。
軽自動車の場合、維持費が普通自動車と比較して安く済むのもメリットの一つです。
例えば、自動車税は車を保有すると、毎年捻出しなければなりません。普通車の場合、どんなに安くても年間約25,000円かかりますが、軽自動車税の場合、一律年間10,800円なので、普通車の半分以下の納税額で済みます。
また、車の部品の中には消耗品もあり、定期的に交換が必要です。軽自動車の消耗品は普通車と比較してリーズナブルなので、メンテナンスコストも少なくて済みます。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車購入時の注意点とは?

軽自動車には普通自動車にはないメリットがありますが、その反面、軽自動車がゆえのデメリットも見られます。
以下では、軽自動車を保有するにあたっての注意点についてまとめました。
軽自動車は、全長3.4メートル・全幅1.48メートル・全高2.0メートル以下で設計しなければならないという規格があります。
普通自動車よりもコンパクトサイズに設計されているので、どうしても車内スペースは狭めです。
各メーカー、少しでも快適に乗車できるように車内スペースを広くするための企業努力はしています。しかし、それでも普通車と比較すると、見劣りしてしまう点は否めません。
家族に小さな子供がいる場合、軽自動車でも窮屈には感じないかもしれませんが、大人4人で乗車するとなると、窮屈に感じる車もあるでしょう。
大人数で乗る場合や大きな体格の方が利用する予定がある場合には、実際に車に乗って快適にドライブできるか確認することをおすすめします。
軽自動車の規格は大きさだけでなく、エンジンの排気量も含まれます。
軽自動車ではエンジン排気量が660ccまでと決められています。エンジン排気量が少ないと、エンジンパワーは不足しがちです。
街乗りをする際にはそこまでエンジンパワー不足を感じる場面は少ないかもしれませんが、坂道を登っていく時になどにはパワー不足を感じるかもしれません。
特に「多く乗車している」「たくさん荷物を積み込んでいる」時に、坂道を上るのは厳しいでしょう。
また、スピードもそれほど出ないため、高速道路を走行する際には、後ろからあおられる危険性もあります。
自分の主要な用途にマッチしているかどうか、十分検討して購入しましょう。








