軽自動車を使わない状態になると、一時抹消(一時使用中止)を検討する方もいるでしょう。しかし、頻繁に手続きすることはないため、どのように行えば良いか分からないという方も多いかもしれません。
この記事では、軽自動車を廃車する際、一時抹消登録の種類や必要書類、手続き方法、代理人による手続き方法について詳しく解説していきます。
軽自動車を廃車する方法は4種類ある

軽自動車を廃車にする手続きには、以下の4種類があります。
- 一時抹消登録(一時使用中止)
- 永久抹消登録(解体返納)
- 解体届出
- 輸出予定届出
それぞれ、廃車する目的や状況によって手続き方法が異なります。
ここからは、軽自動車を廃車にする4種類の方法について詳しく解説していきます。
一時抹消登録(一時使用中止)とは、車の登録情報を一定期間だけ抹消する手続きのことです。普通自動車の場合は一時抹消登録、軽自動車の場合は一時使用中止といいます。
一時使用中止の手続きをするケースは、海外出張や長期入院などによって、長期間にわたり車を使用しないときに行います。
例えば、中古車販売店で販売されている車は、購入されるまでは公道を走行することがありません。そのため、一時使用中止を行います。
つまり、ナンバープレートがついていない状態で展示されている車は、一時使用中止にしている状態だといえます。
軽自動車が公道を走行する必要性がない場合、一時使用中止にしておくことで税金対策をしている一面もあります。
永久抹消登録(解体返納)とは、車の登録情報を完全に抹消する手続きのことです。普通自動車の場合は永久抹消登録、軽自動車の場合は解体返納といいます。
車を解体して使用不能にするので再登録はできず、二度と使用することができなくなります。
解体返納を行うケースとして挙げられるのが、車体の経年劣化です。軽自動車は普通自動車よりもコンパクトで車のパーツが損耗しやすいため、耐用年数が短い点があります。近年では、性能や品質も向上し、走行距離や耐用年数が長くなっているのも事実です。
しかし、年式が13年以上経過すると、軽自動車税種別割や自動車重量税も重課されてしまいます。
廃車にするか迷うかもしれませんが、維持費や経年劣化による故障のリスクを考えると、廃車にすることで負担を軽減できる点はメリットだといえるでしょう。
解体届出とは、一時使用停止手続きを行った後に軽自動車を解体し、登録情報を完全に抹消する手続きのことです。具体的には、車を一定期間使用しない状態にしていて、その後必要が無くなったため処分するときに行います。
こちらも解体返納と同様、軽自動車を再登録することはできず、二度と使用することができなくなります。
解体届出を行う際は、事前に車を解体しなければなりません。そのため、解体業者に依頼をして解体が完了してから手続きします。
輸出予定届出とは、軽自動車を海外に輸出するときに行う手続きのことです。
日本車は海外でも品質が良好であることが知られており、需要が高く人気があります。例えば、年数経過により日本の中古車販売店では売れない車であっても、海外では販売できるかもしれません。その場合は、輸出することで中古車販売業者は利益を得ています。
近年、車買取業者や廃車専門業者は、国内だけではなく海外にも拠点を持ち、海外輸出を行っている業者が多いです。そのため、一時抹消登録後に輸出予定届の申請をすることになります。
また、個人の所有者であれば、海外移住などの理由から日本で使っていた軽自動車を海外で使う際、輸出予定届出をすることもあります。
軽自動車を一時使用中止するメリット

軽自動車に限らず、自動車の一時抹消を行うことによってメリットはいくつかあります。
ここからは、軽自動車を一時使用中止するメリットについて詳しく解説していきます。
軽自動車を一時使用中止すれば、軽自動車税を納める必要がなくなる点はメリットと言えます。
軽自動車税は、毎年4月1日現在で登録されている軽自動車が課税対象です。そのため、軽自動車を乗らない状態であっても、登録されたままであれば軽自動車税を納税することになります。
これは、軽自動車に限らず普通乗用車も同様に自動車税の課税対象になります。
一時抹消登録や一時使用中止を行えば、自動車検査証返納証明書が交付され、基本的にナンバープレートは返還することになります。
ちなみに普通乗用車を年度途中に抹消する場合、翌年の3末分までを月割りで自動車税の還付を受けることができます。しかし、軽自動車は還付の対象外になる点は注意が必要です。
軽自動車税を納めなくて済むようにするには、3月31日までに一時使用中止にすることがポイントです。しかし、その時期の軽自動車検査協会での受付は混雑する傾向がありますので、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。
軽自動車の一時使用中止を行ったほうが良いケースは、車に一定期間乗らない状態になり、その後車を再利用するときです。具体的には以下のような場合です。
- 単身赴任により、一定期間車を使用しない環境で生活する
- ご自身は運転しないが、数年後に子どもや孫がその車を使用する可能性がある
- 長期間の入院により車を使用しない状態になった
ただし、車を使用しない状態で保管しておくと、エンジンやバッテリー、ボディの劣化も進みます。定期的なメンテナンスを実施したり、自動車カバーを取り付けたりすることが大切です。
いつ使用するか不透明な場合には、車買取業者に依頼して売却することで、保管中に行うべきメンテナンスの手間が省けるかもしれません。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車を一時使用中止する手続き方法

それでは、軽自動車を一時使用中止するためには、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。事前に知っておけば、登録する際に困りません。
ここからは、軽自動車を一時使用中止するときの必要書類や手続き方法について詳しく解説していきます。
まずは一時抹消をする際の必要書類について紹介します。軽自動車と普通自動車では用意するものが若干異なりますので注意しましょう。
軽自動車を一時使用中止する際に必要な書類は以下になります。
- 自動車検査証(車検証)
- ナンバープレート(車両番号標)2枚
- 申請書(軽第4号様式):自動車検査証返納証明書交付申請書、自動車検査証返納届出書
- 申請依頼書 ※代理人が手続きする場合に必要
- 軽自動車税(種別割)申告書
申請書(軽第4号様式)は、軽自動車検査協会のホームページでダウンロードするか、軽自動車検査協会の事務所や支所の窓口で入手できます。
・自動車検査証
・ナンバープレート
・申請書(第3号様式の2)
・手数料納付書
・印鑑証明書
・実印
・委任状(代理人が申請する場合のみ)
一時使用中止の手続きをする場所は、軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所や支所、分室で行います。
手続き方法は以下の通りです。
- 軽自動車検査協会事務所の窓口で申請書(軽第4号様式)を入手して、案内に沿って、必要事項を記入する
※事前に準備していれば不要 - 申請書類一式とナンバープレート(2枚)を用意して窓口で提出する
- 自動車検査証返納証明書を受け取り、記載内容に間違いがないか確認して、問題がなければ手続き完了
自動車検査証返納証明書を受け取る場合には、申請手数料350円がかかります。
受付日時は、平日月曜日から金曜日の午前8時45分から11時45分、午後1時から4時まで(祝日および12月29日から1月3日を除く)となっていますので注意してください。
自動車検査証返納証明書とは、軽自動車を解体しない状態で一時使用中止の登録を行い、完了したことを証明する書類です。この書類によって軽自動車の所有者が誰であるか確認できるため、盗難されたとき不正流通できないようになっています。
書面に記載されている内容は、所有者の氏名や住所・登録番号・車体番号・車の型式・一時使用中止が行われた記録などです。
ちなみに普通自動車は、一時抹消登録を行うと「登録識別情報等通知書」が交付され、自動車検査証返納証明書と同じ役割を果たしています。
一時使用中止をした後の軽自動車の利用・解体について
軽自動車を一時使用中止した後、再び利用することになった場合や結局使わないので解体して処分するとき、どのような手続きを行えば良いのでしょうか。どちらのケースでも手続きが必要になりますので、方法を知っておくと安心です。
ここからは、一時使用中止をした後の軽自動車における利用・解体の手続き方法について詳しく解説していきます。

軽自動車を再び使用することになった場合は、中古新規登録手続きが必要になります。その際、車検も受けるため必要書類が多くなります。
手続きする際に必要な書類は、以下の通りです。
- 自動車検査証返納申請書
- 新所有者の住所を確認する書面 住民票や印鑑証明書(発行後3か月以内)
- 譲渡証明書
- 自動車損害賠償責任保険証明書
- 点検整備記録簿
- 保安基準適合証(交付を受けている場合は発行後15日以内)
- 申請依頼書(代理人が申請する際に必要)
- 新規検査申請書(軽第1号様式)
- 申請審査書
- 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 自動車重量税納付書
- 軽自動車検査票(持込検査のときは必要)
車検を受けるときに注意しなければいけないのは、一時使用中止している車は公道を走行することができないということです。検査場に車両を持ち込む際は、業者にレッカー移動を依頼するか、仮ナンバーの取得が必要になります。仮ナンバーを取得する際は、自賠責保険にも加入しなければなりません。
また、軽自動車は自動車保管場所証明書(車庫証明)を手続きの際に用意する必要はありませんが、自治体によっては、再登録後に「保管場所の届出」を警察署に提出するケースもありますので確認しておきましょう。
中古新規登録の流れは以下の通りです。
- 車検の検査予約を行う
- 軽自動車を軽自動車検査協会に持ち込み、車検を通す
- 軽自動車検査協会の窓口で中古新規登録の手続きを行う
- 税窓口で税金申告書を提出し、軽自動車税や自動車重量税を納税する
- ナンバープレートを受け取って取り付ける
一時抹消登録後、再び車を使用する場合は、車検を通して手続きを行うため、慣れない方にとっては難しいかもしれません。不安な方は、業者に代行して行ってもらうことをおすすめします。
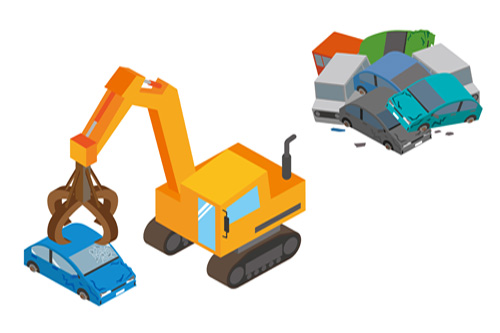
軽自動車を再び使うことなく解体処理を行う場合は、解体届出の手続きを行います。この手続きをする際は、事前に解体業者に依頼をして解体処理をしておく必要があります。
車の解体が完了すると、解体業者から「使用済自動車引取証明書」が渡されます。その証明書に記載されているリサイクル券番号(移動報告番号)の記入が必要になりますので、保管しておきましょう。
解体届出の際に必要な書類は以下の通りです。
- 使用済自動車引取証明書
- 解体届出書(軽第4号様式の3)
- 申請依頼書(所有者以外が手続きする際に必要)
解体届出は、自動車検査証返納届を行っている車が対象です。ナンバープレートや自動車検査証は返還しているため、必要書類が少なくて済みます。
なお、解体届出書と申請依頼書は、軽自動車検査協会事務局・支所窓口か協会ホームページでダウンロードができます。
また、解体届出にかかる費用は以下の通りです。
- 車両解体費…一般的な相場は1万円~2万円前後
- 車両運搬費…移動距離や業者によって異なるが5000円~1万円程度
解体届出の申請にお金はかかりませんが、事前に解体する際に費用がかかることを覚えておきましょう。
一時抹消登録(一時使用中止)を代理人が行うケースについて
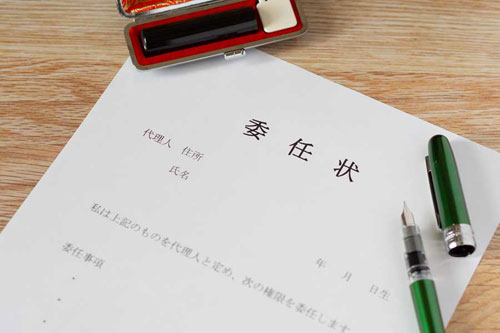
一時抹消登録(一時使用中止)を行う際に所有者が行わず、代理人が行うことがあるかもしれません。
ここからは、一時抹消登録を代理人が行うケースについて詳しくお伝えしていきます。
自動車検査証に記載されている所有者本人が、一時抹消登録(一時使用中止)の手続きを行えないときは、代理人が手続きをしても問題ありません。
申請書類に委任状(申請依頼書)を追加して提出することになります。
手続きや申請を代理人が行う場合、本人と代理人の関係が親族や血縁関係であることが条件になります。
しかし、廃車に関する手続きは、特別な制限は設けられていません。つまり、知人や友人、買取業者や解体業者などであっても、代わりに廃車手続きを行えるということです。
車の各種手続きは、事前に用意するものや専門知識が必要なケースが大半です。そのため、素人が手続きを行うにはハードルが高いといえます。
さらに、軽自動車検査協会や運輸支局は平日の日中のみ受付している関係上、仕事を休んで申請をする必要もあり、手間と時間がかかるのがネックです。
したがって、一時抹消登録のみならず、廃車手続きを行う際は、車買取業者や廃車専門業者に依頼して行うことも検討すると良いでしょう。廃車専門業者は、解体から廃車手続きまで無料で行っている場合もあります。
ご自身で手続きするのが不安な場合は、専門業者に相談してみることをおすすめします。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?








