軽自動車を所有している方や、これから購入を検討している方の中には、8ナンバーにすることを考えているという人もいるでしょう。しかし、8ナンバーにすると何が変わるのでしょうか。
この記事では、8ナンバーの概要や取得条件について詳しく解説します。届け出の具体的なやり方や、メリット・デメリット、そして車検費用についても解説しますので、8ナンバーにするか迷っている方はぜひ参考にしてください。
8ナンバーとは?

8ナンバーとは、「特殊用途自動車」のことです。ナンバープレートに「8」の数字が記載されていることから、8ナンバーと呼ばれています。
例えば、警察車両・消防車・給水車など、特定の用途に使用されていたり、特殊な設備を備える自動車を指します。
8ナンバーの「8」は、自動車の種類を示す数字のことです。自動車の種類には、特殊用途自動車以外にも、乗用自動車と乗合自動車・建設機械・貨物自動車があります。
8ナンバーの種類
8ナンバーの種類は、以下の4つがあります。
- 緊急自動車
- 特定の事業に使用する自動車
- 運搬や医療介護に使用する自動車
- その他の使用目的がある自動車
緊急自動車とは、パトカー・消防車などの自動車のことです。緊急時に使用される自動車を指します。
特定の事業に使用する自動車とは、給水車・霊柩車・教習車などです。法令で定められた特定事業で使用する車が当てはまります。
運搬や医療介護に使用する自動車とは、寝台自動車・リフト車などです。緊急車両や特殊事業以外で、特定の作業目的に使用される自動車を指します。
その他の使用目的がある自動車とは、キャンピングカー・宣伝カーなどです。
軽キャンピングカーの場合、4ナンバー(貨物用軽自動車)、5ナンバー(乗用軽自動車)、8ナンバー(小型特殊軽自動車)の3種類があり、種類によって手続き方法が異なるため、注意が必要です。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車が8ナンバーを取得する条件

軽自動車が8ナンバーを取得するためには、「キャンピング車」としての要件を満たす必要があります。具体的には、就寝設備の数、調理スペースの大きさ、積載スペースと乗用スペースの仕切り、特殊設備の面積、貯水排水設備、室内の高さを満たす要件です。
就寝設備の数は、乗車定員の3分の1以上の大人用就寝設備が備わっている必要があります。乗車定員が2人以下の場合は、大人用が1人以上あれば問題ありません。
調理スペースの大きさは、調理台等調理に使用する場所が、0.3m以上×0.2m以上の平面であることが必要です。また、コンロなどで炊事ができること、耐熱性や耐火性があること、換気が行えることが条件です。
また、8ナンバーの要件には、積載スペースと乗用スペースに仕切りを設ける基準もあります。仕切りは、適切な隔壁や保護仕切りが必要です。
さらに、特殊設備の面積は運転席を除く床面積の半分を超えていること、10L以上の貯水排水設備が備わっていること、室内の高さが1,600mm以上であることも要件に含まれます。
もし調理台の高さが850mm以下なら、天井の高さは1,200mmでも要件を満たします。
8ナンバーを取得するための手続き

軽自動車が8ナンバーを取得するためには、8ナンバー取得に必要な設備を備え、構造変更の届け出を行います。
それぞれ必要な内容について、詳しく見ていきましょう。
8ナンバーを取得するためのキャンピングカーは、構造要件を満たす必要があります。構造要件は車両の要件のほか、車室内で居住するための設備を設置する要件もあります。
例えば、冷蔵冷凍車の場合、部品積載設備や冷凍装置が必要です。一方でキャンピングカーの場合は、大人が十分に就寝できるスペースを確保する必要があります。就寝スペースは座席との併用が可能で、格納式や折り畳み式でも問題ありませんが、上面全体が連続した平面となる必要があります。
また、水道設備は10L以上のタンクを設置し、洗面台などに水を供給できる構造でなければなりません。
調理スペースにLPガスを設置する場合は、車室内と隔壁で仕切られ、換気が十分にでき、衝撃を受けても損傷しない場所に取り付ける必要があります。
軽自動車を8ナンバーに変更する場合は、軽自動車検査協会でナンバープレートの変更手続きをする必要があります。なお、普通自動車の場合は、運輸支局での手続きです。
申請書は、軽自動車検査協会に用意されています。書類は2号様式で、書き方を確認しながら自宅などで記載したい場合は、軽自動車検査協会のサイトからダウンロードすると便利です。
ナンバープレートの変更手続きでは、以下の必要書類を忘れないようにしてください。
- 車検証
- 自動車重量税納付書
- 軽自動車税種別割納税証明書
- 手数料納付書
- 自賠責保険証明書
- 自動車検査票
- 点検整備記録簿
必要書類は、車検証と一緒に保管されていることがあります。しかし、軽自動車税は各自で支払っており、支払いを証明する書類は別に保管されていることが多いため、注意が必要です。
また、記載間違いがあった場合に修正するため、認印も持参してください。手続きを代行してもらう場合は、委任状も必要です。
構造変更検査とは?
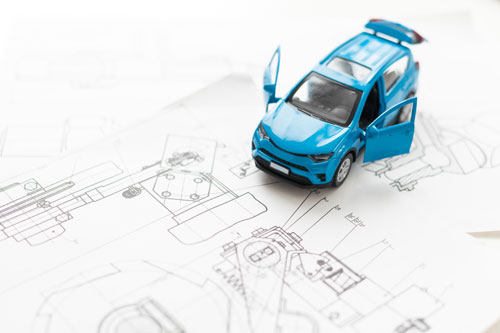
構造変更検査とは、軽自動車が保安基準に適合しなくなる場合に受ける検査のことです。自動車の高さ・長さ・幅・最大積載量・乗車定員・車体形状を変更した場合は、構造変更検査を受ける必要があります。
軽自動車の場合は、高さ±4cm・長さ±3cm・幅±2cm・車両重量±50kg以上の変化があった場合に構造変更検査が必要です。ただし、軽微な変更の場合、構造変更検査が不要で記載変更のみで済みます。
大幅な改造を加えているのにも関わらず構造変更検査を受けない場合は、違法改造とみなされます。車検に通らないばかりか、懲役6ヶ月または罰金30万円が課せられる恐れもあります。
構造変更検査に合格したら、8ナンバー取得前に行う手続きがあります。まずは、検査で確定した重量税を軽自動車協会で支払わなければなりません。
続いて、持参した書類を提出しましょう。書類に問題がないことが確認されると、新しい検査標章(ステッカー)と車検証が交付されます。
古いナンバープレートはプラスドライバーを使用して取り外し、返納窓口に返却します。新しいナンバープレートの代金を支払うと、新しいナンバーが交付されるので、自分で新しいナンバープレートを取り付けてください。
古い検査標章を剥がし、新しく交付された検査標章に貼り替えましょう。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
8ナンバーのメリットは?

軽自動車が8ナンバーになると、いくつかのメリットがあります。
費用面や手間の軽減などのメリットがあるため、8ナンバーに変更する前に確認しましょう。
軽自動車が8ナンバーになると、自動車税が安くなります。
5ナンバーの普通軽自動車は、平成27年4月1日以降に新規登録された自動車税は10,800円です。
一方、8ナンバーの軽キャンピングカーの場合、自動車税が5,000円に減税されている地域があります。それは、8ナンバーの軽キャンピングカーを四輪貨物と分類している地域の場合です。
ただし、自治体によっては5ナンバーの普通軽自動車と同額に設定している地域もあるため、注意が必要です。詳しくは、お住まいの自治体ホームページなどでご確認ください。
自賠責保険とは、自動車を使用する際に強制的に加入する保険のことで、車検時に支払っています。
自賠責保険料は、自家用乗用車の場合24ヶ月で17,650円ですが、8ナンバーの「特殊用途自動車」で「三輪以上の自動車(軽自動車を除く)」の場合は19,980円となり、保険料が高くなります。
一方で、軽自動車の場合は、8ナンバーになると自賠責保険料が安くなるのが特徴です。詳しい保険料の額は、車検の項目で詳しく解説します。
なお、自賠責保険は、年々値下がり傾向が見られています。料金が適切なのかどうか毎年審議が行われており、年によっては前回よりも自賠責保険料が下がることもあります。
8ナンバーの軽自動車の車検は2年に1回のサイクルです。普通貨物車は1年に1回、車検を受ける必要がありますが、軽自動車の場合は普通車でも貨物車でも2年に1回の車検となります。
2年に1回の車検で済むと、車検時にかかる費用の支払いが2年サイクルとなるため、計画的に車検費用を積み立てられる点がメリットです。
また、毎年車検がある場合はその都度税金や検査費用が発生するため、2年車検のほうが全体的にお得になります。
8ナンバーの軽自動車の場合、普通貨物車と比べて高速道路の料金が安くなります。8ナンバーの軽キャンピングカーは、軽自動車と同じ扱いになるためです。
キャンピングカーの場合、車体が大きくなるため、軽キャンピングカーでも普通車と同等の高速道路料金がかかる恐れがあります。しかし、8ナンバーなら軽自動車の扱いとなり、休日割引や深夜割引も同じように受けられるため、高速道路料金がお得です。
特に遠出することが多いキャンピングカーユーザーにとっては、高速道路の料金差は気になる部分でしょう。高速道路料金が普通車扱いか軽自動車扱いかで、走行距離によっては1,000円以上の料金が変わることがあるため、見逃せないポイントです。
8ナンバーのデメリットは?

軽自動車が8ナンバーになるとメリットがある一方で、デメリットも存在します。
8ナンバーになることで逆に手間やコストがかかる可能性に注意が必要なため、詳しく解説します。
8ナンバーを扱わない保険会社があるため、軽自動車が8ナンバーになると、任意保険会社を選ぶのが面倒になる可能性があります。
8ナンバーは特殊用途自動車に該当するため、取り扱える保険会社が少ないのが理由です。
特殊用途自動車はキャンピングカーも含まれますが、警察車両や消防車両など特殊な車両が多いため、扱っていない保険会社が多い状況です。特にキャンピングカーの場合は、車両ごとに形状や設備が異なるため、保険料を決めるデータが不足しており、対象外とする保険会社が少なくありません。
ちなみに一般の保険会社が扱う自動車保険は、自家用5種とされる車両が対象です。軽自動車・普通自動車・軽貨物自動車・小型貨物車・小型乗用車のみを対象とする保険会社が多いため、8ナンバー対応の保険会社選びは手間がかかります。
軽自動車を8ナンバーにするには、要件を満たす必要があります。追加で設備を導入する必要があり、その費用がデメリットです。
例えば、ベッド・キッチン・トイレなどの設置費用がかかります。設備を入れるために車両の内部構造を変更する必要があるため、8ナンバーに変更する際の初期費用が高額になる可能性があります。
また、8ナンバーになった後も、設備の整備費用が必要です。調理器具や水道設備を導入した場合、定期的なメンテナンスが必要で、故障時には交換費用が発生します。
8ナンバー車の車検費用は?

軽自動車が8ナンバー車になると、車検費用が変わります。車検にかかる工賃や整備費用のほか、税金や保険料なども変わってくるため、確認しておきましょう。
車検料金とは、車検を代行する費用のことです。依頼する業者によって料金が異なります。
8ナンバーの場合は、普通乗用車とは異なる特殊な設備が備わっているため、車検料金を高めに設定している業者が多い傾向です。車検料金には、点検料・検査料・車検代行手数料が含まれています。
車を車検に通すには、走行に問題がない状態である証明が必要となるため、点検や検査が必要です。点検料や検査料は、業者によっては「整備料」と表記されている場合があります。
車検に通せる状態ではない場合は、追加で部品の交換や整備が必要となるため、その料金は別途必要です。特に8ナンバーの場合は、設備の点検や整備も必要になるため、普通乗用車と比べて車検料金が高額になりやすい特徴があります。
普通乗用車の車検料金は安い場合で1万円代から数万円程度ですが、8ナンバーはさらに高額になることが一般的です。
自賠責保険料とは、公道を走る際に必ず加入しなければならない自動車保険の料金のことです。
自動車に対する保険は、自賠責保険と任意保険の2種類があり、任意保険は加入しなくても問題ありませんが、自賠責保険に加入しないと車検に通りません。
すべての自動車が自賠責保険に加入する理由は、交通事故を起こした際に被害者へ支払う損害賠償を補てんする意味があるからです。被害者が死亡または重度の後遺障害を負った場合、高額な賠償金が発生するため、個人で支払えないリスクを回避する目的があります。
自賠責保険料は車種や用途によって異なります。2023年の自動車損害賠償責任保険基準料率によると、8ナンバーの軽自動車は「特殊用途自動車」に分類されており、24ヶ月で11,290円です。軽乗用車の場合は24ヶ月で17,540円であるため、8ナンバーの軽自動車は通常より自賠責保険料が割安です。
8ナンバーの車検は2年ごとであるため、自賠責保険料も24ヶ月の支払いが必要になります。
重量税は、車両総重量によって異なります。8ナンバーの軽自動車の場合、1トン以下では8,200円、2トン以下では16,400円です。
一方、軽乗用車の場合は一律で6,600円です。8ナンバーの軽自動車は装備が多くついている場合もあり、重量税が割高になってしまいます。
車検の印紙代は、検査手数料として支払う料金のことです。
印紙代は、車検を依頼する業者が「指定工場」か「認定工場」かによって異なります。指定工場は軽自動車検査協会へ行かなくても保安基準適合証の交付を受けられるため、印紙代が安くなります。一方で、認定工場は軽自動車検査協会に車を持ち込む必要があるため、印紙代が高くなるのが特徴です。
- 指定工場:1,800円
- 認定工場:2,200円
車検時に支払う印紙代には、国に納める検査登録印紙と、機構に納める自動車審査証紙の2種類の料金が含まれています。印紙は、税金を納めたことを証明するもので、車検を依頼した業者が代わりに購入しています。
印紙代を安くしたい場合は、指定工場が多いディーラー・車検専門店・自動車販売店などに車検代行を依頼すると良いでしょう。
車検の検査ラインを持たない業者は認定工場に分類されます。








