初めて車を購入した人にとって、これから払うであろう税金は気になるポイントです。軽自動車であれば普通車と比べて金額は少ないとされていますが、支払いのタイミングなど不慣れであれば不安に思う人も少なくないでしょう。
この記事では、軽自動車の税金を支払うタイミングはいつなのか解説します。また、金額や納付方法、注意点についても解説するため、この記事を読めば税金に関する不安が払拭されるでしょう。
軽自動車税は通知書に記載されている期間内に支払う

大原則ですが、軽自動税の支払いについては通知書に記載されている内容をよく確認しましょう。
軽自動車税は、毎年4月1日に車を所有している人が支払わなければならない税金です。市区町村から納税通知書が送付されるため、記載されている内容に沿って処理しましょう。多くの自治体では納期を普通車と同じ5月末日と定めています。
滞納してしまうと車検を受けられないため注意が必要です。車検を受けられなければ「無車検車」に該当し、罰則が科された上に免許停止処分が下されます。
軽自動車税は2種類ある

ここからは、軽自動車税について詳しく紹介していきます。
大きく分けて2種類の税金によって軽自動車税は構成されており、課される内容によって名称や課税タイミングが異なります。そのため、正確に違いを把握しておきましょう。
環境性能割は車を購入し、取得したタイミングで課税される税金です。三輪以上の車両を購入する際の取得金額に応じて金額が決定されます。
「取得価額×税率」が算出方法として定められており、燃費基準の達成度などに応じて非課税もしくは1~3%で税率が決定されます。
例えば、200万円の車を購入した場合、2020年度の燃費達成基準をクリアしていれば20,000円が税金として徴収されるイメージです。
非課税になる車は電気自動車など環境性能に配慮された車種が該当します。
この税金は車の取得時に1回のみ課税されるため、購入時の初期費用の一部と考えて差し支えないでしょう。
種別割は毎年4月1日時点で軽自動車や原動機付自転車などを所有している人から徴収される税金です。
所有車両を使用する場所(つまり住んでいる場所)を管轄する市区町村が課す地方税の一部であり、毎年徴収されます。そのため、環境性能割と違って車を維持するためのランニングコストです。
普通車と同じように5月末日を納付期限としており、翌年3月末日までの1年間分の税金を前払しています。
税率は車種や排気量によって区分けされており、毎年一定の金額を納めなければなりません。ただし、初回登録から13年以上経過した車に関しては課税額が上がります。そのため、13年経過したタイミングで車の買い替えを検討する人も少なくありません。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車税を支払うタイミング

軽自動車税を支払うタイミングについては、納税通知書に記載されている納付期限を確認しましょう。納付期限までに納付できなければ滞納扱いとなるため注意が必要です。
税金に関する書類は原則として、毎年5月初旬から中旬にかけて車検証に登録されている住所に送付されます。そのため、年度の途中で引っ越しをした場合には車検証の住所更新を忘れずに行いましょう。
支払方法は銀行や郵便局、コンビニエンスストアでの店頭支払いです。自治体によってはクレジットカード決済やスマホ決済、電子マネー決済など多種多様な支払方法に対応しています。
ただし、店頭支払い以外の方法で納税した場合、領収書が発行されない点に注意しましょう。領収書が必要な場合は店頭で支払うことをおすすめします。
軽自動車税の金額

軽自動車税の金額は車種区分や用途によって金額が定められています。
大項目として「四輪」と「三輪」に区別されており、四輪の方が税額は高額です。
また、四輪の中でも「乗用」と「貨物用」に分類されます。そして、それぞれの用途に応じて「自家用」と「営業用」にさらに区別されており、自家用の方が税金は高額です。
例えば、四輪で自家用車の場合、税額は年間で10,800円です。同じ四輪でも営業用は6,900円であるため、およそ1.6倍の金額差があります。
とはいえ、普通車(自動車税)に比べると軽自動車税の金額は安価に設定されています。自動車税も排気量に応じて金額は変わりますが、排気量の最も少ない1,000cc以下であっても25,000円です。2倍以上の金額差が発生するため、軽自動車はコスパに優れた車種といえるでしょう。
軽自動車税の納付方法
税金の支払い方法はいくつかありますが、最寄りの銀行や郵便局といった金融機関の窓口もしくは、コンビニで支払うことができます。
自治体によっては電子決済も利用可能で、バーコード決済やクレジットカード決済を利用できれば、現金の用意が不要なため簡単に支払えます。ただし、領収書が出ない点に注意しましょう。領収書が必ず必要な人は窓口での支払いをおすすめします。
ここからは、軽自動車税の納付方法について詳しく解説していきます。

1つ目の方法は納税通知書を利用した現金納付です。
毎年5月の初旬から中旬にかけて納税通知書が送付されます。送付された納税通知書をもって金融機関の窓口やコンビニで支払いましょう。
また、市区町村の役所の納税課でも支払いができるため、役所での用事があれば合わせて納税できます。
メリットは支払いが簡単に完結することでしょう。さらに支払い完了後は領収書が発行されます。領収書が必要な方にとっては外せない方法です。
デメリットは納税のために外出しなければならないことです。そのため、利用のしやすいコンビニ支払いを選ぶ方も少なくないでしょう。
2つ目は口座振替を設定して納付する方法です。支払いを忘れやすい人にとっておすすめです。
メインバンクの銀行口座と紐づけることで、時期になれば自動的に引き落とされるため、納付のために出かける必要もない点がメリットでしょう。
ただし、事前の手続きを済ませなければ利用できません。手続きの際に必要なものとして、例えば口座の預金通帳や届出印、車検証等の自動車の登録番号がわかる書類が挙げられます。そのため、書類の準備に手間がかかる点はデメリットかもしれません。
さらに、口座内に十分な預金を確保しておく必要もあります。残高不足であれば引き落とされないため、気づかないうちに滞納してしまっているリスクもあるでしょう。
3つ目はクレジットカードに紐づけて納付する方法です。各自治体の支払いサイトを経由してオンラインで決済します。
納付するために外出する必要がなく、自宅で簡単に支払える点が魅力です。ただし、納税時に手数料が330円(税込)ほど発生する点には注意しましょう。手数料を支払いたくない場合、他の納付方法を選ぶことをおすすめします。
また、納付後に車検用の納税証明書は郵送されません。陸運局では電子的に情報を保存しているため問題はありませんが、システムへの情報反映に3週間ほどかかるため、車検の直前に納付することは避けましょう。
4つ目はペイジーに登録して納付する方法です。一部の都道府県で利用できる支払方法であるため、利用可能かは事前の確認が必要です。
ペイジーは各種税金や電話料金の支払いに利用される決済方法です。ペイジー用の支払い番号を用意し、提携の金融機関ATMもしくはインターネットバンキングを利用して支払います。そのため、支払い用口座の残高には注意しておきましょう。
残高がなければ口座振替と同様に納付できません。とはいえ、残高不足がわかれば必要な金額を預け入れれば支払えるため、滞納のリスクはないでしょう。

5つ目はスマートフォンを使用して納付する方法です。
昨今、PayPayをはじめとしたバーコード決済など様々なオンライン決済の方法ができています。自宅で支払いが完結し、いつでも手続きができるため、忙しくて支払いに行けない人にとっては便利な方法といえるでしょう。
ただし、スマートフォンで納付した場合も領収書が発行されません。そのため、領収書が必要な人にとっては避けた方が良い方法です。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
軽自動車税の節税方法

軽自動車税は、車を購入したタイミングや毎年決まった時期に支払わなければならない税金ですが、節税方法はあるのでしょうか。
税金の種別によって軽減措置が定められています。そのため、措置内容に沿えば、いくらか支払金額をおさえられるでしょう。また、車の購入時期によっても金額は変わります。
事前に知っておけば節約できるお金があるため、ここから紹介する内容を参考にして車の購入を検討してみてください。
軽自動車税(種別割)は、環境性能の高い車に対して優遇措置が設けられています。これを「グリーン化特例」と呼びます。
対象となるのは、電気自動車や燃料電池自動車など、排出ガスが少なく燃費性能に優れた車両です。
グリーン化特例が適用されると、翌年度の軽自動車税(種別割)が最大で75%軽減されます。具体的な軽減率は車種や性能に応じて25~75%の軽減が適用されます。
この特例は軽自動車に限らず、普通自動車にも適用可能です。特に普通自動車ではプラグインハイブリッド車も対象となるため、購入を検討する際には環境性能を重視することで、翌年度以降の維持費を大幅に抑えられます。新規登録時に適用されるため、購入時期にも注意しておきましょう。
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で車を所有している人に課税される仕組みです。したがって、4月2日以降に軽自動車を購入すれば、その年度分の軽自動車税を支払う必要はありません。この購入タイミングを意識することで、1年分の税金を節約できる可能性があります。
一方、普通自動車にかかる自動車税(種別割)は年度途中に取得した場合、取得月の翌月分から月割で課税される仕組みです。そのため、普通自動車の場合は購入時期が月初か月末かで税金の支払い額が変わりません。むしろ月初に購入する方が、その分早く車を利用できるというメリットがあります。
軽自動車の場合は、4月1日を過ぎてから購入するだけで税金面での恩恵があるため、購入時期についてはよく検討することをおすすめします。
軽自動車税の支払いに関する注意点
ここからは、軽自動税を支払う際に注意しておきたいポイントについて紹介します。
税金であるため、基本的に気を付けなければならないポイントは「遅延」でしょう。滞納している状況に陥ってしまえば無駄なお金が発生します。
また、納税すると証明書を受け取れます。特に気にせずに受け取っている人がほとんどかと思いますが、車検のある年には大事に保管しておかなければなりません。
さらに税額が上がるタイミングが合ったり、誤って支払ってしまった場合など様々な注意点があるため、おさえるべきポイントをよく理解しておくことが重要です。

支払期限内に納付が完了しなければ、税金を滞納している状況になります。結果として延滞金が発生することで、無駄なお金を支払わなければなりません。
延滞金の金額は支払いが完了したタイミングによって異なります。基本的には納付期限の翌日から滞納機関のカウントが始まります。納付期限の1か月後を境に金額が大きく変わるため注意が必要です。
例えば、納付期限翌日から1か月以内に支払い終える場合、当初の納税額に「納税額×2.4%」の延滞金が発生します。
1か月を超えた場合は「納税額×8.7%」まで金額が上がります。長期間の遅延は悪質性を問われるためでしょう。
さらに納付をしなければ、最終的に財産を差し押さえられるかもしれません。
期限内に支払うことは軽自動車税だけではありません。どのような税金においても支払いが遅れてしまえば延滞金は発生するので注意しておきましょう。
軽自動車税を納付すると納税証明書が発行されます。この書類は車検時に必要です。書類を紛失してしまったり、車検までに間に合わなかったりした場合は車検を受けられません。
普通車はオンラインで納税の確認ができるようになったため、原則として納税証明書の提出は不要になりましたが、軽自動車は従来通り紙書類の提出が必要です。
とはいえ、クレジットカード決済やモバイル決済による納税ができるようになったため、オンライン確認はできます。ただし、支払ってから確認ができるまでに時間を要するため、車検直前の納付である場合は現金決済により証明書を受領するようにしましょう。
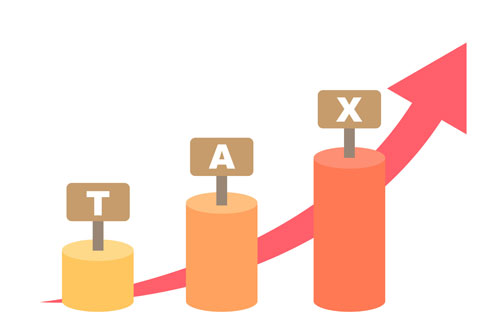
普通車にも共通する内容ですが、車の使用年数が13年を超える場合、税額が増加します。このことを「経年車重課」といいます。
増額する理由は、使用年数がかさめば最新のエコ技術を搭載していない車になるため環境負荷が高いためです。環境負荷の低減が主な理由だとしても、税額はおよそ20%も増加するため、ユーザーにとっては大きな負担となるでしょう。
また、自動車重量税においても経年重課が適用され、13年目と18年目に大きく税額が変わります。
普通車(自動車税)の場合、年度途中で車を廃車、譲渡すると月割りした税金が還付されます。
しかし、軽自動車(軽自動車税)で同じような状況になったとしても還付はされません。
普通車と同じように考えていると損をした気分になりますが、あらかじめ覚えておきましょう。
延滞期間が1か月以内であれば納税額の2.4%分、1か月以上延滞していれば納税額の8.7%分が延滞金として徴収されます。
具体的な金額は次の通りです。
四輪車の乗用かつ自家用であれば税額は10,800円であるため、延滞金の金額は延滞期間が1か月以内であればおよそ260円、1か月以上であればおよそ940円となります。さらに滞納し続けると財産を差し押さえられる可能性もあるため、速やかに支払いましょう。








