軽自動車の購入を検討しているなら、国や自治体が提供する補助金制度を活用して賢く費用を抑えるのがおすすめです。特に、電気自動車(EV)やハイブリッド車など環境性能に優れた次世代自動車には手厚い補助が用意されており、購入時の負担を大きく軽減できます。
この記事では、補助金の種類や申請手続きのポイント、さらに減税制度との併用方法などをわかりやすく解説します。
お得に軽自動車を購入するための知識を身につけましょう。
軽自動車の購入は補助金を活用しよう

軽自動車を購入する際、少しでも費用を抑えたいと考えるのは誰しも同じです。そのようなとき、知っておきたいのが、国や地方自治体が提供する補助金制度です。
これを活用すれば、購入時の負担を大幅に軽減できます。特に環境に優しい次世代型の車には、手厚い支援が受けられるため、新車購入を考えている人には見逃せません。
ここからは、近年注目されている新しい補助金制度や軽自動車を購入する際に使える補助金について詳しくご紹介します。
新車の軽自動車を購入時に活用できる補助金
新車の購入は家計に大きな影響を与えますが、補助金制度をうまく活用すればその負担を軽くできます。
中でも、国の提供するクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)は、多くの人にとって注目すべき制度です。また、自治体ごとに異なる補助金も合わせて利用することで、さらなる節約が期待できます。
まずは基本的な補助金について見ていきましょう。
環境に配慮した次世代自動車を支援するために設けられたのが、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金、通称「CEV補助金」です。
この制度の対象となるのは、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)、プラグインハイブリッド車(PHV)など、環境負荷の少ない車両です。クリーンディーゼル車や超小型モビリティも含まれているため、環境を意識した軽自動車選びをする際に心強い支援となるでしょう。
補助金を受け取るためには、車の登録時期や条件に応じた申請が必要であり、申請手続きに関する情報は事前にしっかりと調べておくことが大切です。ディーラーや販売店でも詳しく案内してもらえるため、購入時に相談するのがおすすめです。
国の補助金制度に加え、自治体ごとに提供される独自の補助金制度も大きな魅力です。
例えば、札幌市では、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の購入に対して最大30万円の補助が設けられています。
東北地方では、岩手県金ケ崎町がハイブリッドカー購入者に対して5万円の補助を提供するなど、地域によって支援内容が異なるのが特徴です。
また、神奈川県では燃料電池車(FCV)を購入する際に最大101万円の補助を受けられる制度があり、非常に大きな経済的メリットを得られます。
さらに福井県では、次世代自動車普及促進事業補助金として、FCVの購入時に最大100万円の補助を提供しており、これは国のCEV補助金と併用可能です。
ただし、各自治体の補助金制度は地域ごとに異なるだけでなく、申請できる期間や条件も限定されている場合があります。そのため、車を購入する際には、自分が住んでいる地域の公式サイトや自治体の窓口でしっかりと情報を収集し、適切なタイミングで申請することが大切です。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?
CEV補助金の対象車、金額、申請方法について
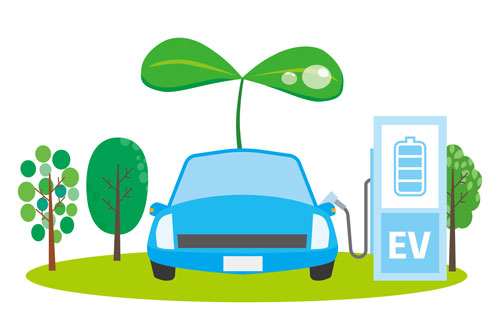
環境に配慮した車の購入を考えているなら、ぜひ知っておきたいのが、CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)です。国の支援を受けることで、これまでよりもハードルが高く感じられたエコカーが、手の届きやすい選択肢に変わるかもしれません。
ここでは、補助金の対象車、金額、申請方法について詳しく解説します。
補助金を受けるには、対象となる車種であることが条件です。それは、電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池車といった環境性能が優れた次世代車です。
近年では、軽自動車にもこれらの技術が積極的に導入されており、軽EVなども対象車両に含まれます。
ただし、補助金の適用範囲は国の政策だけでなく、地域ごとに異なる場合もあります。具体的な対象車両のリストは、一般社団法人次世代自動車振興センターなどが公表しているため、必ず事前に確認しましょう。
また、自治体ごとの独自補助金が追加で受けられることもあるため、住まいの自治体の制度も調べておくと良いでしょう。

補助金の金額は車種ごとに異なり、令和5年度補正予算に基づく場合、電気自動車(EV)では最大85万円、軽EVでは最大55万円、プラグインハイブリッド車(PHV)も最大55万円となっています。また、燃料電池車(FCV)には、上限255万円という高額な補助が用意されています。
ただし、メーカー希望小売価格が840万円を超える車両の場合は、補助金額に0.8を乗じた金額が適用される仕組みです。高級車ほど補助金の割合が抑えられる点には注意が必要。
具体的な補助額は対象車両によって異なるため、購入前に次世代自動車振興センターのWebサイトで確認しておくと安心です。
補助金の申請にはタイミングが重要です。令和5年度補正予算におけるCEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の総額は、約1,291億円に上り、2024年3月28日から申請受付が開始されています。
しかし、この補助金には予算の上限があり、予算が消化され次第受付が終了する早い者勝ちの制度です。そのため、車を購入したらすぐに申請することが推奨されます。
申請期限を逃すと補助金を受け取れないため、購入時期の計画や情報収集は欠かせません。補助金制度の最新情報や予算の消化状況は、公式Webサイトで随時確認するようにしましょう。
補助金を受けるには、車両を購入した後、1ヶ月以内に申請を行う必要があります。申請に必要な書類は、以下の通りです。
- 交付申請書
- 本人確認書類
- 車検証の写し
- 購入時の領収証の写し など
これらの書類を揃えた上で、指定された方法で次世代自動車振興センターに提出します。
申請は郵送またはWebを通じて行えますが、書類の不備や提出の遅れが発生すると手続きが長引く恐れがあります。そのため、事前に必要書類をしっかりと確認し、ディーラーなどと連携して手続きを進めるのがベストです。
さらに、個人が電気自動車を購入する場合には、J-クレジット制度への参加も必要です。この制度は、環境に配慮した活動による二酸化炭素の削減効果をクレジットとして取引する仕組みであり、補助金の申請時には登録が必須となっています。
審査の進捗状況については、次世代自動車振興センターの公式Webサイトを定期的に確認することをおすすめします。Webサイト上には申請状況の確認方法が詳しく案内されており、自分の補助金申請がどのステータスにあるかを確認できます。
また、進捗が遅れているように感じた場合は、問い合わせ窓口を活用して状況を把握するのも一つの方法です。
補助金と一緒に減税ができる「グリーン化特例」とは?

環境に優しい車を購入する際、補助金だけでなく税金面でも優遇されるのがグリーン化特例です。
この制度は、電気自動車やハイブリッド車、クリーンディーゼル車など、環境性能の高い車を所有している場合に適用される減税制度です。同時に、古く環境負荷が大きい車には増税が課される仕組みになっています。
対象となる税金は自動車税および軽自動車税です。
エコカーを選ぶことで購入後の維持費を抑えられ、補助金と組み合わせることで、さらに経済的なメリットが期待できます。
ここからは、グリーン化特例について詳しく解説していきます。
当初、グリーン化特例は2023年度末で終了予定でしたが、政策変更により2026年4月まで延長されることが決定しました。この延長によって、要件を満たす軽自動車であれば引き続き減税が適用されます。
例えば、電気自動車やプラグインハイブリッド車、燃料電池車などの環境性能の高い車を所有している場合、自動車税や軽自動車税が約75%減税されるケースもあります。これにより、環境性能の高い車を購入する経済的メリットが一段と大きくなりました。
なお、税制度は毎年見直される可能性があるため、最新情報を自治体の公式サイトなどで確認することが重要です。
グリーン化特例の対象となる車両は、年々条件が変化している状況です。
2024年からは対象条件がより厳しくなり、すべてのクリーンディーゼル車が一律に減税されるわけではなく、車種ごとに25%~100%の減税率が設定されています。
また、電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)については、引き続き免税対象とされており、非常に優遇されています。
ただし、注意すべき点として、2025年5月以降にはさらなる条件の見直しが予定されており、現行の基準での優遇が必ずしも将来まで続くとは限りません。そのため、これから軽自動車を購入する場合は、その時点での最新の基準を必ず確認することが大切です。
特に、新たな規制が導入されるタイミングでは、適用条件の細部が変更される可能性があるため、最新情報を常にチェックし、購入のタイミングを見極めることが求められます。

グリーン化特例の減税率は、車両の環境性能に応じて3段階に分かれています。環境性能が特に高い車には75%の減税が適用され、それ以外の車種には50%や25%の減税が適用される仕組みです。
例えば、電気自動車や燃料電池車は、ほとんどのケースで75%の減税が受けられるため、毎年支払う税金が大幅に軽減されます。
一方で、初度登録から13年以上が経過したガソリン車や11年以上経過したディーゼル車は増税対象です。古い車両に対しては、自動車税が約15%増税され、軽自動車税も約20%引き上げられます。
お得に車を所有したいなら、減税率の高い車に買い替えたほうが良いでしょう。
エコカー減税は、自動車重量税が対象となっており、車両の燃費基準をクリアすることで減税が適用される仕組みです。例えば、電気自動車や燃料電池車など、環境性能の高い車を購入する場合には重量税が免除されるか、大幅に減額されます。
一方、環境性能割は2019年に導入された新しい課税制度で、新車購入時に課せられる税金です。この制度では、車の燃費性能や排出ガスの基準を満たすことで税率が軽減されます。車種によっては購入時の税負担が大きく異なるため、車を選ぶ際には環境性能割の適用状況を確認することが重要です。
補助金を利用する際の注意点
電気自動車や燃料電池車などの次世代自動車を購入する際、補助金制度は大きな経済的メリットをもたらします。
しかし、補助金は無条件に支給されるわけではなく、申請手順や条件を満たさなければ受給できません。また、申請期限や予算枠の制限、受給後の車両保有期間といった細かなルールを知らないと、予期せぬトラブルにつながることもあります。
ここからは、補助金を利用する際に知っておきたいポイントを詳しく解説します。

補助金制度の多くは、国や自治体が設定した限られた予算内で実施されており、その予算が上限に達した時点で受付が終了します。
国が提供するCEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)も、年度ごとに予算が決められており、申請は基本的に先着順です。そのため、予算が尽きてしまった場合、申請しても補助金は受け取れません。
このようなリスクを避けるためには、車を購入する前に必ず補助金の予算状況を確認することが重要です。特に、人気の車種や新型車の発売時期には申請が殺到し、予算消化が早まることがあります。
また、年度末には予算枠が埋まりやすいため、スケジュールに余裕を持ち、できるだけ早めに行動するよう心がけましょう。
補助金を受けて購入した車には、一定期間の保有義務が課されることが一般的です。この期間は「処分制限期間」と呼ばれ、多くの場合、3年から4年程度が設定されています。
この期間内に車を売却、譲渡、または廃車にした場合、受け取った補助金の一部を返還しなければなりません。例えば、3年間の保有義務がある車を2年目に売却した場合、補助金の50%を返納するケースが多く見られます。
ただし、事故や天災による廃車など、やむを得ない事情がある場合は例外が認められることも。この場合、自治体や補助金の管理機関に事情を申告し、審査を経て返還義務が免除または軽減されることがあります。
車の購入を考える際には、この保有期間のルールをしっかりと理解し、計画的に車を使うことが大切です。
補助金は、車両の代金を全額支払った後に申請し、審査を経てから支給されます。
多くの人が誤解しがちですが、補助金は購入前に前払いされるものではありません。そのため、車両購入時には全額分の資金をあらかじめ用意しておく必要があります。
申請から補助金が交付されるまでには、通常1〜2ヶ月程度かかるとされていますが、審査が混み合う時期にはさらに時間がかかる場合もあります。
また、ローンで車を購入する場合でも補助金を受け取れますが、申請には領収証や支払い証明書などの書類が必要です。これらの書類が不備なく揃っていないと審査が遅れる原因になるため、購入時にしっかりと確認しておきましょう。
補助金には申請期限や予算枠が定められているため、これらを無視してしまうと補助金を受け取れない可能性があります。
特に、年度ごとに予算が設定されている場合、締切日や予算消化状況によって申請できるかどうかが決まります。そのため、最新の情報をこまめにチェックし、早めに必要書類を準備することが大切です。
地方自治体が提供する補助金制度も同様に、限られた予算内で運用されているため、地域によっては競争率が高くなる場合があります。
申請が遅れると受付終了に間に合わないことがあるため、購入を検討し始めた段階から制度の詳細を確認しておくと安心です。また、申請書類に不備があると審査が遅れる原因となるため、書類の内容は何度もチェックし、余裕を持ったスケジュールで申請するようにしましょう。
補助金制度は毎年見直されるため、適用される条件や補助金額が年度ごとに異なります。
例えば、前年に対象となっていた車種や補助金額が、翌年には条件変更によって対象外となることも珍しくありません。そのため、補助金を利用して新車の購入を考えている場合は、最新情報をしっかりと確認することが重要です。
情報源としては、一般社団法人次世代自動車振興センターの公式サイトや、お住まいの自治体の発表資料をチェックすると良いでしょう。
また、補助金の申請には締切や条件が細かく設定されているため、ネット上の古い情報を鵜呑みにせず、公式の最新情報を参照することが大切です。

CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の対象となるのは、基本的に新車の購入です。そのため、中古車や登録済み未使用車(いわゆる新古車)は対象外です。
ただし、一部の地方自治体では、中古車に対しても独自の補助金を提供しているケースがあるため、住んでいる地域の制度を事前に確認することをおすすめします。
また、軽自動車に関しても、自治体によって対象となる車種や要件が異なるため、購入を決める前に自治体の公式サイトや窓口で対象車両の最新情報を確認しましょう。対象外だと思っていた車が実は補助金の対象だった、というケースもあるかもしれません。
補助金を受け取った際の税金面の影響についても把握しておきましょう。
個人が受給する補助金は原則として非課税扱いとなりますが、法人が受け取った場合は課税対象となります。
法人の場合、補助金は事業収益とみなされるため、適切な会計処理が必要です。この際、圧縮記帳と呼ばれる特別な会計手続きによって、税負担を軽減可能です。
圧縮記帳を利用すれば、補助金を受け取った年度の課税所得を抑えられるため、企業にとっては大きなメリットとなります。こうした税金面の処理については、税理士に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。

CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の申請には、厳密な締切が設けられており、新車の登録日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
ここで注意したいのが、登録日と納車日は異なるという点です。一般的に、車の登録はディーラーが代行して行うため、登録日と実際に車が納車される日には数日から数週間のタイムラグが生じることがあります。
つまり、納車されたから申請しようと思っていると、すでに締切を過ぎてしまっている可能性も少なくありません。こうした事態を避けるためには、車の登録日を事前に確認し、余裕を持って申請手続きを進めることが重要です。
ただし、補助金が交付されるのは車両代金の支払いが完了し、申請が審査を経た後になるため、ローンの支払いには直接充てられません。しかし、補助金が交付された後に繰り上げ返済に利用可能です。
補助金の支給までには1〜2ヶ月ほどかかるため、資金計画をしっかりと立てた上で購入を進める必要があります。また、申請時にはローン契約書や支払い証明書などの書類が必要になる場合があるため、購入時に必要な書類をきちんと保管しておくようにしましょう。
軽自動車の売買をする際の必要書類とは?








