車にとってなくてはならない書類の一つが「車検証」です。その車検証を車に入れておかない、つまり不携帯のまま車を運行した場合に罰則があるのをご存じでしょうか。
車検証は車に関する情報が記載されている大事な書類です。また、車検証以外にも携帯しておかなければいけないものもいくつかあります。
そこで今記事では、不携帯だと罰則を受けてしまうものを車検証とそれ以外のものについて紹介し、あると便利なものもあわせて紹介していきます。
車検証は車に関する情報がすべて記載されている
車検証の正式名称は「自動車検査証」です。車検証には、その車にまつわるすべての情報が記載されています。
この国では車も「財産の一部」として取り扱われることとなっています。車の名義を登録する際に印鑑証明が必要となっているのもそのためです。
車検証にはその車の情報だけでなく、車に対する権利関係も記載されている重要な書類ということになるります。
車検証に記載されている情報一覧

それでは、車検証に記載されている情報について詳しく見てきましょう。車検証はA4サイズの小さい書面の中に、大切な情報が凝縮されて記載されています。
車検証には大きく分けて3つの情報がかかれているため、ここで詳しく解説をしていきます。
車検証に記載されている情報の一つ目は、車そのものに関する内容です。
車検証に記載されている車の情報は以下のような車の姿形といったハード面の情報が多く記載されています。
- 車名(メーカー名)
- 車の寸法(全長、全高、全幅)
- 排気量
- 車両重量と車両総重量
- エンジンの型式 など
上記の内容に加えて車固有の情報として「登録番号(ナンバー)」と「車体番号」が記載されています。この情報は、この世に2つ以上存在しない情報となっています。
車体番号について少し解説をすると、車体番号は自動車メーカーによってボディのフレーム部分に打刻されています。これ以外にも、ボディに貼り付けられたコーションプレートと呼ばれる金属製のプレート(ステッカーのメーカーもあり)にも、記載をされています。
車検証に記載されている情報の2つ目は、その車を所有(使用)している人について記載がされています。
この欄には以下の3項目が設けられています。
- 所有者の氏名及び住所
- 使用者の氏名及び住所
- 使用の本拠地の住所
車の買い方によっては、ディーラーが「所有権留保」をしている場合や「リース会社が絡んでいる」場合もあり、車によってどのような所有と使用の形態なのかということがわかるようになっています。
車検証には、その車の車検有効期限が記載されています。
普通乗用車の場合を例に挙げると、新規登録(新車で購入)した際には3年間の車検有効期間が設けられており、最初の車検期間を継続する(車検を受ける)と2年間延長されます。この期限内に車検証を更新しないと国が定める保安基準を満たしていないこととなり、その車は行動を走行することができなくなります。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
車検証は常に携帯していなければならない

車検証は、車を運行する際に必ず携帯しなければならない旨が法律で定められています。
車検証を携帯していないと罰則を受けるのか、必ず原本でなければならないのか、という点について確認をしていきましょう。
車検証を車に積まず(携行せず)に公道を走行すると車検証不携帯となります。警察官はいちいち車検証が入っているかどうか確認することはまずありませんが、検問や事故時の対応の際に車検証の提示を求められた際に携行していないと罰金(反則金)も科せられます。
その罰金の金額は明確ではありませんが「50万円以下」と法律で定められています。違反点数につきましては0点ですが、罰金が重いので必ず車検証を携帯するようにしましょう。
車を運転する際、車検証の原本を携帯しなければならないのが原則です。ただし、やむを得ない事情がある場合はコピーでも代用できるケースもありますので紹介します。
そのケースとは「名義変更などの手続きのために車検証を代理人に渡しているケース」です。
車検証に記載されている内容を変更するためには陸運支局へ行く必要がありますが、陸運支局の窓口が開いているのは平日の日中のみとなっています。土日休みの人の場合は、平日に時間を作ることが困難な場合も多いかと思います。
その場合は誰かに代理をしてもらってその手続きをしてもらうこととなりますが、その人に頼んですぐに手続きをしてもらい、その日のうちに手続き後の車検証を戻してもらうというのは、物理的に難しいこともあるでしょう。
車検証が無いために車が走らせられないと、もしものときに役に立ちません。あらかじめ車検証をコピーしたものを車内に置いておくことで、代用することができる場合があります。
そのため、警察官に車検証を見せることがあった場合、正当な理由を伝えることでOKとなることもあります。その正当な理由を示すために、とった車検証のコピーにあらかじめ以下のような記入をしておくといいでしょう。
「○○(コピーをとった目的や名義変更など)のためにコピーで代用、依頼先は○○」
あくまでも緊急時のための応急的な対策ですから、この方法を常用することはできません。手元に車検証が戻ってきたらすぐに車内に保管するようにしてください。
車検証を紛失してしまった時の対処法

もしも車検証をなくしてしまって見つからないという場合は、車検証を再交付してもらう必要があります。車検証の再交付は、ナンバープレートの地域を管轄している陸運支局でしか行うことができません。
例えば、品川ナンバーの車検証の再発行をする場合は、品川ナンバーを管轄する陸運支局で手続きをします。東京都内であっても、練馬や足立の陸運支局では再発行してもらうことができないので注意が必要です。
車検証を再発行する際に必要なものは以下になります。
- 使用者の印鑑もしくは委任状
- 使用者または代理人の本人確認ができるもの(顔写真付きの身分証明書)
- 理由書(再発行の理由が紛失や盗難の場合はその理由書を持参する)
- 印紙代(300円)
上記の内容に加えて「自分自身の車のナンバー」も必要ですので、あらかじめ確認しておいてください。
さらに、陸運支局は平日の日中しか窓口が開いていませんから、平日に休みが無い方の場合は、休暇をとらなければなりません。車検証を紛失してしまうと手間もかかりますし、お金もかかるため、車内に必ず保管するということを徹底しましょう。
車検証と合わせて携行しなければならいものとは
車を公道で走行中に不携帯で罰則を受けるのは、車検証だけではありません。実は車検証以外にも不携帯が発覚した場合に違反となって、切符を切られて免許の累積点数が増えたり反則金を支払う必要が出てきたりする場合があります。
ここでは、車検証以外で不携帯の場合に罰則を受けるものを4つ紹介していきます。
公道を走るすべての4輪と2輪の自動車に加入が義務づけられているのが、「自賠責保険(強制保険)」です。ナンバープレートがついている自動車は、加入していなければ一般道を走行することもできません。
車検証と同様に自賠責保険の証券を携行して走行しないと「不携帯」として罰則を受けることとなります。これは自動車損害賠償保障法の第8条において「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けなければ、運行の用に供してはならない」と定められているためです。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険の証券を「不携帯で運行した場合には30万円以下の罰金が科せられます。もし自賠責保険の期限が切れていたり加入していなかったりした場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
それに加え、無保険運転は交通違反として違反点数6点を科せられるため、少なくとも30日の免許停止処分となってしまいます。
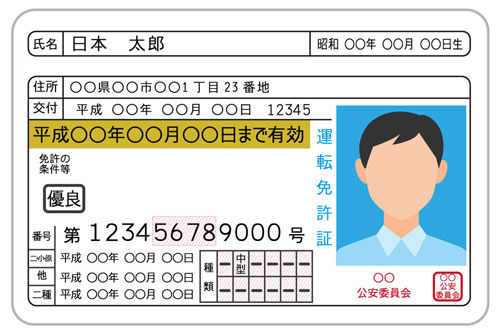
当たり前のことではありますが、運転免許証を携行していない状態で車を運転するのは法律違反となります。これは道路交通法の第95条第1項で「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められているためです。
その都度警察官が免許証を持っているかどうか確認することはありませんが、検問などのタイミングで警察官から免許の提示を求められた場合に免許証を提示できないと、「免許不携帯」として取り締まりを受けることになります。その際に科せられる罰則の内容としては「反則金3,000円」で違反点数は0点ですが、免許を持ち歩いていないだけで反則金を支払うのは無駄なことです。
免許証は車を運転する際には必ず携帯しましょう。ちなみに免許不携帯ではなく無免許運転の場合はさらに罰則が重く、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
意外かもしれませんが、車に車載していないと罰則を受けるものがあるので、覚えておきましょう。それは、「三角表示板」です。
どのようなものかわからないという方もいるかもしれませんので説明をすると、三角表示板は反射材を表面に取り付けた三角形の道具です。主に、自分の乗っている車が故障などが原因で路上に停止している際に、後続の車に停止していることを教える目的のために使います。
この三角表示板は滅多に使用することはありませんが、車に携行していないで路上に停車せざるを得なくなった場合に「故障車両表示義務違反」として罰せられることとなり、普通乗用車及び2輪車は6,000円の反則金と1点の違反点数が科せられます。最近の車には三角表示板が標準装備されていないことが多いので、カー用品店などで購入して車内に携行しておきましょう。

運転免許を取得したばかりの人が車に取り付ける初心者マーク(若葉マーク)もまた、該当する人が車を運転する際に周囲の人から見える場所に貼り付けていない場合には罰則を受けることとなります。罰則の内容としては反則金4,000円、違反点数1点となります。
免許を取得したばかりの人は、累積点数が3点を超えると「初心者講習」を受けなければならなくなるため、必ず初心者マークを車に取り付けるようにしましょう。初心者マークはカー用品店などで販売されており、マグネットで車のボディに貼り付けるものと吸盤で窓ガラスの内側に吸着させるもの、ステッカー式でガラスの外側などに貼り付けるものがあります。
最近発売されているエコカーなどにおいては、車のボディの材質が軽量化などの目的で鉄からアルミに代わっていることもあり、マグネットのタイプだと取り付けられないものもありますので気を付けましょう。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
罰則はないけど携行しておくと助かるもの
車検証を不携帯の場合、警察に捕まったら罰則を受けることとなります。罰則を受けないけれど、車を運転するときに携行しておくともしものときに役立つものについて紹介をしていきます。
それは、「任意保険の保険証券」と「JAFの会員証」、そして「工具類」の3つです。持っていないからといってダメだというわけではありませんが、それぞれ携行することでどういったメリットがあるのかということについて、解説していきます。

車を所有する大半の人が加入しているのが、任意保険です。任意保険を契約すると証券レス(Web証券)特約などに加入している場合を除いて、基本的に加入している保険会社から保険証券が届きます。
任意保険は、基本的に事故などが発生場合に使用します。保険会社に連絡をするとき、気が動転していて連絡先がわからなくなってしまったりということがあるでしょう。
加入しているディーラーなど代理店の担当者がいる場合は、その担当者に連絡をすれば、と思うかもしれません。しかし、ディーラーなどの休日や夜遅くの事故などで連絡がつかない場合もあるかと思います。
そういった場合は、保険証券に記載されている緊急連絡先に電話をすることになりますが、保険証券が無ければ連絡することもできません。こういうときに備えて、加入している任意保険の連絡先がわかる保険証券を車検証と一緒に、車内に保管しておきましょう。
証券が無い場合は、加入状況や緊急連絡先がわかるWebページなどを印刷して車内に保管するようにしてください。
ロードサービスといえば、JAFが国内最王手です。昔からJAFに加入している人や、ディーラーなどで車を購入したタイミングなどで加入したという人もいるはずです。
JAFについては個人会員の場合は自分が保有している車ではなく、加入している会員個人にサービス内容が適用されています。そのため、車内に会員証を保管しておくというよりは普段持ち歩く財布に会員証を入れておくと外出した際に活用することができます。
最近はスマホアプリで会員証を表示することもできますので、事前にインスト―ルしておくといいかもしれません。JAFはロードサービスだけというイメージが強いかもしれませんが、会員限定の優待サービスが充実しています。
会員証を提示すると飲食やレジャー施設の利用料金が割引されることも多いので、チェックしておくといざというときにお得に使うことができるでしょう。

最後に、携行しておいて役立つかもしれないのが工具類です。これも保険証券やJAFの会員証と同様に無くても困らないときの方が多いですが、万が一の際に役立ちます。
例えば路上でタイヤがパンクしたとき、最近の車には車載ジャッキやナットを外すレンチが搭載されていない、ということが多く、パンク修理キットを使用しなければならないということもあるかと思います。こういうときはやむを得ませんが、夏タイヤから冬タイヤに自分で交換しようとしたときに無いと不便です。
車載工具として採用されているパンタグラフジャッキやレンチ類は数千円で購入することができますので、持っておいて損はないでしょう。
これ以外に持っておくと役立つのがドライバーやソケットレンチ類です。車の部品類は基本的にネジかボルトで留められています。
最近の車はLED化されているものが多いので電球切れということはあまり起きませんが、ウィンカーバルブの交換などの際にこれらの工具があると役立つこともあります。お店に頼んで工賃を支払えばやってもらえますが、バルブの交換などは自分自身でも十分にできる作業です。
工具の交換費用はかかりますが、そう簡単に壊れるものではありません。長い目で見ればトータルコストは抑えられることができます。








