フォグランプは、霧や雨などの悪天候下で視界を確保するために点灯するライトです。ヘッドライトなどの他の灯火と同じように、フォグライトの個数や取り付け位置、点灯するか否かなども車検の検査項目に含まれています。
車検前に慌てなくて済むように、また日頃の事故防止も含めてフォグランプの必要性や明るさや取り付け位置などを知っておくことが大事です。また、ライトが切れた場合は交換しなければならないので、交換にかかる費用や交換方法なども知っておくと役立つでしょう。
フォグランプはどの部分のランプ?

車を運転する際に、霧や強い雨が降るとどうしてもドライバーの視界が悪くなります。フォグランプは悪天候時でも道路の見通しをよくするために照らす灯火です。
日本語では霧のランプという意味があります。霧は空気中に水滴が浮遊している状態なので、周囲の景色が霞んで見通しが悪くなります。
フォグランプを霧の中で点灯させることで、自車の存在を他の車に示すことができると言えるでしょう。フォグランプは車の前後に装備されています。
車の前部のフロントフォグランプはヘッドライトの下辺りにあり、主に対向車が来た時に自車の存在に気づかせるのが目的です。車の後部のリアフォグランプはテールランプの下辺りについています。
特に後続車から自車を見つけやすくし、追突を防ぐ役割があります。フォグランプは強い光なので、濃い霧の中でいきなり点灯すると、一瞬目の前が真っ白になってしまうほどかなり眩しいのが特徴です。
それは、霧の中の水滴に光が当たると光が乱反射してしまうためです。対向車や後続車のドライバーが過度に眩しく感じないように、フォグランプは下向きについており、足元を広範囲に照らせるようになっています。
フォグランプは、基本的に天候不良で視界が悪い時に点灯するライトです。道路交通法でも、夜間はヘッドライトやテールランプなどの灯火をつけなければならないと定められています。
夜間のフォグランプの点灯は特に法律では義務付けられていません。逆にヘッドライトをつけないで、フォグランプやスモールライトのみを点灯した状態での走行は法律違反になります。
フォグランプは遠くを照らすことはできないので、歩行者など発見しづらいため交通安全上も危険だと言えます。また、晴天時にフォグランプをつけたまま走行すると対向車のドライバーの視野を妨げるのでやめましょう。
もし走行中に急な豪雨や濃い霧の発生に見舞われたら、慌てずにまずは減速します。その際、後続車から追突されないように、ブレーキを数回踏んでランプを点灯させて知らせることも大事です。
そして、ヘッドライトと共にフォグランプを点灯させ、道路の白線や周りの景色に目を配りながら路外にはみ出ないように十分注意して走行します。それでも視界がかなり悪い場合は、駐車場に入るもしくは安全な路肩などに車を寄せて、ハザードランプを点灯させてしばらく停車してください。

車検は車種によって期間は異なりますが、概ね新車購入から3年後に1回目、以降2年ごとに受けなければなりません。車検を受けないで公道を走行すると、無車検で道路交通法違反となり罰せられます。
さらに、免許停止の行政処分も科せられます。車検を行うのは、そもそも国が定めた保安基準に適合した車かどうかを調べるためです。
エンジンやブレーキやタイヤ、ワイパーなど検査項目がいくつかあり、一つでも適合しない場合は再検査となり整備しなおしてからもう一度車検を受けることになります。
ヘッドライトやテールランプなどの灯火類と同じように、フォグランプも車検で検査対象となるライトの一つです。フォグランプは下向きで足元を広範囲に照らすライトですが、非常に強い光を放ちます。
光の強さや角度などに規定がないと、後続車や対向車のドライバーがかなり眩しく感じてしまうことがあります。そうなると視界不良となって走行の妨げとなり、交通事故を招くリスクも高まるでしょう。
フォグランプが正しく装着されているか、車検で厳しく検査する必要があります。
フォグランプに関する保安基準

車検の検査基準とされる保安基準には、フォグランプに関する規定もあるのでチェックしておきましょう。フォグランプに関しては、ランプの個数や色、取り付ける高さや光の強さなどが決められています。
光がどのような向きでどの範囲を照らすのか、照射方向も他の車の走行に影響を与えるので重要な検査項目の一つです。検査項目のうち、一つでも保安基準を満たしていないと車検に合格できません。
保安基準を満たすように整備しなおす必要があるなど厳しくなっています。
フォグランプの色はどんな色でもいいわけではありません。白色もしくは薄い黄色と決められているので、注意しましょう。
ネットショップなどではオレンジ色や青色などのフォグランプが販売されていますが、他の色は保安基準適合外となります。また、フォグランプは車の前後、左右につけるのが一般的です。
フォグランプを複数つける場合、全て同じ色で統一しなければなりません。例えば左を白色、右を黄色にするなど他の色を混在させるのはNGです。
また、車の後ろにつけるリアフォグランプの色は赤色と決まっています。
フォグランプを取り付ける数に関しても規定があります。車の前部に取り付けるフロントフォグランプは、個数に制限がありません。
ただし、同時点灯個数は決められています。同時に3つ以上点灯するライトは保安基準に反します。
左右で2個ずつ取り付けることは可能ですが、4個同時に点灯するライトは車検に通りません。特に2個以上取り付ける場合は注意が必要です。
車の後部に取り付けるリアフォグランプの場合は、取り付け個数は2個までと決められています。

ヘッドライトやテールライトの下部というように、フォグランプの取り付け位置は決まっています。中でも地面からの高さに関しては、フロントフォグランプとリアフォグランプでは細かな規定があるので注意が必要です。
まずフロントフォグランプは、照明の上にある縁の高さが地面から0.8m以下、下の縁は地面から0.25m以上となっています。さらに、照明の1番外の縁は車の一番外側から0.4m以内でなければなりません。
またリアフォグランプは、照明の上にある縁の高さが地面から1m以下、下の縁の高さが地面から0.25m以上となります。テールランプの照明から0.1m以上離して取り付ける必要があります。
少しでも規定からはみ出していると車検に通りません。自分で改造しなければ、フォグランプは規定通りの位置に取り付けられているはずです。
点検を業者に任せれば保安基準に適応しているか確認してもらえるので、安心できます。
光の明るさ表す単位のうち、車のライトに関してはカンデラという単位がよく使われます。カンデラはある方向に照らされた光の角度、光の強さを表した単位です。
光を照らす範囲のうち一番明るい箇所の光度、眩しさを数値化しています。フォグランプの光度は決められていて、2005年までは1万カンデラ以下でした。
しかし、2006年以降は光度に関しての規定は撤廃されています。ただし、あまりに光度が高く、他の車両の走行を妨げると判断された場合は車検では不合格になるかもしれません。
市販されているフォグランプは車検仕様になっており、改造しない限りは光度が高すぎるフォグランプを装備することはないとされています。

フォグランプの光はとても明るいため、光の照射角度によっては他の車両のドライバーに過度の眩しさを与え、走行を妨げるリスクがあります。そのため、車検ではフォグランプの光の照射向きに関しても検査がなされます。
もともとフォグランプは下向きに設置しなければいけません。光の照射方向である光軸が上向きになっている、光が上方向に分散しているライトは保安基準適応外です。
また、光が当たる部分と当たらない部分の境目をカットラインと呼びます。このカットラインは真っすぐでなければなりません。
ラインが曖昧で特に光がラインの上に伸びている場合や、ラインそのものがない場合は車検でNGとなるので注意しましょう。
車が好きな人だと、自分の趣味で車をカッコよくカスタマイズする機会もあるでしょう。車のカスタマイズ自体は、特に法律に反することにならないので自由です。
しかし、結果的に車検の基準となる保安基準を満たさない改造をしてそのまま車検に出すと再検査となり、整備しなおさなければならなくなります。場合によっては整備不良で取り締まりを受け、行政処分が科されることもあるので注意が必要です。
特にフォグランプをカスタマイズする際は前後での個数や同時点灯個数、色や取り付け位置などのきちんと確認しておきましょう。保安基準に適したランプを選び、正しく取り付けることが大事です。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
取り付けていなくても法律違反にならない

もし自車にフォグランプが装備されていなかった場合、車検に通らなのではないかと心配になる人もいるでしょう。しかし、フォグランプはもとから装備されていなくても法律上は問題ありません。
フォグランプには装着義務がないので、ついていなくても車検は通ります。一方、ヘッドライトやテールランプは車の装備として装着していなければならないため、フォグランプとは異なります。
技術が進み、足元を照らしフォグランプの役割も同時に担えるヘッドライトを装着した車もあるくらいです。またフロントフォグランプを搭載した車は多いですが、車の後部のリアフォグランプを装着した国産車はかなり少ないとされています。
リアフォグランプは主に輸入車に多く装着されているので、国産車を乗る人には馴染みがないかもしれません。特に装着されていなくても車検には通るので、必要がなければ改めて装着しなくても大丈夫です。
車検を受ける前に確認するのを忘れ、いざ車検でフォグランプをつけた際にランプが切れていて点灯しない場合もあるでしょう。フォグランプが点灯しないと故障とみなされ、保安基準適応外となり車検は通りません。
ただし、フォグランプの装着自体が法律上義務付けられていません。球切れのフォグランプを外して車検を受ければ、フォグランプの装着なしと判断され、検査項目から外されるので車検は通るはずです。
また、フォグランプは左右に装着されているので右は点灯し、左だけが球切れという場合も再検査となります。装着されている以上左右のランプがきちんと点灯することが条件となるからです。
フォグランプが装着されているのに片方だけ球切れのまま走行していると、整備不良となり取り締まりを受ける場合もあるので注意しましょう。

フォグランプのバルブ(電球)には、ハロゲンランプとHIDランプ、LEDランプの3つの種類があり、それぞれバルブの寿命が異なります。ハロゲンランプはやや明るめの優しい光が特徴で300~500時間と一番寿命が短いです。
HIDランプは少し青みがかった発光色でハロゲンランプの3倍ほどの明るさがあり、寿命は1,500~2,000時間です。最も寿命が長いLEDランプは、HIDランプほどは明るくないですが、2万時間以上使用できます。
フォグランプは霧や豪雨など天候不良時にのみ点灯させるランプなので、使用時間もヘッドライトやテールランプよりは短いのが一般的です。LEDランプにしておけば20年程は使用できる計算となるので、車によっては交換の必要がないかもしれません。
逆にハロゲンランプにすると長くても500時間までと約3~5年で球切れとなる可能性もあるので、交換しなければならないとされています。
寿命でなくても何らかの原因でフォグランプが球切れを起こし、交換しなければならない場合もあります。フォグランプの交換費用は、バルブの種類によって異なります。
寿命が短いハロゲンランプは1,000円~3,000円程と比較的安いです。次いでHIDランプは2,000円~5,000円程、一番長持ちするLEDランプは5,000円~1万5,000円程です。
これらの部品代に加え、ディーラーやカー用品店、ガソリンスタンドや整備工場などの業者に交換を依頼すると工賃がかかってきます。工賃は業者によって異なりますが、2,000円~8,000円位だとされています。
ディーラーの場合はランプも純正品なので高く、技術料がかかるので工賃も割高ですが、確かな技術力があるので安心できるはずです。一方、カー用品店などはバルブの在庫も豊富なので、安くあげることは可能でしょう。
フォグランプはセルフ交換ができます。特別な工具は不要ですが、ドライバーや軍手などを準備してください。
フォグランプのバルブはバンパーの端に位置するので、タイヤの隙間から手が入るようにハンドルを切ってから車を停めます。
タイヤの隙間から手を差し込み、ドライバーを使ってねじなどを外してからフェンダーカバーをべりべりと剥がします。
フォグランプにつながるコネクターを引っ張り外します。そして左右どちらかに回転させてバルブを取り出します。
新しいバルブをコネクターにつなげて、フェンダーカバーを被せてねじなどで元通りに固定します。
最後にフォグランプをつけてきちんと点灯するか、角度などに問題はないかを確認すれば完成です。
フォグランプの交換は割と簡単なので、車にあまり詳しくない人でもできそうです。しかし、難しいと感じる場合は無理をしないで業者に依頼しましょう。
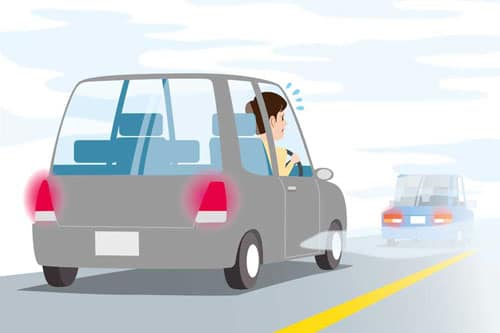
フォグランプは、バルブの種類によって寿命の長さが異なります。寿命の短いハロゲンランプから、寿命の長いLEDランプに交換することも可能です。
ただし、寿命が長くても急に故障して点灯しなくなってしまう場合もあります。点灯しないまま気づかずに走行していると、万一霧や豪雨に見舞われた際に、視界が不明瞭となり交通事故を起こしかねません。
フォグランプのみならず、スモールライトや特に後方のブレーキランプ、テールライトなどの故障は気づきにくいものです。故障にいち早く気づくためにも、日頃から点検しておくことが大事です。








