車検を行ったときに「勘定科目が何にあたるのか」知りたいと思うことがあると思います。
車検は新車からであれば3年、それ以降は2年ごとに受けなくてはなりません。事業主だと、節税対策として経費計上したいと思っている方もいるでしょう。車検はまとまった費用がかかるので、少しでも抑えたいところです。
今回は車検を行った際に、勘定科目はどのように振り分ければいいのか、仕訳の方法について注意点も含めて詳しく解説していきます。
車検費用の内訳は何があるか

一概に車検費用といっても、どのようなものか分からないという方も多いかと思います。基本的に車検をするときは「合算でいくらになるか」が重要視されるためです。しかし、料金の内訳を知ることも重要なことです。
勘定科目の説明に入る前に、車検費用の内訳を確認していきます。車検費用に含まれる内訳は以下の通りです。
- 自動車重量税
- 自賠責保険
- 車検基本料
- 法定点検料
- 車検代行手数料
- 整備修理費用
- 印紙・証紙代
大きく分けると自動車重量税や自賠責保険、収入印紙代は国や保険会社に支払う「法定費用」として、その他の項目は車検や点検整備を依頼して自動車整備工場等に支払う「点検整備費用」が内訳に含まれており、勘定科目にも反映されます。
それでは、実際に勘定科目に振り分けて考えていきましょう。
車検費用で使う5つの勘定科目
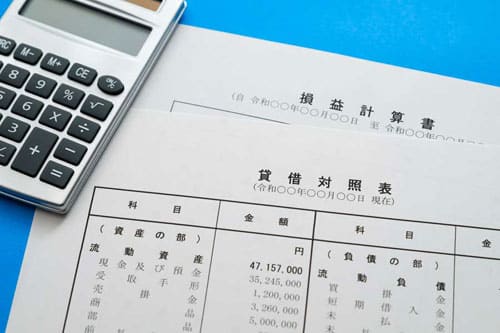
勘定科目をする際、内訳費用がそのまま使えるのであれば良いのですが、そうならないところが分かりにくいところです。
経理処理を行っている方であれば、それほど違和感がないかもしれませんが、実際に仕事で使わないのであれば知っておく必要があります。
車検費用で使う勘定科目は5つあります。「車両費(修繕費)」「租税公課」「保険料」「支払手数料」「事業主貸」です。こちらを勘定科目に振り分けていきましょう。
それでは、5つの詳細を解説していきます。
車両費(修繕費)は、今回の場合だと「車検基本料」「法定点検料」「整備修理費用」の勘定科目となります。
厳密にいうと、車両代は車両に関する支出を示す勘定科目であり、修繕費は固定資産の維持管理に必要な支出を示す勘定科目になります。ただ、どちらを使っても問題ないので使いやすい勘定科目を利用しましょう。
また、会計処理をするときに車両費を勘定科目で利用するときには、その他に「ガソリン代」も計上することができます。
自動車の維持管理で使う項目ですが、会計処理が複雑にならないように細かく仕訳をしておくと、より管理がしやすく財務指標として分かりやすくなります。
租税公課は、国や地方公共団体に納める税金(租税)のことです。
車検のときに一緒に支払う「自動車重量税」と、車検の検査手数料を納めるときに使用する「印紙証紙代」費用が租税公課の勘定科目になります。
その他、租税公課を勘定科目として計上できるものとして「固定資産税」「都市計画税」「事業税」「事業所税」などがあります。
しかし、租税であっても経費として計上できない項目もありますので、注意が必要です。
保険料は、車検の際に支払う「自賠責保険」の保険料が当てはまります。
自賠責保険は法律上加入が強制されている保険です。未加入の自動車を運転すると、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金が科せられます。
その他に経費として計上できる保険料は「火災保険」「地震保険」などです。事業所や店舗など、保険の対象が事業用になっている保険が対象になります。そのため、個人事業主自身や自宅が対象の保険については、計上することができません。
支払手数料は、今回の費用として「車検代行手数料」が当てはまります。車検を代行してもらった費用を勘定科目として計上します。
支払手数料とは、銀行・郵便局などの金融機関で振り込みを行ったときにかかる手数料や、弁護士や税理士などの専門家に報酬を支払った場合に使う勘定科目です。
その他にはクレジットカードの売上手数料や解約手数料、フランチャイズのロイヤリティーの手数料なども含まれます。
事業主貸は、使用している車を仕事とプライベートで兼用するときに、按分計算した状態で個人使用分を除外するときに使う勘定科目です。
実際、どのくらいの頻度で利用しているかを明確にする必要があります。例えば仕事とプライベートで5:5の割合で使用していたとすると、車検代として50%は経費として計上できることになります。
特に個人事業主であれば、確定申告の際に計上も可能です。
車の使用目的と普段運転する頻度で計上できる車検代も変わってきますので、きちんと明確にしておきましょう。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
車検費用の仕訳方法3つ

車検費用で使う勘定科目について理解できたかと思います。それでは、具体的に仕訳をする方法を3つ解説していきましょう。
仕訳方法として「税込みの仕訳」「税抜きの仕訳」「個人事業主の仕訳」があります。
車検費用の内訳から勘定科目で仕訳をしていきましょう。
車検経費の内訳は、次のようになった場合を想定します。
- 自賠責保険料・・・20,010円
- 自動車重量税・・・23,600円
- 印紙証紙代・・・1,200円
- 車検基本料・・・17,000円(税込18,700円)
- 法定点検料・・・12,000円(税込13,200円)
- 事務手数料・・・1,000円(税込1,100円)
- 修理整備料金・・・30,000円(税込33,000円)
- 車検代行手数料・・・6,000円(税込6,600円)
- 税込価格合計・・・117,410円
税込みで仕訳した場合です。
車検基本料(18,700)+法定点検料(13,200)+修理整備料金(33,000)=64,900
自動車重量税(23,600)+印紙証紙代(1,200)=24,800
事務手数料(1,100)+車検代行手数料(6,600)=7,700
自賠責保険料(20,010)=20,010
この4つの勘定科目が左側の「借方」に計上されます。
そして右側の「貸方」には例えば現金で支払った場合は「現金」と記入して、かかった費用117,410円(車両費+租税公課+手数料+保険料)を計上します。
税込処理の仕訳は、理解しやすく簡単にできることが長所です。消費税の計算をすることもないので短時間で作成することもできます。
※個人事業主の場合、税金が発生する売上げが1,000万円以下のときは、消費税の支払い義務が生じないため、消費税を気にしなくて良いとされています。
車検経費の内訳は、次のようになった場合を想定します。
- 自賠責保険料・・・20,010円
- 自動車重量税・・・23,600円
- 印紙証紙代・・・1,200円
- 車検基本料・・・17,000円(税込18,700円)
- 法定点検料・・・12,000円(税込13,200円)
- 事務手数料・・・1,000円(税込1,100円)
- 修理整備料金・・・30,000円(税込33,000円)
- 車検代行手数料・・・6,000円(税込6,600円)
- 税込価格合計・・・117,410円
税抜きの仕訳をした場合です。
車検基本料(17,000)+法定点検料(12,000)+修理整備料金(30,000)=59,000
自動車重量税(23,600)+印紙証紙代(1,200)=24,800
事務手数料(1,000)+車検代行手数料(6,000)=7,000
自賠責保険料(20,010)=20,010
課税対象の消費税をこの勘定科目に加える=6,600
税込みと違うところは、「仮払消費税等」の勘定科目が加わったことです。ここで消費税のかかった費用を記入してください。
税抜きは5つの勘定科目が左側の「借方」に計上されます。
そして右側の「貸方」に先程と同じように117,410円(車両費+租税公課+手数料+保険料+仮払消費税等)を計上します。
税抜き処理で行うと、「経営に役立つ指標になること」「ものを購入したときに全額費用にしやすくなること」という点がメリットです。
税抜き処理をすることで、基本的に消費税は利益に影響を受けることがありません。それに比べて税込処理をすると、消費税の分だけ売上総利益が高くなります。そのため、税抜き処理をすることでより正確な数字を把握できるので経営判断にも役立ちます。

個人事業主の車検に対する仕訳は、車の使用状況に応じて異なります。
所有する車を100%ビジネス用に使用しているという場合は上記2つの仕訳で問題ありません。
車をビジネスとプライベートで兼用しているという場合は「事業主貸の勘定科目」を使います。プライベートで使っている分については、按分して支払うことになるため、全額を経費として計上することはできない仕組みです。そのため、按分比率がポイントになります。
車検経費の内訳は、次のようになった場合を想定します。
例えば、ビジネスで6割、プライベートで4割使用していたとします。按分比率はビジネス:プライベート=6:4です。
そうすると、4割については「事業主貸」として経費から差し引くことになります。
- 自賠責保険料・・・20,010円
- 自動車重量税・・・23,600円
- 印紙証紙代・・・1,200円
- 車検基本料・・・17,000円(税込18,700円)
- 法定点検料・・・12,000円(税込13,200円)
- 事務手数料・・・1,000円(税込1,100円)
- 修理整備料金・・・30,000円(税込33,000円)
- 車検代行手数料・・・6,000円(税込6,600円)
- 税込価格合計・・・117,410円
税込みでの仕訳
車検基本料(11,220)+法定点検料(7,920)+修理整備料金(19,800)=38,940
自動車重量税(14,160)+印紙証紙代(720)=14,880
事務手数料(660)+車検代行手数料(3,960)=4,620
自賠責保険料(12,006)=12,006
プライベートで車を使用している経費(46,964円)を計上します。=46,964
このケースであれば、車検でかかる費用の6割にあたる70,446円が経費として計上されます。残りの4割46,964円をプライベートでの車検費用として事業主貸の勘定科目に取り入れます。
上記5つの勘定科目(車両費+租税公課+手数料+保険料+事業主貸)を左側の「借方」に記入します。そして右側の「貸方」には合計金額の117,410円を記入します。
車の利用比率によって計上金額も変わってきますので、明確にしておくと良いでしょう。
車検費用を個人事業主が経費として計上するには、条件があります。それは、車をビジネスで使用している場合です。
経費として計上できる要因として、仕事をする上で使用したものが前提となります。例えば、個人事業主でプライベート用に車を持っていて使用していても、車検等を含めた車にかかる経費は計上することはできません。
しかし、先程触れたようにビジネスとプライベート兼用で車を使用しているときは按分して計上は可能です。その際に、ビジネスとプライベートの使用比率が6:4だとすれば、車にかかる経費の60%を計上することができます。
個人事業主の確定申告
個人事業主で何かと大変なことの一つとして、確定申告があります。毎年2月あたりから申告を行っていくのが通例です。
事業を行っている以上、税金を納めることは義務です。確定申告で車検費用の全額又は一部を経費として計上するときには「青色申告」と「白色申告」があります。
青色申告については「青色申告決算書」に記入し、白色申告については「収支内訳書」に記入します。
次からは、個人事業主が確定申告する際の注意点を中心に、解説していきましょう。
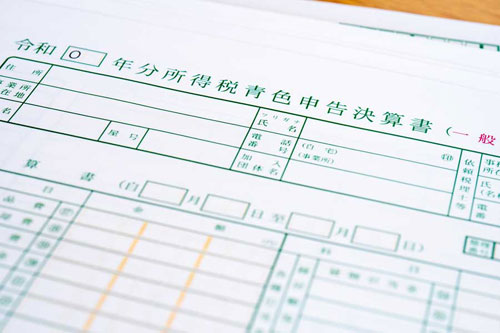
初めて青色申告するケースです。
まず事前に「所得税の青色申告承認申請書」を最寄りの税務署に提出しておく必要があります。書面は税務署にあるのでそれを利用しましょう。
青色申告決算書は、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。その用紙に金額を記入していきますが、以下3点を注意点として挙げておきます。
青色申告の青色申告決算書は車両費の項目がありません。貸倒金の下に空白があり、そこに追記することで計上できます。
車検でかかる按分された事業分を、そこに記入していきます。ガソリン代や高速道路代なども計上できるのため、その際には合算して記入しましょう。
こちらも青色申告の青色申告決算書には項目が記されていません。車両費と共に空白部分に追記することになります。申告する期間内に支払手数料が他にもあるときは、合算して計上します。
青色申告決算書には保険料という勘定科目がないので「損害保険料」の勘定科目に記入します。損害保険料はその他のものとして、事業をする際に使用している火災保険や自動車保険も計上できます。

節税対策を考えると、青色申告すれば最大650,000円の控除を受けられるため、所得税負担を減らすことが可能です。しかし、手間と時間がかかるため、白色申告にする場合もあります。
例えば帳簿をつけるときに、白色申告の場合「単式簿記」であるのに対して、青色申告は「複式簿記」で記録する必要があります。
複式簿記の方が、経費がかかったときに資産が減少したという詳しい財務状況を把握しやすくなります。そのため、青色申告は手間がかかる分、経費の詳細が分かりやすくなるので控除されることも頷けます。
しかし、車検を計上するときも含め、確定申告に手間をかかたくないときには、白色申告で計上するのも良いでしょう。
最近は取引内容を入力していくだけで、会計ソフトが自動で複式帳簿にデータ反映してくれるものもあります。複式簿記による記帳も、負担は以前より軽減してきていると言えそうです。








