今では愛車をカスタマイズしてオンリーワンの車にしている方も少なくありません。マイカーを保有している方で、車をDIYしようと考えている方もいるでしょう。
ここで注意しなければならないのは、車をDIYしたら車検を通過できるのかという点です。保安基準を無視した改造をすると、車検に引っかかってしまいます。
そこで、ここでは車検を意識したカスタマイズ方法についてみていきます。また、最近ではキャンピングカー用にDIYする方も多いようです。その際の注意点についてもまとめました。
車をDIYしても車検に通る?

そもそも車をDIYした場合、車検を通すことができるかどうか疑問に思っている方も多いでしょう。結論から言うと、ケースバイケースです。
車検の基準を意識してDIYすれば、問題はありません。しかし基準を超えるような改造をしてしまうと車検を通せなくなるので、注意が必要です。
自家用車であれば、新車なら3年後、それ以降は2年に1回のペースで車検を受けることが義務付けられています。これは、車を安全に走行させることが目的です。
もし点検されていない、基準を満たしていない車が公道を走行していると、それだけ事故リスクが高まります。事故防止の観点から、車検が実施されています。
車検をクリアするということは、必要最低限安全に走行できるだけの車であることの証明です。車をDIYするには、安全に走行できるだけの担保があるかどうかが重要になります。
そのため、車の走行性能や安全性にかかわるようなところの改造は控えましょう。一方、安全性に関わらない部分で手を加えることは問題ありません。

車検は、国の定める保安基準をクリアしているかどうかチェックする手続きです。もし保安基準に適合しないDIYをしてしまうと、車検に通らなくなってしまいます。
保安基準は幅広い項目が規定されています。車の大きさや排気ガスなどさまざまな基準があり、それらを全てクリアしなければなりません。
自動車メーカーは、この保安基準を意識して各車種を製造しています。そのままの状態で運転していれば、部品がひどく摩耗しているなどの一部例外を除き、車検を通過できます。
一方、DIYしてこの保安基準を逸脱した改造をすると、車検を通過できません。保安基準の範囲内でDIYするように心がけましょう。
車をDIYするにあたって注意しておきたい点は、取り付ける部品の選択です。もし指定部品を使用していれば、純正パーツでなくても車検を通せる確率は高いからです。
指定部品はタイヤ、シフトレバー、ステアリング、マフラーカッターなど幅広いアイテムが挙げられます。指定部品と純正パーツを交換すれば、車検通過する公算は高くなります。
ただし、指定部品であれば何でもOKかというと、そうではありません。保安基準の中には車のサイズや重量なども含まれます。たとえ指定部品でも、それを取り付けることで規定されたサイズや重量をオーバーすれば、車検は通りません。
全体的な観点から車検を通せるかどうか考えましょう。
愛車を改造することで、保安基準で規定された車のサイズや重量をオーバーすることもあります。この場合、基本的には車検は通りません。
しかし中には、大きさがオーバーしたり指定部品ではないパーツに交換しても、安全性を確保できる場合もあるでしょう。この場合、「構造変更申請」をして認められれば車検通過は可能です!
構造変更申請は、陸運支局もしくは自動車検査登録事務所で行います。もし不備がなければ、申請して10日前後で結果が通知されるはずです。
審査を通過すると、今度は実車検査が行われます。これで問題なければ、改造が認められて車検を通過することができます。
もしどうしても保安基準を超える改造をしたければ、構造変更申請の手続きを済ませておいてください。
マイカーをキャンピングカーにDIYする際の注意点

アウトドアが趣味という方の中には、マイカーをキャンピングカーに変えようと考えている方も多いでしょう。キャンピングカーを購入するとなると、かなりの費用がかかってしまうからでしょう。
乗用車をキャンピングカーにDIYする場合も自家用車と同様で車検のことを意識しなければなりません。
DIYするにあたって頭に入れておくべきことについてまとめました。
日本には独自のナンバー制度があります。ナンバープレートを見ると地名の横に数字がありますが、この数字の一番左が何かによって、車両区分がわかります。
自家用車の場合、3ナンバーや5ナンバーが多く、これが乗用車の区分となります。一方、キャンピングカーは8ナンバーのものが中心です。
日本の法律上、キャンピングカーは特種用途自動車扱いになり、この特種用途自動車のナンバーが8になります。8ナンバーの車は、他にもパトカー、消防車、冷凍車などが含まれます。
もし本格的なキャンピングカーを購入するのであれば、この8ナンバーを取得しなければなりません。
本格的なキャンピングカーではなく、ハイエースなどの乗用車をDIYして実質的なキャンピングカーにするケースも少なくありません。
もし乗用車をDIYにしてキャンピングカーにした場合、ナンバーはどうなるのでしょう。結論から言うと、キャンピングカーに改造しても8ナンバーをとるのは難しいです。
8ナンバーを取得するためにはいろいろな条件があります。例えば、乗車定員の1/3以上が就寝できる設備が必要です。また、水道及び炊事設備を有することが8ナンバーを取得するための条件となります。
設備があればいいというわけではなく、室内高が1,600mm以上必要です。国産のバンで最大サイズでも1,600mmの高さを確保できないので、DIYで8ナンバーを取得するのは困難と考えましょう。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
乗用車の内装をキャンピングカー仕様にDIYする際の車検への注意点

バンなどの車両を購入してキャンピングカーにDIYしようと思っている方もいるかもしれません。DIYするにあたって、内装をキャンピングカー仕様に変更する方も多いでしょう。
その際には、いくつか注意しなければならないポイントがあります。それを以下にまとめましたので、これらのポイントを押さえた上でどう改造するか考えてください。
キャンピングカーに改造するにあたって、フルフラットにしようと思っている方もいるかもしれません。そうなると後部座席を取り外す必要があります。
実は後部座席を取り払う場合、そのままでは車検で引っかかってしまいます。車両によって乗車定員が決まっていて、その人数分の座席とシートベルトが確保されていないといけないからです。
もしフルフラットにするのであれば、乗車定員変更のための構造変更申請手続きをしなければなりません。手続きが認められれば、フルフラットでも車検を通すことは可能です。
ただし、定員を変えたらそれ以上の人数は乗車できません。3名に変更した後4人で乗車すると、法律違反となりますので注意しましょう。

後部座席を取り外して、定員変更の手続きをすれば車検を通すことができます。しかし、これが認められるのは4ナンバーのバンの場合です。
5ナンバーの乗用車の場合、後部座席を完全撤去するのは認められていません。5ナンバーの乗用車の場合、運転席の後ろにある空間の中で乗車スペースが50%以上なければならないからです。
もし5ナンバーの乗用車をキャンピングカーに変更したければ、2段階の変更手続きが必要です。
- まずは乗用車から4ナンバーの貨物車に変更する
- 乗車定員の変更手続きをする
ここまで行って、初めて後部座席を撤去してフルフラットのスペースが確保できます。
キャンピングカーにDIYするにあたって、荷室部分を木でカバーするカスタマイズを検討しているという方もいるかもしれません。ウッディな感じになって、アウトドア感が増すでしょう。
ここで問題になるのは、車の内装では難燃性素材を使わなければならないという規定です。それは車両火災が発生した際に火事の度合いを最小限にするためです。
しかし、荷室を木でカバーするのは車検を通すにあたって問題ありません。まず、難燃性素材の使用が義務付けられているのは運転者もしくは客室であって、荷室部分は適用外となります。
また木製の板を取り付けても厚さ3mm以上のものなら、難燃性と認められます。厚さの条件を満たしていれば、木材を使用しても問題ないわけです。
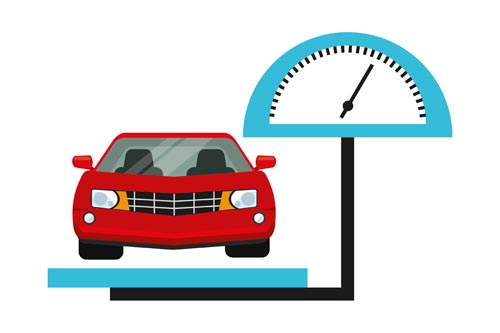
保安基準の中には、車両の総重量も含まれます。車検証に記載されている重量50kgの誤差の範囲内であれば、問題ないこととなっています。
ただ、車両の種類によって車検に出す際の作業が異なります。
設備は原則取り外さないといけません。車を車検に出す際に、車内に入れている荷物は全て出すことになります。
ただ、設備は荷物扱いになりますが、車検証の重量と50kg以内の誤差で、ベッドのように固定されているのであれば、取り出す必要はありません。心配であれば、整備工場の担当者などに相談しておきましょう。
設備を取り出す必要はありません。もともと設備として搭載されている車なので、そのまま車検を通すことができます。
キャンピングカーに自家用車などをカスタマイズした場合、注意しなければならないのは車検の有効期間です。これは、改造後にナンバーがどうなるかによって変わってきます。
従来通りのペースで車検を通します。初回は3年後、2回目以降は2年に1回のペースで車検を受ける必要があります。
従来の自家用車とは車検の期間が異なるので注意が必要です。初回から2年に1回のペースで車検を受けないといけません。
軽自動車は初回から2年ごとに車検を受ける必要があります。それ以外の場合、車両総重量で変わってきます。8トン未満であれば初回は2年後、それ以降は毎年です。8トン以上だと初回から毎年車検を受ける必要があります。
DIYした車をユーザー車検で通すには?

車をDIYする方の中には、メンテナンスなど車いじりが好きな方も多いかもしれません。すると、車検を受けるにあたってディーラーなどにお願いするのではなく、自分で検査をしたいと思う方もいるでしょう。
自分で検査を通すユーザー車検も、近年注目を集めています。もしDIYした車をユーザー車検で通すのであれば、注意すべきことがいくつかあるので紹介します。
車検を受けるにあたって、必要書類を準備しなければなりません。
ディーラーなどお店にお願いするのであれば、車検証、自賠責保険証明書、自動車納税証明書、印鑑が必要です。
ユーザー車検の場合、お店と比較して提出すべき書類が増えます。上で紹介したもの以外に「自動車検査票」「自動車重量税納付書」「継続検査申請書」「定期点検整備記録簿」が必要となります。
また、自賠責保険証明書は新旧2枚(車検までの期間をカバーしているものと所見後の期間をカバーしているもの)も、用意しなければなりません。
車検を受ける前に、保険の継続手続きをする必要があります。自賠責保険の継続手続きは、代書屋でも対応しています。運輸支局付近にあるはずなので、こちらで手続きするのも一考です。

ユーザー車検を受けるにあたって、事前予約は必須です。
お店の場合、閑散期であれば当日持ち込みで受けられる場合がありますが、ユーザー車検の場合認められません。
ユーザー車検の予約ですが、国土交通省のホームページに自動車検査インターネット予約システムがありますので、こちらで申し込みます。ネット申し込みなので、24時間好きな時にいつでも手続き可能です。
ただし、車検を行うのは平日のみになっているので、仕事をしている方は注意してください。年末年始(12月29日から1月3日)は運輸支局が閉まっているので、ユーザー車検は受けられません。
また、受付時間も決まっています。細かく決められていますが、基本16時までとなっているのでスケジュールの調整をしてから申し込みましょう。
ユーザー車検を受ける当日ですが、まずは運輸支局で事務手続きを行います。
「自動車検査票」「自動車重量税納付書」「継続検査申請書」を入手して必要事項の記入をします。これらの書類はホームページからも入手可能です。記入方法は運輸支局に見本がありますので、こちらを参考にして作成してください。
その他には、自動車重量税や検査手数料の支払いをします。さらに、自賠責保険の継続加入手続きを代書屋などで行いましょう。
全ての手続きを完了したところで、運輸支局の窓口に書類を提出します。問題なければ、実際の車検を受ける流れです。車検に合格すれば、車検証が交付されます。
もし不適合とされた場合、2週間以内であれば不適合箇所のみの検査を受けて、クリアできれば車検通過扱いになります。
ユーザー車検のメリットの一つに、費用の安さが挙げられます。
ディーラーなどのお店にお願いした場合、車検基本料、部品交換費用などがかかりますが、ユーザー車検の場合、法定費用だけになります。
法定費用は車種によって異なります。小型車の目安としては30,000円程度、ミニバンなどの場合は60,000円程度で車検が受けられると思ってください。
ディーラーで車検を受けるとなると、場合によっては100,000円近くかかる場合もあります。それと比較すると、かなりコストを圧縮できるのが分かるでしょう。
DIYした車をユーザー車検に出すにあたっての注意点

DIYした車をユーザー車検に出す場合には、専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。保安基準の中には専門的な知識が必要な項目もあるからです。
中には、ある程度元に戻さないと基準を満たさない恐れがあります。もし車検をクリアできるかどうか心配であれば、テスターを前もって受けるのがおすすめです。
もし、テスターで引っかかる項目があれば、車検合格するのは厳しいと考えてください。
テスターは民間のサービスで、1500~3500円程度費用がかかります。自分の判断だけでは車検通過できるかどうか心もとなければ、テスターに出してみるといいでしょう。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!








