個人事業主や会社経営している方の中には、ビジネス用として車両を保有しているケースも多いでしょう。この場合、車両を必要経費として計上することが可能です。
しかし、1年間で全額経費として計上するのではなく、減価償却という手法を使うのが一般的です。
この記事では、事業用車両を購入した場合の減価償却で処理する仕方について解説します。
また、車を保有していると車検を定期的に通す必要があります。車検は経費として計上できるのか、勘定科目はどのようにすべきかについても紹介します。
車検費用を経費として計上することは可能?
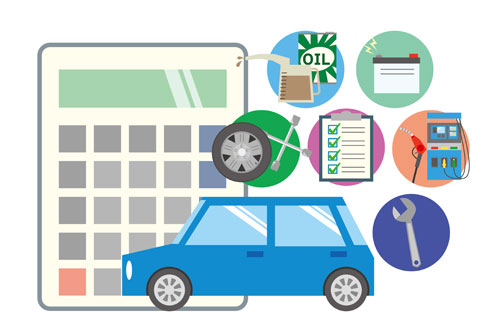
事業用車両を車検に通した場合、経費として計上できるかどうかは、どのような形態で仕事をしているかで変わってきます。
個人事業主のように自分で仕事を行っている場合は経費として計上可能です。
しかし、会社員のような給与所得者は経費としては認められないので、注意してください。
個人事業主で、自分で仕事を取ってきて報酬を受け取っている方なら車両を経費として計上できる可能性があります。ただし、車を保有していれば全員計上できるかというと、そうではありません。
個人事業主でビジネスで車両を利用している場合には、経費として計上が可能です。しかし、プライベートで乗っているだけで事業のためには使用していないという場合には、経費として計上できいないことになっています。
ただし個人事業主だと、事業用とプライベート用両方で車両を利用しているケースが多いかもしれません。この場合は、事業用の部分だけ経費として計上できます。
例えば、車検費用が100,000円だったとして、事業用とプライベート用半々で車を利用していたとします。この場合、車検費用の半分つまり50,000円分は計上可能です。
実際に事業用に自動車を使っている場合、車両関連の費用は経費として計上可能です。そのため、車検以外の費用も経費として計上できる可能性があります。
具体的には自動車税や自動車取得税などの自動車関係の税金や、自賠責保険と任意保険などの保険料も経費として計上可能です。
その他にもガソリン代や高速道路をはじめとした有料道路の通行料、駐車場を別に借りている場合にはその費用も経費になります。
さらに、タイヤ交換などのメンテナンスにかかったコストも該当します。
ただし100,000円以上の費用がかかっている場合は、処理の仕方が変わりますので注意してください。それは、減価償却という形で処理が必要になるからです。
個人事業主は一定の条件を満たしていれば、車に関する費用を必要経費にできます。しかし、会社員となると話は別です。
会社員などの給与所得者は、車に関する費用は経費計上できません。原則マイカーを事業で使用することはないからです。
会社員は、仕事のために自家用車を使用したら給与所得控除が適用されます。この控除が事実上の経費計上になるので、さらに必要経費にはできないわけです。
ただし、一部例外もあります。自家用車で会社に通勤している場合、特定支出控除が適用されるかもしれません。これは、会社から交通費の支給がないことが前提条件となります。
また、特定支出控除はガソリン代や有料道路の通行料のみが該当します。車検の費用は適用外です。
車検費用と勘定科目の関係

個人事業主の場合、車検費用を経費として計上できます。この場合、車検費用の勘定科目がどうなるのか気になるところでしょう。
「車検費用」と言っても、その中にはいろいろな料金が含まれています。その項目ごとに勘定科目も変わってきます。
車検費用は、「点検・整備費用」と「法定費用」の2つの項目に分類されます。そして項目ごとに処理の仕方が違ってきます。
点検・整備費用とは、車検を担当する工場に支払う費用のことです。点検や整備に関する費用、整備工場に車検をお願いするにあたっての代行手数料などが該当します。
法定費用とは、国や保険会社に支払う費用のことです。法律によって、自動車の所有者には支払い義務が課せられている費用があります。
それは、自動車重量税や印紙代などの税金です。
また、公道を運転する際には自賠責保険への加入が義務付けられています。この自賠責保険料も法定費用の一つになります。
点検・整備の費用として、まず車検基本料については「修繕費」もしくは「車両費」という勘定科目を使いましょう。
修繕費は固定資産のメンテナンスに必要な支出、車両費は車に関する支出を意味します。
どちらを使っても問題ありません。管理しやすいほうを使用してください。
車検代行手数料や部品交換した場合の費用も、同じような扱いで構いません。
ただし、部品交換費用については若干注意が必要です。もし修理したことで車の使用可能期間が延びた、価値がアップしたら、これは税務上の資本的支出に該当するかもしれません。
資本的支出に該当すれば、減価償却を行う必要が出てきます。ただし、支出が200,000円未満で、修理を3年サイクルで行っているのであれば、「修繕費」として処理しても問題ありません。
心配であれば、税理士など専門家に相談しましょう。
法定費用に関する勘定科目は、自動車重量税や印紙代の税金関係は「租税公課」で処理してください。自賠責保険料については「支払保険料」で処理するのがおすすめです。
ただし、自賠責保険は次に車検を受ける2年間分の保険料を前倒しで支払う形です。該当の事業年度以外の保険料まで含まれるということになります。そのため、「前払費用」もしくは「長期前払費用」と呼ばれる勘定科目が適切です。
通常であれば、当期の保険料分を損金として算出しますが、自賠責保険は法律によって、車の所有者は強制的に加入しなければならないと決められています。保険料を支払わないと、公道で運転ができなくなってしまうため、支払った事業年度に2年分の保険料を損金として処理できます。
車検費用の内訳によって、消費税のかかるものとそうでないものがあります。会計処理をするにあたって、消費税の分類について理解しておきましょう。
まず、整備費や車検代行手数料は課税の対象となります。また、自動車重量税や印紙代などの税金関係は不課税です。さらに、自賠責保険料は非課税扱いになります。
ここで混乱しやすいのが「不課税」と「非課税」の違いです。両方とも消費税はかかりませんが、その内容は異なります。
不課税とは、もともと消費税のかからない取り引きを指します。一方、非課税とは、本来消費税がかかるものの社会政策的な配慮から消費税をかけないものを指します。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
車検費用を経費計上する流れ

個人事業主で、事業のために車を使っているのなら車検費用を経費として計上できます。では、実際に経費計上するにはどうすればいいのでしょう?
ここからは、経費計上するための一般的な流れについて紹介します。これから帳簿をつける際は参考にしてみてください。
車検費用を経費計上するのであれば、費用に関する明細書を用意しましょう。車検の中にはいろいろな名目の費用が含まれていて、項目ごとに勘定科目も変わってきます。
車検費用の中で、どれをどの勘定科目で計上すればいいか、明細書を見て確認してください。
車検を受けて明細書をもらったら、なくさないように保管しておくことが重要です。
また、申告の前に明細書がきちんと保存されているか確認してください。申告直前に明細書がなかなか見つからなくて、書類作成に手間取らないようにしましょう。
車検に関連する領収書も、しっかり保管しておきましょう。住所変更登録をする際の車庫証明取得の費用なども、場合によっては経費計上できるかもしれません。
明細書が集まったところで、それぞれの項目をどの勘定科目で処理するか割り振りましょう。
車検費用をひとくくりで計上することはできません。
用途や性格の異なるいろいろな費用を、まとめて経費として計上できないため、項目ごとに適切な勘定科目をつけて、経費として処理します。
勘定科目の決め方は、厳格な決まりはありません。自分で自由に設定して大丈夫です。
ただし、広く使われている一般的なものを使用したほうが、確定申告の手続きもスムーズです。また、1回特定の勘定科目に決めたのであれば、それを継続的に使用したほうがいいでしょう。
個人事業主の中には、自家用車を事業用とプライベート用の兼用で使用している方も多いでしょう。この場合、車両に関する費用を全額経費計上できるわけではありません。
あくまでも事業用で使用した部分だけを、経費計上します。これを「家事按分」といいます。
ではどのように比率を決めるかというと、いろいろな方法が考えられます。
一般的には走行距離をベースにして、そのうち何割が事業用になるかで算出する方法です。
例えば全体の6割が事業用であれば、車の費用の6割を経費として計上できます。
青色申告で車検を計上する場合
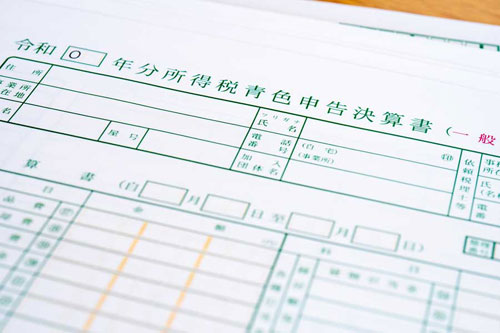
個人事業主の中には、青色申告で申請している方も多いでしょう。一般的な白色申告と比較して、基礎控除が多くなるなど税制面で様々な優遇を受けられます。
ただし、青色申告の場合は車検の費用を計上するにあたっていくつか注意すべきポイントがあります。そのポイントについてまとめたので、参考にしてみてください。
青色申告する場合、損益計算書を作成する必要があります。その中で、車検に関する費用を記載します。
損益計算書の中には、車両費という項目は含まれていません。ではどう処理するかというと、貸倒金の下にある空白の部分に追加してください。
損益計算書に計上する場合は、車検費用の他にもガソリン代などの車両に関する経費があれば、合算して計上します。
例えば事業分が4割だとした場合、車検費用が100,000円、ガソリン代が100,000円、高速道路の料金が50,000円かかれば、家事按分するとそれぞれ経費は40,000円、40,000円、20,000円になります。
車検費用とガソリン代と高速道路の経費をすべて合わせた100,000円を車両費として計上します。
車検を通すにあたって、自動車重量税や印紙代などの税金を納める必要があります。これらの項目は「租税公課」として処理します。
青色申告の損益計算書にある経費項目の中では、租税公課がトップの項目です。
租税公課には税金関係の金額をすべて合算して処理します。自動車重量税や印紙税の他にも、車検の時に支払うわけではありませんが、自動車税も含めないといけません。
自動車税も家事按分をして、事業分だけを経費として計上します。
車検を受ける際、次の車検までの自賠責保険料を前納します。この自賠責保険料も経費として計上可能です。損益計算書では「損害保険料」という項目で処理します。
損害保険料には自賠責保険の他にも、任意保険も該当します。また貸事務所を借りている場合、火災保険にも入っている可能性が高いです。火災保険も損害保険料に含まれます。
さらに自宅で仕事をしている場合でも、火災保険に入っていればこちらも損害保険料に該当します。
しかし、家事按分しなければならないので注意してください。
これら保険料はすべて合算することになるので、見落としているものはないかしっかり確認しましょう。
車を購入した場合の処理方法
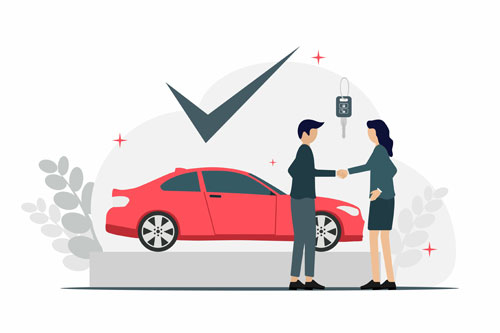
個人事業主の方の中には、これから事業用の車両を購入しようと思っている方もいるでしょう。この場合、通常の経費計上ではほぼ処理できないので注意してください。
車両の場合は原則、減価償却という形で処理をしていくのが一般的です。どのように処理すればいいかについて、ここでは詳しく見ていきます。
車を購入した場合、事業用で使用するのであれば経費計上は可能です。しかし、通常の1年間で必要経費に計上するのではなく、減価償却という形になるでしょう。
減価償却は100,000円を超えるような高額なものを対象にした処理方法となります。数年に分けて、徐々に一定割合を経費計上する形です。
減価償却の方法は、耐用年数によってその期間中に徐々に経費計上するやり方となります。
毎年どのくらい経費計上するか、「定額法」と「定率法」のいずれかを選択します。
定額法と定率法については後ほど詳しく説明しますが、一般的に個人事業主が減価償却をする場合だと、定額法を選択することになるでしょう。
減価償却するにあたって、毎年いくら経費計上するかで重要な要素になるのが耐用年数です。
耐用年数とは、固定資産として価値のある期間を指します。
耐用年数というと、車両が寿命を迎えるまでの期間のことだと思う方が多いかもしれませんが、そうではなく、国税庁が種類別で年数を定めているのでそれに基づき処理します。
車両の場合、どのような種類かによって耐用年数は異なります。
- 総排気量が660cc以下の小型車やダンプ式の貨物自動車が4年
- ダンプ式以外の貨物自動車や報道通信用の車両が5年
- 上記以外はすべて6年
自家用車であれば小型車以外、6年が耐用年数になります。
減価償却の方法は、少し前述しましたが「定額法」と「定率法」の2種類があります。
定額法とは、毎年決まった金額を経費として計上するので、毎年同じ金額になります。
一方、定率法とは、その時々の償却されていない残高に一定の割合をかけて経費計上する方法です。最初のうちは計上額が大きく、徐々に少なくなっていきます。
一般的に個人事業主であれば定額法、法人であれば定率法が適用されます。
しかし、必ず個人なら定額法を採用しなければならないかというと、そうではありません。個人でも定率法で処理することも可能です。ただし、定率法で減価償却する場合、税務署に事前申請しなければならないので注意してください。
自家用車の場合、耐用年数が6年間であるというのは新車購入した場合の話です。
中には中古車をマイカーとして購入する方もいるでしょう。この場合、耐用年数は6年間ではありません。
中古車の場合、利用できると推測される残り期間をベースにして、減価償却を進めます。では、その残り期間はどれくらいかというと、購入した車が耐用年数を経過しているかどうかで処理が違ってきます。
その車の法定耐用年数の20%が中古車の耐用年数になります。つまり、普通車の中古車を購入して耐用年数を経過している場合は、6年×20%=1.2年ということになります。
経過年数を差し引いたものと経過年数の20%を合算したものになります。例えば法定耐用年数が6年で4年経過している場合、(6-4)+(4×20%)=2.8年が中古車の耐用年数となります。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!








