かつては走行距離が10万kmに近づくと車の寿命と言われていました。しかし、今では技術が進化したこともあって、10万kmを超えた車でも現役で走行している姿も珍しくありません。
メンテナンスをこまめにやっていれば、20万kmを超えても問題なく走れる車両もあります。
ただし、20万kmを超えてきた場合、車検に通すかどうかで悩むという方もいるでしょう。
この記事では、走行距離が20万kmを超えた車を車検に通すべきか、通した場合の注意点についてまとめました。
20万㎞を超えた車を車検に出すべきか?
走行距離20万kmを超えた車を車検に通すべきかどうかは、人によってそれぞれでしょう。
マイカーに愛着があれば、車検を通して引き続き乗り続けるのも選択肢の一つです。
ただし、20万kmを超えた車を車検に通す場合、他の車両と比較して余計な費用がかかります。ここからは、その費用について詳しく説明していきます。
車検に通すべきかは、その費用について理解してから判断しましょう。
整備に時間と費用が掛かる

20万kmを超えた車両は、いろいろとガタがきている可能性が高いです。部品の劣化が進んで、交換や修理も必要になるでしょう。
そのため、20万kmオーバーの車を車検に出すと、点検・整備費用が高くつく可能性があります。
特にエンジンや足回りは、10万kmが一つの区切りとされています。20万kmとなれば、もう1回エンジンや足回りの整備を丁寧に行わなければなりません。
見積もりを出してもらう時には、点検・整備費用がいくらになるのか確認してください。
また、20万kmを超えた車両の場合、部品がもうすでに生産中止になっている可能性があります。その部品を調達するのに手間を取るため、車検に時間がかかる恐れもあります。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
自動車税が高くつく可能性

車を所有している人は、毎年自動車税を納めないといけません。自動車税とは、毎年4月1日の時点で車を保有している人に対して課税される税金です。
自動車税の金額は排気量をベースに決められていますが、これに加えて年式によっても税額が変わってきます。新車登録されてから13年以上経過したガソリン車は、税額が約15%もアップしてしまいます。
ちなみに、ディーゼル車では11年以上で税額アップの対象となり、ハイブリッド車の場合は税額アップはされません。
20万kmを超えている車は、この条件に達している可能性が高いです。通常よりも多く自動車税を負担してもその車に乗り続けたいのか、慎重に判断しましょう。
自動車重量税も高くなる

車検を受ける際に自動車重量税を納税しているでしょう。自動車重量税とは、文字通り車両の重さに合わせて税額が決まる税金です。
この自動車重量税も年式によって重課される税金なので注意してください。その上、新車登録から13年と18年の2段階で税額がアップします。
走行距離が20万km超の車両の場合、新車登録から18年以上経過している可能性が高いです。そのため、通常よりも余計に納税する計算になります。
例えば、車両重量が1.5〜2トン以下のミニバンで2年自家用区分の場合、自動車重量税は13年未満で32,800円、13年以上で45,600円、18年以上で50,400円です。
18年以上経過した車両は、13年未満の車両よりも17,600円も余計に課税されます。
これだけの出費をしても構わないか、よく考えたほうがいいでしょう。
軽自動車税も高くなる
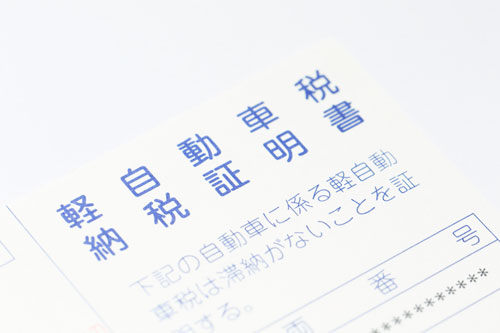
マイカーとして、軽自動車を所有している世帯も多くなっています。燃費が良くメンテナンスコストを安く抑えられるとして人気の車種です。
軽自動車の場合、普通自動車とは別で、軽自動車税を納税する義務があります。
軽自動車税についても、新車登録から13年以上経過すると重課税の対象となります。従来よりも約20%税額がアップします。
軽自動車税は、自動車税と比較して税額の安いのも人気の理由の一つです。しかし、古い車に乗り続けていると、その旨味が少なくなってしまいます。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
走行距離20万㎞超の車に乗り続けても大丈夫?

走行距離20万km超の車を車検に通すとなると、余計な費用がかかってしまいます。しかし、中には車に愛着を持っているので、そのまま乗り続けたいと考える方もいるでしょう。
20万km超の車両を引き続き運転するのはどうなのかということについて、ここで詳しく見ていきます。
問題なく走行できるのか、リセールバリューはあるのか解説します。
「自動車の寿命は走行距離10万km、新車登録から10年」という話を聞いたことがあるかもしれません。確かに、このようなことはかつて言われていました。
しかし、この格言は一昔前までの話です。今では10万kmを経過して、新車登録から10年以上経過した車両でも普通に街中を走行しています。
日本車は性能がよく耐久性に優れているので、海外でも人気です。海外に目を向けてみると、走行距離が20万kmや30万kmでも未だに走り続けている車両も少なくありません。
なぜ車の寿命が延びたのか、これはいろいろな事情が考えられます。技術革新によって性能が良くなったことも一因として挙げられますが、道路環境が整備されたことも大きいでしょう。
走行距離10万kmを超えている車だからと言って、すぐに処分しなければいけないわけではありません。
車の寿命が飛躍的に延びている背景として、性能面の進化が大きく関係しています。
車はなぜ寿命を迎えるのかというと、それは各種部品の劣化です。
特にエンジンの劣化が進んでしまうと、走行中不具合が出たり、最悪エンジンが止まったりします。しかし、今では各部品の性能や耐久性も上がっています。
また、塗料の性能が向上しているのも、寿命が延びた一因です。塗膜が外気から車両を守ってくれるので、ボディが劣化しにくくなりました。
そのため、走行距離10万km、20万km経過している車両でも買い替えずに乗り続けるドライバーも増えています。
一昔前までは、走行距離5万kmを超えると買取価格がガクッと下がると言われていました。そして、走行距離10万kmを超えた車両にはほとんど値がつかないというのが定説でした。
しかし、今では10万kmを超えた車両でも、コンディションが良ければそれなりの価格で売却できます。
また、買取業者の中には、海外に販売チャンネルを持っているところもあります。海外市場では日本車は耐久性に優れるということで、高い人気があります。
海外では、走行距離20万kmを超えた車でも乗り潰す感覚で購入する方も少なくありません。20万kmを超えた車でもきちんと整備して走れる状態なら、リセールバリューは十分あります。
走行距離20万㎞超の車のメンテナンスのポイント

走行距離20万kmを超えた車でも、現役で走行することは十分可能です。ただし、いろいろな部品の劣化や摩耗が進んでいることがあるので、こまめにメンテナンスをする必要はあります。
では、具体的にどのような部分に注意をすればいいのでしょうか?
以下にメンテナンスのポイントをまとめましたので、整備をする際の参考にしてみてください。
タイミングベルトは走行距離20万kmに差しかかってくると、寿命が近づいている可能性が高いです。
タイミングベルトとは、エンジンの点火やバルブ開閉などのタイミングに関わる重要な部品です。
タイミングベルトの交換時期は10万kmと言われています。20万km前後であれば、2度目の交換が推奨される時期です。
タイミングベルトはゴム製のものが中心です。耐久性には優れているものの、長く使い続けるとゴムが伸びてしまう、ひびが入ってしまう可能性が考えられます。
タイミングベルトが切れてしまうと、エンジン内部に大きなダメージを与える恐れがあります。その上、タイミングベルトのあるところにはカバーがかけられている車が多いです。外からは様子がわからないので、整備工場などで一度確認してもらうことをおすすめします。
車の心臓部と言われるのがエンジンです。エンジンがかからなければ、車を走行させることはできません。
エンジンも他のパーツ同様、長く使い続けていれば劣化も進みます。エンジンの不具合を早期に発見すれば、パーツ交換や修理だけで回復させられるかもしれません。
エンジンの不具合の症状として主なものは、異音がする、白煙が上がる、オイルがすぐに減るなどが挙げられます。これらの症状があれば、たとえ問題なく走行できていても整備に出しましょう。
エンジンが完全に壊れてしまうと、エンジン本体をまるまる交換しなければなりません。かなりの費用がかさみますので、異変を感じたらすぐに対処してください。
バッテリーの状態がどうかは、車の寿命を判断する有力な材料と言われています。
バッテリーの交換は、2~3年に1回のペースが好ましいとされます。
バッテリーの寿命が近づいていることは、症状で判断可能です。エンジンのかかりが悪い、バッテリー液がすぐに減ってしまう、ヘッドライトをつけた時に十分な光量が確保できないなどです。
寿命が差しかかっているバッテリーをそのまま使い続けると、電気系統の故障のリスクが高まります。最悪バッテリーが上がって、車が動かなくなる原因にもなりえます。
バッテリーの寿命が近づいてきたら、早めに交換しましょう。
エンジンオイルはこまめに交換したほうがいいと言われています。それはエンジンのコンディションを保つためです。
ガソリン車の場合、走行距離10,000kmもしくは1年、ターボエンジンの場合は走行距離5,000km、もしくは半年が交換のタイミングとされています。
ただし、車種によって若干異なる場合もありますので、メーカーの推奨交換時期をチェックしてください。
劣化したエンジンオイルをそのまま使い続けていると、エンジンに大きな負担がかかります。エンジンのパフォーマンスが十分発揮できなくなったり、ひどくなるとエンジントラブルが起きやすくなったりします。
オイルの警告ランプが点灯するまで交換しなくていいと考える方もいるかもしれません。しかし、警告ランプが点灯するのは状況がかなり悪化してからです。その前にこまめに交換したほうがいいでしょう。
ウォーターポンプは、エンジンの熱を冷ますためのパーツです。ウォーターポンプも定期的に交換したほうがいい部品の一つです。
ウォーターポンプの交換時期は、10万km程度と言われています。しかし、走行距離20万kmに差しかかっているのであれば、交換の時期も近づいていると判断してください。
ただし、この交換時期の差しかかる前に車両によってはウォーターポンプに不具合が発生する可能性もあります。冷却水の漏れや、エンジンの周辺で「キーン」といった甲高い音がする時は注意が必要です。
ウォーターポンプに異常が発生している状態でそのまま走行するとエンジンがオーバーヒートを起こしかねません。
走行距離20万kmに近づいているのなら、足回りのメンテナンスを進めておきましょう。特にタイヤの状態がどうかは、自分でもチェックすることが可能です。
タイヤの溝の中にある四角い目印があります。これはスリップサインといって、露出するとタイヤの摩耗がかなり進んでいる状態と解釈できます。
溝の深さが4mm程度までに摩耗しているのであれば、タイヤ交換をすることをおすすめします。
特に摩耗が進んでいなくても、5年を目安にタイヤ交換をすると安心です。
タイヤの摩耗が進むと、グリップ力が失われていきます。特に雨の日など路面がツルツルの時には、スリップしてしまう可能性があります。
また、タイヤのゴムの劣化についてもチェックしてください。ひび割れなどがあれば、速やかに交換しないと走行中にパンクする恐れが高まります。
デフオイルの交換もこまめに進めておきましょう。
デフオイルとは、ディファレンシャルという左右のタイヤの回転数を調整する部品で使われるオイルのことです。
デフオイルもエンジンオイル同様、長く使い続けると劣化が進みます。大体、走行距離2万kmもしくは2年経過での交換がおすすめです。
車の乗り方によっては、これよりも早く交換のタイミングが来るかもしれません。コーナリングを頻繁に行っていると、劣化が進みやすいと言われています。
ディファレンシャルそのものは、そんなに壊れる部品ではありません。しかし、デフオイルを交換していないと故障するリスクも高まりますので、注意が必要です。
定期的に洗車を行うことで、車の寿命を延ばせます。
このように言われると「洗車と車の寿命は関係ないのでは?」と思う方もいるかもしれません。
しかし、ボディの汚れや錆をそのまま放置しているとボディが劣化します。特に腐食が進むと、他の部品の故障になる原因になりえます。
洗車する際に目に見える部分だけでなく、ボンネットの中やボディの下もできる限り綺麗にしておきましょう。
特に雪国や海の近くに住んでいる方は、こまめに洗車することをおすすめします。雪国や海の近くは、塩害の発生リスクが高い地域です。塩分は錆の発生を促進する性質があるので、特に下回りを綺麗にして塩分を取り除きましょう。
走行距離20万㎞に来たらどうすればいい?

愛車が走行距離20万kmに差しかかってきたのであれば、考えるべきことがあります。それは、修理に出すか処分するかです。
まずは、引き続き車に乗り続けたいかどうかを決めましょう。その上で修理するか処分するかを選びましょう。
もし引き続き愛車に乗り続けたいと思っているのであれば、整備工場でメンテナンスをお願いしましょう。
別に問題なく走行できていても、整備に出すのがおすすめです。
走行距離20万km前後の車であれば、表に出ていない劣化があるかもしれません。本格的に故障する前に必要な整備をすれば、費用も安上がりです。
また、必要に応じてオイルや冷却水の交換や補充も進めておきましょう。
自分でできるメンテナンスはないか、整備工場の担当者からアドバイスをもらうのもおすすめです。
走行距離20万kmを気に買い替えたい、燃費が悪くなったり走行に支障が出たりしているのであれば、車を処分しましょう。
しかし、いきなり廃車手続きをするのはもったいないです。買取業者に出せば、いくらか値がつく可能性は高いです。最近では、事故車や不動車でも買い取ってくれる業者もあります。
廃車にするとなると費用がかかってしまいます。廃車に出す前に売却できないか、いくつか業者をあたってみるといいでしょう。査定を受けるだけなら無料なので、損をすることはありません。








