車を所有している以上、必ず定期的に受けなければならないのが車検です。しかし、車検では一体どんなことを検査しているのだろう…と疑問に感じている方は多いかもしれません。
車検の検査項目を知識として覚えておくと、愛車を車検に通すためのコツやポイントが分かります。また、車好きの方ならユーザー車検を行うことも可能になるでしょう。
この記事では、車検という制度の概要を踏まえつつ、その検査項目を解説します。
車検のチェック項目とは?
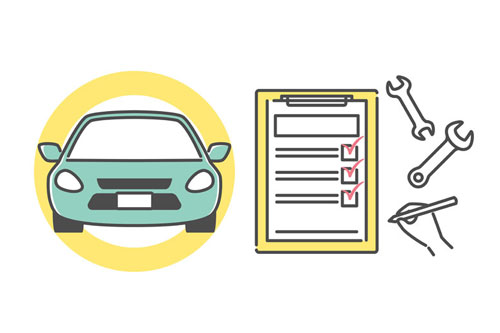
車を所有していると避けて通れないのが、定期的に受けなければならない車検です。
しかし、車検を受けなければならない法的義務やその重要性は認識していても、実際の車検でどのような点を検査しているのかを把握している方は少ないかもしれません。ここでは、その詳しい内容を説明します。
車検の内容を知っておくと、検査に通るか不安なときの対策にもなります。また、車に興味がある方ならユーザー車検のヒントにもなるでしょう。
そもそも車検とは?
車検とは、車が保安基準を満たしているかどうかを確認する「自動車検査登録制度」の略称です。確認のためのチェック項目も決まっており、チェックをパスしない車は、そのままだと公道を走れません。
保安基準は、安全や環境保護の観点から、その車が公道を走っても問題がないかを判断するために定められています。
もともと自動車は安全面や環境保護に配慮して製造されていますが、その後、オーナーの使い方次第で状態は変化します。車検の目的は、そうした変化によって予期せぬ事故などが起きないようにすることです。
乗用車の場合は購入してから3年後に一度車検を受けて、その後は2年ごとに受けるなど、車種によってその周期は異なるので注意しましょう。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
車検のチェック項目の概要

車検は、どこで受ける場合でも、また検査員が誰であっても、チェック項目は全て一律に定められています。
最初に行われるのは、車と車検証の内容が矛盾していないかをチェックする「同一性」の確認です。
次にタイヤ、窓ガラス、運転席から見た各種メーターなどの「外装・内装」のチェックとなります。
最後にライトやランプなどと呼ばれる灯火装置、ワイパー、ウインドウォッシャーなど、車の「外回り」を見ていきます。
車検では、車そのものを検査する前に、まず車と車検証の内容が一致しているかどうか確認する「同一性の確認」を行います。車種・車体番号・ナンバーなどの内容に矛盾があると、車検は受けられません。
次に行うのが外装のチェックです。まず、タイヤがどれくらい摩耗しているか、ヒビが入っていないかを確認します。タイヤの最も摩耗している溝の深さが1.6ミリ以下である場合は交換が必要です。
続けて、窓ガラス等のヒビの有無をチェックします。ここでチェックするのはフロントガラスや側面のガラスだけではなく、サイドミラーなども対象となるので、事前にセルフチェックする際は忘れないようにしましょう。また、ヒビが入っていなくても、貼っている着色フィルムの内容によっては不正改造と見なされるので気を付けてください。
そして、各種メーターの点滅・点灯状況もチェックを受けます。エアバッグ警告灯やシートベルト警告灯などのうち、どれか一つでも点滅していた場合は車検に通りません。
次に、シートベルトの状態やヘッドレストの存在など、車の内装も目視で確認されます。
発煙筒の有効期限が意外と盲点なので、事前にセルフチェックしておくといいでしょう。
次にチェックするのは、車両の外回りです。まずは車に装備されている灯火装置全般をチェックし、ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、バックランプ、ナンバー灯、ウインカーが全て点灯するかを確認します。
普段公道を走っていると、こうした灯火類が電球切れを起こしている車を見かけたことがあるかもしれません。自分ではなかなか気付きにくいものなので、車検前にセルフチェックする場合は見落とさないよう注意しましょう。
ワイパーも、きちんと作動して水しぶきなどをはらえるかチェックします。また、ウインドウォッシャー液が正常に噴射されるかどうかも確認対象となります。ノズルが詰まっているなどの原因で液がうまく出ないこともあるので、注意が必要です。
マフラーも、取り付け位置や音、触媒に異常がないかチェックします。マフラーは長期間使っていると劣化して穴が開いたり断熱材が詰まったりして音が大きくなり、検査で引っかかってしまうことがあります。
そして、ベアリングを保護しているドライブシャフトブーツや、ハンドル操作に関わるステアリングラックブーツも検査対象です。いずれも異常があると、車のコントロールに関わる重要なパーツです。
車検で落ちやすい項目とは?

次に、特に車検で落ちる原因になりやすい項目を紹介しましょう。
ヘッドライトはレンズに黄ばみ・曇りがあったり、保安基準を満たさない社外品のバルブに交換していたりすると車検に落ちます。
老朽化によってブレーキがうまく利かずに検査で引っかかるというパターンもあります。直進したときの車のズレを見るサイドスリップ検査では、1メートル走行して5ミリ以上ズレが出る状態だと車検に落ちます。
運転時のコントロールに大きく関わってくるため、いずれかに破れがあると確実に車検に落ちます。
車検で落ちたらどうなるの?

車検に落ちた場合は、問題ありと見なされた部分を改善する必要があります。その上で再検査を受けますが、車検当日に改善することができないと、再検査前に車検の有効期間を過ぎてしまうこともあるでしょう。
車検に通らないまま有効期間の満了日を過ぎた場合、その車で公道を走ると法律違反になります。それを防ぐためには、満了日から15日間だけ公道を走ることができる「限定自動車検査証」を発行してもらいます。
限定自動車検査証とは、車検証の代わりになるものです。15日間に再検査を受けてパスすれば問題ありません。
もし車検切れの状態で、限定自動車検査証なしで車を移動させるとなると、積載車での移動や仮ナンバーの取得を検討する必要が出てくるので注意してください。
再検査でチェックするのは、前回の検査で問題があった箇所だけなので、すぐに終わるでしょう。一方、有効期間満了日から15日間を過ぎてしまうと、検査は最初からやり直しになってしまうので注意してください。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
車検前の法定点検では何をチェックしている?
多くの場合、車検と一緒に法定点検を受けますが、法定点検では何をチェックしているのでしょう?
法定点検は車検とは別物です。車検は「点検」が目的なのに対し、法定点検は車の「整備」を目的にしています。
多くの場合、車検と法定点検は黙っていても同時に行われます。車の整備が行われ次に車検を受けるという流れになるので、実際には、よほどのことがなければ車検には通るものです。
法定点検は受けなくとも罰則がないので、車検だけを受けて法定点検を受けず、費用を節約するという考え方もあります。しかし、整備を怠って車検に落ちれば結局二度手間になりコストがかかるので、やはりワンセットで業者に依頼するのが得策でしょう。
車検前にセルフチェックできる箇所

車検で問題なく合格するように、あらかじめ車の状態についてセルフチェックを行うのも有効的です。
では、検査のプロでなくとも事前にチェックできるポイントにはどんなものがあるのでしょう。以下で詳しく見ていきます。
エンジンルームは素人には敷居が高く感じられるかもしれませんが、オイルの残量や液漏れの有無くらいなら確認するのも簡単です。
まず、エンジンオイルのレベルゲージをチェックし、規定通りの量が入っているか、また変色していないかを見ましょう。
ブレーキオイルやウォッシャー液も、同じように量と汚れ具合を確認することをおすすめします。
ウォッシャー液のタンクは、冷却水用のリザーバータンクと似た形をしているので注意してください。
運転席で行う日常的な運転操作を通して、セルフチェックできる箇所もたくさんあります。
ホーンが正常に鳴るかどうか、ワイパーの動作に問題はないか、動作に問題がなくてもワイパー自体が老朽化していないかなどを見てみましょう。
ライトやランプなどの灯火類も、普段の運転では電球切れに気付かないことが多く、検査で引っかかりやすいです。
また、メーターパネルの警告灯が点灯していれば何らかの不具合が考えられます。そもそも、警告灯が正常に点灯するかどうかも重要です。
あとは内装も要チェックです。前のシートのヘッドレストが外れていたりシートベルトが壊れていたりするなどの異常があれば、保安基準を満たしていないので車検には通りません。
タイヤは消耗品なので摩耗は避けられません。
摩耗が原因で溝の深さが1.6ミリ未満になり、スリップサインと呼ばれる印が出ていたら交換が必要です。また、劣化によって亀裂が入っている場合も同様です。
フロントガラスやサイドガラス、またミラー類も普段からチェックしておきましょう。稀に、飛び石や温度差によるヒビ割れが発生していることがあります。
また、フロントガラスや運転席よりも前方のサイドガラスに、透過率が70%を下回る紫外線カットシートなどを貼っていると車検には通りません。
以上の内容を見ていくと分かりますが、車検のチェック項目の中には、素人でも事前に点検しておけるものも多くあります。
車検前だからと慌てずに点検や修理をするのではなく、日常的に不具合のチェックをするようにしましょう。
特殊な車種が受ける車検や検査について

車検と言えば、多くの場合は自家用の普通自動車や軽自動車の新規検査・継続検査のことを指します。
しかし、車の検査にもいろいろあり、改造車や輸入車が受ける検査、特殊な車種が受ける検査などもあります。以下で詳しく見ていきましょう。
バイクの場合、車検のチェック項目は6つに大別されます。乗用車と同じく同一性の確認から始まり、騒音や排ガスの検査、ブレーキの制動力チェック、スピードメーター、ヘッドライトの光量などです。
多くの項目は、通常の運転時に大きな異常がなければ問題なくクリアできるでしょう。
費用については法定費用として約2万円がかかり、それ以外の諸費用としてさらに約2万円以上がプラスとなります。
車をカスタマイズ(改造)したことで、車の構造が車検証に書かれている内容と異なる場合は、「構造変更検査」を受けなければなりません。いわば改造車用の車検で、これを受けると前回の車検の内容はいったんリセットされます。
構造変更検査は、ボディサイズの変更や乗車定員の変更など、改造によって保安基準に抵触する恐れが生じた場合に受けなければなりません。これをパスせずに通常の車検を受けても、落ちる可能性が高いです。
「改造によって車が新しく生まれ変わったことで、車検証の内容も一から作り直しになるんだ!」と、考えると分かりやすいでしょう。
予備検査は、まだ新規登録されていないナンバーを持たない車に対して行われます。この検査にパスすると「自動車予備検査証」が発行され、検査証の有効期限である3カ月以内に、新規登録の手続きができるようになります。
廃車にしてナンバーが付いていない車をオークションで入手した場合、こうした予備検査が必要になります。オークションで「予備検査付き」と記されている車を見かけることがありますが、これはナンバー取得のための新規検査とは異なりますので注意しましょう。
後述しますが、予備検査は並行輸入車に対しても行われます。海外向けの車は日本国内の保安基準に合致しないことも多く、新規登録を行う前に、一度予備検査を実施します。
ユーザー車検は、車検を業者に依頼せずにユーザーが自分で行うものです。
検査項目は業者に依頼した場合と同じなので、車の扱いに慣れている方なら、事前にセルフチェックやメンテナンスを行って合格させることができるでしょう。
ユーザー車検は、一度申し込みをすると3回まで連続で検査することができます。検査後に書類を提出してチェックを受けますが、これで不合格となっても、合計3回までは連続してチャレンジできます。
車検を行う場所は陸運局です。そこに自分で車を持ち込み、検査することになります。
ユーザー車検の魅力は、業者に依頼しないため車検費用の何割かを節約できる点です。しかし、法定費用は一律にかかりますので気を付けましょう。
外車(輸入車)も車検の項目は国産車と同じですが、基準値の設定やその測定方法が独特な上に専門の知識・技術・機器も必要となります。
もしも購入する場合は、車検を受け付けてくれる業者が限られてくるという点は覚えておきましょう。
並行輸入車とは、日本国内のメーカーが海外向けに製造販売した車を、いわば日本に逆輸入したもので、逆輸入車とも呼ばれます。
並行輸入車は、輸入直後に試験を行い、そのあと予備検査を受けて、そこから改めて車検を受けて新規登録するという3段回での手続きが必要になります。
まず、並行輸入車は、輸入直後に排ガス試験と加速時の騒音試験(アメリカ車に限る)を受けなければなりません。個人ではできないので、国内3カ所にある専門機関で実施することになります。
この試験をパスすると、書類を作成して審査を受けます。そして予備検査を経て自動車予備検査証を入手し、それから期限までに新規登録を済ませるという流れです。
普通の外車(輸入車)なら、最初から日本の保安基準を満たした仕様になっています。そのため、専門知識が必要ではありますが比較的簡単に車検も通るでしょう。
しかし、並行輸入車は新規登録までの手続きがこのように大変です。手間と時間がかかることを覚えておきましょう。
工事現場などで使われる大型の建設機械、物品を運搬するための荷役運搬機械、それに高所作業車などは、車両系建設車両として「定期的自主点検」を行う必要があります。
定期的自主点検は、労働安全衛生法に基づく規則です。こうした車両を扱う事業者は、1年以内ごとに1回ずつ検査を行わなければなりません。
検査の種類は、自社内の有資格者が検査者となって行う「事業内検査」と、外部の登録検査業者が依頼を受けて行う「検査業者検査」に分けられます。








