ゲリラ豪雨などの異常気象の影響で、近年は車が水没する事故が増えています。しかし重大事故に至らなくても、ある程度の大きな水たまりを通過するだけで、車は大きなダメージを受けることがあります。
例えば、エンジンやマフラー内部に水が入れば車は動かなくなりますし、電気系統が水をかぶった場合も同様です。そのため、深い水たまりや冠水した道路を通過した場合は、車の状態を点検しましょう。
この点検のポイントについて詳しく解説していきます。
水たまりや冠水した道路には要注意!
車を運転していると、異常気象に遭遇し、水たまりや冠水した道路を通らざるを得なくなることがあるかもしれません。こうした場所を走行した場合に発生しやすい故障や不具合、それを含めた注意点などを詳しく説明していきます。
車体がどこまで浸かると危険なのか

大きな水たまりや冠水した道路を走行する場合、安全に走れるのは「水面がタイヤの高さの半分以下」の水深までだと言われています。ただし、これも大まかな基準で、水しぶきが高く上がる速度で走れば、水面よりも上の位置にまで影響が及ぶでしょう。
また、コンパクトカーやセダンのような最低地上高の車両と、SUVタイプのようにタイヤが大きく車高も高い車とを比較すると、水たまりや冠水から受ける影響も異なってきます。
オフロードでの走行を前提に製造されているスズキのジムニーやトヨタのランドクルーザーなどは、特に心強いでしょう。
総じて、水面が車の底面に達するほどの水深であれば、そこが限界だと考えられます。それ以上だとマフラーや吸気口から泥水が流入し、車の重要部品に影響を及ぼしかねません。
それでも突っ切って脱出し、後に修理に出すことができればまだ良いほうです。最悪の場合は、エンジンやラジエーターが故障して立ち往生する恐れもあります。
車が水の中にはまった場合、水の高さがドアの下端よりも上に来たらかなり切迫した状況です。そのまま水かさが増えないならまだ安心できますが、確証がない場合はすぐに脱出しないと命に関わります。
水の高さが上がってくると、水圧が思いのほか強くかかります。水面がドアの下端よりも上に来てさらに水かさが増すと、車内からドアを開けるのは少しずつ難しくなります。これは、スライドドアでも同じです。
そのまま水かさが増し続けて水面がタイヤよりも上に達すると、今度は車体が浮き上がるかもしれません。タイヤには気体が詰まっているので浮袋の役目を果たす形になってしまうためです。
車が流され車内に水が侵入し、ドアの半分ほどの高さまで来ると、内側から開けるのはほぼ不可能となります。
水たまりの水面がドアの下端を超えそうになったら、リアウインドウやドアガラスを割って車外へ脱出することを考えましょう。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
考えられる故障とそのメカニズム
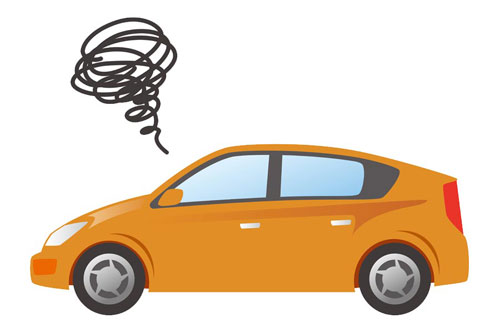
水たまりや冠水道路を走行するとそれだけで車の故障リスクが高まりますが、具体的にどのようなメカニズムで、どういった形での故障や不具合が生じるのでしょう?
以下では、走行不能になりかねない最も危険な3つのパターンを説明します。
まず、エンジンの空気の取り入れ口である「吸気口」から水が入り込むことが考えられます。
吸気口は、車のボンネットに近い最も上部にあり、ここから取り入れた空気がガソリンと混ざることで点火・燃焼します。つまり、ガソリンを燃やして車を動かすのに欠かせない装置が吸気口です。ここが浸水すると詰まってしまい、空気を取り込めなくなります。
もちろん、ちょっとした豪雨や水はね程度ならめったに詰まらない設計にはなっていますが、冠水道路は特に注意しましょう。吸気口そのものが水に浸かることは少ないものの、冠水道路での激しい水はねが原因で浸水を許すことがあります。
特に、速度を上げて大きな水しぶきを上げると、タイヤハウスからエンジンルームへと浸水し、吸気口が詰まる確率も高まります。
吸気口が詰まりさらに泥水がエンジン本体に及べば、エンジンが完全に壊れるかもしれません。
これを防ぐには、冠水状態の中では焦らずにノロノロと運転することです。
車は、マフラー(排気口)から浸水しても走行不能になることがあります。
マフラーはバンパーの下にあるので、水面がドアの下部やフロアにまで達したら、マフラーに浸水している可能性が大きいです。
車のエンジンは、ガソリンと空気を混ぜた混合気を燃焼させて車を動かします。この時発生したガスがマフラーによって外に排出されるものが、いわゆる排気ガスです。
排気ガスが排出されないと、空気の取り込みと燃焼がうまくいかなくなります。つまり、冠水道路でマフラーに浸水して詰まってしまうと、それが原因でエンストが起きるということです。場合によってはそのまま排気系やエンジン自体の故障にもつながります。
これを防ぐには、冠水道路では減速し、必要以上に水はねを起こさないことです。エンジンの回転数を落とさずに排気ガスを絶え間なく出し続ける方法もありますが、これをやりつつ減速するのはテクニックを要するので、まずは慌てずゆっくり脱出するようにしましょう。
「電装品」と呼ばれる電気・電子機器にとっても、水は天敵です。
漏電対策はなされていてもやはり電気系統は水に弱く、また重量物ゆえに車体の下部に設置されているものもあるので冠水時には大変不利です。
車体の下部に設置されており、冠水時にダメージを受けやすいものとしてはEVやPHEV(プラグインHV)用の大型バッテリーが挙げられます。シートの下やトランクの下に配置されていることが多いです。
こうした電装系が水に浸かって故障すると、まず電子部品のショートによって制御システムが作動し、走行不能になることがあります。それに加えてパワーウインドウや自動スライドドアが作動しなくなれば、車内からの脱出もままならなくなるでしょう。
とはいえ、水たまりや冠水した道路を通過したことが原因で車が故障する場合、電装系が中心に壊れることはあまり多くありません。そうなる前に吸気口やマフラーが詰まるケースが大半です。
故障しなくても車に起こる不利益がある

車が泥水に浸かると、上述の通り故障や不具合が起きるリスクが高まります。しかし仮に故障まで至らなかったとしても、車を乗り続ける場合や売却する場合などに、大きな不利益を被ることがあるので覚えておきましょう。
水没した車の場合、たとえ故障や不具合が起きなかったとしても、売却査定で不利になることがあります。泥水を被った車は「水没車」と見なされるからです。
水没車とは、日本自動車査定協会(JAAI)によって、集中豪雨や洪水でフロア内に浸水したものと定義されています。こうした車はその時は特に問題がないとしても、後に腐食による故障や不具合、雑菌やカビによる悪臭の発生、汚れ、不衛生さから査定時に減点されます。
この減点の計算方法は、車両の基本価格×減点率です。例えばフロアまで水没したなら減点率は30%ですが、エンジンが車の床下にある場合は、フロアに浸水しただけでもさらに減点率が上がります。また、クッションの上部まで浸水すれば40%、ダッシュパネル上部までいけば50%です。
いずれもエンジンや電装系に故障が起こり得るレベルなので、こうなると水没車や事故車を専門に買い取る業者でないと値段がつかないでしょう。
水たまりや冠水道路を通過して車内まで水浸しになった車は、衛生面や乗り心地の観点からも問題があります。それは汚水をかぶったことで、悪臭・カビ・サビが発生しやすくなるからです。
汚水をかぶった車はクリーニングすることもできますが、フロアまで浸水した場合はフロアマットやカーペット、シート、さらに遮音材と呼ばれるスポンジにも染み込んでいます。それらを全て新品交換しないと雑菌の繁殖は抑えられず、カビや悪臭の発生は避けられないでしょう。
また、そうしたパーツを新品と交換しても、クリーニングの及ばない場所が必ずあるので、車を完全に綺麗にするのは難しいとされています。
基本的に車は通気性が悪く温まりやすい構造になっているので、雑菌やカビにとっては繁殖しやすい環境です。
また、海水を被った場合は塩分によって金属部品の劣化も進み、故障や不具合が起きやすくなります。
水に浸かった車体の点検ポイント

ここまで説明した通り、車が汚水に浸かってしまったら、その車は全般的に様々なリスクを背負うことになります。
そのため、浸水したらすぐ業者に見てもらうのが一番なのですが、その前に不具合がないかどうか自分で点検するポイントを3つ紹介します。
水たまりや冠水路で車が水没した場合に最も気を付けなければならないのが、吸気口かマフラーから水が入り込んでエンジンに異常をきたすことです。
水没した状態から無事に抜け出してその後も異常がないように感じられても、真っ先にエンジンを点検するようにしてください。
水没後のエンジンの具合を確認する最も簡単な方法は、オイルの状態をチェックすることです。エンジンの内部に水が大量に入り込むと、水とオイルが混ざって「乳化」という現象を起こし白っぽくなります。普段レベルゲージを見慣れている方なら、この状態になっていればすぐに気付くでしょう。
ただし、それが致命的な状態であるかどうかは、最終的には専門家に判断してもらうのが得策です。
ここまで見てきた内容からも分かる通り、一度水没した車は、今後どのような面で不具合が生じるか分かりません。急に走行不能になったりしないうちに、専門の業者に見てもらいましょう。
浸水によって部品の隙間に水が入り込むと、ブレーキの効きが悪くなることもあります。水たまりや冠水道路を通過した直後は、ブレーキを数回踏んで異常がないか確認してください。
ブレーキの多くがディスクブレーキといって、露出している構造なので濡れやすく乾きやすいです。
一方、軽自動車やコンパクトカーなどで多く採用されているドラム式の場合は露出が少なくなっています。ドラム式は一度濡れると乾きにくいので、ブレーキに不具合があればすぐに修理しましょう。
水たまりや冠水が理由で起きる故障は、他にも様々なものがあります。例えば、台風や水害に伴って流されてきた瓦礫などが泥水の下に沈んでおり、気付かずに通過してタイヤがパンクするケースです。
また、タイヤは泥水に浸かってしまうとホイールの内部にサビが発生することがあります。そうなるとタイヤやホイールの交換が必要となる場合が出てきます。
冠水の度合いによってはブレーキローターの交換が必要となったり、ホイールが取り付けられているハブベアリングにサビの発生や異物の混入があると、走行時に異音が発生したりすることもあります。
車体が水に浸かることによる直接的な故障について前述しましたが、フロアに浸水すると、その直後は問題がなくても「湿気」で不具合が起きることもあります。
車のフロアの下には吸音材と呼ばれる厚いスポンジがあり、水をたっぷり吸っています。車内の温度上昇や暖房の使用により、吸音材に染み込んだ水分が蒸発すると結露が生じます。その水滴で電装系に異常をきたすこともあるので、注意しましょう。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
保険の対応について

水たまりや冠水道路を走行したことで車が故障したら、自動車保険(任意保険)の車両保険の補償を受けられるか確認してみましょう。
車両保険にはいくつかのタイプがありますが、自然災害で車が水没した場合も多くの場合は補償されます。ただし、いくつか注意点もありがあります。
まず、水没による故障が発覚したら時間を置かずにすぐ保険会社へ連絡してください。あまり間が空くと、その故障の原因が水没のせいだと立証しにくくなるためです。
また、車両保険は原則として修理のための費用が補償されます。しかし修理費が保険金額を上回る場合や、エンジンもやられて修理不能だった場合は「全損」扱いとなり、設定された額しか支払われないので自己負担が必要となります。
さらにこうした形で車両保険を使うと、次の年の等級がランクダウンすることも覚えておきましょう。過去に事故を起こした契約者に設定される「事故有り係数適用期間」も1年分プラスとなるので、要注意です。
冠水道路を走る際の注意点

水たまりや冠水道路に遭遇したときの対処法は、「そうした場所をすぐに避ける」ことです。
泥水は水深が分かりにくいので、もしもうっかり深みにはまった上に車内に浸水してきたら、慌てずに退避しつつ、場合によっては車を捨てて脱出することも考えましょう。
水たまりや冠水道路では、ある程度の水位に達すると車もあっという間に動かなくなります。無理に走行すれば吸気口やマフラーから水が侵入してエンジン停止、タイヤが水没すれば車体が浮いて操縦不能、ドアにまで水が達すれば開かなくなって命に危険が及びます。
こうしたケースに備えて準備しておくと心強いのが、窓ガラスを割るのに使う脱出用ハンマーや、シートベルトカッターです。電装系が故障するとパワーウインドも開かなくなるので、最後の手段として使うといいでしょう。
車の窓ガラスは簡単には破壊できず、基本的にハンマー以外で割るのは困難です。また、フロントガラスは割れないので覚えておきましょう。
大雨時の危険度の判断基準について

ここまで、大雨などによる車の走行時のリスクや注意点を説明してきました。ではそうした事態を避けるにはどのような対策が有効なのでしょう?
以下では、大雨が降った時の危険度を判断する基準となるものを3つ紹介します。
自然災害が多発していることから、近年重要度が増しているのがハザードマップです。主に市町村が作成しており、集中豪雨や台風が起きた場合に浸水や土砂災害の発生リスクが高い地域を事前に確認できます。
ハザードマップを確認すれば、特に冠水しやすい場所が把握できるでしょう。スマホなどでも気軽にチェックできるので、天候や河川の状態が普通ではないと感じた段階で、危険な場所と比較的そうでない場所を調べておくことが大切です。
雨量を基準として危険度を判断するのもおすすめです。車を運転する際は、地域ごとの大雨や洪水情報をチェックしましょう。
また、気象庁のホームページには、雨の降り方から受ける印象によって運転時の危険度が分かる「雨の強さと降り方」という一覧表も設置されています。
普段よく通る道路の場合、大雨の際に危険かどうかを事前にイメージしておくのも大切です。例えば、河川や用水路・排水溝と並行していたり田んぼに面していたりする道路は、水があふれると道路との境界線が分からなくなります。
また、高架下やアンダーパスは水が溜まりやすい上に、一度はまると脱出しにくい構造です。山沿いの道路でも土砂崩れや道路の寸断、孤立化の危険があるので、慣れた道でも普段から迂回路などを把握しておきましょう。








