自動車は数多くの部品で構成されていますが、安全性を担保する部品として非常に重要な役割を担うのがブレーキです。ブレーキパッドはブレーキを構成する部品のひとつで、運転するほどに劣化していく消耗品です。
この記事では、重要部品であるブレーキパッドの点検方法や寿命、交換時期の目安や費用について解説します。車を安全に運転できるようにするために、ブレーキパッドについて正しく理解し、快適なカーライフを送りましょう。
車の点検ではブレーキパッドも確認しよう!
車の点検時には、消耗部品の状態を確認し、適宜交換していかなければいけません。交換部品というと、バッテリーやエンジンオイルが思い浮かびますが、ブレーキパッドも忘れてはいけない重要な消耗部品です。
ブレーキは自動車を制動するため、安全性において極めて重要な役割を担う部品です。ブレーキパッドを万全な状態に保つことは、事故の減少につながります。事故が減れば車や命が守られることはもちろん、修理による費用や自動車保険料の低減にも結び付くため、間接的に経済メリットを享受できます。
ブレーキパットについて正しい知識を持ち、車の点検時には他の消耗部品と同様に精査しましょう。
ブレーキパットとは?

ブレーキは、車のタイヤの回転を止めるための仕組みです。ブレーキには大きく分けると、「ディスクブレーキ」と「ドラムブレーキ」の2種類があります。
ブレーキパッドはディスクブレーキを構成する部品です。ディスクブレーキはタイヤとともに回転する金属の円盤(ディスクローター)を両側からブレーキパッドで挟み込み、摩擦の力で回転を止める仕組みです。強い回転を止めようとすれば、パッドは摩耗します。
交換時期が過ぎてもそのまま使い続けると、摩擦力が弱まってブレーキが効かなくなったり、ディスクローターが傷ついたりして修理費が発生してしまいます。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
ブレーキパットの種類
ブレーキパッドは大きく分けて「レジン系パッド」と「メタル系パッド」の2種類があります。レジンは樹脂、メタルは金属を意味します。
それぞれブレーキパッドの素材を表しており、素材の違いによるメリット、デメリットが存在します。2種類のブレーキパッドの特徴を理解し、車の使用目的によりどちらのタイプが適しているのかを把握しておきましょう。
レジン系パッドは、金属や樹脂を混ぜ合わせたものを樹脂で固めた素材で作られたブレーキパッドです。
素材が柔らかいためソフトなブレーキングに適しており、街乗りが多い自動車になじみやすい特徴があります。また価格が安いというメリットもあります。
デメリットは、急ブレーキなどの強いブレーキングの際の制動力が、硬い素材のものに比べて低いことです。他にも耐久性が短めであること、湿度が高い日は制動力が低下することが挙げられます。
メタル系ブレーキパッドは、金属を加工した素材で作られたブレーキパッドです。
硬い素材のため、強いブレーキングに対する制動力が高いことが最大のメリットで、スポーツタイプの自動車に適しています。部品としての耐久性がレジン系パッドより長いのも特徴です。
一方、硬い素材でディスクローターを挟み込むため、ブレーキ鳴きしやすくディスクローターを傷つけやすいというデメリットがあります。レジン系パッドより価格も高めです。
ブレーキパッドを交換するタイミング

ブレーキパッドはディスクローターに対して、力をかけて挟み込むことで回転を止める役割を果たします。従って、使用する度にブレーキパッド自身にも力がかけられるため、徐々に削られていく部品です。
ブレーキパッドは、新品の状態で10mmほどの厚みがあります。目安として10,000km走行するごとに1mmずつ摩耗していくといわれています。残りの厚みが2mm~3mmになったら交換しましょう。
自動車の使用具合によって摩耗ペースには差が生じるため、ブレーキパッドが新品の状態から30,000~50,000km走行したタイミングで点検するのがよいでしょう。
また、バイクのブレーキパッドは消耗が激しく、5,000km~10,000kmが交換の目安といわれているため、注意してください。
ブレーキパッドの交換には費用がかかりますが、薄いブレーキパッドの使用は周辺のブレーキ部品の損傷につながり、他の部品に対してさらなる費用がかかる原因にもなり得ます。
以上のことから車検通過の可否よりも、安全の目安とされるブレーキパッドの状態を意識して交換するのがよいでしょう。
ブレーキパッドの残量を確認する方法
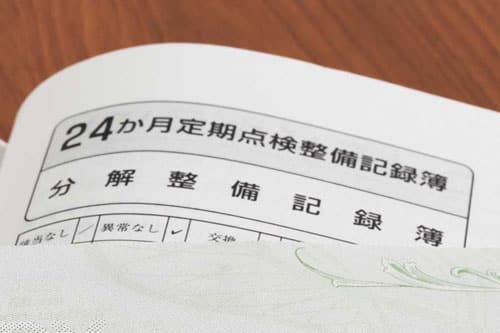
先ほど紹介した通り、ブレーキパッドの交換目安となる厚さは2mm~3mmです。しかし、車の点検時にブレーキパッドの残量を確認できなければ、交換の必要があるかどうかを判断できません。
ここでは、ブレーキパッドの残量を確認する方法を5つ紹介します。いずれも現在の残量をミリ単位で確認できるものではないため、あくまでも交換の予兆を知る手段として理解してください。
1つ目の方法は「点検整備記録簿」の確認です。点検整備記録簿は、車の定期点検を受けたときに結果が記録されている用紙です。一般的には車検証ホルダーに車検証とともに格納されています。
点検整備記録簿には、点検時点においてのブレーキパッドの厚さが1/10mm単位で前後輪それぞれに記載されています。
走行距離10,000kmで1mm摩耗するという目安がありますが、最後に交換してからの走行距離と照らし合わせることで、自分の運転ではどのくらいのペースで摩耗が進んでいるのかを割り出すことが可能です。
点検時に交換の必要に迫られていなくとも、今後の目安として重要な情報となるでしょう。
2つ目の方法はブレーキをかけたときの異音の確認です。
ブレーキパッドにはインジケーターという部品がついており、パッドの残量が減ってくると、ブレーキをかけたときに異音を発します。異音を認識したら、ブレーキパッドを点検し、必要に応じて交換しましょう。
異音の種類と症状には、以下のようなものが挙げられます。
- 「キー」「シャー」…ブレーキパッドの残量が僅か
- 「カラカラ」…ブレーキパッドの割れ
- 「ゴー」…ブレーキパッドとブレーキローターの金属部の接触、もしくはその間に異物の付着
なお、ブレーキパッドの交換直後に異音を感じたときは、取り付け不良やブレーキローター側に不具合の可能性があるため、速やかに対応してください。

3つ目の方法は、ブレーキ警告灯の確認です。サイドブレーキを引くと、運転者の前面に赤色で表示される「!」のような表示がブレーキ警告灯です。
ブレーキ警告灯はサイドブレーキを引いていなくても、ブレーキパッドの厚みが僅かになると、例外的に点灯します。従って、サイドブレーキを引いていないときにブレーキ警告灯が表示されたら、ブレーキパッドの交換が必要であると思ってください。
なお、ブレーキ警告灯は、ブレーキフルードという、ブレーキパッドに力を伝えるために油圧を調節するオイルの減少を認識して点灯します。ブレーキフルードが漏れ出てブレーキ警告灯が点灯している可能性もあり、極めて危険な状態で運転していることになるため、早急に業者に見てもらいましょう。
4つ目の方法はブレーキフルードの残量の確認です。
エンジンルーム内には黄色い液体の入ったブレーキフルードのタンクがあります。ブレーキパッドが摩耗すると、ブレーキフルードが流れ出やすくなるため、タンクの液面が少なくなります。従って、ブレーキフルードの減少はブレーキパッドの摩耗の進行を意味します。
ただし、あくまでもブレーキパッドとブレーキフルードを同時に交換していた場合の目安である点に注意してください。
5つ目の方法は、目視で確認する方法です。車体からホイールを取り出し、ブレーキキャリパー(ブレーキパッドの動きを制御する部品)の点検窓から直接ブレーキパッドの視認が可能です。
ただし、車体の解体には車に対する専門知識と専用の工具が必要なため、誰でもできる方法ではありません。不慣れな人がやろうとすると、重大な事故につながる恐れがあります。自信のない人はプロの整備士に依頼する方が無難です。
車検付きメンテナンスパックは必要なのか?費用対効果を徹底解説!
ブレーキパッドが減った状態で運転し続けるリスク

ブレーキパッドの厚みが3mm以下になると、ブレーキの効き目の低下を実感しはじめ、故障や事故を引き起こすリスクが高まります。ブレーキ警告灯も3mmを下回ると点灯するのが一般的です。
さらに走行を続けて1mm~2mmまで薄くなると、事故のリスクがより高まるほか、ブレーキそのものが壊れかけます。ブレーキが悪化した状態で走行を続けると、止まりたいタイミングで止まれなくなり、重大な事故につながってしまうため大変危険です。
ここまで摩耗する前に、早めの点検、交換を心がけましょう。
ブレーキパッドの交換が早まる運転
ブレーキパッドの消耗スピードの目安は、およそ10,000kmにつき1mmですが、あくまでも一般的な目安です。急ブレーキや、下りの山道をフットブレーキで減速するといった運転を多用すると、それだけブレーキパッドの消耗が早くなります。
つまり、乱暴なブレーキを頻繁にかけることがブレーキパッドに多大な負担をかけることなります。
日ごろから余裕を持った安全な運転を心がけるとともに、山道ではエンジンブレーキを活用して、フットブレーキの負担を軽減するなど工夫しましょう。
ブレーキパッドの交換費用

ブレーキパッドの交換費用は「本体価格」と「交換工賃」からなります。
本体価格は四輪分で1セットとなっており、軽自動車で7,000円~、普通自動車で8,000円~が相場です。
交換工賃は業者によって差がありますが、1セットで6,000円~10,000円程度が相場です。
ブレーキパッドの交換は頻度が高いものではないうえに、一度にそれほど高額な費用がかかるわけでもありません。ぎりぎりまで使おうとせず、早めに交換を検討しましょう。
車を業者に預けなければならないほど時間のかかる作業ではなく、交換費用もそれほど高額ではありません。交換が必要と感じたら気軽に整備業者に相談しましょう。また、ガソリンスタンドでも店舗によっては交換可能なため、気になればお近くの店舗に問い合わせてみてください。
ブレーキパッドの交換費用を抑える方法

ここでは、ブレーキパッドの交換費用をできる限り抑える方法を解説します。
前述したとおり、ブレーキパッドの交換費用はそれほど高額ではありません。しかし、ブレーキパッドの摩耗は非常にゆっくりと進行します。そのため、まだ使える、もう少し減ってからにしようと交換を先延ばしにし、結果的に車を危険にさらしてしまいます。
交換費用を少しでも減らせられれば、早めの交換に踏み切れるため、安全な状態を保ちやすくなるでしょう。
通常時にただブレーキパッドだけを交換するよりも、車検や定期点検の際に交換する方が費用を安く抑えられます。
ブレーキパッドの交換費用は、ブレーキパッド本体と交換工賃の合計金額です。車検や定期点検時に交換すると、交換工賃が点検作業や他の部品の交換作業とひとまとめにされるため、安く済みます。
たった数千円ではありますが、交換のタイミングによって安くなることを知っておけば、無駄な費用を払わずに済みます。少しでも負担を少なくするため、ぜひ車検・点検のタイミングを活用しましょう。
ブレーキパッドの交換は、新車を販売しているディーラーよりも、カー用品店や修理工場で行う方が安く済むことがあります。
カー用品店や修理工場では、自動車の純正製品以外の部品を取り扱うことが多いためです。安全性が確保できれば、純正製品にこだわらないという方には、これらの場所で交換することをおすすめします。
ブレーキパッドは他人の目に触れることはないため、見た目にこだわる必要はないでしょう。少しでも費用を抑えることに重きを置くのであれば、カー用品店や修理工場でブレーキパッドを交換しましょう。
ブレーキパッドを自分で交換することも、費用を抑える方法の一つです。自分で交換できれば、一般的に交換費用として必要な5,000円~の費用がかかりません。
しかし、自分で交換するには自動車に対するある程度の知見とスキルが必要です。加えて、安全性に重大な影響を及ぼす部品であるため、不慣れな方や自信のない方は業者に任せる方が無難です。
DIYなどのモノづくりやセルフメンテナンスが得意な方は、業者に依頼するよりも安く済ませられる、ぐらいに認識しておくのがよいでしょう。
ブレーキパッドの交換費用を抑える最後の方法は、日ごろから丁寧な運転を心がけることです。
これまでの記事の中で、急ブレーキやフットブレーキに頼った長い下り山道の運転は、ブレーキパッドの消耗を早めると説明しました。すなわち、毎日の丁寧な運転、もっと細かくいえばブレーキパッドの摩擦を強くかけすぎないような運転を行えば、その分パッドの消耗は緩やかになり、交換周期を長くとれるようになります。
長く車に乗る生活の中でブレーキパッドの交換頻度が減れば、それだけ交換費用を抑えられます。
丁寧な運転が費用を抑えることにつながるのは、ブレーキパッドに限ったことではありません。タイヤの消耗が減り、ガソリンの消費量が減り、事故も減ります。従って丁寧な運転は、安全面においても経済的な面においても大変重要なことだといえます。
ディーラーで交換すると、純正製品を適用するため費用が高くつくことがあります。ブレーキパッドは見た目に影響を及ぼす部品ではないため、他のパーツに比べて純正にこだわる理由は高くないでしょう。少しでも交換費用を抑えたい人は、ディーラー以外の場所で交換することをおすすめします。








