個人や法人の事業主が事業用車を購入する時、残価設定型クレジットを組むことは可能です。しかし、会計上の処理として、減価償却はどうなるかよくわからないという人もいるでしょう。
「残価部分にも減価償却費はかかってくるのか」「経費としてどう計上されるのか」なども知っておくと便利です。
また、残クレとよく似ているカーリースとも比較してみました。経費計上するには、どちらがお得かなども紹介するのでぜひ参考にしてください。
残価設定型クレジットのからくり

車を購入する際に耳にする残価設定型クレジットは、一般的な分割返済をするローンとは少し異なります。
まず、ディーラー側は、購入したい車両の数年後のおおよその買取価格を決めています。そして、車両本体価格からその予想買取価格を引いた金額で、月々の支払額を決めるというものです。数年後の買取価格は「残価」と呼ばれ、ローン返済の最終回まで残価は保証されます。
そして、ローンの最終回の支払い前に「残価を支払って車を買い取る」か「車をそのまま返却して残価を支払わずに契約を終了する」か「残価分を下取り額として車を下取りに出して、乗り換えるか」の3択から選べる仕組みとなっています。
残価設定型クレジットの大きな魅力というと、月々のローン返済額が通常のローンより少額になる点です。残価分を差し引いた金額でローンを組むので、車両本体価格そのものでローンを組む通常ローンよりも、お得になります。
さらに、ローン契約終了時に自身のライフスタイルや経済状況に応じて、車や残価の支払いをどうするか選べるのも利点の一つでしょう。下取りに出せば、残価の支払いなしで新たにまたローンを組んでの乗り換えが可能となります。
このことから、短い期間で新車に乗り換えたい人にも適していると言えます。
残価は最終回の支払いまで据え置かれます。すなわち、金額が保証されているということです。中古車市場での価値が下がったとしても残価は影響を受けず、契約当初の価格で下取りに出すことができます。
残価設定型クレジットには思わぬ落とし穴もあるので、予め把握し気を付けた方が良いでしょう。
まず、利息がフルローン並みに高くなるという点です。残クレの金利は残価分に対しても設定されます。ローン返済は残価を差し引いた金額での分割となりますが、利息は元本にかかってくるからです。
次に、残価保証条件を満たさなければ、契約終了時の査定において追加金の請求がくる可能性もあります。
具体的には、ローン返済中の交通事故で車に傷や凹みがついてしまった場合です。程度によって査定の減点対象となり、減点数に応じて追加金が発生します。
また、走行距離には上限が設けられており、上限をオーバーした場合も1㎞につきいくらというように追加金の請求がなされます。
他にも中古車として再販することを前提としているので、カスタマイズは禁止です。カスタマイズが確認されたら、これも追加金の清算が必要となるでしょう。
残価設定型クレジットで車をローン購入しても経費で落とせるのか?

法人、個人含めて事業用で車を購入する場合も、自家用と同様に残価設定型クレジットを利用することが可能です。
社用車を購入した場合も、車購入費を経費として計上することができます。社用車は会社の固定資産となりますが、車購入費を全額経費で落とすことができないので注意は必要です。
車購入費は大きな出費となるので、そのまま経費計上すると会社の資金が大きくマイナスとなります。そのため、減価償却をした上で経費計上する決まりになっています。
減価償却分だけが経費として落とすことができるというわけです。

例えば、電話代は通信費、会社案内のパンフレット作成は広告費というように項目が分けられています。
固定資産の購入は、減価償却費という勘定科目で記録されるのです。年月が経過すると、固定資産は劣化して年々価値が下がっていきます。
例えば、パソコンも使用するにつれてバッテリーなどが劣化し情報処理速度が遅くなるなど、性能が落ちていくものです。その固定資産を年ごとに分割して経費としましょうというのが、減価償却の目的だと言えます。
高額の固定資産の費用を一括で経費計上すると、利益がたちまち黒字から赤字に転落してしまうでしょう。そうなると、「銀行からの融資も打ち切られるリスクがある」など、会社経営上のデメリットが生じます。
分割して計上すれば会社の利益も出しやすくなるはずです。

社用として購入した高額なものでも直接業務に使用しない、時間とともに劣化しない固定資産は減価償却の対象とはなりません。車は営業や商品の運搬など仕事に使われることもあります。
また、時間の経過とともに部品が劣化して価値が下がります。そのため、会社の社用車として購入した車も、高額な固定資産となるので減価償却の対象となるのです。
車の場合は耐久年数が普通車は6年、軽自動車は4年と法律で決まっています。
固定資産によって耐久年数は異なりますが、耐久年数分だけ減価償却した分を、経費として計上できるということになります!
また、車の減価償却費を求めるのに、毎年一定の割合で償却する「定率法」と、同じ額で償却する「定額法」の2つの計算式があります。定率法は、減価償却の1年目の負担額が多く、翌年から少しずつ額が減っていくのが特徴です。建物や特許権などの権利は定額法を使うと決まっていますが、車の場合はどちらでも選べます。
早く費用化したいならば、定率法を選ぶのが良いでしょう!

残価設定クレジットで社用車を購入した場合、車両本体価格から残価を差し引いた金額でローンが組まれます。
経費として計上する際、残価部分は減価償却の対象にならないと思うかもしれませんが、実際は残価部分も減価償却の対象となるので間違えないようにしましょう。
減価償却は原則として、車取得価格をベースにしています。残価はあくまでローンの最終回の支払いに据え置かれただけで、車の車両本体価格が残価分値引きされたわけではないからです。
例えば、5年の残クレで480万円の車を購入したとします。「残価は120万円」として、残り360万円は毎月6万円の返済になります。この場合の減価償却は360万円ではなく、車両本体価格の480万円がベースとなります!
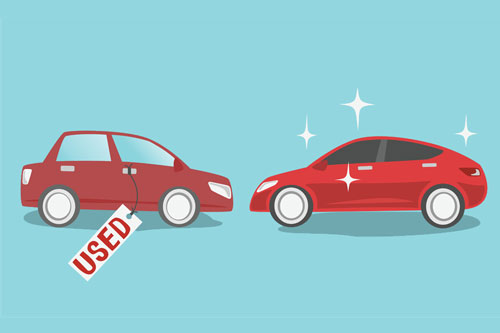
新車の減価償却費を算出する場合、耐用年数は普通車で6年と決まっています。しかし、購入時に新車ではなく中古車の場合、耐用年数が違ってくるので注意が必要です。
新車よりも中古車の方が当然耐用年数が短いので「簡便法」という計算方法が用いられます。
(法定耐用年数)-(経過年数)+(経過年数)×0.2=中古車の耐用年数
という式で算出されますが、1年未満の端数は切り捨てます。
例えば、経過年数が2年の普通車の場合を見てみましょう。普通車の法定耐用年数は6年です。
計算式
6-2+2×0.2=4年と算出できます。
中古車の場合は、初年度登録から16~30ヶ月までは4年、31~45ヶ月までが3年となっており、最短期間は2年です。
耐用年数が少ないと、その分減価償却費として経費計上が多くできるので節税に効果的だと考えらえます。
ただし、注意しなければならないのが中古車の改良や改造です。新車の車体価格の50%以上の金額をかけて中古車を直してしまうと、新車と同じ耐用年数になってしまいます。
中古車を修理する際は修理費にも気を付けましょう!

残価設定型クレジットで事業用車を購入すると、経理上の仕訳の仕方が結構複雑になります。そのため、経理に詳しくないと帳簿の作成などがややこしいので間違えやすくなります。一般的なマイカーローンで事業用車を購入する時とはまた、会計処理が異なるので注意が必要です。
残価は120万円として設定してみましょう。耐用年数は6年で減価償却費は定率法で計算します。
すると1年目は159万8400円で、2年目は106万6132円、3年目は71万1110円、4年目は47万5735円、5年目は47万5735円、そして6年目が47万2887円と減価償却費が計算できます。
毎年各金額が経費として計上されます。
1年目は480万円から帳簿がスタートし、減価償却費を差し引いた金額320万1600円が1年目の帳簿の最終的な額面です。そして2年目の帳簿は320万1600円からスタートし、減価償却費を引いた金額が最終的な額面となります。
それを6年目まで同じ要領で帳簿につけて、会計仕訳していきます。
残クレと似ているカーリースとは?

カーリースは、残価設定型クレジットと仕組みが似ていると言われ、話題になることが多いでしょう。
カーリースは、車両本体価格から数年後の車の価値、残価を差し引いた額に税金や保険料などの一部維持費をプラスした金額を分割にして、リース代を算出します。
残価を差し引いた額という点は残クレと似ていますが、税金などの維持費がリース代に含まれるところが残クレとは異なる点です。
カーリースの契約終了後は、基本的に車を返却するか、同じ車に対し再リース契約を結ぶか、別の車で新たにリース契約を結ぶかを選びます。
リース会社によっては、残価分を支払えば買取できる場合もあります。契約終了後については、内容は少し違いますが残クレも3つの選択肢がある点は似ていると言えるでしょう。
カーリースの利点

カーリースにもいくつかメリットがあります。
まず、リース代に税金や自賠責保険料、車検費用などの維持費が含まれているという点です。車検時にまとまった費用がかからず、毎月のリース代に分散されているのでお金の管理をしやすいと言えます。
リース会社では各メーカーの様々な車種に対応しています。そのため、乗りたい車を見つけやすく、リース契約を新たに結ぶ際も別メーカーの車を選ぶことが可能です。
残クレは各メーカーごとにプランがあるので、特定のメーカーの車を乗り続けたいという人には良いでしょう。しかし、メーカーを変えたい時は新たに該当車種のメーカーと残クレ契約を結ばなければならず、手続きが面倒になります。
審査からリース契約手続きまでをネットで済ませられるリース会社が多いので、手続きが効率的なのもメリットの一つだと言えます。
頭金も不要なので、貯金がなくても新車に乗ることができるのも魅力の一つです。
残価設定ローンを組んだ車は買取に出せる?買取に出すための条件などを解説
カーリースのマイナス面

逆にカーリースにはマイナス面もあります。
基本的に契約途中での解約はNGです。また、契約内容の変更も認められていない場合が多いでしょう。万一解約したいとなると、損害金の支払いを請求されることになる場合がほとんどです。
事故などで車が全損し、修理できずに廃車にせざるを得ない場合など仕方のない事情があっても、中途契約は損害金が発生してしまうので要注意です。
リース契約には契約終了時の中古車市場の価格が左右するオープンエンド契約があります。その場合、契約終了時に車の価値が下がると、追加金が発生します。
逆に市場の価格に影響を受けないクローズドエンド契約もあるので、契約時にどちらの形態かを確認しておかなければ、追加料金を請求されることにもなるので注意しましょう。
リース契約終了後は、車を返却することが前提なので、ほとんどの場合カスタマイズやドレスアップはできないとされています。万一カスタマイズした場合は、返却時までに原状回復しておかなければなりません。
他にも走行距離に上限が設けられていて、月間500~2000㎞位までとなっている場合が多いです。距離をオーバーすると追加金が発生することもあります。
カーリースなら全額経費で計上できる

カーリースでは、車の名義は借主ではなくリース会社になっています。つまりリース契約期間中は、リース会社所有の車にリース代を支払って借りているにすぎず、期間が終わったら返却するという形式です。
そのため、残クレと違って車は固定資産とはなりません。リース代は事業に必要な経費として全額計上できるというのも、事業主にとっては大きな魅力です。
経費が多くなればその分、節税対策にもなります。リース代は毎月定額で費用も決まっているので、そのまま費用を計上すればよいので面倒な会計上の処理もありません。
特に個人事業主の場合、経費の計算に頭を悩ませる必要もなくなるというわけです。
カーリースの減価償却費について
カーリースの場合、借主に代わって希望の車をリース会社が購入することになります。従ってリース会社に所有権があるため、事業主が社用車をリースしても当該社用車は会社の固定資産とはなりません。あくまで仕事に必要な経費に過ぎないのです。
減価償却費は、固定資産を経費として計上する際に会計上必要になってきますが、固定資産でないリースの社用車はそもそも減価償却することはありません。シンプルにリース代全額を経費計上すれば済みます。
残価設定ローンを組んだ車は買取に出せる?買取に出すための条件などを解説
事業用車購入時に残クレを組む場合は注意が必要

個人、法人を問わず事業主が社用車を購入するのに、残クレを利用すると通常ローンを組むよりは月々の支払いを抑えることができます。
ただし、高額な財産となる車は固定資産と見なされるので、最終回までに据え置いた残価分を含んだ車両価格分が全て減価償却の対象です。また、残価を支払って車を買い取った場合は、その後も減価償却が続きます。
車両を下取りに出す、もしくは返却すると帳簿の価額と残価との間に金額差が生じ、それが売却益となってしまいます。そうなると、課税対象となり、税金面で損する可能性もでてくるので注意が必要です!
そして何より、カーリースはリース代全てが経費として計上できますが、残クレの場合は全て経費にできません。事業主にとっては、残クレを組むよりカーリースを活用した方がお得になることが多いと言われているのです。
社用車が欲しい場合は特に、経費のことも考慮に入れながら何を利用するかを慎重に検討すべきです。








