自賠責保険は軽自動車も加入しなければならない自動車保険の一つです。保険料は離島などを除いて全国一律で決められています。
しかし、毎年保険料が適正であるかを検証が行われるので、年によっては改定され、これまでより値上がりもしくは値下がりすることもあるかもしれません。
交通事故の増減や経済情勢などを鑑みて保険料が決まるとされています。
2020年4月に改定された軽自動車の自賠責保険料はいくらになったのか、他の車種とも比較した上で見ていきましょう。また、自賠責保険の補償内容や請求法保なども紹介します。
自賠責保険の内容
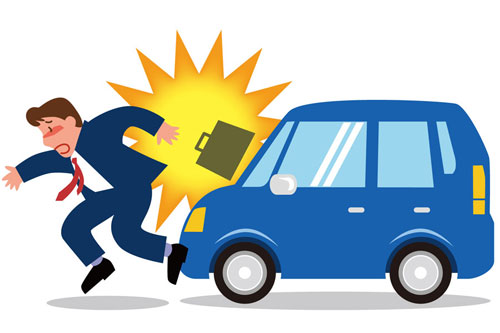
自賠責保険は、法律により加入が定められている強制保険です。
自動車損害賠償保障法では、公道を走行する全ての車両は自賠責保険に加入しなければならないと定められています。そのため、未加入のまま公道を走行した場合、法律違反となり罰せられます。
自賠責保険は主に交通事故の被害者を救済することが目的です。しかし、救済といっても被害者が死傷した際の対人補償のみとなっているのが大きな特徴の一つとなっています。
物が壊れた際の補償である対物補償はなされません。被害者の車や自転車などが壊れても、自賠責保険からは何ら賠償されないということになります。
対人補償は被害者が亡くなった場合、ケガをした場合、後遺障害を負った場合について支払い限度額が決まっています。限度額を超える賠償金が請求される場合もあり、その際は運転者が自由意思で加入する任意の自動車保険がカバーすることになります。
もし自動車保険が未加入ならば自腹となってしまいます。
自動車損害賠償保障法
第5条「自動車は、この法律で定める自動車損害賠償責任保険の契約を締結されているものでしか運行の用に供してはならない」とあります。
ここでいう自動車は、道路運送車両法によると農耕作業用の小型特殊自動車を除く全ての自動車となっており、当然軽自動車も含まれます。つまり、軽自動車も必ず自賠責保険に加入しなければなりません。また、原付を含むバイクも加入義務があります。
軽自動車で自賠責保険が未加入だと法律違反になる

自賠責保険に未加入で公道を走行した場合は、法律違反となり罰せられます。
自動車損害賠償保障法
第86条「1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられる」と規定されています。
加入していたとしても、保険の契約期限が切れたまま更新されなかった場合は無保険運行となるので注意が必要です。さらに、公道を走行中に警察から取り締まりを受けると、道路交通法違反として検挙されます。違反点数は6点で即30日間の免許停止処分が科されることになります。
無保険運行は罰金・罰則と免停という行政処分のダブルで処罰されることになります。
自賠責保険の加入と更新はいつ?

自賠責保険は自分で保険会社を選んで加入手続きをすることもできます。ただし、一般的には車を購入した際にディーラーが加入手続きも一緒に行ってくれるので、販売店を通して購入したという場合は加入を忘れることはないでしょう。
また、保険には期限があり、契約期間が過ぎると期限切れの状態になってしまいます。そうなると法律違反で罰則を受けるのみならず、万が一事故を起こして相手を死傷させても保険金が下りなくなってしまいます。
自賠責保険は保険の期間が、車検から次の車検までに設定されている場合がほとんどです。車検を受ける際に更新手続きをすれば保険期間が切れることもありません。
ディーラーや整備工場などへ車検に出す際に一緒に更新手続きをするのが一般的となっているので、まず忘れるということはありません。
ただ、自賠責保険の期間を車検時に設定していないと、期限切れに気づかないこともあるので注意が必要です!
自賠責保険の保険料の基準利率は、損害保険料率算出機構という団体により各保険会社から提出された保険金の支払い状況や契約状況などのデータや外部団体からのデータをもとに算出されています。
算出された基準利率は、損害保険料率算出機構から各保険会社へ提供されて、自賠責保険加入時や更新時にみなさんが保険料を支払っています。
また、事業用や自家用といった車の使用目的、普通車や小型車、軽貨物車や軽乗用車といった車種によって、交通事故の発生率や発生した際の被害の程度に違いがあります。保険料が車種によって異なるのは、そのためです。
また、地域によって人口や車の保有率、交通量や事故発生率なども異なるので、本土と沖縄、離島諸島とでは保険料に差が見られます。
一旦決定した保険料は、社会環境の変化などにより可能性があるので毎年検証されています。改定の必要があれば、金融庁長官に報告がなされて自賠責保険審議会での審議により、基準利率が決まります。

自賠責保険料の改定は2017年以来3年ぶりです。今回の改定により平均で16%ほど保険料が値下がりました!
自賠責保険料は、損害保険料率算出機構により毎年検証されています。保険は公的な要素が強く、損失も利益も出ないようにという「ノーロス・ノープロフィットの原則」によって保険料が決定される仕組みです。
保険料改定の背景としては、前回2017年の保険料改定時に想定された基準よりも黒字になっているからだとされています。黒字になった理由は自動車の安全性能の向上などによる交通事故の減少が考えられます。

軽自動車の自賠責保険は、1ヶ月分~37ヶ月分まで保険料が決められています。
自賠責保険は車の購入時に加入し車検時に更新されていくのが一般的です。そのため、購入時から初回の車検までの3年間である36ヶ月だと2万8910円となっています。
2回目の車検からは2年ごとになるので24ヶ月だと2万1140円、25ヶ月では2万1780円となります。
改定前の保険料は24ヶ月で2万5070円だったので、上記の改定後と比較すると「3930円」も安くなったことが分かります。
普通車の自賠責保険料は?

普通車の自賠責保険料も1ヶ月~37ヶ月ごとに金額が決まっています。そして、購入時に加入し車検ごとに更新されます。
車の購入時から1回目の車検までが3年なので、36ヶ月で2万9250円、37ヶ月だと3万170円です。
2回目以降の車検からは2年ごとになるので、24ヶ月で2万1550円、25ヶ月だと2万2210円となっています。
改定前の保険料は24ヶ月で2万5830円だったので、上記の改定後と比較すると「4280円」も値下げされています。
バイクや原付の自賠責保険料は?

バイクの自賠責保険も購入時に加入し車検ごとに更新されるのが一般的です。そして、バイクは排気量によって保険料が違ってきます。
排気量が125㏄超え、250㏄未満の小型自動二輪車は24ヶ月で1万160円、36ヶ月では1万2600円となります。
改定前の保険料は24ヶ月で1万2220円だったので、上記の改定後と比較すると「2060円」の減額となります。
排気量が251㏄超えの小型二輪自動車の場合は24ヶ月で9680円、36ヶ月で1万1900円となります。
改定前の保険料は24ヶ月で1万1520円だったので、上記の改定後と比較すると「1840円」の減額となります。
自賠責保険料を車種ごとに24ヶ月で比較してみましょう。
- 軽自動車は2万1140円
- 普通車は2万1550円
- 原付バイクは8950円
- 125㏄超で250cc未満のバイクは1万160円
- 250ccを超えるバイクは9680円
車種で見ると、原付が一番安く、次に排気量が250㏄を超える大きいバイク、250㏄未満のバイクと続きます。軽自動車と普通車の差額はわずか410円です。
それぞれの車種によって改定率は異なりますが、全車種において平均16.4%の改定率となっています。
自賠責保険の補償対象

自賠責保険の補償対象は、交通事故の相手方である「被害者の身体に対する補償のみ」に限定されています。加害者の運転者が死傷しても補償はなされません。
自賠責保険では、他人の身体への損害に対して補償するという決まりがあります。つまり、運転者と運行供用者以外の方に対する補償ということです。
そのため、加害車両に乗っていた運転手や社用車を運転していた従業員などがケガをしても補償はされません。
一方、同乗者の場合は補償されます。交通事故で相手の車や自転車などが破損したり、建物や家屋、塀やガードレール、電柱や信号機などが壊れると修理費が必要となります。
また、相手の車が全損となれば買い替える必要も出てくるでしょう。物の破損に対する補償、いわゆる「対物補償」は一切ないのが自賠責保険の落とし穴でもあります。
物によってはかなり高額な賠償金を請求されますが、自賠責保険に加入していても賠償できないので全て自腹で弁償することとなってしまいます。
自賠責保険の補償内容
自賠責保険では、主に相手方の被害者が亡くなった場合とケガをした場合、後遺障害を負った場合の3つのケースにおいて補償がなされます。それぞれの賠償額は制限があり、支払いの限度額が決まっています。
限度額を超える賠償金を請求された場合は、超えた部分についてのみ自分で支払わなければなりません。支払額や支払額の決め方は、自動車損害賠償保障法の中の支払い基準で明確に決められています。
支払基準により、きちんと計算された賠償金を受け取ることができるので、公平さが保たれているといえるでしょう。
対人補償①相手方が亡くなった時

交通事故で被害者が亡くなった場合、補償額は被害者1人につき最大3000万円までが限度額として賠償されます。
補償内容としては、まず通夜や火葬、お墓などにかかる葬儀費が100万円まで支払われます。ただし、香典返しや墓地にかかる費用は含まれません。
また、被害者がもし生存していれば将来取得したと予想される収入から生活費を除いた逸失利益も含まれます。就労可能時間か扶養者の有無などを考慮して算出され、被害者本人と遺族の慰謝料も補償に含まれています。
被害者本人は400万円、遺族は人数により金額が異なります。遺族慰謝料請求権があるのは、被害者の父母や配偶者、子です。遺族1名では550万円、2名では650万円、3名以上で750万円となります。さらに被害者の被扶養者がいれば、200万円がプラスされます。
対人補償②相手方が傷害を負った時

被害者がケガをした場合、1名につき最高120万円を限度額として賠償金が支払われます。
補償内容は、治療関係費として治療や手術、処置や入院などにかかる治療費の実費が含まれます。さらに、12歳以下の子供の親などの付き添い、医師が看護が必要と認めた場合の被害者への入院中、もしくは自宅での看護料、通院の付き添いにかかる看護料も含まれます。
入院は1日4200円、自宅での看護では通院1回につき2100円などです。入院中に必要といった諸雑費が1日1100円まで支払われます。
また、通院するための移動にかかった通院交通費や、義肢や眼鏡、補聴器や松葉づえなどの義肢などの費用が実費支払われますが、眼鏡は最大5万円までです。
また、必要な診断書や診療報酬明細書などの発行にかかった費用も含まれます。手続きに必要な交通事故証明書や、印鑑証明書などの発行費である文書料や、事故によるケガで仕事を休業となった際の収入減少分、基本的に1日6100円休業損害も含まれます。
また、身体的肉体的苦痛への補償として、1日4300円の慰謝料も支払われます。
対人補償③相手方が後遺障害を負った時

被害者が交通事故での損害によって後遺障害を負った場合は、障害の程度によって支払われる賠償金の限度額も違ってきます。
神経系統の機能や、精神、胸腹部臓器への障害で介護が必要なケースのうち、常に介護を要する場合は限度額4000万円までです。
そこまで重度でない随時介護を要する場合は、最大3000万円となっています。
前記に該当しない後遺障害は第一級3000万円から、第14級75万円まで等級によって限度額が決められています。
補償内容には、後遺障害を負ったことにより労働能力が損なわれ、将来起こりうる収入減少分を補う逸失利益や慰謝料なども含まれています。逸失利益は身体に負った障害の等級や収入額、労働可能期間などを総合的に見て算出される仕組みです。
慰謝料は等級ごとに金額が異なり、被害者に被扶養者がいる場合は増額となります。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
軽自動車の自賠責保険の請求の仕方
自賠責保険の保険金の請求は、加害者側が自身が加入している自賠責保険の保険会社へ請求するというの一般的ですが、中には手続きが面倒であったり、自身もケガをしているなどの理由で、なかなか請求手続きに動けない加害者もいます。
自賠責保険は被害者の救済を目的としているため、それでは被害者は救われません。そのため、自賠責保険では被害者も保険金請求ができるシステムになっています。
例えば、被害者が入院もしくは通院加療中で治療費などを病院に支払った場合、保険金が下りるまでは被害者の実費です。通常は総損害額が決定しないと保険金が支払われませんが、被害者請求の場合は、被害者が病院などに治療費を支払う度に保険金を請求できることになっています。
軽自動車の自賠責保険の請求期限と仮渡金について

自賠責保険は請求期限が決まっているので注意が必要です。
被害者側に損害賠償金を支払ってから3年以内となっています。
起点が死亡が被害者が死亡した時、傷害は事故発生時、後遺障害は病状が固定した時期となります。それぞれのケースで起点から3年以内が請求期限です。
3年が経過すると、保険金を請求の権利が消滅してしまいます。ただし、何らかの理由で請求が遅れてしまい3年を過ぎる場合は、保険会社に連絡すると時効更新が認められることもあるので覚えておいてください。
被害者が自賠責保険金を請求し、実際に保険金が下りるまでは多少時間がかかります。その間もケガの治療費や休職で収入が減ってしまうことで、まとまったお金が必要となるでしょう。そんな時は、一時金としてお金が受け取れる「仮渡金」という制度も被害者は利用できます。

自賠責保険の保険金請求には様々な書類が必要となります。
- 保険金・損賠賠償額支払請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 医師の診断書もしくは死亡診断書
必要な書類は、診療報酬明細書や通院交通費請求書が必要です。印鑑証明書と戸籍謄本も準備しましょう。
必要な書類は、診療報酬明細書と通院交通費明細書、付添看護自認書または看護料領収書、休業損害証明書などです。印鑑証明書や戸籍謄本も必要になります。
必要な書類は、休業損害証明書、印鑑登録書、後遺障害診断書などが必要です。
他にも、必要に応じてレントゲン写真なども請求されるかもしれません。
また、請求権者が何人もいる場合は、1名を代表として他の人の全員分の委任状と印鑑証明書が必要となるので覚えておきましょう。

自賠責保険請求から支払いまでの流れを見てみましょう。
事故が起こり、被害者が負った損害に対し加害者が賠償金を支払います。
- 自賠責保険加入の保険会社へ必要書類を提出すると、保険会社は書類の内容を確認し、損害保険料率算出機構の調査事務所へ書類を送付します。
- 調査事務所では、事故の状況や損害の程度、事故と損害の発生の因果関係などを調べることになるでしょう。自賠責保険での支払いが妥当であれば、保険金額は適正かを調査し、保険会社へ報告します。
- 保険会社は保険金の支払額を決定して加害者側に保険金を支払いますので、加害者が受け取り被害者に支払います。
ただし、自賠責保険は被害者救済の立場から、被害者側からの請求も可能です。
被害者が請求する際は、保険金の総支払額が決定する前に、保険金の請求手続きがを行うことができます。また、治療などでかかった費用を請求すればその都度支払うという形が取られています。
保険金は交通事故で被害者が損害を負った場合、全てのケースで支払われるわけではありません。支払われない場合もあるので気を付けましょう!
まず、被害者側に重度な過失が認められる、100%被害者の落ち度による事故の場合は保険金は下りません。
例えば、被害者の車が赤信号無視で交差点に進入する、スピードの出しすぎなどで道路のセンターラインを大幅にはみ出して対向車と衝突した場合などが当てはまります。また、追突事故において、追突した車両の方が被害者の車両となる場合もです。
こういった事故は無責事故と呼ばれており、自賠責保険の支払い対象からは除外されます。

自賠責保険は法律で加入が義務とされている保険なので、公道を走行させる場合は必ず加入しなければなりません。また、加入していても、保険契約期限が経過して期限切れとなれば加入していない状態と同じです。
通常は、車購入時に加入し車検時に更新するので、加入や更新を失念することはまずないでしょう。ただし、車検のない原付などのバイクは特に更新を忘れやすいので注意しなければなりません!
- 補償が対人補償のみであること
- 対人補償でも賠償金の限度額が決まっており全て保険金ではカバーしきれないケースがあること
なども覚えておいてください!
そして、対物に関しては全く補償がなされないので、事故の物を壊した際に賠償金は自腹になってしまいます。万が一に備えて、対物補償もあり対人についても無制限と補償が手厚い「自動車保険」にも加入しておくべきです。
自動車保険は保険会社によって補償内容も保険料にもかなり違いが見られ、加入するかどうかは自分の意志に委ねられています。各保険会社の補償内容を比較しながら、自分にあった任意保険を探し、加入しておきましょう。








