自賠責保険は全ての車に加入義務があります。その加入の証拠となるのが「自賠責保険証明書」です。これは運転する時に車検証と一緒に必ず携帯しなければならない重要書類です。
この記事では、自賠責保険証明書の詳しい記載内容から、シチュエーションに応じて見るべき箇所、証明書を紛失・汚損・破損した場合の再発行方法まで解説します。
自賠責保険証明書とは?
ごく一部の例外を除いて、全ての車は自賠責保険に加入することが法律で義務付けられています。そして、加入している事実を証明するのが「自賠責保険証明書」です。
正式には「自動車損害賠償責任保険証明書」といい、自賠責保険に加入している車は公道を走る際、常に携帯していなければなりません。
契約内容もこの一枚の書類に全て記載されているので、万が一事故に遭遇してしまった場合や、車検の際など、折に触れて中身を確認されることになります。
自賠責保険証明書の概要

自賠責保険証明書はさまざまなシーンで用いられ、また公道での走行時には携帯していないと処罰される重要書類です。
この書類の持つ役割と重要性、そしてどのようなどのような手続きを経て発行されるのか、概要を説明します。
自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」と言います。
自動車損害賠償保障法によってごく一部を除くほぼ全ての車がこの保険へ加入することを義務付けられているため、「強制保険」とも呼ばれています。
自賠責保険に未加入の「無保険」状態で公道を走ることは厳禁です。また、自賠責保険に加入していることを証明する自賠責保険証明書を携帯することも、ドライバーの義務となっています。
車検を定期的に受ける普通乗用車などの場合は、車検証と一緒に保管していることが多いでしょう。
一方、車検を受けない原付バイクなどの検査対象外軽自動車の場合、必要なのは自動車保険証明書の携帯だけではありません。「自賠責ステッカー」と呼ばれるシールをナンバープレートに貼っておく必要があります。シールを貼っていないと、やはり摘発対象となります。
自賠責保険証明書は、その車が自賠責保険にきちんと加入していることの証です。公道を走るのも車検を受けるのも自賠責保険に加入していることが条件なので、車に関してはあらゆるシーンでこの証明書が必要と言えます。
また、道路を運転する際はこれを携帯していないと処罰されます。単に重要書類だからというだけでなく、自分の身を守るためにも常に携帯しましょう。
何らかの理由で警察から自賠責保険証明書の提出を求められ、もしも携帯せずに公道を走っていたことが判明したら処罰されることになります。
自動車損害賠償法第8条によると、不携帯というだけで30万円以下の罰金と定められています。
さらにこの時に自賠責保険の有効期限が切れており「無保険」の状態だった場合には、1年以下の懲役か50万円以下の罰金です。違反点数は6点で免許停止処分となるでしょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
発行の流れ①車検を受ける車両の場合

自賠責保険証明書が交付されるまでの大まかな流れを説明します。
まず、車検制度の適用を受ける一般的な普通乗用車の場合は、ほとんどが車検と同時に自賠責保険の加入・更新も行われます。
つまり新車登録の時点でまず自賠責保険に加入し、あとは車検ごとに有効期限が更新されるということです。
車検を行う業者が手続きを代行してくれることがほとんどなので、多くのユーザーは自賠責保険の手続きの存在を意識することはないでしょう。
車検を終えて新しい車検証が発行されると、同時に自賠責保険証明書も発行されます。これらはメンテナンスノートなどと一緒にひとまとめでグローブボックスなどで保管している方が多いでしょう。
次の車検の時に新しく更新されるので、自賠責保険の有効期限は、車検の有効期間をカバーする形で、少しだけ長めに組まれるのが一般的です。
もしもこうした手続きを自分で行いたい場合は、車検の前に業者に断っておく必要があります。
発行の流れ②車検を受けない車両の場合

車検を受けない原付バイクや排気量250cc以下の小型バイクの場合、自賠責保険の加入は販売店で代行してもらえますが、更新は自分で行うことになります。
自分で手続きを行うと、自賠責保険証明書はいつ交付されるのでしょう?
まず、損害保険会社の代理店であるバイクの販売店や、インターネットを介して手続きを行うと、ステッカーと一緒に自賠責保険証明書が後日送付されてきます。この場合、手元に届く前に自賠責保険の有効期限が切れてしまうと公道を走れないので注意しましょう。
一方、損害保険会社で直接手続きをしたり、コンビニで加入や更新をした場合は、証明書もステッカーも即日交付されます。
特にコンビニは大変便利で、24時間・365日受付可能な上に、更新も保険会社から届く通知ハガキ一枚で済ませられます。
ただし、コンビニごとに提携している損害保険会社が異なるので、保険会社がどこなのか確認しておいたほうが安心です。
自賠責保険証明書の記載内容
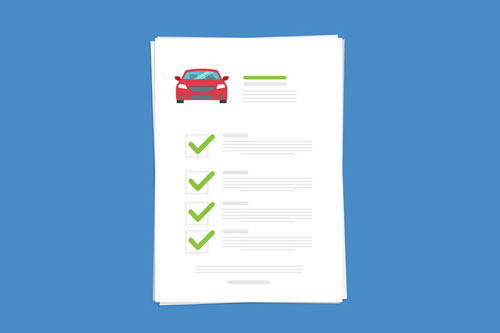
ここまで、自賠責保険証明書の役割やその重要性、発行までの流れなどを説明してきました。次にこの書類に記載されている内容について詳しく解説していきます。
まず、自賠責保険証明書には「登録番号」と「車両番号または車台番号」が一つの項目に、そしてその隣に「自動車の種別」が記載されています。
「登録番号」とは、いわゆるナンバープレートに記されている番号のことです。
「車両番号または車台番号」とは、車1台1台に付与されている番号で、登録時から廃車時まで変わらない車のマイナンバーのようなものです。
「自動車の種別」は、自家用・営業用の使用形態の区別と車種が記載されています。
自賠責保険証明書には、保険の有効期限も記載されています。
車検制度が適用される車の場合、車検を受けると自賠責保険の有効期限も更新されます。
原付バイクなどの検査対象外軽自動車も更新時期になると通知ハガキが届くなどしますが、有効期限は自分でも覚えておきましょう。
車検時に自賠責保険を更新する場合、自賠責保険の有効期間は車検期間よりも1カ月多くするのが一般的です。例えば、車検が2年おきなら自賠責保険は25カ月分を契約するということです。
その理由は、双方の有効期限が切れるタイミングの違いにあります。車検と自賠責保険が同日に有効期限を迎える場合、自賠責保険は車検よりも12時間早く切れるルールになっているので、その分がカバーできるようにひと月分だけ長く契約したほうが安心なのです。
一方、車検がない検査対象外軽自動車の場合は、1~5年の範囲で期間を選択することができます。
自賠責保険証明書には、支払われた保険料と保険会社による収納印も記載されています。
書面右側の下部には領収書もあるので、保険料を納付した事実やその納付日なども確認できるでしょう。
収納印は印刷されていることがほとんどですが、中には直接押印する様式もあります。そうした様式が使われている場合、収納印の押印漏れがあると保険金を請求する際にトラブルになることがあるので注意しましょう。
自賠責保険証明書には契約者の住所・氏名も記載されているので、発行されたら間違いがないか確認しておきましょう。
この記載内容は車検証と一致していなくても問題ありませんが、証明書と車検証のいずれかの住所・氏名が現況と異なる場合はすぐに「変更手続き」が必要です。
さらに、もしも名義が異なっていたら、別途「名義変更の手続き」が必要になります。
「住所氏名の変更手続き」と「名義変更の手続き」は、異なるので注意が必要です。
自賠責保険は国によって作られた制度ですが、実際の運用は民間の損害保険会社で行われています。そのため、自賠責保険の契約内容を変更したい場合や事故に遭遇した場合は、自分が契約している会社に連絡しなければなりません。
この契約会社は、自賠責保険証明書の下部に「管理店名」とその「所在地」が書かれているのですぐに確認できます。
自賠責保険の加入・更新手続きは簡単ですが、それ以外の事柄では保険会社に直接連絡しなければならないことも多いです。保険会社が知りたい場合は、自賠責保険証明書のどこを見るといいのかだけでも覚えておくといいでしょう。
自賠責保険証明書の右側には、「自賠責保険についてのご案内」として、保険の詳しい内容が記されています。
自賠責保険の概要や万が一事故に遭遇した場合の支払い内容の一覧表、保険金の請求方法などが確認できます。
また、自賠責保険という制度は「自動車損害賠償保障法」という法律によって運用されていますが、法律が改正されたり変更点が生じると、この「ご案内」の欄に表示されます。
文字も細かいので、よほどの場合を除いてチェックする方は少数派かもしれません。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
状況に応じて自賠責保険証明書のどこを見るべきか

ここまでで、自賠責保険証明書の内容を詳しく説明しました。それでは、事故に遭ったときや契約内容を変更したいときなどは、この証明書のどこを見るといいのでしょう?
ここからは、状況ごとの確認箇所を詳しく説明します。
万が一事故に遭遇してしまったら、保険会社に連絡する必要があります。加入している損害保険会社がどこなのかは、自賠責保険証明書に記載されているので確認しておきましょう。
また警察に連絡をすると、警察で現場検証を行い、「交通事故証明書」が作成されます。
交通事故証明書は、保険金を請求する際に必要となる重要な書類です。そして、自賠責保険の契約内容や保険会社を書く欄があるので、こちらも自賠責保険証明書を確認しながら記入します。
もし自分が交通事故の被害者になり、事故の加害者からの賠償がなされない場合、「被害者請求」のためにこの証明書が必要になることもあります。
通常、自賠責保険は事故の加害者が請求しますが、「被害者請求」も可能です。この時、加害者が加入している保険会社が分からないと請求できませんが、事故証明書によって会社名を確認できます。
自賠責保険の有効期限が切れてしまった状態で、車を公道で走らせると摘発対象になります。
有効期限や更新のタイミングが分からなくなったら、すぐに確認しなければなりません。
車検ステッカーや自賠責ステッカーを見れば有効期限が分かりますが、自賠責保険証明書を見ても分かります。保険の有効期限が記載されているので、すぐに分かるでしょう。
厳密に言うと、書かれている期日の正午12時に切れることになります。それまでに更新の手続きを済ませて、新しい証明書やステッカーを入手しておくことが必要です。
実際には、車検と一緒に自賠責保険も更新したり、更新のタイミングで損害保険会社からお知らせが来たりします。そのため、保険の有効期限についてあまり神経質になる必要はないでしょう。
とはいえ、車検ステッカーや自賠責ステッカーなどで外から見ても常に更新時期が分かるようにしておかないと違反となります。その意味でも、保険期間や更新時期は常にはっきり分かるようにしておきましょう。
自賠責保険の契約者の住所・氏名・名義に変更があった場合も、まずは自賠責保険証明書を確認しましょう。手続きのためにどこの損害保険会社に連絡すべきかが分かります。
住所・氏名の変更手続きをする場合
契約者の印鑑(氏名変更した場合は変更後の印鑑)、自賠責保険証明書、車検証、そして保険会社によっては新しい住所・氏名が確認できる書類を用意します。
そして保険会社の窓口に出向くか、カスタマーセンターなどに電話をして手続きを行ってください。
名義変更の手続きをする場合
ネットオークションなどを含め、個人間での車両の譲渡がなされた場合は名義変更手続きも必要です。
自賠責保険証明書、譲渡人と譲受人の捺印がある自賠責保険承認請求書、手続きをする人の本人確認書類を用意して、保険会社の窓口へ行きましょう。
なお、本人確認書類は手続きをするのが譲受人であれば、譲渡人の実印と印鑑証明書が必要です。また譲渡人が手続きをするなら、免許証、保険証で事足ります。
車を乗り変える場合、既に契約している自賠責保険を新しい車に引き継ぐことが可能です。これを「車両入替」といます。
この場合も自賠責保険証明書に記載されている損害保険会社に直接連絡をして手続きを行うことになります。
なお、原付から車へ、原付からバイクへ…という形で、異なる車両同士で車両入替することはできません。この場合は、新たに自賠責保険を契約し直します。できれば新しい車両が納車される前に手続きを済ませるのが理想的です。
また車を廃車にする場合も、やはり損害保険会社に直接連絡して、自賠責保険を解約することになります。
登録事項等証明書(抹消記録あり)といった廃車した事実が確認できる書類が必要なので、解約手続きは廃車が完了してからになります。その他、自賠責保険証明書や本人確認書類、印鑑、それに保険料が返金される場合は振込先の口座情報も必要です。
手続きの際は、念のため一度保険会社に必要書類などを確かめるといいでしょう。
自賠責保険証明書やステッカーを紛失した、あるいは汚損・破損して識別不可能な状態になってしまったら、再発行の手続きが必要です。
代理店などではできないため、証明書記載の損害保険会社を確認して連絡しましょう。
必要書類は念のため個別に確認したほうがいいですが、ほとんどの場合、保険会社で受け取れる再交付申請書、印鑑、身分証明書になります。
また、汚損・破損した場合は、識別不能になった自賠責保険証明書や自賠責ステッカーがあれば、持参してください。
自賠責保険証明書の紛失や識別不能により損害保険会社が確認できない場合は、その車を購入した販売店や、車検時に手続きを代行してくれた業者に聞くとすぐに分かります。
コンビニで手続きをしていた場合は、そのコンビニと提携している損害保険会社を確認してください。
それでも手掛かりがつかめない場合は、損害保険会社へ1件ずつ電話をして確かめるしかありません。登録番号や車台情報などの情報を伝えて、契約があるか確認しましょう。
自賠責保険証明書を確認して記載ミスや漏れ、現況と異なるなどの内容があれば、すみやかに「管理店」を確認して損害保険会社へ連絡し、変更手続きを行いましょう。
項目によっては、記入ミスや漏れがあると、車検や保険金請求の手続きがスムーズにいかないことがあります。
原付バイクなどの加入手続きをコンビニで行う場合などは、要注意です。コンビニで気軽にできるのは利点ですが入力ミスも生じやすく、再発行手続きが必要となることがあります。








