全ての車の加入が法律で定められている自賠責保険は、なぜ任意保険である自動車保険とは別に存在しているのでしょう?
ここでは、そんな自賠責保険の存在理由や必要性について解説していきます。また、全国どこでも一律である契約内容とその保険料の決まり方と支払方法についても紹介します。
さらに事故発生時に補償される範囲や自賠責保険制度の運用の仕組みなども説明します。
そもそも自賠責保険とは何か

自賠責保険は、正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、ごく一部を除く全ての車に加入する義務がある「強制保険」です。
この保険は、昭和30年代に施行された自動車損害賠償保障法という法律にのっとって運営されています。強制保険という性質上、自賠責保険は有効期限が切れた状態で車を運行すると処罰されることもあります。また、車検制度が適用される車は車検と同時に自賠責保険の有効期限も更新されるというシステムなのが特徴的です。
自賠責保険が存在することによって、交通事故の被害者は必ず一定の補償を受けることができます。しかし、補償金額には上限があるので必ずしも損害をカバーしきれるとは限らないことに注意が必要です。
ちなみに、農業協同組合・中小企業等協同組合・消費生活協同組合が「共済」として取り扱うものを「自動車損害賠償責任共済」と呼びます。制度区分が異なるだけで、ほぼ同じ制度と考えて差し支えありません。
自賠責保険に関するルール・原則

はじめに、自賠責保険に関係するルールや原則を説明します。
自賠責保険は損害保険会社や共済組合が取り扱っているものの、単なる保険商品ではなく、国によって定められた一つの「制度」なので、法律などにのっとり厳格に運用されています。
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という法律にのっとって運用されています。この法律には、自賠責保険についての様々な規定が記されており、自賠責保険のルールや内容の全てはこの法律に基づいています。
自動車損害賠償保障法が生まれたのは昭和30年です。この頃は交通事故の死者が日清戦争の死者数を上回ったとして「交通戦争」という言葉が生まれた時代でした。その中で、交通事故の加害者の責任追及と被害者の保護のために制定されています。
法律の全体的な条文は、第一章の「総則」から第六章の「罰則」まで構成されています。
交通事故時の加害者の賠償責任や「強制保険」としての自賠責保険の性質、保険料の基準を審議する審議会のことまで、自賠責保険に関する内容はほぼ網羅されていると言えるでしょう。
とはいえ、実際に自賠責保険を取り扱っているのは損害保険会社です。コンビニやインターネットを利用した手続きが可能かどうかは、会社ごとに異なるので、細かな点は条文で確認できないこともあります。
ごく一部の車を除き、公道を走る自動車は必ず自賠責保険に加入しなければなりません。
自賠責保険に未加入の「無保険」の場合、車検が受けられない上に処罰されるなど、様々なペナルティが待っています。処罰の内容は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに違反点数6点で即座に免許停止になるというものです。
とはいえ、車検制度が適用される多くの乗用車の場合、車の登録時や車検時に業者が自賠責保険の加入や更新を済ませてくれます。そのため、保険の加入状況について神経質になる必要はありません。
一方、このルールは車検を受けなくてもいい原付バイクなどの「検査対象外軽自動車」も対象となるので注意が必要です。これらの車については、持ち主が購入時や更新時期に自ら加入や更新を行うことになっています。
自賠責保険という制度には、「ノーロス・ノープロフィットの原則」という運用上の原則があります。
自賠責保険には、利益(Profit)も損失(Loss)も発生しないということです。
通常、損害保険会社が扱う自動車保険には「商品」という性質があるため、販売にあたり会社の利益も計算されています。しかし、自賠責事業では保険料に利益は含まれず、発生した剰余金も特別会計で管理され、損害保険会社などの間で分配されます。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自賠責保険の仕組み
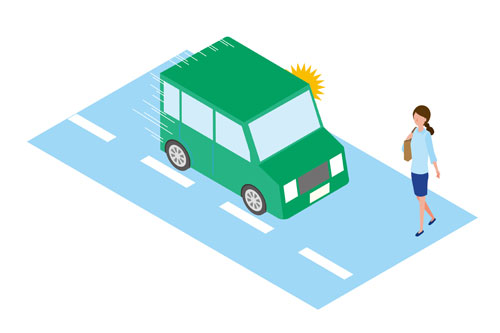
ここまで、自賠責保険という制度の土台となっている法律や原則について説明しました。
次に、自賠責保険のそもそもの目的や、実際の運営主体はどこなのか、また補償対象は何なのかなど、その全体的な仕組みについて解説していきます。
自賠責保険の目的は簡単に言えば「交通事故の被害者の保護」です。
自動車事故における加害者の責任を明確にすると同時に、被害者の損害を最低限補償しようというのが、自賠責保険の趣旨です。
交通事故が起こると、加害者が被害者に損害賠償を支払うほどの経済力がない可能性があります。そんな場合に、最低限の補償をするために定められたのが自賠責保険です。
保険と言いつつも、社会保障的な性格が大きいと言えるでしょう。
自賠責保険は国の定めた法律によって運用されており、社会保障的な性質があります。
しかし、実際に運用するのは民間の損害保険会社や協同組合で、あらかじめ定められた契約内容にのっとって加入・更新の手続きなどを請け負っています。
そのため、損害保険会社や協同組合は、自賠責保険への加入を断ることはできません。取り扱う体制は組織ごとに様々ですが、契約内容はどこで加入しても共通です。
自賠責保険の加入・更新の手続きを行うのは車の所有者です。しかし、厳密にいえば自賠責保険で保険の対象となるのは「車」のほうなので、たとえ契約者と実際の運転手が違っていたとしても特に問題はありません。
例えば、息子が運転しているバイクの保険契約者が父親になっていて、万が一事故が起きればちゃんと自賠責保険で補償されます。その時の運転手が誰であったとしても、あくまでも「その車」が対象となる保険なのです。
自賠責保険の契約内容

自賠責保険は、保険料の金額体系や補償内容などが、あらかじめ決まっています。地域や車種ごとの違いも含めて全国一律です。
それでは、具体的にどのような内容になっているのか、以下で詳細を説明します。
まず自賠責保険の最も大きな特徴として挙げられるのは、保証されるのが「交通事故の被害者」に限られるという点です。
自賠責保険に加入している車が事故を起こし、それが原因で他人に怪我をさせた場合に保険金が支払われます。
しかし、衝突した物や破損した車の修理代、加害者の怪我の治療費には自賠責保険は適用されません。あくまでも他人を巻き込んだ人身事故に対してのみ適用されるということです。
また、自賠責保険には「事故の被害者からも保険金を請求できる」という特徴があります。
通常は、事故の加害者が自分が加入している自賠責保険について保険金を請求することになりますが、加害者が何らかの理由で賠償を拒むようなケースもあります。そんな時は、事故の被害者側から加害者が加入している自賠責保険の損害保険会社に申請すれば、保険金を請求することが可能です。
こうした点からも、自賠責保険は「被害者救済」に重きを置いていることが分かります。
自賠責保険の保険金は支払基準が決まっており、これに基づいて迅速・公平に支払われます。
その支払い上限額は被害者1名ごとに決まっており、被害者が2名以上いる場合でもそれぞれに上限まで支払われます。
金額は被害者1名につき傷害120万円、後遺障害4,000万円です。
「後遺障害」については、第1級~14級までの等級が障害の程度に応じて定められており、もしも常時介護が必要な程度の障害が残った場合は4,000万円が支払われるなど、内容が細かく決められています。
被害者が入院・通院することになった場合も、2021年4月以降に起きた事故の場合は支給額が1日あたり一律で4,300円です。さらに、これに治療期間をプラスした総額を計算することになります。
また被害者が亡くなった場合には、自賠責保険から遺族に対して最大3,000万円の慰謝料が支払われます。内容を詳しく見ていくと、被害者本人に対するものと遺族に対するものに分けられています。
自賠責保険は強制保険なのに対し、自動車保険は任意保険です。そのため、自動車保険に加入する・しないは自由ですし、加入する場合の契約内容も保険会社ごとに異なるので自由に選べます。
また、自賠責保険は交通事故の「被害者」のみを最低限救済するものです。事故を起こした加害者側の怪我や車などの損害の補償は含まれないので、任意保険に入ることでカバーする必要があります。
自賠責保険で補償しきれない分は自動車保険に入っておくことで、補償してもらえます。
自賠責保険の加入・更新・解約方法

ここまで、自賠責保険という制度の成り立ちや契約内容を説明してきました。では、実際に加入・更新する場合や解約したい場合などはどのように手続きをするといいのでしょう?
以下で詳しく説明していきます。
普通乗用車などの場合、その車が新車として登録される際にディーラーによって自賠責保険への加入手続きが行われます。そのため、納車される際は、既に自賠責保険が加入済みの状態となっています。
自賠責保険の加入手続きは、自分で行うことも可能です。その場合は車を購入する際に、自賠責保険の手続きを自分で行うことをディーラー側に伝えておけば大丈夫です。しかし、わざわざ自分で行うメリットは特にありません。
一方、原付バイクのような「検査対象外軽自動車」の場合は、原則的に自賠責保険への加入手続きは自分で行いますが、ほとんどの場合バイクを購入したお店が代理店として手続きを代行してくれます。
自賠責保険は、誰がどこで契約しても内容が変わらないため、販売店などに全て任せて問題ありません。それでも自分で手続きをするとしたら、損害保険会社、代理店、郵便局、コンビニなどで行うことができます。
自賠責保険の更新手続きも、普通乗用車などは何も言わなくとも車検の際に行われます。そして車検が終了すると、新しく自賠責保険証明書が発行されます。
一方、車検を受けない原付バイクなどは、更新時期に損害保険会社から通知ハガキが届くことが多いです。そのタイミングで保険会社や代理店、コンビニなどで更新手続きを自分でします。
その際、自賠責保険証明書や自賠責ステッカーは、後日郵送となるケースもあるので、注意しましょう。
自賠責保険の解約は、その車を廃車(抹消登録)する時に限り行うことが可能で、多くの場合は車両を引き取った業者側で手続きをしてくれます。
ただし、車を乗り換えるのであれば解約ではなく「車両入替」となりますが、車種や保険料が同一であることなどの条件があるため、新規加入する場合が多いです。
解約する際、保険期間の残存期間によっては支払済みの保険料の一部が返金されます。わずかな日数の差で金額に違いが出てくることもあるので、その点が気になる場合は解約手続きだけ損害保険会社で行ってもいいでしょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
保険料について

ここまで、自賠責保険の仕組みと、実際の加入・更新・解約の方法を説明しました。
次に加入・更新の際に私たちが支払うことになる保険料について、その金額の決定基準や、いつどこで支払うことになるのかを解説します。
自賠責保険の保険料は、一定の基準料率に基づいて定められています。この基準料率は「損害保険料率算出機構」という機関が算出しており、この算出結果の審議の結果によっては、次の年度からの保険料が変わることもあります。
この保険料の変動の根拠となるのは、事故発生率の増減です。
こうした変更の手続きの経緯は、同機構のWebサイト内でも議事録を公開することによって周知されており、アクセスすればすぐに確認することができます。
自賠責保険の加入や更新の手続きを業者が代行してくれる場合は、保険料も立て替えてくれています。そのため、実際の契約者はその立替分を業者に対して返済する形になります。
保険の加入は納車手続きの中で行われ、更新は車検時に行われることがほとんどです。どちらにしても、見積書や請求書の各種費用の内訳を見れば、自賠責保険料の費用も含まれていることが分かるでしょう。
一方、加入や更新を自分で行う場合は、それぞれの手続き場所で支払うことになります。これは、原付バイクなどの検査対象外軽自動車も同様です。
損害保険会社の窓口、郵便局、コンビニ、Webサイトなどで保険料を支払います。
なお、自賠責保険料は「前払い」という性質を持っています。車種により1~5年の期間で加入することが多く、その年数分の保険料をまとめて支払わなければなりません。
保険金について

ここまで、私たちが自賠責保険の加入や更新時に支払う保険料について説明しました。
次に、交通事故の被害者に支払われる保険金について、その金額はどのように決まるのか、また請求はどのようにするのかを解説します。
自賠責保険で補償される金額も、社会環境や経済状況などに応じて変動します。
保険金の支払基準は金融庁・国土交通省の告示に基づいて設定されていますが、「平均余命年数」「物価・賃金水準」「近年の保険金の支払状況」などが反映されます。
他にも、法定利率が変更されると後遺障害に対する逸失利益の計算にも影響を及ぼすため、これが保険金額の変更に繋がることもあるでしょう。
保険金の金額も、保険料と同様に常に変動する可能性があります。
契約している損害保険会社に、自賠責保険の保険金を請求するやり方などを説明します。
基本的には契約者(事故の加害者)が、事故の内容や被害者・加害者の詳細、自賠責保険証明書番号などを保険会社へ届けることになります。
ただし、加害者の対応や事故の内容によっては、保険金の請求がなかなか行われないこともあります。この場合は、被害者保護の観点から、被害者自身が保険金(損害賠償額)を請求することも可能です。
また、賠償額が確定するまでに時間を要するような場合でも、被害者側は葬儀費や治療費といった当面の出費の補償を必要とすることがあります。この場合も「仮渡金」という形で、被害者から前払請求することが可能です。
そして、自賠責保険から支払われた保険金の金額などについて納得がいかない場合は、「自賠責保険・共済紛争処理機構」という機関に相談することもできます。これは国の監督を受けている公正・中立・専門的な機関なので安心して利用できます。








