車を運転する際には、いくら安全運転を心がけていても、万一の事故に備える必要があります。特に運転免許を取ったばかりの未成年者であれば、事故率が高くなる傾向があります。
事故に備えて、自賠責保険や任意保険を契約することは未成年者でも可能なのでしょうか?
この記事では、車に関する自動車保険について詳しく解説していきます。今後の保険への加入での参考にしてください。
未成年であっても自賠責保険は強制保険
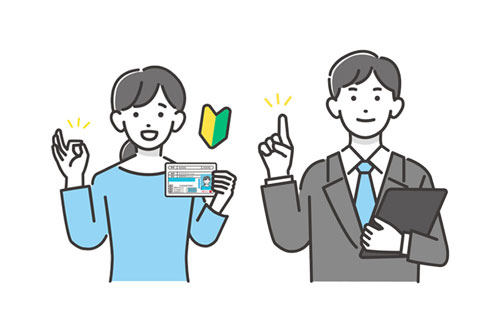
民法上、未婚の未成年者は1人で契約できないことになっていますが、2022年4月1日以降は成人年齢が変わり、18歳以上が成人となるため、親の同意がなくても契約できるようになります。ただし、保険会社により対応は異なりますので、問い合わせて確認するのが賢明です。
自賠責保険は「強制保険」とも言われ、車検を通す時に加入が必要となります。車の所有者が未成年者であったとしても、加入は必須ということです。
原動機付自転車を含む全ての自動車は、自動車損害賠償保障法という法律により、自賠責保険に加入しなければ公道を走行してはいけないことになっています。
もし自賠責保険に加入していない車を公道で運転した場合には、以下の罰則が科せられます。
- 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 違反点数6点で30日間の免許停止処分
このように、自賠責保険に未加入で公道を走った場合の罰則は重いです。
自賠責保険に加入していないと車検も通らないため、忘れるケースはあまり多くありません。しかし、一番の問題となるのが、車検を通すのを忘れてしまい、乗り続けているケースです。そのため、車検の有効期限がいつまでなのか必ず確認しましょう。
自賠責保険の特徴は、車の所有者に保険加入を義務付けているところにあります。
安全運転で走行していたとしても、いつ事故を起こしてしまうかは分かりません。事故を起こせば、被害者に対する賠償金の支払いが必要な可能性も高いです。
そのため、自賠責保険には被害者の救済のために強制で入らなければならない保険として導入された背景があります。
そんな自賠責保険の補償内容は、以下の通りです。
被害者1名につき120万円
①介護を要する障害(被害者1名につき)
常時介護を要する場合(第1級)4,000万円
随時介護を要する場合(第2級)3,000万円
②上記2つ以外の後遺障害
(第1級)3,000万円~
(第14級)75万円
被害者1名につき3,000万円
気をつけなければいけないのは、自賠責保険に加入せずに人身事故を起こしてしまった場合です。もともと自賠責保険で支払われる賠償金は、全て自己負担になってしまいます。
任意保険に入っていたとしても、実際に支払われるのは自賠責保険の補償限度額を超えた金額だけになります。つまり、被害者が死亡したケースでは、自賠責保険加入で3,000万円を限度額として保険金が支払われ、限度額を超えた分を任意保険で支払うことになるということです。
しかし、自賠責保険に未加入で死亡事故を起こしてしまうと、この3,000万円を自分で賠償することになってしまいます。
自賠責保険に加入していない車のことを「無保険車」と呼ぶことがあります。
前述しましたが、自賠責保険に未加入の車を運転してはいけないことになっています。そのため、うっかり保険の更新を忘れている状態にならないように、国土交通省でも対策を講じています。
例えば、路上での取締の強化や、自賠責保険期間終了後に6ヶ月を過ぎても再契約のない場合に注意喚起の書面の郵送を行っています。
公道を走行する時には自賠責保険の加入が必須ですので、くれぐれも有効期限が切れないように気をつけましょう。
自動車保険は未成年者の名義でも契約できる?

自動車保険は、万一のリスクに対応するために必要です。そのため、未成年者でも自動車保険は契約可能です。
しかし、未成年者の自動車保険の契約については、法定代理人(親権者など)の同意の署名を必要としている保険会社が多数を占めています。
なお、未成年者であっても、結婚している場合や、就業している(企業等に勤務をして毎月給与の支払いを受けている)場合は、法定代理人による同意が不要になるケースもあります。
自動車保険の契約をする時に登録が必要な名義は、契約者だけではありません。実際に保険を受ける対象となる「記名被保険者」の名義を登録することも必要です。
未成年者が自動車保険を契約する場合、契約者として加入することが難しくても、親が契約する自動車保険の記名被保険者であれば補償を受けることができます。
具体的に説明すると、主となる車の契約者を親にして、自分は記名被保険者として登録するという方法です。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
未成年者の自動車保険料が高い理由とは?

未成年の自動車保険の料金は、それ以外の年齢層より高くなることが一般的です。それは、事故率が高いことが要因としてあります。
ここからは、未成年者の自動車保険が高くなる理由について詳しく解説していきます。
未成年者の事故率が高いということは先ほどお伝えしました。
実際の事故原因としては、スピード超過や運転操作ミスが主な原因となる傾向にあります。
警視庁が発表している令和3年度における交通事故の発生状況によると、「原付以上運転者(第1当事者)の年齢別層別免許保持者10万人当たり交通事故数」は以下の通りです。
20~24歳:605.7件
25~29歳:424.9件
30~34歳:329.1件
35~39歳:299.4件
40~44歳:292.8件
45~49歳:299.5件
50~54歳:299.0件
55~59歳:304.4件
60~64歳:302.6件
65~69歳:302.5件
70~74歳:336.0件
75~79歳:390.7件
80~84歳:429.8件
85歳以上:524.4件
出典:警視庁「令和3年中の交通事故の発生状況」
これを見ると分かる通り、16~19歳が一番交通事故率が多くなっていて、次に20~24歳と続きます。
交通事故が発生する確率が高くなってしまうため、保険会社は未成年者の保険料を引き上げるようにしているのです。
上記の交通事故発生件数の状況を見ても分かりますが、年齢に応じて交通事故率に変化があります。そのため、保険会社では運転者の年齢条件を定めることによって保険料を割引する制度を設けています。これが「運転者年齢条件」です。
年齢制限は、年齢ごとの事故率を基準にして保険会社が設定しています。一般的には、事後率が低い30代~40代は割引率が高くなり、未成年や20代前半、60代以降は割引率が低くなる傾向があります。
そのため、26歳以上限定で自動車保険に加入すれば、「年齢制限なし」の場合に比べて、保険料を安くすることが可能です。
未成年者の場合は「年齢制限なし」の保険に加入しなければなりません。割引率がない状態になり、保険料が割高になるということです。
自動車保険では、保険料を決める際に「等級制度」を利用します。
等級制度は、1等級~20等級まであり、等級数が大きくなるほど保険料の割引率が高くなる制度です。
新規契約における等級は6S等級(セカンドカー割引適用時は7S等級)からスタートし、1年間保険を利用して事故が起きなければ次年度に1等級上がり、割引率が高くなっていきます。
しかし、事故を起こして保険を使用すると、事故の状況によって次年度から事故ごとに3等級または1等級引き下がるため、割引率は低くなってしまいます。
未成年であれば自動車保険は新規契約になるケースが多いため、6S等級か7S等級から契約することになるでしょう。そうなると、どうしても保険料は高くなります。
未成年者が自動車保険を安くする方法とは?

未成年者の自動車保険が割高になる要因についてお伝えしてきましたが、保険料を安く抑えるための方法はあるのでしょうか?
ここからは、保険料を安くするための方法を4つ紹介していきます。
1つ目は、通販型自動車保険を選ぶことです。
自動車保険を扱う保険会社は、通販型と代理店型があります。
通販型とは、ネットなどで加入ができる保険会社のことです。事務所の維持費や人件費を抑えることでコストダウンを図っているため、保険料が安く設定されています。
また、車を購入する時に、販売店が自動車保険の代理店と提携している場合があります。そのまま契約するのではなく、通販型と代理店型の保険料を検討した上で決めると良いでしょう。
2つ目は、契約条件を変更することです。
これは、自動車保険の加入を行う際に、未成年が保険契約者として手続きする方法とは異なります。
家族で共有する車が加入している保険の補償内容を変更することで、未成年者もその車を使用することができるという方法で、「運転者年齢条件特約」に関する条件を変更することがポイントです。
運転者年齢条件を未成年者が適用できるように、年齢条件なしに変更すれば、保険の適用範囲が全年齢対象になります。
しかし、保険料は変更前に比べて割高になることは覚えておきましょう。
3つ目は、親の等級を引き継いで使用することです。
前述した通り、自動車保険の新規契約は6等級からスタートしますが、以前から利用している自動車保険の等級を、同居している家族に引き継ぐこともできます。
そのため、親が入っている自動車保険が高い等級になっているのであれば、未成年の子供に引き継ぐことができるのです。高い等級を引き継げば、新規加入よりも保険料は安くなります。
等級を譲ったあとに親が新規で自動車保険に加入することになったとしても、保険料は未成年者が新規で加入するよりもトータルでお得になる場合が多いです。
4つ目は、免責金額を高めに設定することです。
免責金額とは、実際に事故を起こしてしまった場合、支払われる保険金額のうち損害額を設定した分だけ自己負担する金額のことです。
例えば、事故を起こして損害額が30万円だったケースで考えてみましょう。免責金額を設定していなければ、保険金を30万円受け取ることが可能です。しかし、免責金額を10万円に設定していれば、10万円を自己負担して残りの20万円分を受け取ることになります。
免責金額を高めに設定すると保険金の受け取る額は少なくなりますが、その代わりに月々の保険料を抑えることができます。
実際のところ、保険を使うことで等級が下がり次年度の保険料が高くなるため、10万円以下の事故であれば、自己負担にするとお得になることが一般的です。
大きな事故を起こす可能性に備えて、自動車保険の加入は必要ですが、特に未成年者の保険料は高くなります。新規加入であれば免責金額を高めに設定するというやり方も、保険料を安くする方法として知っておくと良いでしょう。
車の選び方で保険料を抑えることができる?

ここまで保険料が年齢と等級で決定される点についてお伝えしてきましたが、それ以外に保険料を決める基準はあるのでしょうか?
保険料は事故率が高くなれば引き上がる傾向にあります。そのため、車種の選び方にも関係してきます。
ここからは、車の選び方による保険料の変化について詳しく解説していきます。
自動車保険は、年齢や等級以外に「型式別料率クラス」が適用されています。これが車種によって保険料が変わる仕組みです。
型式別料率クラスは、車の型式に応じてリスクを17段階に区分しています。(自家用軽自動車については3段階に区分されています。)
算出される内訳としては、以下の4項目があります。
- 対人賠償
- 対物賠償
- 傷害(人身傷害・搭乗者傷害)
- 車両保険
保険金の支払い実績が少ない型式ほど数値は小さくなり、保険金の支払い実績が多い型式は大きくなります。つまり、型式型料率クラスの数字が大きくなるほど、保険料は高くなってしまうというわけです。
例えば、コンパクトカーと高級車で比較すると、コンパクトカーの場合は料率クラスが全体的に小さめであるため、保険料が安く設定されます。しかし、高級車の場合は修理費が高額になることや盗難の対象になりやすいため、車両保険の料率クラスが大きめに設定されることから保険料が高くなる傾向があります。
保険料を抑える方法としては、型式別料率クラスの数字が低い車を利用することがポイントになるでしょう。
ちなみに、型式別料率クラスの算出は、損害保険料率算出機構が型式ごとの事故実績に応じて提示しており、それを基に保険会社が適用しています。
型式別料率クラスは、1年に1度見直しが行われます。型式によっては事故が急増すると料率クラスが上がり、保険料が引き上がることもあります。
等級や契約条件が同じであっても保険料が上がる場合はあるので注意が必要です。
事故を未然に防ぐ安全装備が搭載されている車に関しては、事故発生率を少なくすることから、保険料が優遇される場合があります。
対象になる車はASV(先進安全自動車)で、その中でもAEB(衝突被害軽減ブレーキ)を搭載していることがポイントです。
そして、用途車種は自家用普通乗用・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車です。その車が販売から3年を経過していないことも適用条件となります。
ただし、軽四輪乗用車の場合は、型式別料率クラスの導入がされるまで期限なしで受けられるとされています。
注意しなければならないのは、適用条件が自分の車が納車されてから3年間ではなく、車が実際に販売されてから3年間であるという点です。
この条件は保険会社によって異なりますので、対象の車であれば保険会社に確認しておくと良いでしょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
1日自動車保険とは?

未成年者が運転免許証を取ったとしても、頻繁に運転するのではなく、たまに車を運転するのみであれば、自動車保険に加入するまでもないでしょう。その際は、「1日自動車保険」を利用するという方法もあります。
1日自動車保険は、必要な時に必要な分だけ補償を選び加入できる点が大きなメリットです。日常的に利用しなければ、保険料を抑えて運転することができるようになります。
料金も数百円から数千円で、ネットやコンビニで申し込みが可能です。
そして、基本的に他人の車を運転することを前提とした保険になっています。そのため、友人の車や家族所有の自動車で、運転者限定条件から外れた状態であれば、利用することができます。
しかし、自己所有の車や配偶者所有の車、レンタカー、会社所有の社用車などの車を運転する際には加入できません。必ず補償内容を確認しましょう。








