自動車保険は、「自賠責保険」と「任意保険」の2つから成り立っています。中でも、自賠責保険は加入が義務付けられている「強制保険」とも呼ばれています。
ほとんどの人がこの2つの保険に加入していますが、どちらか1つの保険に加入していれば問題ないと認識している方もいます。しかし、自賠責保険は任意保険に比べると金額が安く一律であるがゆえに、補償範囲にも大きな違いがあることを覚えておかなければなりません。
この記事では、自賠責保険の保険料や補償内容について詳しく解説していきます。
自賠責保険とは?

自賠責保険とは、交通事故による被害者救済や加害者が負うべき経済的な負担を補填するために法律に基づいて作られた保険です。
対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含む全ての自動車に加入が義務付けられています。人気が上昇傾向にある電動キックボードも原動機付自転車に該当するため、自賠責保険への加入が必要です。
自賠責保険に未加入で公道を走行することは法律により禁止されています。走行した場合には罰則に科せられ免許取消となることもあるので必ず加入しているか確認しておきましょう。
ここからは、自賠責保険の特徴や誕生した経緯について詳しく見ていきます。
自動車には自賠責保険と任意保険の2種類がありますが、この2つの違いについてご存知でしょうか?
どちらも同じ保険と認識している方は意外と多いですが、この2つの保険は補償範囲や保険料など様々な違いがあります。
自賠責保険は、「自動車損害賠償保障法」という交通事故の被害者救済を主な目的として運用されています。正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といいます。加入するのは車の購入時や車検時です。
車検義務のない乗り物(原付や小型バイクなど)は購入時に加入した後、満期日までに自分で加入の更新手続きを行います。
任意保険と違い、被害者救済のために運用されているので保険料は一律です。
エンジンを搭載した乗り物で公道を走行する際、自動車損害賠償保障法(自賠法)により自賠責保険の加入が義務付けられています。
自賠責保険は、戦後の高度経済成長期に誕生しました。戦後の復興に伴って自動車の保有台数は増大し、1955年には130万台を超えました。
車の保有台数やドライバーが増加すると、車による人身事故も増加していきます。1956年には死者6,000人、負傷者が10万人を超え社会問題へと発展しました。
国に対して、被害者の救済措置の検討が求められました。その結果として、国が法律を制定し、法律により定められた保険で対応することとなりました。これが現在の自賠責保険となっています。
本来、損害保険の保険料はどの保険も一律でした。しかし、保険という商品販売の自由化に伴い、1998年に保険料率の自由化が進んだのです。
それまで、損害保険は損害保険料率算出機構という料率算出団体が自動車保険や火災保険の料率を決定していました。それに基づき、保険会社は同じ料率で販売していました。
料率は、保険商品の値段を決めるための基準ということです。それが自由化してから、保険会社は独自の保険商品を開発し、料率を設定するようになりました。
一方で、自賠責保険は国が定めた法律に基づき保険料を設定しているため、各保険会社が設定することはできません。
自賠責保険の保険料は一律
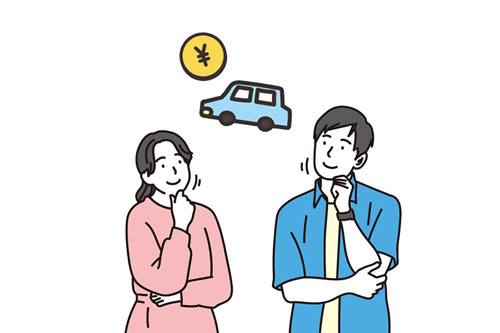
自賠責保険は、交通事故の被害者救済のため法律に基づき設けられた保険です。そのため、原付を含む全ての自動車に加入義務があります。
しかし、任意保険とは違い、どの保険会社で加入しても保険料は一律です。その理由は、保険料の決め方や補償範囲にあります。
自賠責保険の保険料は、毎年1月に金融庁が開催する「自動車損害賠償責任保険審議会」で改定の有無を審議、決定します。
例えば、2019年の場合は1月16日の審議で「2019年度の保険料は2018年度と同額に据え置く」と決定しました。
それでは、自賠責保険はどのような基準で算出されるのでしょう?
自賠責保険の基準料率は「保険料率の三原則」に基づき決定します。
保険料率の三原則とは、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであってはならないというルールのことです。
自賠責保険は、社会政策という側面を持った保険であり、その保険料率は、能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でできる限り低いものでなければならないと法令で定められています。
そのため、利潤や損失が生じないように算出することが必須であり、このことを「ノーロス・ノープロフィット」といいます。
また、自賠責保険は「強制保険」とも呼ばれています。強制で加入しなければならない保険と呼ばれるだけあって、それだけ公共性の高い保険であることが分かるでしょう。
自動車は利用する目的や自動車の種類などにより、事故が発生する頻度や被害の程度に差があります。自賠責保険では、用途や車種などによって異なるリスクを区分して保険料率に差をつけています。
このような点から、本土(北海道・本州・四国・九州)、離島(沖縄県、沖縄県の離島など)によっても異なる保険料が設定されているのです。
強制加入が原則の自賠責保険ですが、保険料の支払方法も車種によって違います。
前述したように、自賠責保険は自動車を利用する目的や自動車の種類によってリスクが異なるため、用途・車種別に区分を設けています。
主な自動車の区分は以下の通りです。
- 自家用乗用自動車
- 軽自動車
- 自家用小型貨物自動車
- 自家用普通貨物自動車
- 事業用小型貨物自動車
- 営業用普通貨物自動車
- 自動小型二輪自動車
- 原動機付自転車
この他にも、パトカーや霊柩車などの特殊車両も保険料は区分されます。
自家用乗用車や軽自動車、貨物車などの自賠責保険は、車検時の加入が必須です。そのため、ディーラーや整備工場に車検依頼をした際に2年間もしくは1年間の保険料を代納してもらいます。
車検義務のない250cc以下のオートバイや原付は、保険満了時までに自分で加入の更新手続きをします。保険代理店や整備工場でも受け付けてくれますが、コンビニでの加入もできるようになりました。
自賠責保険は原則現金払いですが、保険会社によってはクレジットカード決済やQRコード決済といった、キャッシュレス決済ができるところもあります。そのため、保険会社の最新情報を確認しておきましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
保険料一覧

自賠責保険は車種によって保険料に差があります。
しかし、公共性の高さとノーロス・ノープロフィットなどの概念に基づいて決定しているので、任意保険のように細分化はされていません。例えば、コンパクトカーでも大型SUVでも普通乗用車であれば保険料は同じです。
それでは、令和3年4月1日以降に適用された自賠責保険の保険料を一覧でご紹介していきます。
| 保険料 | 期間 |
|---|---|
| 27,770円 | 37ヶ月 |
| 27,180円 | 36ヶ月 |
| 20,610円 | 25ヶ月 |
| 20,010円 | 24ヶ月 |
| 13,310円 | 13ヶ月 |
| 12,700円 | 12ヶ月 |
| 保険料 | 期間 |
|---|---|
| 27,330円 | 37ヶ月 |
| 26,760円 | 36ヶ月 |
| 20,310円 | 25ヶ月 |
| 19,730円 | 24ヶ月 |
| 13,150円 | 13ヶ月 |
| 12,550円 | 12ヶ月 |
| 保険料 | 期間 |
|---|---|
| 31,870円 | 25ヶ月 |
| 30,840円 | 24ヶ月 |
| 19,220円 | 13ヶ月 |
| 18,160円 | 12ヶ月 |
| 保険料 | 期間 |
|---|---|
| 37,980円 | 25ヶ月 |
| 36,710円 | 24ヶ月 |
| 22,430円 | 13ヶ月 |
| 21,130円 | 12ヶ月 |
| 保険料 | 期間 |
|---|---|
| 33,840円 | 25ヶ月 |
| 32,730円 | 24ヶ月 |
| 20,250円 | 13ヶ月 |
| 19,120円 | 12ヶ月 |
| 保険料 | 期間 |
|---|---|
| 11,390円 | 37ヶ月 |
| 11,230円 | 36ヶ月 |
| 9,440円 | 25ヶ月 |
| 9,270円 | 24ヶ月 |
| 7,440円 | 13ヶ月 |
| 7,270円 | 12ヶ月 |
| 保険料 | 期間 |
|---|---|
| 16,220円 | 60ヶ月 |
| 14,110円 | 48ヶ月 |
| 11,960円 | 36ヶ月 |
| 9,770円 | 24ヶ月 |
| 7,540円 | 12ヶ月 |
| 保険料 | 期間 |
|---|---|
| 13,980円 | 60ヶ月 |
| 12,300円 | 48ヶ月 |
| 10,590円 | 36ヶ月 |
| 8,850円 | 24ヶ月 |
| 7,070円 | 12ヶ月 |
自賠責保険の補償範囲と保険金について

保険料の支払いが完了していれば、自賠責保険に加入したことになります。もし事故を起こしてしまった場合は補償を受けることができます。しかし、その範囲と保険金の限度額は決まっているので注意が必要です。
自賠責保険の目的は自動車事故の被害者に対する基本補償を確保するためです。被害者の人身損害について、政令で定められた保険金など限度額の範囲内で支払われます。
被害者に対して迅速かつ公平な保険金の支払いを確保するために損害保険会社は「傷害」「後遺障害」「死亡」それぞれの損害額の算出基準に則り支払います。
自賠責保険の限度額は、傷害や死亡、後遺障害などに至るまで、それぞれの場合に程度に応じた支払限度額が設定されています。
傷害によって受けた損害は、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが支払われます。治療関係費の内訳は、治療費や看護費の他に通院費や義肢などの費用、診断書作成料まで含まれます。
それに加えて、事故証明書発行や住民票取り付けなどに必要な文書料、事故により休業や休職に伴う補償、そして交通事故による肉体的、精神的ダメージへの補償が慰謝料として支払われます。
これら全てを含み、限度額は1名あたり120万円です。
後遺障害による損害では、障害の程度に応じて失った利益(収入)および慰謝料などの支払いをします。
後遺障害とは、交通事故で受けた損傷が元で傷害を負ったとき、精神的または肉体的に負った損傷が継続される状態のことです。
後遺障害の認定は、傷害と後遺障害との間に相当因果関係が認められ、かつ、医学的に認められる症状となります。さらに、自動車損害賠償保障法施行令別表第一または第二に該当することが条件です。
限度額は常時介護を必要とする場合(第1級)4,000万円です。
そして、随時介護を必要とする場合(第2級)3,000万円から始まり、最終は(第14級)75万円となります。
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、被害者、遺族の慰謝料が支払われます。
限度額は1名あたり3,000万円です。
自賠責保険の加入は車だけではない

自賠責保険は車検の有無は関係なく、公道を走行するバイクや原付も加入しなければなりません。
どこへ何を持参すれば加入手続きができるのか分からず、未加入のままという事態を招かないために自賠責保険の加入方法についてご紹介します。
まずは自賠責保険の加入と更新に必要なものを見ていきましょう。
軽二輪自動車(125㏄~250㏄以下のバイク)の場合は以下の持ち物を用意しましょう。
- 軽自動車届出済証
- 現在契約している自賠責保険の証券(更新の場合)
- 保険料
原付の場合は以下の持ち物を用意しましょう。
- 標識交付証明書
- 現在契約している自賠責保険の証券(更新の場合)
- 保険料
自賠責保険の更新や加入手続きは、損害保険会社のほかに自動車保険代理店やコンビニでも可能です。
損害保険会社や自動車保険代理店では、書類を窓口に提出し保険料を支払えば加入できます。窓口に行かずにインターネットで契約ができる場合もあります。
コンビニで加入する場合は店内にある情報端末で申し込み、レジで保険料を支払ます。コンビニによって加入方法が異なる場合がありますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自賠責保険の保険料を支払わないとどうなる?

原則として、自賠責保険の保険料は前払いかつ現金払いです。保険料を支払っていないということは、自賠責保険に未加入であることを意味します。
自賠責保険は法律に基づいて加入義務のある保険のため、交通事故を起こしたかどうかにかかわらず、未加入で公道を走行すれば罰則対象となります。
自賠責保険に未加入の車やトラックが人身事故を起こすと、自賠責保険から支払われる賠償金が全て自己負担になります。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険での補償限度額を超えた金額だけです。
例えば、被害者が死亡して支払う保険金が8,000万円とします。自賠責保険に加入していれば限度額3,000万円まで支払われ5,000万円が任意保険で賄われることになります。しかし、自賠責保険に未加入だった場合はこの3,000万円を自分で賠償しなければなりません。
また、事故を起こさなくても、自賠責保険に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険の証明書不携帯でも30万円以下の罰金が科せられます。無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。
それに加えて、車やトラックは車検時に自賠責保険に加入するため自賠責保険への未加入は無車検で走行していることが大半です。無車検の車で走行した場合、違反点数6点、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となり違反点数によっては免許取消となります。
自賠責保険に未加入でバイクや原付を公道で走行したり、保険期間が切れた状態で交通事故を起こして見つかった場合は、車やトラック同様、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、6ヶ月の範囲内で免許停止処分になります。
「車検義務のないバイクや原付は自賠責保険へ加入していることが分かりにくいから、加入していなくても事故さえ起こさなければ大丈夫」という考えの人がいますが、これは大間違いです。
バイクや原付は自賠責保険に加入するとステッカーが交付され、ステッカーをナンバープレートの指定の場所に貼ることが義務付けられています。そして、そのステッカーは保険期間が即時に分かるように、保険の満期年ごとに色が違います。
自賠責保険の契約は最長5年ですが、2019年以降は「赤色→黄色→緑色→青色→橙色→紫色→黄緑色」と7色をローテーションにすることで、色を見るだけで有効期限年が分かるようになりました。
ステッカーの交付により、バイクや原付の所有者が自賠責保険に加入しているかどうがが、ひと目で分かる仕組みになっているので、未加入の場合はすぐにバレます。








