自動車を運転している以上、どんなに気を付けていても交通事故に遭遇するリスクはゼロにはできません。いざという時のために自動車保険に加入することは大事です。
「自動車保険」と一言で言いますが、いろいろな保障の種類があります。自動車保険の種類を理解して、自分にとって何が必要か検討しましょう。
また自動車保険には「特約」といってピンポイントで付け足しできる物もあります。こちらも自分に必要な物を付けるようにしてください。
自動車保険の種類は自賠責と任意が基本

自動車保険の種類は2種類に大別できます。それが、今回紹介する自賠責保険と任意保険です。
自賠責保険は、強制的に加入が義務付けられている保険です。一方、任意保険は加入するかどうか、当人の自由意思で決めることができます。
それぞれどのような保険なのかについて、以下で詳しく見ていきます。また、任意保険には加入すべきかどうかについても確認していきましょう。
自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」と言います。この自賠責保険は、すべての自動車とバイクに対して法律によって加入が義務付けられている保険で、強制保険ともい言われています。
もし自賠責保険に入っていない車を公道で運転すれば、法律違反で処罰の対象です。また、自賠責保険に加入していない車は車検を通すことができません。
自賠責保険はあくまでも、交通事故の被害者の救済を目的とした保険です。よって、被害者のいる事故が保険金支払いの対象であり、対人賠償のみとなります。
そのため、物損事故の場合保険金は一切支払われません。交通事故で自分がけがをしたとしても、それに対する補償はありません。
私たちが日常で「自動車保険」と呼んでいるのは、自賠責保険ではなく任意保険です。任意保険は加入が「任意」と言われている通り強制ではないため、加入していない車を運転しても違法ではありません。
しかし、自動車の保有者の多くが任意保険に加入しています。2017年のデータによると、自動車保険の加入率は約7割に達しています。
また、任意保険は自賠責保険よりも補償範囲が広いです。
例えば、自賠責保険では自らに対する補償はありませんでした。任意保険に加入していれば、自分自身や同乗者に対する保険もかけられます。
また、保障内容は自分で決めることができます。自分が必要な保障にターゲットを絞って契約することも可能です。保険料はかかってしまいますが、いざという時のために加入しておいた方がいいでしょう。

前述した通り、任意保険はあくまで任意なので加入するかどうかは自由です。しかし、いざという時のために、任意保険に加入しておいた方が無難でしょう。
自賠責保険も対人事故を起こしたときに保険金が支払われますが、補償範囲が決まっているため相手をけがさせた場合は120万円、死亡させてしまった場合は3000万円が上限です。
一見すると、かなりのまとまった金額が支払われるイメージがあるかもしれませんが、いざ実際に事故を起こすとこの程度の金額ではとても賄いきることはできないでしょう。
特に相手を死亡させてしまった事故の場合、かなりの賠償金の支払いを請求されます。過去の事例を見てみると、3億円や5億円といった、個人が支払える範囲を超えるような賠償金の支払い命令が出ることもあります。
自賠責保険だけだと、3000万円以上は自分で払わないといけません。任意保険なら上限が無制限なので億単位の賠償でも賄えます。
自動車保険種類一覧を紹介
上記で解説したように、任意保険には万が一のために加入しておいた方がいいでしょう。
任意保険は、保障内容を見ると3タイプに分類できます。そして、3タイプの基本保障を見ると、さらに7種類分類できます。
ここでは自動車保険の基本を構成する3タイプの保険について解説します。

はじめに、賠償責任保険を紹介します。
対人のほかに対物にも、ときとして高額賠償を請求される場合があります。商業車やお店に突っ込んでしまったケースなどは、逸失利益の金額も加味されるためです。
対人賠償は無制限としているところがほとんどとなっています。特に相手が亡くなってしまった、後遺障害の残るような重傷を負わせてしまった場合には、かなりの高額賠償になる可能性が高いためです。
対象になるのは事故の被害者です。歩行者や自転車のほかにも、自動車同士の事故で相手をけがさせたり死亡させたりしたケースも含まれます。
さらに、車同士の事故で相手方に同乗者がいた場合も補償の対象となります。ただし、自分や自分の運転していた車の同乗者については補償されません。
対物賠償保険も無制限としている保険がほとんどです。例えば商業施設に突っ込んでしまって営業できなくしてしまった場合、休業損失も補償しなければならないためです。
誰かの所有物だけでなく、公共の物に何らかの損害を与えた場合でも補償の対象となります。電柱やガードレールに衝突して何らかの損害も与えた場合などに適用されます。
こちらも相手方の物損に対する補償ですので、駐車するときに誤って自宅の車庫を壊した場合などは補償の対象外となるので注意しましょう。

2つ目のタイプとして、傷害補償保険があります。
治療費については実費負担分が保険金の対象ですが、治療費のほかにも保険金が支払われることがあります。
例えば、けがをして入院することになった場合や後遺症が残ってしまった場合には、当面仕事ができなくなるかもしれません。その間の逸失利益などが保険金として支給されます。
また、場合によっては介護が必要な状況に陥ることも考えられます。この際の介護費用についても保険金でカバーできるので、いざという時のために加入しておいた方がいいでしょう。
これだけ聞くと、前述した人身傷害補償保険とは何が違うのか疑問に思うかもしれません。人身傷害補償保険との違いは、支払われる額についてです。
人身傷害補償保険は、実際にかかった費用や逸失利益分が保険金として支払われます。一方、搭乗者傷害保険の場合は定額払いです。あらかじめ契約で定められた金額が一律で支払われます。
人身傷害補償保険の場合、保険金が支払われるまで一定期間かかります。しかし、けがの治療費など出ていくお金は待ってくれません。そこで、搭乗者傷害保険で定額をいったん受け取ります。それで当面必要な費用の支払いに充てることができるのです。
交通事故には、運転ミスで壁に突っ込んでしまった、電柱とぶつかった場合などの自損事故もあります。このような自損事故のための保険として、自損事故保険があります。
自損事故保険は、車同士の事故の場合でも補償の対象になる場合があります。
例えば100対0といって、相手の過失割合がゼロの交通事故の場合でも、自損事故保険に入っていれば保険金が支払われます。どのような事故に遭遇するか分からないので、自損事故保険にも加入しておきたいところです。
交通事故で自分が被害者になった場合、相手から賠償金を受け取ることができます。
しかし、相手が自賠責保険にしか加入していない場合、十分な補償を受けられないかもしれません。そのようなときに加入していれば、自分の保険で賠償金を賄うことができる保険があります。それが、無保険車傷害保険です。
無保険車傷害保険の上限額は、基本的に対人賠償保険と同額です。ただし、無制限としている場合には2億円が上限となるので注意しましょう。
また、相手の自賠責保険で一定額保険金は支払われます。そのため、自賠責保険金の金額分を差し引いた賠償金が支払われます。

3つ目のジャンルになるのが車両保険です。
自動車保険の保険料の中で、車両保険の占める割合が大きいです。もし保険料をできるだけ節約したいと思うのであれば、あえて車両保険をはずすという方法もあります。
車両保険は交通事故から自損事故まで、幅広い事故で車が損傷を受けた場合に保険金が受け取ることができます。また、事故以外で車が損傷を受けた場合でも補償の対象です。
具体的には、地震以外の自然災害やいたずらの被害に遭った場合です。新車など価値の高い車両であれば、車両保険にも加入しておいた方がいいでしょう。
自動車保険の特約の種類一覧
任意保険は、上記で紹介した7種類の基本保障のほかにも特約を付けることが可能です。
特約を付けることで補償範囲が広くなり、安心感を与えてくれるでしょう。一方で保険料は高くなってしまうので、そのバランスをどうとるかがポイントです。
特約は、各保険会社オリジナルの物も用意されています。その中で主だった物について、いくつかピックアップしてみたので紹介します。

弁護士を自分で付けるとなると、場合によってはかなりの費用が必要になるかもしれません。その費用を保険で賄えれば、気軽に弁護士に相談できます。
弁護士費用特約は保険会社によって範囲が異なり、交通事故に限っている物もあれば、日常生活で弁護士を雇う必要が生じたときまで保障してくれる物もあります。
個人賠償責任特約の特徴は、自動車に乗っているとき以外の事故の賠償を賄ってくれる点でしょう。具体的には、お店でうっかり商品を落として壊してしまった、自転車で歩行者をはねてけがさせてしまったときなどです。また、ペットを飼っていて、そのペットが誰かに噛みついてけがした場合も補償の対象となります。
個人賠償責任特約に加入する際には注意が必要です。個人賠償責任特約は、自動車保険以外でも特約として用意している商品があります。
例えば、火災保険の特約でしばしば見られます。もし火災保険の特約に加入していれば、重複契約になってしまうので注意してください。
自動車事故を起こしたとき、対物賠償では相手の車両の時価を上限として補償されます。ところが相手の車両によっては、時価を超える修理費用が発生するかもしれません。
この場合、保険金で賄った残りの部分は自前で支払うことになります。そこで、対物差額修理費用補助特約を付けていれば、時価を超える修理費用の部分も保険金で対応できます。
相手の車が年式が低く時価が安い、特殊な車両で修理が難しいと対物賠償ではカバーできないかもしれません。相手方とのトラブルを避けたければ、加入しておいてもいいでしょう。

ファミリーバイク特約に加入していれば、相手への賠償だけでなく、自分がけがした場合でも保険金が下ります。また、自分だけでなく家族が運転しているときに事故を起こしても補償の対象です。
自動車保険の保険料を安くするためには、年齢制限を設ける方法があります。一定年齢上の保障に限定すれば、保険料が安くなります。
自動車保険で年齢制限を設けていても、ファミリーバイク特約は年齢は無制限です。子供がバイクに乗ることが多いといったときには加入するといいでしょう。
自動車保険は基本的に車両単位で契約します。よって、自分の車以外の車両を運転した場合には保険の対象外です。そこで他車運転特約に加入しておけば、他人の車を運転するときでも安心です。
もし他車運転特約に入っていない状態で他人の車で事故を起こすと、その人の保険を使わないといけません。事故を起こすと3等級ダウンしてしまうので、車の保有者の保険料が上がります。このような迷惑をかけないために、特約に加入しておくといいでしょう。
アウトドアが好きでグループでドライブすることが多く、他人の車のハンドルを握る人にはおすすめです。
自動車保険の年齢条件とは

自動車保険は必要であるものの、保険料は安くしたいと思っている人も多いでしょう。保険料を安くするテクニックはいくつかありますが、その一つが「年齢条件を限定する方法」です。
交通事故を見てみると、若い人の方がリスクが高いです。年齢が上になればなるほど事故リスクが低くなるので、一定年齢より上の人に限定すればそれだけ保険料も安くなります。
そこで年齢条件を上げることで保険料を安くできます。一定年齢より上の人しか運転しなければ年齢条件を付けるのがおすすめです。
自動車保険の3種類の年齢条件とは
運転者の年齢条件を付ける場合、おおむね以下の3種類に分類できます。
- 年齢条件を付けない
- 21歳以上
- 26歳以上
全年齢保障よりも21歳以上、21歳以上よりも26歳以上の方が保険金が安いです。ただし、この年齢の区分の方法は保険会社によって異なり、30歳以上や35歳以上といった条件を設けている自動車保険もあります。
しかし、年齢条件を設けていても例外があります。友人をはじめとした家族以外の人や、別居の未婚の子が帰省していて実家で運転しているときに事故を起こした場合などです。
原付の場合は、年齢条件は2種類だけという物が多いです。全年齢保障もしくは21歳以上となっているので注意しましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
記名被保険者の年齢で6種類に分類できる
運転者の年齢限定は3種類です。しかし26歳以上の場合、記名被保険者によってさらに細かく区分できます。それは、以下の6種類です。
- 30歳未満
- 40歳未満
- 50歳未満
- 60歳未満
- 70歳未満
- 70歳以上
対人賠償保険の場合、30歳未満と70歳以上とでは較差がおよそ1.34倍あると言われています。
このように細かく区分しているのは、事故リスクに基づいているためです。基本的に年齢が上になればなるほど、事故リスクは減少します。
ところが、年齢が60歳以上になると上昇傾向になります。高齢者ドライバーは判断力や運動能力が低下するためで、リスクを反映した保険料設定にしなければいけません。
自動車保険の年齢条件変更のタイミング
自動車保険は年齢条件を設定すると保険料を安くできます。しかし、この年齢条件は常にずっと同じにしておくわけにはいきません。
子供が成長して、自分の車を運転することもあるでしょう。親の年齢に合わせて条件設定していると、子供が事故を起こしたときに自分の保険が使えないといったこともあり得ます。そのため、定期的に年齢条件の見直しをしてください。
特に、以下で紹介するライフイベントのときには年齢条件を確認しておくべきです。
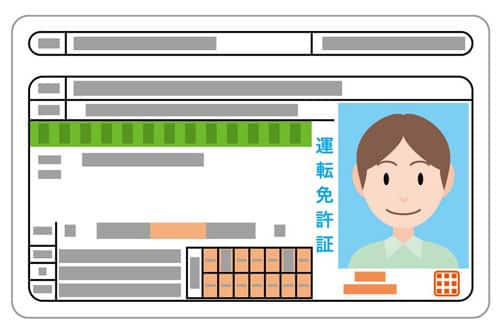
子供が成長して、運転免許を取得すれば、実家の車を運転する機会があるかもしれません。この場合、もし夫婦の年齢に合わせて自動車保険の契約をしている場合、子供の年齢に見直す必要があります。
もし子供が21歳未満であれば、年齢を問わず保障の契約内容を変更してください。変更しないと子供が運転しているときに事故を起こした場合に自動車保険の補償が受けられなくなってしまいます。
保険料は倍近く上がってしまうかもしれませんが、実際に事故を起こすと場合によっては億単位の莫大な賠償金を請求される可能性もあります。よって、年齢条件の見直しを速やかに行っておいた方がいいでしょう。
子供が独立した際には、再度自動車保険の年齢条件を見直しましょう。
それまでは、子供の年齢に合わせて条件設定していたはずです。子供が独立して家を出れば、子供の年齢を気にする必要はありません。夫婦の年齢をベースにして条件変更することで保険料が安くなり、家計の節約につながります。
例えば、子供が定期的に帰省して、実家の車を運転したとします。この時に事故を起こした場合、年齢条件よりも下でも補償は受けられます。年齢条件を変更しても、別居の子供は年齢条件に関係なく補償されるからです。
ただし、夫婦など運転者を限定している場合は対象外なので注意してください。
自動車保険の保険会社の種類

自動車保険を見てみると、いろいろな保険会社が商品をラインナップしていることがわかります。自動車保険の自由化に伴い、新規参入が増えているからです。
自動車保険の選択肢が増えたということは、より自分たちのニーズに合致する物が見つかりやすいです。安易に契約するのではなく、じっくり比較して、どれに加入するか決めましょう。
現在、多種多様な保険会社で自動車保険を取り扱っています。一昔前までであれば、自動車保険というと限定されていましたが、今保険会社が増えている理由は「自動車保険の自由化」に伴ってです。
1990年代の後半に立て続けに決められたのが、保険業法の改正や、リスク細分型保険の導入、保険料率の自由化です。同じ条件だとどの保険会社で契約しても保険料はほぼ一緒でしたが、自由化が進み同じ条件でも保険会社によって保険料が変わるようになりました。
さらに、近年では通信販売で自動車保険を取り扱う会社が増えています。ダイレクト型と言って、ネットなどで自動車保険を申し込むことも可能です。
自動車保険の自由化を受け、いろいろな会社が新規参入を果たしました。現在では自動車保険を取り扱っている保険会社はさまざまですが、大きく3種類に分類できます。
損保では自動車保険の厳しい競争が起こることを予見し、合併や統合を進めて大きな会社に統一されました。
ダイレクト型と言って、通販で取り扱うことで人件費を圧縮し、安い保険料を実現している商品が増えました。
海外に本社のある保険会社が続々と日本に進出して、自動車保険の販売を進めています。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!








