車を運転中に交通事故で、同乗者がケガをしたり残念ながら亡くなったりする場合もあるでしょう。その際、同乗者が受けた損害を補償する保険が任意の自動車保険にはあります。
それは「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」です。
この2つの保険を比較すると、保険金額、支払いのタイミング、補償内容などが異なります。同乗者の補償をより手厚くするためにはどうすればよいか、2つの保険内容を掘り下げながら説明していくので保険選びの参考にしてください。
自動車保険の補償内容

加入するかどうかを自由に決められる任意保険には、様々な補償が含まれています。
- 交通事故で相手方である被害者が死傷した場合、葬儀費用やケガの治療費、慰謝料などが補償される「対人賠償補償」
- 相手方の車や第三者の建物、塀やガードレール、電柱などの交通工作物などの物が破損した場合の補償となる「対物賠償」
- 加害者である運転者自身や車の同乗者が死傷した場合の損害を補償するのが「搭乗者傷害補償」や「人身傷害補償」
- 単独事故や当て逃げ、災害や盗難などで自身の車が受けた損害に対し補償する「車両保険」
対人賠償は基本的に賠償額が無制限、対物賠償も無制限にすることができます。他の補償に関しては、自分で付けるかどうかや賠償金額についても選ぶことができます。
任意の自動車保険には、車の同乗者が受けた損害を補償する保険がいくつかあります。
交通事故の被害車両に乗っていた同乗者に関しても、運転者同様被害者とみなされます。そのため同乗者が死傷した場合は補償されます。
基本的に加害車両に乗っていた同乗者が死傷した場合にも補償されます。車内限定という条件を付けなければ、契約車両に同乗しなくても補償されます。具体的に歩行中や契約車両以外の車、バス、タクシーなどに乗っていた場合であっても交通事故で死傷すれば補償対象となる保険です。
保険の契約車両に乗っていた同乗者が死傷した場合にのみ補償される保険になります。
それぞれの保険は補償範囲や補償額などに特徴があり、同じ同乗者を補償する保険でも内容が違います。比較して相違点を把握しておくことも大事です。
自動車保険の同乗者補償①対人補償保険

対人賠償保険は、交通事故で被害者を死傷させてしまった時に損害を補償する保険です。
補償の対象は他人となっているので、車の同乗者は血縁関係のない友人や知人の場合は賠償されます。ただし、同乗者が加害者である運転者の配偶者や子供など家族や親族の場合、対人賠償の補償対象とはならないので注意しましょう。
亡くなった場合は、葬儀費用や将来的に得られたであろう逸失利益、身体的精神的苦痛に対する慰謝料などが支払われます。
ケガをした場合に支払われるのは、入院費や治療費、ケガのために仕事ができなかったことに対する休業損害、慰謝料などです。治療費などは実費で、慰謝料は任意保険独自の支払い基準により賠償額が決まります。
自動車保険の同乗者補償②人身傷害保険

人身傷害保険は、保険の契約者やその家族が契約車に同乗中、自動車事故に遭い、死傷した場合の損害を補償する保険です。補償の範囲を広げると契約車両以外のバスやタクシーなどの車に乗車中や、歩行中の事故による損害についても補償してもらえます。
交通事故は相手がいる場合、相手と自分の双方の過失割合によって損害賠償額が決まります。もし人身傷害保険を付けずに同乗者が死傷した場合の損害分は、自分の過失分自己負担です。そのため、特に自分の過失が多い事故の場合、人身傷害保険をかけておけば全額保険で補償してもらえるので安心できます。
逆に相手の過失割合が多い事故の場合、示談が長引けば賠償金もなかなか支払ってもらえないことがあります。そんな時に人身傷害保険を付けてあれば示談が終わってなくても、賠償金が受け取れるという点がメリットです。
他にも単独事故や当て逃げのケースでも同乗者のケガの治療費やその間の収入減を補う休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料などを人身傷害保険から受け取ることができます。
人身傷害保険の補償対象は、保険の契約車両の同乗者です。同乗者が知人や友人などの他人の場合は、基本的に対人賠償から補償されます。
ただし、契約者の配偶者が子供といった家族は対人賠償では補償されない代わりに、人身傷害保険では補償対象となります。つまり、人身傷害保険は契約者とその家族を守るための保険とも言えるでしょう。
そして補償範囲は、契約車両以外の車、バスやタクシーなどに乗っていた場合や、歩行中の自動車事故による死傷の場合も補償されるタイプもあります。補償が車内限定となっていれば、契約車両の同乗者のみの補償です。

人身傷害保険では、保険金額も幅広く設定されています。
保険会社によって設定金額の上限などは異なりますが、おおよそ2億円、1億円から1000万円刻みで3000万円まで設定されています。もちろん、金額の上限を決めない無制限を選ぶことも可能です。
補償額は運転者の年齢や家族構成に応じて必要な補償額を選択できます。実際に支払われる保険金は、保険の約款に定められている損害額算定基準に沿って計算されます。治療費などは実費で支払われ、休業損害は減収分を計算式で算出していく形です。
慰謝料に関しては、事故の状況やケガの程度などによって変わってくるので一概には言えません。自賠責保険では日額が決まっており、対象日数に応じて計算式があります。
任意の自動車保険では保険会社独自の基準に基づいて計算されます。ただし、一般的には自賠責保険より慰謝料の算出額が高くなる場合がほとんどです。
また、事故によるケガが原因で後遺障害が生じてしまった場合も補償を受けることができます。損害保険料率算出機構という団体が後遺障害に関しての調査を行い、障害の程度や介護の必要性、頻度などから保険会社が等級を決めます。等級のランクに応じて補償額が決まるという仕組みです。
自動車保険の同乗者補償③搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険は、保険契約者の契約車に搭乗していた人が交通事故により死傷した場合、受けた損害を補償する保険です。運転者の事故における過失割合に関係なく、契約車両に搭乗している人全てが補償を受けられます。
自賠責保険や相手の任意保険から補償されていても、搭乗者傷害保険からも補償が受けられます。通常、保険というと治療費が実費で支払われることが多いですが、この保険の特徴はケガの部位や程度、症状によって保険金額が決まっていることにあります。
ただし、実際には治療に100万円かかっていても、決められた保険金額が60万円なら搭乗者傷害保険からは60万円までしか支払われません。
支払いのタイミングも入通院日数によって決まっています。入通院の4日以内なら、1名につき治療給付金として支払われるのは1万円です。入通院が5日以上になると、決められた保険金が支払われるという流れになっています。
搭乗者傷害保険は、補償の対象を契約車両に同乗していた全ての人としています。
人身傷害保険の場合は、運転者の配偶者や同居の親族、別居の未婚の子、それ以外で契約車両に乗車していた人となっていますが、搭乗者傷害保険は細かな取り決めはありません。
また、補償の範囲はあくまで契約車両に乗車していた場合のみとなっています。人身傷害保険と違って契約車両以外の車や歩行中の補償はされないので間違えないように気を付けましょう。

搭乗者傷害保険の場合、ケガをした体の部位やケガの程度、症状などによって支払われる保険金が予め決まっています。例えば以下のような形です。
打撲や捻挫などは5万円、骨折や脱臼などは35万円、欠損や切断は15万円
打撲や捻挫などは5万円、骨折や脱臼では30万円
打撲や捻挫などは5万円、骨折や脱臼は35万円、切断や欠損は60万円
打撲や捻挫などは5万円、骨折や脱臼は20万円、切断や欠損は25万円
保険会社によって保険金は異なるので一概には言えませんが、これらは一般的な金額なので参考にしておきましょう。

搭乗者傷害保険や人身傷害保険に加入していても、運転者の重大な法律違反や事故の形態によっては保険金が支払われない場合もあります。運転者の故意または重大な過失によって生じた損害がそれにあたります。
例えば以下のような状態での交通事故です。
- 酒気帯運転
- 酒に酔った状態での運転
- 無免許運転
- 麻薬などの薬物を摂取した状態での運転
また、契約車両の使用時に正当な権利を有する人の承諾を得ないで搭乗中に生じた損害についても、補償対象外となります。許可されていないのに車に同乗していた、盗んだ車に同乗していた交通事故により死傷した場合などが当てはまるでしょう。
他にも地震や噴火、津波などの天災により生じた損害に関しても補償はされません。また、定員オーバーでの乗車や軽トラなどの荷台への乗車など、道路交通法に違反した乗車方法での事故による損害、サンルーフや窓から身を乗り出しての乗車中、車両から降りた後の事故による損害も補償対象外です。
基本的に、正しい乗車方法で座席に座っていた状態での交通事故による、身体への損害に関しては補償されます。それは、シートベルトの着用や子供ならチャイルドシートへの着席も含まれます。天災でも台風や洪水、高潮などは補償対象です。
搭乗者傷害保険や人身傷害保険に入っていても、保険会社の判断によっては保険金が支払われないケースもあるので知っておきましょう。
まずは車の乗り降りの際、ドアを開け閉めした際のケガやワンボックスカーなど特に車内が広い車での、車内の通路を歩行中のケガなどが当てはまります。
また、停車して車から降りる際に地面に足を付けた時の打撲や捻挫などのケガや、荷台と座席を隔てる壁がないようなワンボックスカーで荷台に乗っていた時のケガなども含まれます。
車に乗車しており、乗車方法などが道路交通法の法律に違反していなくても、あらゆる状況で事故は起こるものです。場合によっては同乗者への補償がされないこともあります。
また保険会社によって解釈が異なるので、自身が契約している保険会社では補償対象外でも、別の保険会社では補償対象となる可能性もあります。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い

人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、車の同乗者が被った損害に対して補償される点では同じように見えますが、異なる点も多いので相違点を比較してみましょう。
契約車両以外のバスなどに乗車中、もしくは歩行中というように車外まで広げることができるのが人身傷害補償です。搭乗者傷害保険は契約車両の同乗者のみに限定されています。
人身傷害保険は総損害額であるのに対し、搭乗者傷害保険はケガの部位や程度や症状に応じて補償額が決められています。
人身傷害保険は総損害額が決まってから支払われますが、搭乗者傷害保険は医師の判断でケガに対する治療や入院がスタートして、5日目から支払いが実行されます。
2つの保険は細かい点を比較すると結構違いがあるので、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
補償してもらえる事故
人身傷害保険も搭乗者傷害保険も、双方の過失の割合に関係なく補償される点では共通しています。ただし、この2つの保険は補償の範囲が異なるので注意が必要です。
契約車両の同乗者以外にも、契約車両以外の車、例えばバスやタクシーなどに乗車している時や、歩行中の自動車事故であっても死傷した際は補償されます。ただし、保険を車内限定と設定している場合は、契約車両同乗中に限定されるので注意しましょう。
契約車両に同乗中の自動車事故による、同乗者の死傷時の補償に限定されています。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
補償の対象者

補償対象は主に記名保険者である運転者や運転者の配偶者、運転者と配偶者の同居の親族です。また、別居であっても未婚の子も含まれます。こういった家族や親族に該当する方は、いわゆる車外も含むというタイプに加入していれば、契約車両に同乗していなくても補償対象です。
ただし、他人の場合は車内のみが適用となり、契約車両に同乗していることが補償の条件になっています。歩行中や契約車両以外の車に同乗中は、補償されないので間違えないようにしましょう。
運転者を含み、契約車両に同乗してした人という補償範囲になっており、家族や親族の区別も特にありません。
保険金支払いの時期

人身傷害保険と搭乗者傷害保険では保険金の支払い時期も異なります。
人身傷害保険は、交通事故の相手方と示談交渉が終わっていなくても総損害額が支払われます。示談前なので示談後の認定額とは金額が違う場合もあるでしょう。ただし、加入時に設定した上限金額までしか支払われません。
一方で搭乗者傷害保険は、医師の診断に基づく入院や通院にかかった合計の日数が5日以上経過した時点で、決められた金額の損害額が支払われます。これには事故発生から180日以内であるという条件が付きます。
人身傷害保険は示談前に損害額が支払われると言っても、総損害額が決定するまでに数日間の期間を要するのが一般的です。しかし搭乗者傷害保険では、入院や通院を開始してから5日で損害額が支払われるので、すぐに治療費が必要な人にとってはメリットが大きいと言えます。
支払われる保険金の内容

人身傷害保険と搭乗者傷害保険では、支払われる保険金の内容に違いがみられるので比較してみましょう。
ケガの治療や入院などにかかった費用が実費で支払われます。また、ケガの治療のために休職していた際の休業損害や肉体的精神的苦痛に伴う慰謝料も決められた計算式によって算出されて支払われます。示談交渉により治療費などこれらの総損害額が決まります。
予めケガの部位や程度、症状によって支払われる金額が決められています。例えば、頸部の骨折や脱臼は60万円、頭部の神経や筋などは110万円といった形です。複数の部位にケガを負い、症状が出た場合は一番金額が高い症状や部位の金額が支払われることになります。
また、保険会社によってはケガの部位や症状ごとに金額が変わるのではなく、定額の保険金を支払うところもあります。まず入通院の開始日から4日目に1万円の一時金を支払い、そして5日目以降で一律10万円を支払うという形をとっているところもあります。契約中の保険会社が定額なのか、ケガごとに保険金が異なるのかも確認しておきましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は両方つけるべきか?
自動車事故における車の同乗者が受けた損害を補償する保険として、人身傷害保険と搭乗者保険は補償範囲が重複する部分があります。
ただし、人身傷害保険は契約車両に同乗中という車内補償と、歩行中や契約車両以外の車両に同乗中という車外補償に分けられます。一方で搭乗者傷害保険は契約車両に同乗中のみ、車内補償しかありません。
両方の保険を付けると、契約車両の同乗者に対する補償が重複するので最低限の補償をカバーすることを考えるなら、車内と車外両方を網羅した人身傷害保険にするのもよいでしょう。
ただし、保険料との兼ね合いで契約車両の同乗者に絞るなら、保険金が比較的早く支払ってもらえ、保険料を抑えられる搭乗者傷害保険を付けておくという選択肢もあります。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険を2つとも付けようと思うと、重複する部分があったり、保険料が高くなったりする可能性があります。しかし「限定特約」という形で、特約を活用することで補償の重複や保険料の増額を避けることも可能です。
例えば、同居の家族などが人身傷害保険に加入して入れば、車外補償はカバーされているので安心です。しかし、自身の保険で加入すると補償が重複してしまいます。
この場合は、人身傷害を同乗中のみの補償特約にするのがおすすめです。この特約を付帯させると、契約車両に同乗中のみに補償を限定することができます。補償の範囲を狭くする分、保険料を安く抑えることができます。
自身の加入する保険と家族が加入している保険で、同乗者補償の範囲がどうなっているかを見直してみれば、保険料節約にもつながるでしょう。
また人身傷害補償を軸にして、搭乗者傷害補償を特約として付けるのもおすすめです。人身傷害補償は総損害額が決まらないと保険金が支払われないので、実際に賠償金を受け取るのに時間を要します。一方で搭乗者傷害補償はスピーディーに保険金が受け取れるので、金銭的な負担が軽減されます。人身傷害保険の上乗せ補償という形で特約を付けておくと便利です。
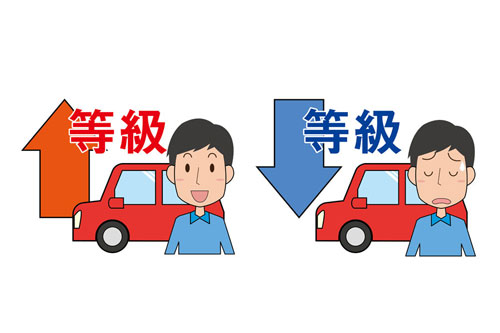
通常任意の自動車保険は、交通事故により保険を使い補償を受けることで翌年から等級が下がり、保険料が高くなります。
人身傷害補償や搭乗者傷害保険のみを使った場合は、基本的に等級は下がりません。しかし、車や物が壊れた場合の補償である車両保険や対物補償を一緒に使うと、一般的に等級が下がってしまいます。交通事故の形態は「3等級ダウン事故」「1等級ダウン事故」「ノーカウント事故」に分けられます。
他人をケガさせて対人賠償が適用された、他人の物や車の破損に対し対物賠償が適用された、単独物損などで車両保険を使った場合などが当てはまります
盗難や台風、大雨などの災害、落書きなどのいたずらなどで車両保険が使われた場合です。
人身傷害保険や搭乗者傷害保険のみ、弁護士費用特約のみ、自転車補償特約のみなどが使われた場合はノーカウント事故に当てはまります。保険を使っても事故としてカウントされないので、等級に影響はありません。

自分の車に家族や友人などを乗せていて、交通事故を起こしてしまい同乗者を死傷させてしまうと、運転者である自分に賠償責任が生じます。その際に同乗者を補償する保険に入っていなければ、双方の過失割合によってはかなりの賠償金を自己負担しなければならなくなるでしょう。
同乗者が数人いれば一人につきいくらというように、賠償金も増えます。運転者自身の万一の場合の備えという意味でも、自動車保険の同乗者に対する補償は充実させておくのがベストだと言えます。
同乗者を補償する保険は「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」があり、2つの保険は重複する部分もあるので、特約を活用してできる限り重複して保険料を損することがないように工夫して加入してください。
また、補償範囲を広くしておくことで、交通事故に巻き込まれた場合でもきちんと補償されるので安心できます。特に人身傷害保険は同乗者の死亡時の賠償が手厚いので、一家の収入を担う人などが加入しておくことを検討してもよいかもしれません。








