一家で2台目の車を所有する際、保険料が安くなる「セカンドカー割引」が受けられることがあります。
ただし、セカンドカー割引を利用するには条件がいくつかあるので、まずは条件の内容について知ることが大事です。さらに、セカンドカー割引を利用することでどのくらい保険料が安くなるのか、利用の際に注意する点などもあるのできちんと把握しておくことをおすすめします。
そして、セカンドカー割引以外にも自動車保険にはお得な割引があるので紹介していきます。
セカンドカーが必要になる時
一家に1台車を所有している状態で、もう1台購入した車はセカンドカーと呼ばれます。セカンドカーは主に以下のような状況の時に必要になるでしょう。
- 夫婦がそれぞれ車通勤するようになった場合
- 子供が産まれて買い物や通院などで車がもう1台あった方が便利だという場合
- 子供が成長して運転免許を取得し、通勤や通学で車を使うようになった場合
- 電車やバスなど公共の交通機関が発達しており、交通の便が良い都会から車以外の交通手段が乏しい地方へ引っ越しした場合
ほとんどの人がこのセカンドカーにも自動車保険をかけます。2台分の自動車保険となると保険料もかさんでしまうので、少しでお得な方法を知り、取り入れたいという人も多いかもしれません。

任意の自動車保険では、2台目以降の車で保険に加入する際はセカンドカー割引が適用されてる場合があります。
2台目だけではなく、3台目4台目と車を購入してもセカンドカー割引は適用されます。保険料の割引は、基本的に自動車保険の等級が優遇される形で保険料に反映されています。
セカンドカー割引を適用させると、通常の保険契約よりもワンランク高い等級で2台目の保険契約をスタートすることが可能です。例え1等級であっても保険料が違ってくるのでセカンドカー割引を使えばお得になります。
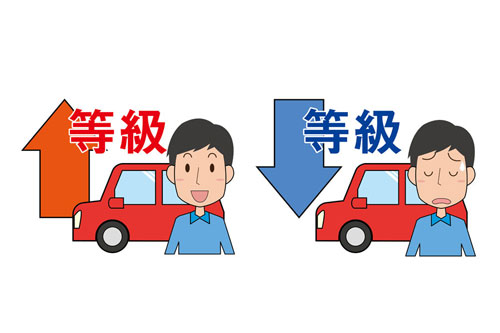
自動車保険でよく使われる等級について知っておくと、保険を利用する上で色々と役立ちます。
契約者が所有もしくは使用する車の総台数が9台以下の契約は、「ノンフリート契約」と言います。そのため、等級というと一般的には「ノンフリート等級別料率制度」と呼ばれているので覚えておきましょう。
ちなみに、車の総台数が10台以上の契約は「フリート契約」と言います。等級は契約者の事故実績に応じて、基本的に1~20等級まで分類されています。
一般的に新規で自動車保険に加入する場合、6等級からのスタートです。無事故もしくは交通事故を起こしても保険を使わなければ、翌年等級が1つ上がって保険料の割引率も高くなり、金額もやや安くなります。
また、事故の形態が保険を使っても等級が変わらない「ノーカウント事故」の場合は等級に変動はないため、翌年等級が1つ上がります。逆に交通事故で保険を使うと、翌年事故の等級が下がるというシステムです。
2台目の車の自動車保険でセカンドカー割引を適用させるには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
条件に該当しない場合は、2台目の車で自動車保険に加入してもセカンドカー割引は適用できないことになっています。そのため、通常の自動車保険の新規加入時と同様に同じように6等級からのスタートです。
セカンドカー割引の条件を全てクリアしていれば、2台目は一つ等級が上がり新規の契約で7等級からスタートすることができます!
6等級と7等級は1等級しか違わないですが、1台目の車が1年間無事故もしくは保険を使わないことが等級を1つ挙げる条件です。たった1等級であっても保険料に差が生じるので、条件をクリアしている場合は利用した方がお得でしょう。
セカンドカー割引適用には条件がある

セカンドカー割引が利用できる条件は大きく分けて7つもあります。
細かく条件が提示されているので、一つずつ該当しているか確認しておくことが大事です。
まず、1台目に所有している車の車種や用途、契約者や等級に関する条件が挙げられます。さらに、契約該当車両となる2台目に関しても車の車種や用途、契約者などの条件があります。
詳しい内容を見ていきましょう。
セカンドカー割引適用の条件として、1台目の車の等級もポイントとなります。
2台目の車が自動車保険に加入する時、1台目の車の等級が11等級以上であるというのが必須条件です。ギリギリ11等級であれば問題ありませんが、10等級なら残念ながらセカンドカー割引は使えなくなってしまいます。
1台目は自動車保険の新規加入時、6等級からスタートしているので、順調にいけば5年間無事故で自動車保険の契約を継続していれば11等級に到達しているはずです。ただし、5年以上保険契約を続けていても、事故で保険を使い等級が下がっていると11等級まで達していない場合もあります。
1台目の自動車保険で現時点の等級はいくつなのかも確認しておかなければなりません。

1台目の車が自家用8種であることもセカンドカー割引の適用条件となります。自家用8車種とは、以下の8つの車種のことです。
- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪自動車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 特殊用途自動車
一般使用の車ならまず問題はないでしょう。念のため車検証で自動車の種別を確認しておくことをおすすめします。
1台目の車の所有者が個人名義というのも条件に当たります。車の名義に関しては車検証に記載されているので確認しましょう。
所有者はローンを完済するまでローン会社やディーラーなどになっている場合が多いです。しかし、便宜上本人以外の名義になっているだけなので、使用者が個人名義なら問題ありません。
所有者がリース会社の名義になっています。車のリースというのは、希望する車をリース会社が本人に代わって購入し、リース契約を結んで一定額のリース代金を支払い車を使用するというサービスです。
車の所有権はリース会社にあり、リース期間が終わったら車を返却するか、リースを継続するかを選ぶことができます。
リースの場合もローンを組んでいる場合と同様、使用者が個人名義であればセカンドカー割引を利用できます。
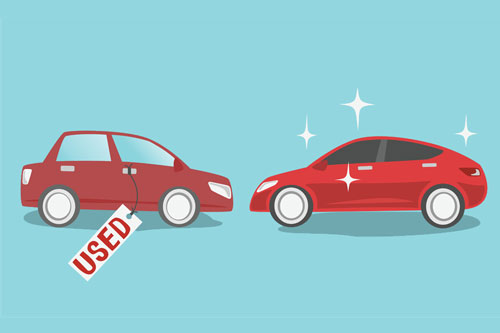
2台目の車、つまりセカンドカー割引の対象となる車の自動車保険加入が、全くの新規契約であることも条件となります。
新たに新車を購入した場合はこれまで自動車保険への加入歴はないはずなので問題ありません。ただし、知人や友人などに車を譲ってもらった場合は既に自動車保険に加入、継続している可能性が高いでしょう。加入していれば一旦解約手続きをしてもらい、新たに加入し直せば新規契約となります。
また、中古車を購入する場合も同様ですが、中古車販売店を通す場合は前の所有者の自動車保険の解約手続きをやってくれるはずです。ネットなどの個人売買の場合は、自動車保険についての確認を忘れないようにしてください。
2台目の車も1台目と同様に、自家用8車種であるのも条件となります。
一般に出回っている車はほとんどこの自家用8車種のどれかに当てはまるので、まず条件はクリアされているはずです。
車検証の自動車の種別という項目を確認すれば、どの車種に該当するか分かるので念のため見ておきましょう。

2台目の車も1台目と同様に車の所有者が個人でなければなりません。会社の車など法人名義の車は該当しないので注意しましょう。
さらに、車の所有者が1台目の記名被保険者と同じもしくは、1台目の記名被保険者の配偶者であることが条件となります。もしくは、1台目の記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族または、1台目の車の所有者と同じであるのどれかの該当していなければなりません。
例えば、妻が免許を取得し、家庭では2台目となる車を購入し、自動車保険に加入することになったとします。1台目の車を夫が所有しているとすれば、1台目の所有者の配偶者にあたるのでこの条件はクリアしていることになります。
もし1台目の車の購入時にローンを組んでいれば、所有者はローン完済まではディーラーやローン会社です。しかし実質上、車を使っている人つまり使用者が個人であれば問題ありません。
この条件は保険会社によって異なる場合もあるので確認してみましょう。
2台目の車は記名被保険者、主として車を運転する人に関する条件があります。
「2台目の記名被保険者が1台目の記名被保険者と同じ」もしくは「1台目の記名保険者の配偶者または、それぞれの同居の親族」でなければなりません。
つまり、セカンドカー割引は知人や友人など血縁関係のない他人では適用されないことになります。親族で、同居していることが必須条件です。親族でも別居していればセカンドカー割引の対象とならないので気を付けましょう。
よくあるのが子供が運転免許を取得して車を購入し、新規で自動車保険に加入するというケースです。1台目の車の記名被保険者は父親もしくは母親、同居の叔母などの場合は同居の親族に当たるので問題ありません。
2台目の車の記名被保険者に関しての条件は保険会社によって違う場合もあります。詳しく1台目の車が加入している保険会社などに問い合わせた方が良いでしょう。
セカンドカー割引の割引率

セカンドカー割引は保険料の割引率が高いので利用すればお得です。
自動車保険は、運転者の年齢によって起こりうる交通事故のリスクも違います。同じ等級でも年齢によって保険料の割増引率も大きく変わってきます。
自動車保険の等級ごとの割引率の目安は、損害保険料利率機構という団体により提示されているので、見てみましょう。
6等級で28%割増、7等級だと11%割増です。
6等級では3%割増、7等級では11%割引になります。
6等級で9%割引、7等級では40%割引です。
6等級で4%割増、7等級では39%割引となっています。
7等級なら全年齢補償以外は全て保険料は割引となります。
例えば、8万円の保険料だと26歳以上補償では6等級が7万2800円、7等級では4万8000円と「2万4800円」もの差が生じます。
1年分だけでも大きな差額が生じることが分かるので、セカンドカー割引を使った方がかなりお得だと言えるでしょう。
等級を引き継ぐと保険料が安くなる

セカンドカー割引を活用する以外にも、等級の引き継ぎを行うと保険料が抑えられます。
2台目の車を購入し、自動車保険に加入する際に1台目の自動車保険の等級を引き継ぎます。つまり、1台目と2台目の自動車保険の等級を入れ替えるということです。
例えば、子供が運転免許を取得して車を購入し、自動車保険に加入するとします。子供は年齢が若いので運転技術の未熟さなどから交通事故の発生リスクが高いため、通常は保険料が高く設定されています。親が無事故で20等級だとしたら、子供が新規契約で7等級になるので、等級を入れ替えることで全体的な保険料を安く抑えることが可能です。
等級を引き継げるには条件があります。まず、等級の譲渡を受ける人が配偶者か同居の親族に限られています。ただ、子供が進学などで遠方で一人暮らしする予定なら、別居する前に手続きを終えれば入れ替えは可能です。
場合によっては等級の引き継ぎができないこともあるので確認しておきましょう。
等級の引き続きは、親族間で車を購入して台数が増える、もしくは廃車にして減る場合にのみ適用される制度です。新規の自動車保険への加入ではなく、既に2台とも加入した状態で途中で等級を入れ替えることはできません。つまり、単に車両を入れ替えて等級を交換することはできないということです。
また、自動車保険によっては等級の引き継ぎができない種類もあります。それは「教職員共済」や「自治同労共済」が当てはまります。
一方、「農協共済」「全労済」「全共済」「日火連」などは共済であっても、条件を満たせば等級の引き継ぎが可能です!
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
補償が被らないように見直しを!ファミリーバイク特約

家族間で2台以上車を所有する場合、自動車保険の補償が重複していることも考えられるので確認してみましょう。
まず、ファミリーバイク特約で考えてみます。
交通事故で相手方と損害賠償請求に関して示談や訴訟を起こす場合、弁護士に依頼した際の費用を負担してくれる「弁護士費用特約」も同様に、補償対象が運転者の配偶者や同居の親族です。
2台目の自動車保険加入時に、ファミリーバイク特約や弁護士費用特約を付帯させたとします。しかし、既に1台目で特約を付帯させていたら、2台目の自動車保険で特約をつけると補償が被る可能性があります。補償は同じだけしか受けられないのに、2台で被った分の保険料を無駄に支払っている、ということです。
提示した特約以外にも、色々な種類の特約があって必要に応じて付帯されているかもしれません。一度自分の自動車保険の特約とその内容、補償対象を見直しておきましょう。
補償が被らないように見直しを!人身傷害保険
死亡した際は葬儀代や慰謝料、ケガをした際は治療費や休業損害などが保険金として支払われます。
運転者と運転者の配偶者や、同居の親族や別居の未婚の子と家族や親族までが、補償対象です。そのため、1台目の車の自動車保険で人身傷害保険をつけていると、同居の親族まで補償対象となります。
例えば、1台目の契約者の子供が車を所有し、新規で自動車保険に加入するとします。1台目の自動車保険で人身傷害保険をつけていれば、子供が加入する自動車保険でつけなくても済むというわけです。
補償が被らないように見直しを!個人賠償特約

例えば、飼い犬が人に噛みついてケガを負わす、マンションの水漏れで階下の部屋が水びだしになるといったケースが当てはまります。
他にも、子供同士で遊んでいて我が子が持っていたおもちゃが他の子に当たり、ケガをさせる、買い物途中でお店の商品を誤って壊すといった日常生活における様々なトラブルも含まれます。
個人賠償特約も、補償範囲が運転者だけではなく、その配偶者、運転者や配偶者と同居の親族、別居で未婚の子です。特に幼いお子さんのいる、ペットを飼っている家ではいざという時に役立つ特約だと言えるでしょう。
例えば、一人暮らしの子供が新しく車を購入して自動車保険に加入するとします。その際、2台目の車の自動車保険に個人賠償特約を付帯させなくても、親が加入している自動車保険で付帯させてあれば補償がカバーされるということになります。
基本的に1台目と2台目の自動車保険の保険会社が別であっても、セカンドカー割引は適用されます。
しかし、2台目の自動車保険を新規契約する際に1台目と同じ保険会社を選ぶことでお得に契約できるキャンペーンも行われているので、チェックしてみてください。
1台目と同じにすると、2台目の契約時の保険料が割引になる保険会社があります。さらに、継続的複数割引というものがあり、翌年以降も継続して同じ保険会社で契約し続けると、2年目以降も保険料の割引が続くというサービスです。
1台目と同じ保険会社にすることで、ギフトカードをプレゼントするという特典をつけている保険会社もあります。しかも年間保険料の額が多いと、受け取れるギフトカードの額も増えます。
1台目の保険会社の補償内容などに満足しているなら、2台目の同じ保険会社で契約した方が保険料が安くなるかもしれません。
保険会社はたくさんありますが、ネットなどで1台目と2台目を同じ保険会社にしたらどのような特典がつくか、または割引が受けられるかを調べてみましょう。

一家で2台目の車を購入する際、セカンドカー割引の条件を満たしていても保険会社からは特にお知らせや勧誘などはありません。
自分で調べて保険会社に連絡し、セカンドカー割引ができる旨を申し出なければ割引を受けることができないので、申し出ないままにすると損です!
その上、セカンドカー割引について申し出ないまま2台目の自動車保険を新規契約し、保険期間がスタートするとセカンドカー割引は適用されないので手遅れとなります。
特にネットで申し込みから契約までの手続きができるネット型保険だと、対面式ではないので自分で気づかないとそのまま保険期間が始まってしまうので、注意が必要です。
セカンドカー割引を受けるためには、2台目の車検証と11等級以上である1台目の車両の保険証券が必要となります。2台目の車が納車されるまで手元に車検証がない場合は、売買契約書や見積もりなど車両情報が分かる書類があれば代用できます。

セカンドカー割引を適用させるための条件は多く、1つでも条件を満たしていないと割引を受けることはできません。
車種や所有者に関しての条件はほぼ満たすことができるでしょう。しかし、一番ポイントとなるのが等級です。
長年車を使用し、自動車保険に加入期間が長くても交通事故を起こして保険を数回使っていると、等級が一旦下がり、1年をかけて1等級上がるのでなかなか11等級に達しない可能性があります。
また、無事故でも1台目を購入し、自動車保険に加入してから5年以上は経過しないと11等級にはなりません。等級が11等級に満たないとなると、セカンドカー割引を適用することは不可能です。
しかし、そんな場合であっても、1台目の等級が7等級以上ならそのまま2台目の新規保険契約時に、1台目の等級を引き継がせることで多少は保険料を抑えることができます。また、保険会社によっては様々な割引サービスがあります。
例えば、ネットからの申し込みで割引になる「ネット割引」、保険開始の月が新車登録から一定期間内なら割引になる「新車割引」、自動ブレーキ装着車なら割引となる「ASV割引」などです。各保険会社でどのような割引があるかをチェックしてみましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!








