自動車保険は、運転者の「年齢」「車種」「年間走行距離」「車の使用目的」などの様々な要素で保険料を設定しています。そのため、年齢が一緒でも車種や年間走行距離などが異なれば、契約者ごとに保険料が違ってきます。
保険料は継続して毎年支払うので、できれば安くしたいという方が多いでしょう。保険料を安くするポイントを押さえ、保険内容を見直し、契約内容を変更していくことが大事です。
それでは、保険料節約のコツを紹介していくので、ぜひ自分の自動車保険を見直すきっかけにしてください。
任意の自動車保険は保険料が異なる

自動車保険は、様々な条件や要素に基づき保険料を決定しています。そのため、個々や保険会社によって保険料が大きく違ってくることがあります。
どのような条件や要素があるのか見ていきましょう。
運転者の年齢が若いと、運転経験が浅いので運転技術がまだ未熟であると判断され、保険料が高く設定されています。逆に年齢が上がると安くなります。補償は主に4つあります。
- 21歳以上補償
- 26歳以上補償
- 36歳以上補償
- 全年齢補償
保険会社によって年齢区分は多少異なり、30歳以上補償などもあります。
運転者が契約者本人のみと限定されると、その分交通事故リスクも減るので、保険料が安くなります。一方で運転者と配偶者のみの配偶者限定にするとやや高く、子供や祖父母など家族が運転する機会があれば、家族限定にすると一番高くなります。
車の大きさや性能などによって保険料も大きく変わってきます。車の型式ごとの事故実績などにより、型式別利率クラスという保険料決定基準が設けられています。この基準に基づき、交通事故発生のリスクが高い「スポーツカー」や盗難に遭いやすい「高級車」などは保険料が高くなるのが一般的です。
運転免許証の色や等級などは、交通事故歴や違反歴などが反映されたものであり、こういった運転歴も保険料に影響してきます。無事故などで保険を使わないと等級が上がり、保険料の割引率も高くなります。
車の使用頻度が高いとその分交通事故の発生リスクも高くなるので、保険料も上がります。使用目的は業務使用が一番保険料が高く、次いで通勤・通学目的、一番安いのが日常・レジャー目的です。
年間走行距離が長いと車を使用する時間も長く、頻度も高いので交通事故発生リスクが高まるため保険料が高くなります。逆に距離を短く設定すると保険料も抑えられます。
車の保険料を安くするには?

車を使用し続ける限り、いつ交通事故に遭遇するかわかりません。そのため車を所有し、使用し続ける限りは万一の備え、自動車保険も契約し続けなければならないでしょう。
長年保険料を支払い続けるなら、少しでも保険料を抑えたいと誰しもが考えるはずです。自動車保険の様々な条件や要素により保険料が違ってきます。
保険料を少しでも安くするには、条件や補償の一つ一つをもう一度見直してみることが大事です。また、契約当初はその条件で良かったけれど、年月が経つにつれて不要となる補償が出てくるかもしれません。
ライフスタイルが変化したり、家族構成が変わったりして不要になったものを変更することで、お得になる条件や補償もあるかもしれません。
車の保険料を安くする方法①契約方法
自動車保険には契約方法の違いにより、「代理店型保険」と「ネット通販型保険」に分けられます。
保険の代理店に出向いて、スタッフと対面式で保険内容の説明を受け、契約するという方法です。どの保険、補償を選べば良いか相談できるので心強い、手続きがスムーズに行いやすいというメリットがあります。
ネットや電話で申し込みができて、郵送などで契約手続きができるというものです。自分で調べて保険会社を選ばなければなりませんが、いつでも手軽に手続きできるというのが魅力です。
保険料だけをみると、代理店型保険は人件費や店舗代がかかるのでその分が保険料に上乗せされ、やや高くなります。それに対して、ネット通販型保険はネットで手続きできる分、手数料がかからないというメリットがあります。
保険料を安くするならネット通販型保険を選んだ方が良いでしょう!
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
車の保険料を安くする方法②運転者の限定

自動車保険では、契約の際に契約車両の運転者の範囲を限定できます。
運転者本人に限定することで交通事故発生リスクも下がるので、保険料が安くできます。ほとんど契約者しか運転しない場合は本人限定にしましょう。その際、家族で出かける時も本人以外の人が運転しないように注意が必要です。
もし配偶者がどうしても運転する機会があるなら、1日だけの自動車保険に加入するなどして対応すれば、本人限定でも問題ありません。
ただし、子供が車の免許を取得して親の車を共有する場合は、万一に備えて家族限定にしておいた方が安心です。
車の保険料を安くする方法③車両保険のタイプ
自動車保険における車両保険を最小限の補償に留めることで、保険料を抑えることもできます。
そもそも車両保険は、付帯させるかどうかを自由に選ぶことができます。例えば登録からかなり年数が経過した車だと、多少こすった傷などは修理しないで買い替えを待つ、という選択肢もあります。
また、大破した場合は買い替えを視野に入れようと考える人もいるかもしれません。こういった場合は車両保険は不要なので付けなくても良いでしょう!
ただ、まだ新車だと事故の際は修理してでも乗りたいという人もいるので、その場合は付けておいた方が無難です。
車両保険は補償の範囲によって保険料が違ってきます。交通事故による損害だけを補償する限定タイプの他、盗難や台風、地震などの自然災害による補償までカバーするワイドタイプがあります。
さらに細かく分けると、交通事故でも当て逃げと単独事故を除くタイプなど、保険会社によって補償内容も様々です。
車両保険をつけないのが一番節約できますが、必要最小限の補償内容を吟味し、選択することで保険料が抑えられるでしょう。
車の保険料を安くする方法④車両保険の免責金額

車両保険の補償範囲に加え、免責金額も保険料を抑えるポイントとなります。
例えば、補償対象の事故で30万円の修理代がかかるとして、免責金額が5万円で設定していた場合は25万円は保険金が下り、5万円は自己負担するということになります。
この免責金額を高くすることで、保険料を抑えることが可能です。
ある保険会社の例を見てみましょう。
保険料は一番高くなります。
1回目の事故は免責5万円、2回目の事故は免責10万円となります。
1回目2回目の事故で共に免責10万円となります。
保険料が一番安くなりますが、1回目2回目の事故の免責金額は共に15万円となっています。
免責金額が多いと逆に事故の際の負担額が増えるので、ゼロにはせずに少額で設定しておくのがおすすめです。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
車の保険料を安くする方法⑤同乗者の補償を最小限に抑える
自動車保険には車の同乗者の損害を補償する保険は主に2つあります。それが「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」です。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、保険金の支払いタイミングや支払い金額の仕組みが違います。
事故で同乗者がケガをした場合、治療などにかかった費用が実費で補償されるのが人身傷害保険です。さらに、総損害額が確定すれば示談前でも保険金が下ります。
一方ケガの部位や症状によって保険金額が決まっているのが搭乗者傷害保険です。医師の診断に基づく入院もしくは通院の合計日数が5日以上を経過したタイミングで保険金が支払われます。
ある程度の貯えがあり、すぐには治療費などの支払いに困らないのであれば、実費補償してもらえる人身傷害保険につけておけば安心です。一方、できる限り早く保険金を治療費に充てたいと考えるなら搭乗者傷害保険をつけるという選択肢もあります。
いずれにせよ、人身傷害保険と搭乗者保険両方をつけると補償が重複するので保険料の負担が増えることになるでしょう。
補償内容をよく調べて、必要な補償を把握して保険を選ぶことが保険料節約につながります。
車の保険料を安くする方法⑥使用目的にも注目

車の使用目的によっても保険料が変わるので着目しましょう。
使用目的が通勤・通学目的なら保険料はやや高くなります。一方で、日常・レジャーになれば保険料はやや下がります。
もし、年間の月平均が15日以上通勤、通学に使用している場合は通勤・通学目的に該当します。
もし、普段は電車通勤で雨や雪など天候が悪い時だけ車通勤にしている場合などは、頻度が低いので日常・レジャー目的の範囲となります。
また、以前は車通勤に使っていたが電車通勤に変わった、退職して通勤していないなど、ライフスタイルの変化により変更があった場合は、保険会社に申し出て使用目的を変更してもらってください。保険料が下がるかもしれないので、一度見直してみることをおすすめします!
車の保険料を安くする方法⑦割引制度を利用
保険会社によって様々な割引制度がありますが、まずは長期優良割引を見てみましょう。
等級に関しても、通常は20等級が最大の等級ですが、22等級まで設けている保険会社もあります。等級が上がると、その分割引率が大きくなるので保険料が抑えられます。
万一事故で保険を使っても、等級の下がり方が緩やかなので保険料も高くなりにくいという点がメリットです。
さらに、他にも以下のような割引があります。
- ネットで保険契約の手続きを行うと保険料が安くなる「インターネット割引」
- 設定した年間走行距離よりも少ない走行距離で済んだ年は、翌年の保険料から走らなかった分の保険料を割り引ける「くりこし割引」
- 保険の開始月が新車登録から49ヶ月以内なら保険料が割り引かれる「新車割引」
- 自動ブレーキなどの安全装置が装備された車なら割引される「自動ブレーキ割引」 など
車の保険料を安くする方法⑧不要な特約を解除する

自動車保険には、基本の補償にプラスする形で特約を付帯させることができます。付帯させるかどうかは契約者が自由に決めることも可能です。
あくまで補償を手厚くするというオプション的な意味合いのある特約にはいくつか種類があります。例えば以下の4つがあります。
- 交通事故の賠償金の示談や訴訟などで弁護士に相談し、動いてもらう際の費用を負担してもらえる「弁護士費用特約」
- 原付を運転中に事故を起こした際に損害を補償してもらえる「ファミリーバイク特約」
- 自動車保険は基本的に1年契約ですが、更新手続きを忘れても自動で更新してくれる「自動更新特約」
- 日常生活で他人を死傷させたり、他人の財物を破損したりした場合の補償をカバーする「個人賠償特約」
どの特約も付帯させていれば万一の際は安心ですが、あまりにたくさん付帯させるとその分保険料がかかります。そのため、特約を見直して生活に必要かどうかを考えて不要なものを外すことで保険料が下がるでしょう。
車の保険料を安くする方法⑨保険料の支払いを年払いにする
保険料の支払い方法や支払い回数によっても、保険料に差が出ます。
自動車保険は基本的に1年契約が多く、前払いで年に1回全額を支払う年払いという方法があります。一方、1年分を12ヶ月で分割し、毎月支払う月払いも可能です。
しかし、月払いにすると年払いよりも保険料の総額が高くなります!そのため、始めにまとまった資金が必要ですが、年払いにした方が保険料が抑えられるうえに1年に1回の支払いで済むのでおすすめです。
また、保険料の支払い方法も「口座振替」「クレジットカード払い」「コンビニ払い」「振り込み」などいくつかあります。
振り込みなどの支払い手段を選ぶと、手数料を契約者が負担しなければならないかもしれません。そうなると保険料を支払うだけで、手数料分損をすることにもなります。
一方でクレジットカード払いにするとポイント還元があり、買い物などに使えるといった利点もあります。
支払い手段に関しても今一度見直して、お得な方法に切り替えましょう。
保険会社を比較してみる

自動車保険は保険会社の数が多く、各保険会社によって補償内容も割引サービスも、そして保険料も違ってきます。少しでも安い保険料で手厚い補償を受けるため、保険会社の補償内容などを詳しく調べることをおすすめします。
その際、いまの自分のライフスタイルにマッチした保険会社を選びましょう。ネットで保険料が安い保険会社をピックアップし、補償内容なども比較してみてください。
そして、利用できる限り割引制度も活用して、より安くて万一の際も安心できるように、保険の補償内容も精査する必要があります。加入したままにしないで、時折保険内容を見直すことも大事です!
車を2台以上所有した場合はセカンドカー割引を使う

一家に1台車を所有しており、2台目を購入時に自動車保険に加入する際は「セカンドカー割引」が適用される場合があります。
例えば、子供が高校卒業後に運転免許を取得して車を購入し、新規で自動車保険加入すると年齢が若く、運転経験が浅いので保険料は高いです。しかし、保険開始時に1等級でも上がった状態なら保険料が安くなります。
セカンドカー割引が適用されるには、以下のような条件がいくつか設けられています。
- 1台目が11等級以上で自家用8車種であり個人所有
- 2台目が新規の加入で自家用8車種である など
全ての条件をクリアしなければならないので確認が必要です。
セカンドカー割引は保険会社からは何もお知らせがないため、自分で申し出て割引を適用してもらうことになります。

一家で2台目の車を新たに購入し、自動車保険に加入する際に1台目と2台目の等級を入れ替えることができます。
この1台目の等級を2台目に引き継ぐのは、同居の親族など条件があるので確認しておきましょう。
例えば、親が車を所有しており、長年無事故で保険の等級が高いとします。次に子供が車を購入して自動車保険に加入する際は、セカンドカー割引を使っても7等級からのスタートです。その際に親の等級が高い場合は、入れ替えることで子供の保険料がかなり節約になります。
親の世代だと、7等級になっても保険料はそこまで高くはなりません。等級の入れ替えは新規の加入の場合のみで、2台目の保険期間がスタートするともうできないので、タイミングを逃さないようにしましょう。
またセカンドカー割引が適用されなくても、等級入れ替えはできる場合もあるので、利用すれば多少でも保険料は安くなるかもしれません。
1台目と2台目の自動車保険で特に契約者が親族関係にある場合、補償内容が重複することもあるので注意が必要です。
多いのが車の同乗者の損害を補償する「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」です。この2つの保険は「運転者とその配偶者」「運転者もしくは配偶者の同居の親族」「別居の未婚の子」まで補償対象に含まれます。
そのため、親が1台目の自動車保険で人身傷害保険に加入していれば、2台目で子供が自動車保険に加入する際に、人身傷害保険に関しては補償が被ってしまうので、2台目の自動車保険は人身傷害保険をつけなくてもよくなり、その分保険料が安くなるというわけです。
自動車保険の補償範囲がどうなっているかを確認し、重複して無駄に保険料を支払わないようすることも保険料節約につながります。

セカンドカー割引は1台目と2台目の保険会社が別であっても、同じであっても1台目の等級など条件を満たしていれば適用されます。
ただし、1台目と同じ保険会社で2台目も契約することで、保険料が割引になることがあります。保険会社を1社にまとめると、連絡先なども同じなので何かと便利です。
更新の時期なども同じ時期にすれば、手続きもしやすいでしょう。1社にまとめると2台目の新規加入手続きも簡単になるなど何かとお得です。
車の乗る頻度が少ない場合、例えば月に数回程度でしかも近場にしか乗らないという人もいるかもしれません。その場合、日常的に車を運転することを前提とした自動車保険に加入すれば、車の使用頻度に対し保険料が高く感じるはずです。
万一に備えて自動車保険には加入しておきたいですが、それでは無駄になってしまうでしょう。そういう場合は、1日だけ加入できる自動車保険があるので、必要に応じて加入すると無駄がありません。
1日わずか数百円で保険に加入できる1DAY保険は、コンビニからも簡単に申し込みができます。自分で車を所有せず、友人や知人の車を借りて運転する時にも活用できる便利な保険です。
必要な時、必要な期間だけ自動車保険に加入することで、万一交通事故を起こしても安心であるうえに、保険料も抑えられるので一石二鳥だと言えます。
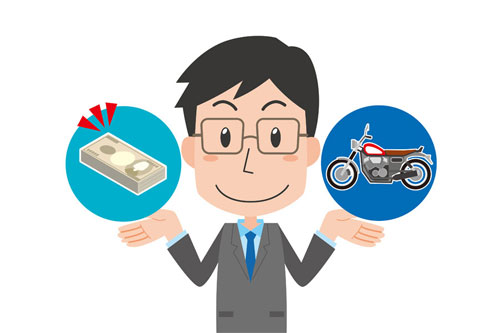
家族が原付バイクを所有し、通勤などに使うことになった場合も万一の交通事故に備えて、保険に加入しておく必要があります。
通常であればバイク保険に加入するのが良いと思われがちですが、家族が車を所有しているなら、自動車保険に「ファミリーバイク特約」を付帯させるのがお得だとされています。
補償範囲に関しては、運転者と配偶者、どちらかの同居の家族などが含まれます。親が自分の自動車保険に特約をつければ、子供が原付バイクを運転しても万一の場合は補償がカバーされるので安心できるでしょう。
車を所有し使用していれば自動車保険に加入しているように、病気やケガなどに備えて生命保険に加入している人も多いでしょう。生命保険は自動車保険とは無関係だと思うかもしれませんが、そうとも限りません。
例えば、家族が交通事故でケガを負った場合、生命保険の種類によっては治療費などをカバーできる場合もあるからです。また運悪く亡くなった際も、生命保険から十分な死亡保険金が下りるようになっていれば、家族が経済的に困窮することもないかもしれません。
そうなると、自動車保険における人身傷害保険や搭乗者傷害保険の補償を手厚くしなくても済む場合があります。生命保険の補償内容も今一度見直し、自動車保険の補償範囲が重複しないように確認してください。

自動車保険は、運転者の年齢や範囲、走行距離や運転歴など様々な条件をもとに保険料を決めています。工夫次第で保険料を抑えることはできるので、ポイントを抑えつつ丁寧に見直してみることが大事です。
「補償が重複していないか」「不要な特約がついていないか」などはよく見直せばわかるはずです。特に更新の時期が近付くと、更新を通知するハガキなどが保険会社から届くので、見直しのチャンスとも言えます。
保険を見直したことで保険料が安くなるということはよくあります。新規契約からそのままの内容で長期間経過している場合は、ライフスタイルの変化などで保険内容を変えた方が良いケースもあるでしょう。
また、2台目の車を購入する際も見直しのチャンスだと言えます。さらに車を新しく買い替える場合は、例えば安全装備がついていれば割引が受けられるなど、新たに利用できる割引があるかもしれません。
少し面倒かもしれませんが、例え少額でも長い期間支払い続けることを考えれば、結構な額になることを見越して見直してみてください。








