親名義の車を子供に譲る際は、車にかけてある自動車保険も一緒に引き継がせることができます。ただし、引き継がせることができない場合もあるので注意が必要です。
子供が親の自動車保険の「等級」を引き継げば、保険料がかなり安く抑えられる場合が多いのでお得になるとされています。また、等級を引き継ぐ以外にも「セカンドカー割引」など一家で2台目以降の車に適用される割引制度があるので、注目してみていきましょう!
自動車保険の3つの名義とは?

自動車保険に関する名義は3つの種類があります。
「契約者」という名義は、保険会社との間で保険契約を結び、保険料を支払う人のことです。契約者は保険加入時に住所や氏名など真実を保険会社に伝え、また変更があったら通知する義務があります。さらに、保険の解約などを申し立てる権利を有します。
「記名被保険者」という名義は、主に契約車両を運転する人のことです。保険の契約者と同一になることが多いですが、必ずしも同一でなくても構いません。この記名被保険者は運転者として扱われるので、記名被保険者の年齢や運転歴などにより保険料が変わってきます。
「車両所有者」という名義は、車両の所有であり車検証にも記載されています。ただし、ローンを組んで車を購入したり、リースだったりという場合は所有者がローン会社やリース会社になっているかもしれません。このケースでは、車検証の使用者が車両所有者として扱われることになります。
親が所有している車を子供に譲渡することは可能です。
例えば、子供が成長して運転免許を取得し車購入資金が貯まるまで、あるいは運転に慣れるまでは親の車を譲ってもらって乗るというケースもあるかもしれません。
車は基本的に名義変更を行えば、親子間や親族間でなくても他人同士でも譲渡できます。その際に親が契約している自動車保険の名義変更を行い、そのまま子供に引き継がせることも可能です。
しかし、友人や知人といった血縁関係のない全くの他人だと、話は違ってきます。親と子は家族であり血縁関係があるため、特別に自動車保険も名義変更をすれば引き継がせることができるとしています。他人の場合は自動車保険を解約して、新たに加入し直す手続きが必要です。

車と同時に、車にかけられていた自動車保険を子供に譲り渡すというケースもあります。この場合、親の保険の等級を子供が引き継ぐことができます。
等級は運転者の事故実績や事故発生リスクに応じて、1~20等級で分けられています。
例えば、1年間無事故で保険を使わなければ翌年1等級上がり、保険料もその分安くなります。逆に事故で保険を使うと、翌年から等級が事故の形態によって1もしくは3ダウンして保険料が高くなるという仕組みです。
保険の新規加入では6等級からスタートなりますが、子供の年齢が若いと運転経験が浅いので、保険に加入した際の保険料が親よりも高くなります。それに対して親は長年無事故なら等級が順調に上がり、それなりに保険料が下がっているでしょう。
ここで親の等級を引き継ぐことで、子供は初めからかなり等級が上がる場合もあり、保険料を抑えることが可能です。
等級は、保険契約期間中に1年無事故なら翌年は1等級上がるという形で、年々少しずつ上がっていきます。
しかし、交通事故を起こし保険を使うことで、下がることもあります。その場合、事故の形態に応じて何等級ダウンするかが決まっていて、原則として3等級ダウンか1等級ダウンです。
3等級ダウン事故に該当すれば翌年等級が3つ下がり、1等級ダウン事故を起こせば翌年等級が1つ下がります。3年もしくは1年かけて上げた等級が、一瞬の事故で下がってしまうのはもったいないです。
また、ノーカウント事故といって、等級に影響しない事故もあり、その場合は翌年無事故と同じように1等級上がります。
親が長年車を運転して、頻繁に交通事故を起こし保険を数回使っていると、等級がかなり低い可能性もあります。保険の新規加入では6等級からスタートするので、もし親の保険が6等級以下だと親の等級を引き継いでも意味がなかったり、かえって保険料が高くなって損したりすることもあるので注意が必要です。

子供が親名義の車を譲り受け、自動車保険も一緒に引き継ぐ場合は、まず親の車の自動車保険が7等級以上であるかを確認します。なぜなら通常、新規で自動車保険に加入すると6等級からスタートとなるからです。
そして、無事故なら翌年には7等級に上がるので、親の保険が6等級なら引き継いでも意味がありません。逆に5等級以下だと保険料が高くなってしまうため、損です。
親の車の保険が7等級以上なら、まずは車両の名義変更を行います。必要書類を揃えて管轄の運輸支局の窓口に提出し、新しい車検証を受け取るという流れになっています。オンラインで申請ができる場合もあるので、確認してみてください。
次に保険契約者の名義変更を行います。保険会社に連絡すれば必要な書類を郵送してもらえるので、記入して送り返せば手続きは完了です。
そして最後に記名保険者の名義変更も忘れずに行ってください。特に、保険料を決める上で記名保険者の年齢や運転歴が重要な要素となるので、変更しないと補償に影響が出たり、等級自体が消滅することにもなるので気を付けましょう。手続きの仕方は保険契約者の名義変更と同様です。
親名義の自動車保険を等級ごと引き継げるのは、子供が親と同居している場合に限るので注意が必要です。例え親子であっても親族であっても、一緒に暮らしていない子供には引き継ぐことができません。
特に子供が進学や就職を機に、親元を離れて一人暮らしをするタイミングで、車が必要となる場合は気を付けましょう。この機会にと、車と自動車保険を親が子供に引き継がせるというケースも多いです。
しかし、この場合は車の名義変更はできても、自動車保険の名義変更はできません。あくまで別居の状態では引き継げないので、子供が同居しているうちにタイミングを逃さないように、自動車保険も名義変更を行っておくことをおすすめします。
配偶者や親族間でも名義の引き継ぎは可能

親子以外であっても、自動車保険の名義を引き継ぐことができます。
しかし、誰でも引き継げるというわけではなく「運転者の配偶者」や「運転者もしくは配偶者の同居の親族」に限られます。また、同居の親族と言っても、あまりに遠い血縁関係では名義を引き継ぐことはできません。
親族の範囲は6親等以内の血族か、もしくは3親等以内の姻族、つまり配偶者の血族に限られています。運転者自身の親族だと1親等の父母や子、2親等の祖父母や孫、兄弟姉妹、3親等のおじおばや甥姪、4親等のいとこや甥姪の子など、割と広い範囲の親せきが該当することになります。
姻族は3親等なので配偶者のおじおばや甥姪までになりますが、あくまでも同居が必須条件となるので注意しましょう!
古い車を処分、売却すれば等級だけも引き継げる

車を譲渡し、車にかけている自動車保険も一緒に引き継がせることはできます。しかし、車は既に所有しているので、自動車保険だけを引き継ぎたいという場合もあるでしょう。
自動車保険の等級だけを引き継がせることも実は可能です。
ただし、等級だけを引き継げるのは同居の親族が必須条件となります。さらに、不要となった車は廃車、もしくは売却しなければなりません。この2つの要件を満たしていれば手続きは可能です。
等級だけを引き継がせる手順を見ていきましょう。
- まず、引き継がせる自動車保険の等級が7等級以上であることを確認してください。
- それから、古い車の廃車、売却を前提として新たな車の車両入替を行い、等級を交換します。その後、古い車は廃車、売却手続きをします。
- 最後に新たな車両の自動車保険の、保険契約者と記名保険者を新しく譲り渡された人に名義変更しましょう。
1台目の車が不要となり、処分もしくは売却したとしても、自動車保険を引き継がせる人がいないといったケースもあるでしょう。
不要となった車にかけていた自動車保険の等級が高い場合、そのまま保険を解約するのはもったいないものです。等級を上げるには何年も無事故でなければならず、せっかく上がった等級も解約により無駄になってしまいます。
もし、今後家族が車を所有する予定があるなら、自動車保険を「中断」させる手続きを取っておくことをおすすめします。中断しておけば、再度保険が必要となった場合、中断時の等級がそのまま反映できるのでお得です。
中断手続きの手順は以下になります。
- まず、保険会社に連絡し、中断証明書の発行を依頼して廃車や譲渡などを証明する資料を提出します。
- そして、中断証明書を受け取れば手続き完了です。
中断証明書があれば最大で10年間は保険を中断しておけます。
子供が2台目以降の車を所有する場合、セカンドカー割引を活用

一家で車を2台以上所有することになった場合、条件を満たせば自動車保険の「セカンドカー割引」を活用することができます。
等級が一つ上がった状態からのスタートになるため、保険料が安くなるのでお得です。
特に子供が運転免許を取得し、車を使うようになり自動車保険に加入すると、年齢が若いのでどうしても保険料が高くなりがちです。そんな時にセカンドカー割引で7等級からのスタートになれば、少しでも保険料を安くできます。
セカンドカー割引の条件とは?
セカンドカー割引を適用するためには、1台目と2台目の車で条件が決まっています。この条件を全てクリアしなければ適用されないので、確認しておきましょう。
また、セカンドカー割引が活用できるとなっても、保険会社からは特にお知らせはありません。自分でチェックし、2台目の保険期間が始まる前に保険会社に申し出なければならないので注意してください。
1台目の車の等級が11等級以上であることが必須です。無事故の期間が5年以上あればクリアできますが、契約途中で交通事故により保険を使うと等級が下がる場合があります。
さらに、1台目が自家用8車種であることも条件の一つです。また、車の所有者が個人であることも必須です。
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪自動車
・自家用小型貨物車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用普通貨物車
・特殊用途自動車
2台目の車の自動車保険が新規契約であり、1台目と同様に自家用8車種であることも条件となります。車の所有者も個人でなければなりません。
また、保険の記名被保険者が「1台目の車の保険の記名被保険者もしくはその配偶者」もしくは「どちらかの同居の親族」であることも条件です。
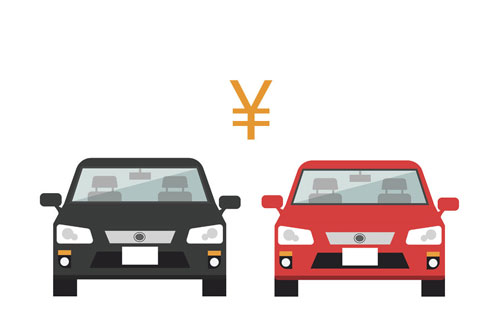
特に2台目の車の自動車保険の保険料を安くするには、車両入替を行うのも一つの手段です。
子供が車を購入して新規で自動車保険に加入するとなると、セカンドカー割引を適用しても7等級からになり、適用できなければ6等級から保険が始まります。そうなると、年齢が若く等級が低い分、保険料が高くなってしまうので経済的な負担が重いでしょう。そこで2台目の自動車保険を新規で親名義にし、親の自動車保険を子供に名義変更します。
親は新規加入で7等級もしくは6等級からの再スタートとなっても、年齢が若くないので保険料はさほど高くはなりません。さらにゴールド免許で優良ドライバーなら、ゴールド免許割引も引き継がせた子供の保険に適用させることができるので、さらにお得になります。
車両入替により、親の自動車保険を子供に引き継がせるためには、どのような手順で手続きを行うか見ておきましょう。
まず子供が新しく車を購入します。そして、親の自動車保険の名義を子供に変更します。(つまり、自動車保険の契約者と車を主に運転する人、記名被保険者を子供名義にするということです。)
そうなると、1台目の親の車が無保険状態になるので、次は親が新規で自動車保険に加入する手続きを取れば車両入替は完了です。

車両入替はどのような場合でもできるわけではなく、できないケースもあるので覚えておいてください。
まず既に親も子供も車を所有しており、それぞれが自動車保険にも加入済みである場合は車両入替はできません。つまり2台目の車に対し、自動車保険を新規契約するタイミングでしか車両入替はできないということです。2台目の自動車保険契約が完了し、保険期間が始まってしまうともう手遅れとなってしまいます。
しかし、この場合でもまだ打つ手はあります。それは、「子供の自動車保険を解約して加入し直す」という手です。
2台目の自動車保険の新規加入からまだ日が浅く等級が低い状態で、1台目の自動車保険の等級が高い場合は、2台目の保険を一度解約して車両入替したほうが保険料が安くなる場合もあるので、検討してみましょう。
自動車保険の名義は、家族や親族ではない友人、知人など血縁関係のない他人には引き継がせることはできません。
引き継ぎは、「配偶者や同居の親族」に限られます。また、子供でも別居となったら引き継がせることはできなくなります。
例えば、知人や友人から車を譲渡される、もしくは購入した場合、知人や友人名義での自動車保険の保険期間が残っていても、そのまま引き継ぐことは不可能です。
無事故期間が長く、いくら等級が高いと言っても名義変更ができない以上、一度解約してもらわなければなりません。
そして、車の譲受人もしくは購入側が再度自動車保険を新規で加入し直さなければならないので、間違えないようにしましょう。

車の購入費用を分割で支払うローンを組んで、新車を購入する人もいます。
例えば車にローンが組まれており、ローンが完済されていない状態で車を譲り渡されるという場合もあるかもしれません。
ローンを組むと、車の名義はディーラーやローン会社になっているのが一般的です。つまり車の所有者は購入者ではなく、ローン会社などです。この場合は本来、車を勝手に譲渡したり、売買したりということはできません。
まずローンを完済させてから名義を購入者に移し、それから譲渡や売買をして名義変更を行い、自動車保険に新規で加入するというのが正しい流れです。
ただし、ローンの返済がほぼ終わっている状態、いわゆる名義残りの状態で譲渡、売買された場合は所有者とみなし、譲受人、購入者名義で自動車保険に加入できるケースもあります。
保険会社によって対応が異なるので、一度問い合わせてみましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
親名義の車を運転する場合の保険はどうなる?

親名義の車を時々借りて運転する、つまり親と車を共有する場合も親が加入している自動車保険の補償対象、補償範囲に子供が含まれているかを確認しておく必要があります。
親が加入している自動車保険の運転者の範囲が「家族限定」になっていれば子供も補償対象に含まれます。ただ、運転者の範囲が「本人」や「配偶者限定」だと、子供は含まれないでの注意が必要です。
また、運転者の年齢条件も確認しておいてください。年齢条件が親の年齢に設定されていると、子供が補償対象になりません。そうなると、子供が親の車を運転中に交通事故を起こしても、保険金は下りないことになってしまいます。
子供が親の車を運転する前に、自動車保険の運転者の範囲や年齢条件を変更しておきましょう。
自分自身が既に自動車保険に加入しており、親名義の車をたまたま運転する場合もあるでしょう。
例えば、家族でドライブや旅行に出かけ、長時間の運転に親が疲れたので、少し運転を代わってあげたり、免許のない祖父母の通院のために親の車を借りて送迎してあげる、という機会もあるかもしれません。
このような場合で親名義の車を運転するにあたり、親の自動車保険の運転者の範囲や年齢条件に、子供が該当するかは確認すべきです。もし該当しなければ、家族や親族であっても交通事故の際は保険金は下りません。
しかし、自分の自動車保険で「他車運転危険補償特約」を付帯させていれば、万一の事故の際も保険で補償がカバーできます。
これは他人名義の車を契約車両とみなして、自分の保険から補償するというものです。ただし、借りた車の損害に関しては、自身が加入している自動車保険に車両保険をつけている場合しか補償されないので、間違えないようにしてください。

知人や友人などの他人から車を少し借りて運転する時は、血縁関係にないので借りた車にかけてある自動車保険の運転者の範囲や、年齢条件などは当然自分に該当しません。
また、友人知人の車でも家族名義の車であっても自身の自動車保険で他車運転危険補償特約が付帯されていない場合、借りた車を運転して交通事故を起こしても、何ら補償はされないのでリスクが大きいと言えます。
また、そもそも自身で車を所有していないので自動車保険にも加入していない、というケースもあるでしょう。この場合、短期間でも加入できる自動車保険があります。それが「ドライバー保険」です。
ドライバー保険は、原則として保険期間は1年間で等級制度があります。また、自動車保険に等級を引き継ぐことはできず、車両補償も付帯できません。21歳未満と21歳以上の2つの年齢区分があって、保険料もそれぞれ異なります。
ドライバー保険以外にも短期で契約できる自動車保険があります。それが「1日自動車保険」です。
1日自動車保険は、1日単位で保険期間が設定できるので、必要な期間だけ保険を継続させることが可能です。また、保険料は1日数百円と1000円未満なので、かなりリーズナブルで手軽にかけやすいと言えます。
年齢などによる保険料の差はなく、等級も設定されていないので誰が加入しても保険料は変わりません。さらに、車両補償を付帯させることもできます。
車両補償なしと車両補償あり、車両補償ありにプラス補償が上乗せできる…など、タイプがいくつかに分けられており、自分で必要なプランが選べます。
そしてコンビニから簡単に手続きできるので、効率的です。急に車を借りて運転することになった場合など、必要になったらコンビニへ行けばいつでも手続きができます。

子供が運転免許を取得し、親名義の車を譲り渡して自動車保険の等級も引き継がせることはできます。
ただし、必要な条件があるので、該当するかをきちんと確認しておかなければなりません。そして、手順もあるので間違えないように手続きをしてください。
また、子供が車を購入し新たに自動車保険に加入するとなったら、セカンドカー割引も適用できます。条件がいくつかあるので、満たしているかもチェックが必要です。
子供は年齢が若い分、どうしても運転経験が浅く交通事故発生リスクが高いとみなされるので、保険料が高くなってしまいます。よりお得で少しでも保険料が抑えられる方法を模索すれば、経済的な負担も軽減するかもしれません。
親が加入している自動車保険の補償内容やお得な割引制度なども見直して、活用できるものはどんどん取り入れましょう!
また保険会社の補償などを比較してみて、よりお得な保険会社があれば乗り換えるというのも一つの手です。








