自然たっぷりの空間で、非日常的な雰囲気を楽しめるキャンプなどのアウトドアレジャーが最近ブームになっています。それに合わせてアウトドアシーンで活躍するキャンピングカーのニーズも高まっているようです。
ただし、キャンピングカーは乗用車と構造も大きさも異なるため、万が一に備える自動車保険も乗用車のものとは少々事情が異なります。
そこで今回は、キャンピングカーの自動車保険について、どのような点が乗用車のものと違うのか、詳しく解説します。
キャンピングカーでも自動車保険は必須!加入条件はどうなってる?
キャンピングカーがその真価を発揮するのは、海や山など比較的混雑の少ないアウトドアシーンです。そのため、他の車や歩行者などが目まぐるしく行き交う都市部より、車対車の接触事故や人身事故に遭遇する確率が低いのは確かです。
しかし、こういった場所では天候や気温の急激な変化による故障や、落石や動物との接触など、日常的な用途では思いもよらないトラブルや事故が発生する可能性があります。
そのため、キャンピングカーであっても、乗用車と同様むしろそれ以上に、万が一の備えである自動車保険に加入しておくことが必要です。
ただし、キャンピングカーは用途や構造が乗用車と大きく異なるため、自動車保険の加入条件や必要となる補償内容、付帯すべき特約なども変わってきます。
キャンピングカーはどんな車?

キャンピングカーと自動車保険の関係を理解するために、まずはキャンピングカーがどんな車なのか知っておきましょう。
キャンピングカーとは、特殊な改造や仕様変更などを施し、一般的な車には備わっていない本格的なベッドやキッチンなど、寝食可能な設備を車内に備えた車のことを指します。
つまり、シートアレンジやグッズの活用で一時的に車内泊ができるようにした車や、簡易的な調理器具を持ち込んでいる車は、用途は似ていてもキャンピングカーではありません。
キャンピングカーのニーズは年々高まっており、一般社団法人・日本RV協会の調査によると、2020年の保有台数は約127,000台と、前年と比べて106.7%増加しているそうです。
キャンピングカーと言ってもたくさんの種類があります。
まず、走行方法による区別として、走行する車両部分と居住スペースが一体となっている「自走式」と、トレーラーなどの居住スペースを車両が引っ張って移動する「けん引式」の2つに分類されます。
また、同じ自走式キャンピングカーでも、ベースとなる車の対応によっても以下のような分類があり、それぞれ特徴や長所・短所が異なるため確認しておきましょう。
キャンピングに適した機能・装備を持つ車体を、専用のシャーシやエンジンなど一から作り上げているキャンピングカーです。キャンピングカーの最高峰であり、居住性の高さや使い勝手抜群だが、価格的には高額になります。
バスをベースにしたキャンピングカーです。本来乗客が座るシート部分を改造して居住スペースにしているため、その広さが魅力で大人数でのキャンプにはうってつけです。
しかし、取り回しが大変でガソリン代などの維持費もかさみます。
ハイエースやキャラバンなどのワンボックス型バンを改造したキャンピングカーです。日常利用しやすくコストも安上がりだが、やや居住スペースが狭めです。
トラックをベースに、荷台部分を居住スペースに改造したキャンピングカーです。バスコンとバンコンの良いところを併せ持っているが、やや改造費が高くつく傾向にあります。
キャブコンの軽自動車バージョンです。乗車定員・居住スペースともに限られるが、運転が楽で何よりあらゆるコストが断然安上がりです。
用途・予算・所有している免許の種類などに応じて、自分にマッチするキャンピングカーを選ぶことが大切です。
キャンピングカーと通常の乗用車はその装備や構造、見た目の違いだけではなく法的にも違う存在として分類されています。
キャンピングカーの多くは道路運送車両法と付随する通達により「特種用途自動車」に分類され、その中でも「特殊な目的に専ら使用するための自動車」に属しています。
一般的な乗用車は3ナンバーまたは5ナンバーです。(貨物は1ナンバーまたは4ナンバー)
一方、キャンピングカーは一目で特種用途自動車であることが判別できるよう、8ナンバーが用いられます。そのため、キャンピングカーは俗に「8ナンバー車」と呼ばれることもあります。
用途や構造が異なるとはいえ、なぜキャンピングカーはナンバーを分けてまで乗用車と区別されているのでしょう?
その理由は、同じ8ナンバーに属している他の車を知れば理解しやすいです。8ナンバーは、キャンピングカーが属する「特殊な目的に専ら使用するための自動車」の他、パトカーや消防車、救急車などの「緊急自動車」、給水車・医療防疫車・採血車などの「法令等で特定される事業を遂行するための自動車」の3つに分けられます。
そして、これらの車は乗用車にはない特別な装備と、特別な役割を持った車ばかりです。つまり、乗用車とこれら「特種用途自動車」との違いが一目で判別でき、その特殊な役割を阻害することがないようにするため、乗用車と異なる8ナンバーを付与しているわけです。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
キャンピングカーと自動車保険との関係
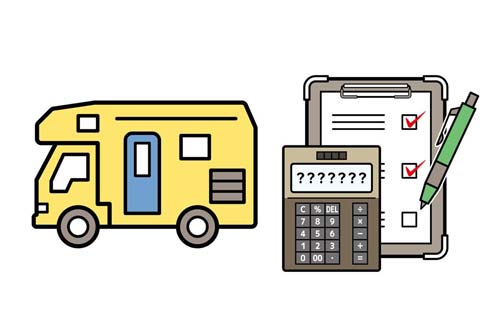
ここまで、キャンピングカーの種類・タイプは様々だが、どれも普通乗用車とは大きく異なる特殊な構造・装備・用途を持っていて、法的な立場も違うことを説明してきました。
ここまで違えば、自動車保険の加入条件や求められる補償内容も変わってくるのは当然です。
ここからは、本題であるキャンピングカーと自動車保険との関係について詳しく整理していきましょう。
まずは、強制保険とも呼ばれる自賠責保険が、キャンピングカーと乗用車でどのように違うのか見ていきましょう。
自賠責保険は通常、2年に1度の車検の時、2年分の保険料をまとめて支払います。8ナンバーであるキャンピングカーの車検も、2年に1度が基本です。そのため、支払うタイミング・回数については乗用車と同じです。
ただし、支払う保険料の金額についてはキャンピングカーと乗用車で変わってきます。
具体的には以下の通りです。(全て24ヶ月契約)
| 普通キャンピングカー | 軽キャンピングカー |
|---|---|
| 22,450円 | 12,200円 |
| 普通乗用車 | 軽自動車 |
|---|---|
| 20,010円 | 19,730円 |
比較すると、普通キャンピングカーは普通車より2,400円程高く、反対に軽キャンピングカーは7,000円程安いです。
つまり、キャンピングカーの自賠責保険料はその種類によって変化するということになります。
任意保険の保険料は、加入者の条件や補償内容、加入する保険会社よって大きく変わります。この点は、基本的に乗用車も同じであるためイメージしやすいかもしれません。
乗用車とキャンピングカーの任意保険における、加入者の条件で変わることが多いのはその用途です。
任意保険に加入する際、契約する車の用途を「通勤・通学」「日常・レジャー」「業務」の中から1つ選んで申告する必要があります。
「通勤・通学」に使用することが多い乗用車と異なり、キャンピングカーの用途は専ら「レジャー」になります。
年齢や運転者の範囲、免許証の帯色や等級など他の加入者条件が同じである場合、「日常・レジャー」目的より「通勤・通学」目的のほうが、2,500円~3,000円程度保険料を高めに設定している保険会社がほとんどです。それは、「事故リスクが高い」という理由からです。
また、対人・対物賠償などの基本補償を手厚くするほど、保険料は高くなっていきます。万が一、事故にあった際に補償が不足すると大変なので、この点は慎重に検討することをおすすめします。
キャンピングカーは、乗用車と構造的にも法律的にも大きく異なります。また、生産台数や流通台数で見ても乗用車より圧倒的にその数が少ないため、車両データや事故発生件数・被害状況などといった各種の統計データが集まりにくい傾向にあります。
さらに、その多くが「改造車」なので、車種や型式が同じであったとしても装備や構造によって大きくその車両価格が変わります。
そのため、乗用車の任意保険のようにインターネットやスマホで簡単に申し込めるというわけにはいかず、窓口への問い合わせが必須となります。
しかし、キャンピングカーの任意保険を、各保険会社が取り扱っていないわけではありません。通販型・代理店型どちらも多くの保険会社がキャンピングカー用の保険商品を用意しています。
前述した通り、キャンピングカー保険を受け付けている保険会社は少なくありません。保険会社へ電話したり、有人店舗へ足を運んだりする場合は手間がかかりますが、キャンピングカーの自動車保険料が乗用車より高くなるというわけではありません。
むしろ、使用用途が「レジャー」に限られていて海や山など比較的混在の少ない場所を走行する機会が多いキャンピングカーは、人身事故や重大な物損事故を起こす可能性が通勤用車両よりも低いと考えられます。そのため、かえって保険料が乗用車より安めに設定されるケースも多々あります。
キャンピングカーの自動車保険を選ぶ時のポイント

キャンピングカーの保険は、ネットで見積もりを確認してすぐ申し込めるというわけにはいきません。プランを選択する作業にはどうしても時間がかかってしまいます。
しかし、しっかりと保険会社や保険のプランを選ばなければ、必要な時に補償が受けられない、余計な保険料を支払ってしまう等の事態につながるため、注意が必要です。
ここからは、キャンピングカーの自動車保険を上手に選ぶうえで、覚えておいてほしい「4つのポイント」を紹介します。
一般向け自動車保険には、1等級~20等級までの「ノンフリート等級」が存在し、等級が上がるほど割引率が増して保険料が安くなります。
そのため、キャンピングカーの場合、ノンフリート等級が引き継げるか気にしている方も多いかもしれません。
結論から言うと、キャンピングカーでもノンフリート等級を引き継ぐことが可能です。さらに言えば、キャンピングカー同士はもちろん、乗用車からキャンピングカーへの等級引き継ぎもその逆も可能です。
キャンピングカーと乗用車は法的に区分されているのに、なぜ等級を引き継げぐことができるのでしょう。なぜならこの2つの車両は、自動車保険の保険適用範囲や加入条件が共通する「自家用8車種」に属しているからです。
なお、自動車保険の適用範囲や加入条件を示す指標として、その他にも「自家用6車種」があります。
キャンピングカーをはじめとする特殊用途車両は、こちらには含まれていません。そのため、加入条件を「自家用6車種」に限定している自動車保険にキャンピングカーは加入できませんし、ノンフリート等級も引き継げないので注意しましょう。
キャンピングカーは用途的に高速走行による重大事故や、人身事故に遭遇する確率が普通車より低い傾向にあります。
一方、山や海などの自然豊かな場所では、バッテリー上がりやパンク、脱輪などといったトラブルに遭遇する可能性は上昇します。
さらに、こういった場所は付近に修理工場やガソリンスタンドなど、トラブルを解決してくれる施設が少ない、もしくは遠く離れていることが多いです。
そのため、自動車保険に付帯されている、応急処置やレッカー移動などのロードサービスの充実度が重要な要素になってきます。
車両保険に加入しているからと言って、損害がいくらでも無制限に保証されるわけではありません。車両保険には補償の「上限金額」が契約時に決められており、契約車両の「時価」によって変わってきます。
キャンピングカーの場合、構造(改造の程度)や装備によって車両の時価が大きく異なり、高額になるケースもあります。そのため、契約前にいくらまで車両保険で補償されるのか、上限金額をしっかり確認することが大切です。
また、キャンピングカーはその性質と用途から飛び石や枝木への接触、落下物などによって細かい傷やへこみなど、軽めの損害を受けることが多々あります。この点と大きく関わってくるのが、車両保険の「免責金額」です。
仮に車両保険の免責金額が「10万円」に設定されている場合、10万円以下の修理・板金などに関しては、車両保険で補償されず契約者が自己負担することになります。
この免責金額もキャンピングカーの維持コストを大きく左右する要素となるため、保険加入時にいくらになっているかチェックしておきましょう。
車両保険には、適用範囲の広いタイプと適用範囲が限定的なタイプの2通りが存在します。
適用範囲の広いタイプは、地震・津波・噴火などを除きほとんどのケースで保険が適用されます。
一方、適用範囲が限定的なタイプは、地震・津波・噴火による補償に加え、自転車との接触事故やあて逃げ、単独事故などでも保険が適用されないため注意が必要です。
また、キャンピングカーはキッチンやトイレ、電化製品など一般的な車にはついていない付属品を数多く備えていることがあります。加入した保険が付属品まで補償してくれるのか、適用範囲をしっかり確認しておくことが大切です。
キャンピングカーは同じ車種・型式であっても、改造内容や装備が異なれば車両価値や使い勝手などが変わってきます。そのため、乗用車の保険よりも、加入する保険会社や補償内容によって保険料の差が大きくなります。
ネットを活用した一括見積もりなどができず、多少手間と時間はかかりますが、複数の保険会社に問い合わせて見積もりを取ることが大切です。
そして保険料はもちろん、補償範囲やロードサービスの充実度、付帯できる特約の種類まで細かく比較し、自分のアウトドアライフにマッチした自動車保険を選びましょう。
レンタルやリースでキャンピングカーを利用する際の注意点

アウトドア需要の高まりに合わせ、キャンピングカーのレンタル・リース業者も増えてきました。こういった業者を利用すれば、高い維持費や購入費・改造費などをかけることなく、手軽にその魅力を満喫できます。
ただし、手軽さやお得感などのメリットだけではなく、以下のような注意点もあります。
- 車体の大きさなどに慣れていないと、運転ミスや駐車ミスなどを起こす可能性がある
- キャンプにうってつけの繁忙期は、料金が高く設定されていることがある
- 貸出時になかった汚れや傷が入った場合、修理代や清掃費を追加請求される可能性がある
利用を検討している場合は、このようなレンタル・リースならではの注意点も頭に入れておきましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
キャンピングカーと自動車保険に関する素朴な疑問

最後に、ここまでの解説でお伝えしきれなかった、キャンピングカーの自動車保険に関する疑問にお答えしていきます。
自分で改造したキャンピングカーであっても、保安基準に適合している「合法」な改造車であれば問題なく保険に加入できます。
反対に、プロが改造を施した車両や専門店で購入した車両であっても、違法改造が少しでもされている場合は自動車保険に加入できません。
合法改造車かそうでないかを見極める方法は簡単です。陸運局で構造変更申請を行い、それが認められ車検もクリアした合法改造車の車検証には、「型式」の欄に「改」という漢字一文字が書き加えられます。そのため、合法か否かは誰でもすぐ判別できます。
乗用車の自動車保険と扱いは同じになりますが、地震・噴火・津波などの自然災害による車両被害は、多くの自動車保険で免責事項と定められているため補償されません。また、スピード違反や飲酒運転など運転者の過度な過失による事故の損害についても、保険金が支払われないこととなっています。
一方、キャンピングカーの保険金不支給事由として多いのは、保安基準を満たしていない違法改造・追加改造が施されているキャンピングカーによる事故です。特に気を付けておきたいのが、保険加入時は合法でも加入期間中に施した改造が「違法」だった場合、保険金が支払われない可能性が高いことです。
例えば、些細なことですが、シートについているヘッドレストを外して運転すると「道路運送車両法の保安基準」に違反します。その状態で万が一事故に遭遇した場合、保険会社が違法改造として支払い拒否の理由に挙げてくる可能性もあります。
キャンピングカーに限ったことではありませんが、基本的には保険加入時の状態を保ったまま、使用していくことが大切です。
けん引式キャンピングトレーラーのトレーラー部分とけん引車両が連結して走行中に発生した事故の場合、けん引車両の加入している自動車保険が適用されます。
ただし、この場合でも保険が適用されるのは賠償補償のみなので、車両保険については別々に契約を締結する必要があります。
一方、トレーラー部分が坂を勝手にくだって障害物にぶつかるなど単独で事故を起こしてしまった場合は、けん引車両の保険が全く適用されないので注意が必要です。
用途的に必要性を感じる場合は、トレーラー部分の保険にも別途加入しておくと安心です。








