契約車両が10台以上あると、自動車保険に加入する際はフリート契約になります。
ノンフリート契約では等級制度があり、等級に応じて保険料の割引率が決まります。しかし、フリート契約の場合は等級などがなく、オリジナルの割引率制度があります。
この記事では、フリート契約の割引率について詳しく見ていきます。また、割引率を決める要素や保険料を節約するためのポイントについてもまとめましたので、参考にしてください。
自動車保険のフリート契約の割引率は最大70~80%

フリート契約の割引率は、保有する車両の台数などによってまちまちですが、最大で70~80%の割引率になることもあります。
この割引率はノンフリート契約と比較しても大きめです。
ノンフリート契約には1~20等級があり、等級が高くなるほど割引率が高くなります。最高の20等級で適用される割引率は63%です。
ノンフリート契約の最高等級と比較しても、フリート契約の割引率は非常に高いと言えます。そのため、法人で複数の車両を保有するのであれば、フリート契約の割引率をうまく活用しましょう。
フリート契約の保険料の算出方法

ノンフリート契約同様、フリート契約の場合も個別に保険料を算出します。
フリート契約の保険料を算出する式は以下になります。
保険料は基本的に区分ごとに算出されて料金が決まります。そのため、用途や車種、契約の条件、付保種目などをベースに算出します。
しかし、フリート契約の場合は「割増引率」や「多数割引」がどうなるかによって、割引になったり割増になったりします。
割増引率は、過去の割増引やこれまで支払った保険金などによって決められます。
多数割引は、10台以上の所有・使用自動車を1枚の保険証券で同時に付保された場合に適用されます。ちなみに多数割引は、一律5%割引となります。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
フリート契約はノンフリート契約よりもお得?
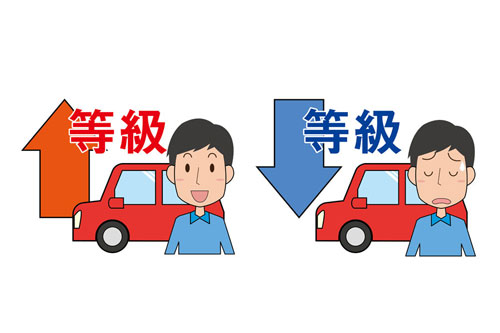
フリート契約は、最大70~80%の割引率になります。20等級で最大63%のノンフリート等級と比較すると、割引率は大きいです。
ただし、あくまでも最大の割引率がフリート契約のほうが高いという意味です。車両の使用状況などによっては、フリート契約のほうが高くなってしまうこともあり得ます。
ノンフリート契約の場合、事故の回数で保険料の割引率が決まります。1回事故を起こして保険を使用すると1~3等級ダウンする可能性があります。
フリート等級の場合、事故の回数ではなく保険金の支払額で翌年度の保険料が決まる仕組みです。もし多額の保険金を支払うような事故を起こしてしまうと、翌年度の保険料がグンと上がる可能性がありますので注意しましょう。
割増引率を決める要素について

フリート契約の保険料は、基本保険料と割増引率と多数割引の合計を掛け合わせて算出します。そのため、割増引率がどうなるかによって、保険料が上がったり下がったりします。
この割増引率を決める要素はいくつかありますので、割増引率を決める主な要素について紹介します。この内容はフリート契約に申し込む前に頭に入れておきましょう。
割増引率を決める要素の一つに、総契約台数が挙げられます。
総契約台数とは、自動車保険に加入するトータルの台数のことです。
契約台数になるのは、契約者が所有して、自分で使用する車両であることが条件です。また、1年以上の契約期間で締結した自動車保険の契約台数になり、契約者が自らを記名被保険者としている場合が該当します。
契約する車両の数が多くなるほど割引率も高くなるので、たくさんの車両を保有しているのであれば、フリート契約にすると保険料がお得になるでしょう。
損害率もフリート契約の割増引率を決める重要な要素の一つです。
損害率とは、保険会社が支払った保険金と法人企業の支払った保険料総額をパーセンテージ化したものです。
法人企業の支払う保険料は保険会社によって算出されるものなので、こちら側はどうすることもできません。しかし、保険会社の支払う保険金はこちらの努力次第で減らすことができます。
保険金額が少なくなれば、損害率のパーセンテージも低くなります。損害率が低ければ、割引率も大きくなってより保険料もお得になるということです。
保険会社の支払う保険金がベースになるのが、ノンフリート契約と異なるところです。もし軽微な事故で大した保険金を受け取らなければ、翌年度の保険料はそこまで上がらない可能性もあります。
前年度のフリート割増引率も、割増引率を決める要素の一つです。
前年度の優良割引率をベースにして、次年度の割増引率に反映されます。割増引率が良好であれば、翌年度の保険料もお得になります。逆に事故を起こして割増引率があまりよくなければ、翌年度の保険料も割高になってしまうので注意が必要です。
ちなみに前年度まで契約台数が9台以下で増車して10台以上になると、自動的にノンフリート契約からフリート契約に移行します。この場合、前年度がフリートではないので割増引率がありません。そのため、平均無事故率をベースにしてフリート契約の初年度の保険料を決める形になります。
割増引率を決める要素は様々ですが、成績計算期間内のものが適用されます。
成績計算期間は、保険期間の後半6か月と前半6か月が該当します。成績計算期間と保険契約期間とではズレがありますので、注意してください。具体例を見てみていきましょう。
例えば、契約期間が4月1日~翌年3月31日だったと仮定します。成績契約期間は契約開始の6か月後の10月1日が起点です。そして翌年の9月30日までが一つのサイクルになります。そのため、優良割引が適用されることになっても、6か月のズレがあるのですぐには反映されません。
また事故を起こすタイミングによっては、次年度の割増率がアップすることもあり得ますので、この点は注意が必要です。
フリート契約の保険料と損害率の関係について

フリート契約の保険料を決めるのに重要な項目となるのが、割増引率です。そして割増引率を構成する要素の中でも、翌年度の保険料のカギを握るのが損害率と言われています。
ここからは、損害率についてさらに掘り下げて詳しく解説します。保険料を決めるにあたって、いかに損害率が重要なポイントになっているか理解しておきましょう。
割増引率は、翌年度の保険料を決める要素の一つです。割増引率を決める要素の中でも特に重要なのが「損害率」と言われています。この部分が、ノンフリート契約との大きな違いです。
ノンフリート契約の場合、1年間の事故件数が重要なカギを握ります。もし1回事故を起こせば、1~3等級ダウンしてしまいます。1年間に2回事故を起こせば、最悪の場合6等級も一気にダウンすることも考えられるので、事故を起こさないようにすることが大切です。
一方フリート契約の場合、損害率が翌年度の保険料を左右します。ノンフリートの事故件数ではなく、事故の内容が翌年度の保険料に大きく影響すると考えてください。
ノンフリート契約の場合ノーカウントや1等級ダウンの事故もありますが、保険を使うと基本3等級ダウンとなります。そのため、翌年度の保険料はかなりの確率で上がるでしょう。
一方フリート契約の場合、損害率が翌年度の保険料を決めます。損害率は支払われた保険金額を支払った保険料額で算出されます。
つまり1回保険を使ったとしても、支払われた保険金額が少額であれば損害率もあまり大きく変化しません。例えば車をどこかにぶつけて、ちょっと修理するために車両保険を使ったとします。
この場合、修理代金がさほど高額にはならなければ、翌年度の保険料もそこまで上がらない可能性があります。ただし、少額でも繰り返し保険金を請求すれば、翌年度の保険料がアップするかもしれません。
フリート契約の場合、損害率が翌年度の保険料を決める重要なカギとなると説明しました。中でも注意しなければならないのは、大きな事故を起こした場合、翌年度の保険料が一気に跳ね上がる恐れがあるという点です。
損害率は、保険会社の支払った保険金額が大きくなると高くなってしまいます。たとえ1件の事故でも、対人や対物賠償で高額の保険金を支払えば損害率も一気に高くなります。
その上注意しなければならないのは、フリート契約は車両1台単位の保険ではない点です。フリート契約は契約者単位なので、1台が起こした事故によってほかの契約車両の保険料も一気に上がってしまうことも考えられます。
1台当たりの年間保険料であれば数万円程度の値上げでも、全ての車となると少なくても数十万円、場合によっては数百万円の負担増になるかもしれません。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
フリート契約の保険料を安くするコツとは?

フリート契約で自動車保険に加入する場合、できるだけ保険料を安くしたいと思う方も多いでしょう。固定費なので、カットできれば財務面の影響も大きくなります。
フリート契約で保険料を節約する方法はいろいろとありますが、その中でも重視したいのが損害率です、損害率を低くするためのポイントについてまとめました。
翌年度の保険料を決める割増引率の中でも、契約者側が唯一調整可能なのが損害率です。
損害率は成績計算期間中に発生した事故に対して、保険会社がいくら保険金を支払ったかで決まります。保険金の支払いをできるだけ少なくできれば、損害率の数値を少なくできます。割増引率も大きくなるので、翌年度の保険料を安くできるということです。
具体的な事例で見ていきましょう。例えば、前年度の保険料が100万円だったとします。もし割引率が50%であれば、翌年度の保険料は50万円です。そして割引率が80%になった場合、翌年度の保険料は20万円となります。
割引率が50%になるか80%になるかで、年間保険料が30万円も変わってくる計算です。
損害率を減らすためには、どのような対策をすればいいのでしょう。損害率を低くするためには支払保険金額を少なくする、言い換えれば事故を減らすことが一番です。
事故を減らすために法人ができることとして、従業員に安全運転の意識を徹底させることが挙げられます。
例えば、定期的に安全運転講習を行うのもおすすめです。なかなか時間が取れなければ、オンラインの講習を実施するのもいいでしょう。
また、飲酒運転対策を徹底することも大事です。アルコールチェッカーを導入し、従業員に飲酒運転させないような対策は効果的だと言えます。
法人でできる交通事故対策として、車両管理システムの導入も一考です。
車両管理システムとは、社用車を一括で運行管理できるシステムです。具体的にはどこにいるのか、加速や減速などどのような運転しているかをリアルタイムで把握できます。
ドライブレコーダーと決定的に違うのが、事故を起こす前に警告できる点です。例えば、危険運転を察知するとアラート通知できるようなシステムも見られます。また危険運転しているドライバーがいれば、個別に指導するなどで事故防止ができるかもしれません。
さらに、事故リスクの高い場所もシステムで把握できます。そのような場所をドライバーに周知し、注意して運転するように指導することも可能です。
個人でできる事故防止対策とは?

保険料を節約するためには、事故を起こさないようにすることが重要です。法人での対策もありますが、やはり運転する個人が日頃から安全運転を心がけることが重要です。
個人が事故を起こさないようにするためにできることはいろいろとあります。その中でも主な対策について、いくつかピックアップしました。
体調管理は安全運転をするための重要なポイントです。体調が悪い、睡眠不足の状態だと自覚はなくても注意力が散漫になっている可能性が高く、危険です。
体調の悪い場合には、無理してハンドルを握らないようにしましょう。会社でもそのように指導して、無理させないように対処することが大事です。
また体調が悪くなくても、長時間運転すると疲労が溜まってしまいます。疲れていると注意力散漫になり、事故リスクも高まります。
そこで長距離ドライブをする際には、定期的に休憩をはさむことが重要です。目安としては1時間に1回のペースで休憩を取れば、注意力が大きく低下することはないでしょう。
時間にゆとりを持って運転することも、重要なポイントです。
交通事故が多くなるのは、時間帯だと朝、年間で見ると12月だと言われています。朝は「遅刻するかも」と焦ってしまう方も多く、12月が年末なので何かと忙しい時期です。焦ってしまって注意力散漫になったり、思わぬミスを起こしたりして事故につながります。
そのため、余裕のあるスケジュール設定にすることが大事です。もし時間にゆとりがあれば、例えば赤信号になる寸前に交差点を進もうとはしないでしょう。
また、一時停止のところもしっかり停まり、周囲の交通状況を確認しながら運転できます。忙しい従業員がいれば、その仕事の一部を別の社員に割り振るなど、会社でも対策を講じましょう。
ながら運転をしないことも、交通事故防止のために有効な対策の一つです。ながら運転をすると、多方面に注意が散漫して思わぬ事故を引き起こしかねません。
特に近年注意しないといけないのが、スマホをいじったりカーナビを操作したりしながらの運転です。
もしスマホに着信があれば、いったん車を停車させてから対応してください。もしくはスマホをバイブにする、または電源を切ってしまっておくようにする対策も有効です。
カーナビは運転するまでに設定を済ませておいてください。同乗者がいる場合には、その人にカーナビの操作を任せてしまいましょう。
ベテランドライバーのやり方を参考にするのも一つの方法です。ベテランドライバーが心がけていることとしてよく耳にするのは、「青になってもすぐに発進しないようにする」ことです。
青になっても、2~3秒待ってから発進するというベテランドライバーは少なくありません。なぜなら、信号が変わる前後は歩行者や車両が慌てて飛び出してくることがあるからです。
特に歩行者の場合、向こうが信号無視していたとしてもこちらの過失割合が大きくなってしまうことも珍しくありません。そのため、何か飛び出してくるかもしれないと日頃から気を付けて運転することが大事です。
青信号になっても少し待ってから発信することも、時間にゆとりがなければ難しいでしょう。ゆとりを持った行動を徹底することは、やはり重要です。








