自動車保険には「等級制度」が設けられており、これによって保険料が決定されています。
交通事故などで保険を使うと、等級にも影響が及ぶことが多いですが、全てのケースで等級に影響するというわけではありません。中には保険を使っても、等級が上下しない「ノーカウント事故」と呼ばれる事故もあります。
では、どういったケースがノーカウント事故になるのか、保険の等級制度に関連させながら紹介していきます。保険を使うかどうか迷った時は、参考にしてください。
自動車保険の等級制度とは?

自動車保険では、保険料の割増引率を定める区分として等級制度を導入しています。
等級は、1~20等級までに分けられており、1等級は保険料が割増しとなり、20等級が一番保険料が安くなるという仕組みです。それぞれ保険の契約者の事故実態に応じて区分されます。
初めて自動車保険に加入する場合、6等級からスタートです。1年間保険を使わなかった場合は翌年から1等級アップして7等級となり、保険料が割引かれます。逆に事故を起こして保険を使うと等級が下がり、保険料は高くなります。
事故の種類と等級の関係について
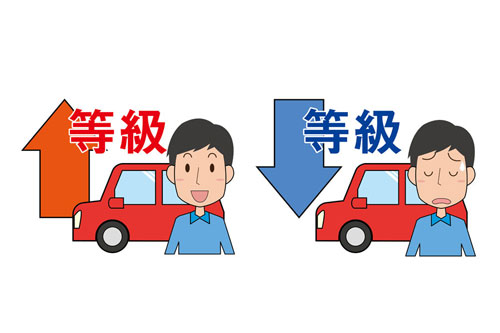
交通事故により自動車保険の補償を受けると、基本的には翌年の契約から等級が下がります。つまり、保険料の割引率も低くなり、支払う保険料の金額が高くなります。
1~20等級のうち、5等級よりも下がると保険料が割増しとなっていきます。自動車保険契約中に、交通事故を起こさない、また保険を使わない期間が長くなればなるほど、保険料は安くなっていくというシステムです。逆に交通事故で保険を頻繁に使うと、支払う保険料は高くなります。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
ノーカウント事故について

自動車保険では、交通事故などで保険を使うと翌年から等級が下がるのが一般的です。
しかし、中には等級が下がる事故としてカウントされない場合もあります。それが、自動車保険でいうノーカウント事故のことです。
ここからは、ノーカウント事故の例を詳しく紹介していきます。
人身傷害保険とは、契約車両に乗車していた運転者、同乗者が事故で死亡、ケガを負った場合の補償を行う保険です。
具体的な補償としては、病院での治療費や働けない間の休業損害、精神的損害などが挙げられます。相手との示談が成立していなくても補償してもらえるので、治療が長引くケースなどで役立つでしょう。
人身傷害保険のみを使う場合は、ノーカウント事故と判定されます。
搭乗者傷害保険とは、契約車両に搭乗していた運転者や同乗者が死亡、ケガをした場合の補償を行う保険です。
人身傷害保険と内容は似ていますが、人身傷害保険は実際にかかった費用を全て補償してくれるのに対し、搭乗者保険はあらかじめ支払われる保険金額が決まっています。
搭乗者傷害保険のみを使う場合も、ノーカウント事故と判定されます。
ファミリーバイク特約はバイクを運転していて事故を起こし、他人を死亡させるもしくはケガを負わせた際や、他人の物を壊した際に補償を受けることができます。
特約なので自動車保険に付随しています。通常のバイク保険よりも保険料を安くできるという点がメリットですが、対象車は125㏄以下のミニバイクや50㏄以下の三輪以上の車両なので注意しましょう。また、この特約1つでミニバイク数台の補償も可能です。
ファミリーバイク特約を使う場合も、ノーカウント事故と判定されるので翌年等級が下がることはありません。
無保険車傷害特約は、交通事故で死亡もしくはケガを負い後遺障害が残ったが、事故の相手方が自動車保険に加入していないといった時に補償をしてくれる特約のことです。
保険に加入していても運転者が年齢条件違反などで保険金が支払われない場合や保険金額が損害賠償額に足りない場合、さらに当て逃げやひき逃げなど事故の相手が不明な場合も当てはまります。
支払われる保険金額は、強制保険である自賠責保険の保険金や相手方が加入している自動車保険の対人賠償保険から支払われる保険金の合計から、不足する分のみとなっています。また、事故でケガを負っても、後遺障害が残らない場合は補償の対象外となるといった条件があるので注意が必要です。
無保険車傷害特約により保険金が支払われる場合、ノーカウント事故となります。
交通事故で身体や物に損害を受ければ、事故の相手方に損害賠償請求を行うでしょう。その際、弁護士に相談したり相手方と交渉してもらったりする時にかかる費用を保険でカバーするのが弁護士特約です。
通常は、事故の相手方への賠償に関する交渉は保険会社が本人に代わって行います。
しかし、自分の過失が0%のもらい事故のケースなどでは、法律で保険会社が交渉できないことになっています。自分で加害者や加害者の保険会社と直接交渉することになりますが、その場合に弁護士に交渉を依頼することは可能です。
相手側から提示された賠償額は妥当なのか、法律のプロでないとなかなか判断も難しいでしょう。弁護士に交渉を依頼すれば、自分の意向を最大限に汲んだ形で賠償金請求をしてもらえるので効率的です。
弁護士費用特約を使う事故の場合も、ノーカウント事故として扱われます。
個人賠償責任特約は、自動車事故以外で日常生活において他人にケガをさせた、他人の物を壊した場合などに損害を補償する特約です。
具体例としては飼い犬が他人に噛みついた、子供が振り回した物が他人に当たってケガを負わせた、などが当てはまります。さらに、お店の商品を誤って破損した、キャッチボールをしていて他人の家の窓ガラスを割ってしまったケースも該当します。
個人賠償責任特約で保険金を請求した場合も、ノーカウント事故と判断されます。
ノーカウント事故に該当する特約事故は、各保険会社によって違ってきます。
前述した代表的なものの他にも「自転車障害特約事故」などが当てはまります。これは、自分や家族が自転車で走行中に転んだり、歩いていたら自転車にぶつかってケガを負ったりした場合などに補償してくれる特約事故です。
また、ロードアシスタント特約を使う場合も該当します。これは、事故や故障により車が自走できない場合、保険会社のスタッフが事故現場でサポートやレッカー手配などをしてくれるものです。
どういった場合にノーカウント事故に含まれるか、加入している自動車保険の内容を確認しておきましょう。
1等級ダウン事故について

自動車保険の等級は、事故などで保険を使わなければ翌年1等級上がります。しかし、事故などで保険を使うと等級が下がります。
等級が下がる事故の中でも、1等級だけ下がる事故が1等級ダウン事故です。1等級ダウン事故は、自分の車に発生した損害を補償する「車両保険」と事故により車内に積んでいたものに発生した損害を補償する「車内身の回り品補償特約」の一方のみ、もしくは両方を使う事故やトラブルが当てはまります。
ここからは、1等級ダウン事故の例を詳しく紹介していきます。
交通事故に遭遇しなくても、台風や高潮、津波や洪水などの自然災害により車が破損したり水没したりで使えなくなってしまったりするケースもあります。また、火災や爆発などで車が燃えた、吹き飛んでしまったということもあるでしょう。
この場合、何も補償がなければ全て自己負担で修理、買い替えをしなければなりません。そうなると経済的負担が大きいでしょう。そこで、車両保険に加入することで損害をカバーすることができます。
自然災害や火災などで車両保険を使うと、翌年の保険契約では1等級ダウンすることになります。
車が盗まれる犯罪の被害に遭った場合、車両保険や車内身の回り品特約をつけていれば、車両損害額や車内に積載していた物の損害額が支払われます。
盗難の場合は、まずは警察に被害の届け出をしなければなりません。被害届の受理番号を聞いて、保険会社に連絡します。盗難の実態調査が必要なため、調査員が実際に被害現場を訪れるでしょう。調査結果が出るまで、1~2ヶ月を要します。
最終的に車両保険を使うと保険金が下りますが、1等級ダウンとなります。
車を運転中に飛んできた物が車にぶつかって、傷がついてしまうというトラブルもよくあります。
例えば、飛び石が車に当たりフロントガラスにヒビが入る、前車のトラックから木材が落下して車にぶつかり、バンパーが凹むといったケースです。
走行中の飛来物や落下物による車の損傷に関しては、車両保険でカバーできることが多いです。
こういったケースで車両保険を使い、車を修理すると翌年1等級ダウンとなります。
駐車中の車のボディに釘のようなものでひっかいた傷をつけられる、マジックで落書きをされるといったイタズラの被害に遭うケースもあります。
このようなイタズラは「器物損壊罪」という犯罪に該当します。警察に被害を届けて犯人を見つけてもらう必要がありますが、なかなか見つからないと相手への賠償も請求できません。
イタズラで車が傷ついて修理する場合、車両保険を使えば修理費はカバーされます。しかし、自分のミスでなくても、車両保険を使えば1等級ダウン事故となるので気を付けましょう。
3等級ダウン事故について

自動車事故のうち、翌年に3等級下がる事故が3等級ダウン事故です。これは、1等級ダウン事故とノーカウント事故以外の事故が当てはまります。
ここからは、3等級ダウン事故の例を詳しく紹介していきます。
交通事故を起こして相手が亡くなった、もしくはケガや後遺障害を負った場合の損害を補償してくれるのが、自動車保険の対人賠償責任保険です。
通常、強制保険である自賠責保険では相手方の身体への損害に対する補償をカバーします。ただし、自賠責保険の賠償額には上限があり、高額になった場合は全額をカバーできません。こういったケースでは、不足分を自動車保険の対人賠償責任保険で補うことが可能です。
対人賠償責任保険を使い保険金が下りた事故は3等級ダウン事故として扱われるので、翌年の保険契約から等級が3つ下がります。
車に衝突や追突して事故の相手方の車を破損させたり、他人の家の壁やガードレールなどを損壊したりという事故はよく起こります。
こういった物損事故の場合、自動車保険の対物賠償責任保険により修理費用が補償されます。
また、自分で家の塀にぶつかり車が凹んでしまったなど、相手のいない単独事故の場合は、車両保険で修理費をカバーすることも可能です。
ただし、対物賠償責任保険や単独事故の車両保険を使う場合は、3等級ダウン事故に該当するので、翌年3つ等級が下がることになります。
交通事故が起こったけれど事故の相手方が現場から逃走して行方が分からない、駐車中の車にぶつけられたなどの当て逃げの被害に遭遇するケースもあります。
本来であれば事故の相手方と示談交渉をし、過失の割合などに応じて補償額が決まります。ただし相手が分からないと交渉が進まないため、車を修理しても費用が支払われないことになるでしょう。
こういった当て逃げのケースも、車両保険のタイプによっては修理費用がカバーされることがあります。しかし、当て逃げで車両保険を使う場合、3等級ダウン事故となるので注意が必要です。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
等級ダウンにプラスして保険料が上がる

事故を起こして自動車保険を使うと、1等級ダウンもしくは3等級ダウン事故の場合は翌年から等級が下がります。保険料の割引率が低くなるので、保険料の金額が上がります。
ただし、事故を起こして保険を使った場合、「事故有係数」という保険の割増率を適用することになっています。つまり、同じ10等級でも無事故で前年の9等級から1等級上がったケースと事故で等級が1等級もしくは3等級下がって10等級になった場合とでは、保険料が違ってくるということです。
無事故の場合は無事故係数が、事故を起こして保険を使った場合は事故有係数が適用されます。例えば、16等級の場合無事故係数は-54%、事故有係数は-32%であった場合、無事故の場合は保険料が54%割引、事故有の場合は保険料が32%割引になるということです。
事故有係数適用期間について

自動車保険で同じ等級であっても、無事故の状態と事故有の状態では適用される保険料の割増率が異なります。いつまで事故有の係数が適用されるかは決められていて、その適用期間を事故有係数適用期間と呼びます。
事故有係数適用期間は1等級ダウン事故、3等級ダウン事故によって違ってくるので気を付けましょう。また、事故有係数の適用期間は上限6年までと決まっています。
ここからは、1等級ダウン事故、3等級ダウン事故の事故有係数適用期間について詳しく説明していきます。
1等級ダウン事故の場合、事故有係数適用期間は1年間となります。
例えば、無事故係数が適用されている10等級の年に1等級ダウン事故を起こすと、翌年は9等級になり事故有係数が1年間適用されます。その後、無事故で保険を使うことなく1年間を過ごせば、翌年に等級が1つ上がり、10等級に戻った上に無事故係数が再び適用となるのです。
つまり、1年間我慢すれば事故の2年後には、事故前と同じ状態に戻るということになります。
3等級ダウン事故を起こした場合、事故有係数適用期間は3年間となっています。
例えば、無事故係数適用で15等級の年に3等級ダウン事故を起こしたとしましょう。その場合、翌年は3等級下がって12等級になった上に事故有係数が適用されます。
無事故で過ごしてその翌年に等級が13等級に上がっても、事故有係数の適用が続きます。その後、無事故で過ごしてさらにその翌年14等級になっても、同じく事故有係数適用期間が継続されます。そして無事故で保険を使わないまま事故から4年後にやっと15等級に戻り、無事故係数が適用されることになります。
保険を使うかは慎重に検討しよう
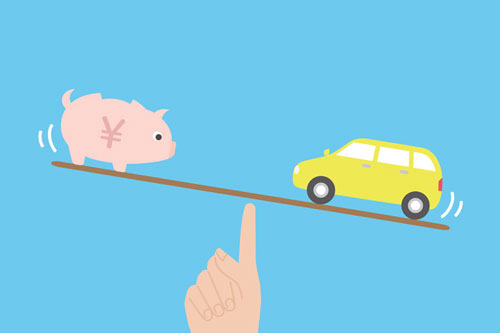
自動車保険を使うと、事故によっては等級が下がってしまう場合があります。さらに事故有係数が設定されているので、保険を使う前に比べると支払う保険料が数年は増額となってしまう可能性もあるでしょう。
事故の相手方から請求された損害賠償額や自分の車の修理代などがかなり高額になる場合は、自動車保険の補償があると負担が軽減されます。ただ、保険を使うと保険料が上がるため、場合によっては損するかもしれません。
事故による損害の補填額と増額となる保険料を比較し、どちらが高額になるかによって保険を使うかを慎重に判断することが大事です。








