自動車保険の契約形態には、フリート契約とノンフリート契約の2タイプがあります。
フリート契約とノンフリート契約は、契約する台数によってどちらで契約するかが変わってきます。また、契約内容や保険料などにも違いがあります。
この記事では、フリート契約とノンフリート契約の違いについて詳しく説明していきます。
また、フリート契約からノンフリート契約、ノンフリート契約からフリート契約に変更する場合の注意点についても紹介しますので、参考にしてください。
フリート契約とノンフリート契約の違いは契約台数
フリート契約とノンフリート契約の違いは、契約台数です。もし10台以上の自動車を所有・使用していて契約する場合には、自動的にフリート契約になります。一方、契約する車の台数が9台以下であればノンフリート契約扱いです。
10台以上の車を個人で所有することはほとんどないため、フリート契約は法人向けの商品と言えます。
ちなみにフリートとは英語で「Fleet」と書きます。日本語に訳すと「複数の船隊」という意味を持つ英単語なので、ノンフリートとは船隊ではないという意味になります。
自動車保険を販売しているのは損害保険です。損害保険は海上保険が始まりだったので、その名残としてフリートという言葉を使っているのかもしれません。
10台以上の車を契約する場合には自動的にフリート契約

フリート契約とノンフリート契約は、契約者が選べるものではありません。契約者の所有・使用している自動車が10台以上あり、自動車保険に加入する際には例外なくフリート契約になります。
ちなみに5台をAという保険会社、もう5台をBという保険会社で契約した場合でもフリート契約扱いになります。所有・使用自動車が10台以上あれば契約先に関係なくフリート契約になるので、振り分けを行っても意味はありません。
所有・使用自動車は、どのようなものかというと、まず契約者が所有権を持っていて、自分で運転している場合が該当します。その他にもリース業者から1年以上の期間の貸借契約で借り入れていて、自分で運転しているようなリースカーも所有・使用自動車扱いになります。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自動車保険は車の所有者もしくは使用者と契約する

フリート契約の特徴として見逃せないのが、契約相手です。フリート契約は所有者もしくは使用者と契約する形を取っています。
前述しましたが、フリート契約は10台以上の車を所有している方が保険に加入する場合に適用されます。これだけの台数を保有するのは、法人である場合がほとんどでしょう。そのため、フリート契約の契約当事者は所有者である法人もしくは車の使用者たる経営者ということになります。
ノンフリート契約の場合は、車両との契約なので、この点が大きな違いの一つです。
例えば、フリート契約を交わした後でもう1台保有車を追加するとします。この場合、すでに交わしているフリート契約と全く同じ条件で保険に加入できるというわけです。
事業所はフリート契約がおすすめ

フリート契約は、契約者単位で加入する自動車保険です。そのため、保有する車両の保険満期日はすべて一緒になります。
前述しましたが、ノンフリート契約の場合は車両単位の契約となります。もし加入する時期が異なると、車両によって満期日はまちまちです。すると、うっかり更新手続きを忘れてしまい、保険から外れてしまう事態も起こりえます。
しかし、フリート契約の場合、すべて同じ満期日なので更新を忘れるリスクは低いでしょう。
また、車両を変更する際、ノンフリート契約の場合は車両入替の手続きを行う必要があります。一方、フリート契約の場合は車を乗り換えても車両入替の手続きは必要ありません。
もし保険未加入の社用車で事故を起こした場合、会社が全責任を負うことになります。そのようなリスクを考えると、フリート契約のほうが安心です。
フリート契約とノンフリート契約の割引について

フリート契約とノンフリート契約には違いがいくつかありますが、その中の一つが今回紹介する保険料です。
フリートもノンフリートも保険料の割引制度があります。しかし、ノンフリートでよく知られる等級は、フリート契約にはありません。
ここからは、保険料の仕組みがどう違うのか詳しく見ていきましょう。
フリート契約とノンフリート契約の保険料の違いとして、料金を決めるベースが挙げられます。
ノンフリート契約の場合、等級制度が適用されます。無事故なら1年間で1等級上がり、事故を起こして保険を使うと翌年度の等級が下がる仕組みです。そのため、契約車両が1年間で何回事故を起こしたかが翌年度の保険料に反映されます。
一方、フリート契約の場合、契約している全車両の事故に伴う支払保険額の総額がベースになります。例えば、1台事故を起こして保険を使ったとします。この場合、契約している全車両の翌年度の保険料が値上がりしてしまう仕組みです。
ノンフリート契約とフリート契約では、契約単位も異なります。
ノンフリート契約の場合、契約単位は自動車1台単位です。車両単位で契約するので、保険料も車両それぞれで金額が変わってきます。
一方、フリート契約の場合は契約者単位となり、全車両共通の割引が適用されます。ここが大きな違いです。
ノンフリートでは、等級というオリジナルのシステムを採用しています。同じ過程で保有している車両でも事故件数や加入時期で、等級が異なり、割引率も違ってくることが珍しくありません。
しかし、フリート契約であれば、車両関係なくすべて一律で同じ割引率が適用されます。
多数割引とは、一つの契約で自動車を複数保有している場合に適用される割引のことです。これは、フリート契約もノンフリート契約も適用されます。ただし、どの程度の割引になるかはそれぞれで異なります。
フリート契約の場合は、一律で同じ多数割引が適用され、割引率は5%です。
一方、ノンフリート契約の場合は、保険会社によって割引率は異なります。また、同じ保険会社でも保有している台数によって、割引率が違ってくるので注意が必要です。
もし少しでも保険料の負担を軽減したければ、複数の保険会社で見積もりを取って比較検討するのがおすすめです。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
フリート契約とノンフリート契約の切り替えについて

今後、契約している車両の台数が変わってくる場合もあるでしょう。今までフリート契約だったのがノンフリート契約、逆にこれまでノンフリート契約だったのがフリート契約に移行する場合もあります。
このように契約が切り替わる際、何か手続きが必要なのか気になる方もいるかもしれません。フリートからノンフリート、ノンフリートからフリートどちらに切り替わるかによって手続きが異なるので、ここで詳しく見ていきましょう。
これまで10台以上の車を保有してきたが、車両を売却するなどして9台以下になった場合、フリート契約ではなくなります。しかし、10台以上だったものが9台以下になった時点で、即ノンフリート契約に移行はしません。
フリート契約には猶予期間が設けられています。次回の保険の満期までにまた車を保有して10台以上になれば、フリート契約のままで契約更新は可能です。
しかし、満期日に9台以下だった場合は、ノンフリート契約に新たに加入することになります。
ノンフリート契約になると、これまでとは異なる保険料になる可能性が高くなります。フリート契約の場合、一律の保険料が適用されますが、ノンフリートの場合は、車両ごとに保険料が算出されます。
これまで保有する台数が9台以下でノンフリート契約だったのが、新たに車を購入して10台以上になるとフリート契約に切り替わります。
ここで注意してほしいのが、通販型自動車保険に加入している場合です。ネットで全ての手続きが完了する通販型の自動車保険では、フリート契約を取り扱っていない場合がほとんどです。そうなると今加入している保険会社で契約ができなくなります。つまり、自動車保険の乗り換えが必要になります。
フリート契約に対応している保険会社の補償内容などを比較して、加入先を決めなければなりません。
代理店が他の保険会社であれば、フリート契約も取り扱っているところも多いです。この場合、保険会社に連絡すれば切り替え手続きに関する案内があるはずなので、その指示に従ってください。
ノンフリート契約で新規加入する場合、6等級からのスタートになりますが、フリート契約ですでに加入している場合、これまでの実績をベースにして適用される等級を個別に決める形となります。
一般的には、フリート契約における割引料率や等級料率に照らし合わせて決めていきます。て、フリート契約の条件に最も近い等級を当てはめます。
これまで無事故を続けてきたのであれば、6等級よりもかなり上の等級を適用される可能性も高いです。しかし、もし事故を起こして料率が下がっていると、等級も低くなる恐れがありますので注意してください。
フリート契約がおすすめの人・ノンフリート契約がおすすめの人
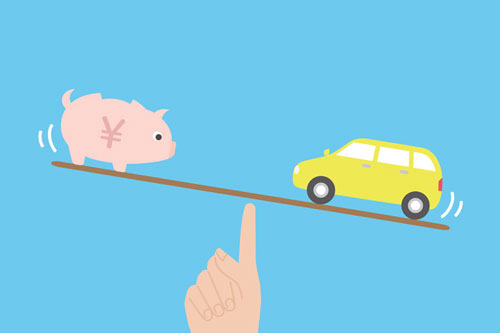
フリート契約とノンフリート契約では割引のシステムなど、異なる点がいろいろとあります。そのため、契約者の条件によっておすすめな契約形態も変わってきます。
自分はフリート契約とノンフリート契約、どちらがおすすめなのか以下にまとめました。適性も踏まえて、保有する車両台数を調整するといいでしょう。
保険料を何よりも重視しているのであれば、フリート契約をおすすめします。なぜなら、フリート契約のほうがノンフリート契約よりも割引率が大きいからです。
ノンフリート契約の場合、最高は20等級になります。20等級だった場合、保険料の割引率は63%です。一方、フリート契約の場合、最大の割引率は80%程度と言われています。
ノンフリート契約と比較して、10%以上差があります。そのため、とにかく保険料の負担を少しでも軽減したいと思っているのであれば、10台以上車両を保有してフリート契約するのがおすすめです。
ただし、事故を起こさないことが前提であることは理解しておきましょう。
サービス内容を重視するのであれば、ノンフリート契約のほうがおすすめです。ノンフリート契約では独自性を出すために、各保険会社でいろいろなサービスを提供しています。
例えば特約です。日常生活賠償特約(個人賠償責任特約)やファミリーバイク特約といった、車とは関係ないところまでケアしてくれる特約も近年出てきています。
また、ノンフリート契約の場合は年齢制限を付けることも可能です。一定の年齢以上の人が運転するように範囲を決めて契約にすれば、保険料を安くできます。法人の中に若手がおらず、ベテランだけがハンドルを握るような会社もあるでしょう。もし車を運転する従業員が全員35歳以上であれば、年齢条件を付けることで保険料がお得になる可能性もあります。
「自分はフリート契約向きだけれども、そのために新規で車両を購入するのはちょっと…」と思った方もいるかもしれません。その場合におすすめなのが、原付を購入する方法です。
フリート契約は、自動車のみが対象ではありません。原付も補償の対象で、1台とカウントできます。原付であれば、安いものだと10万円程度で購入できるでしょう。車1台購入するのと比較すれば、コストを圧縮できるはずです。
さらに、原付を購入すると減価償却扱いで損金として処理できます。節税効果を最大限にするために会社の経営状況をベースにして、購入する価格を検討しましょう。どの原付を購入するのがより大きな税金対策になるかは、税理士に相談するのがおすすめです。
法人向け自動車保険の選び方のポイント

法人で自動車を保有していて自動車保険に加入する場合、何を重視すればいいのでしょう?
ここからは、保有台数が9台以下のノンフリート契約、10台以上のフリート契約に分けて、保険の選び方のポイントについてまとめました。
また、補償内容についても十分検討が必要です。保険料を安くするあまり、必要な補償を外すことのないように注意してください。
9台以下の社用車を保有する場合は、ノンフリート契約となります。この場合、特約などのサービスがどうなっているか比較してください。
保険会社では差別化を図るため、オリジナルの特約を販売しているところも少なくありません。自分たちにとって重宝する特約がラインナップされているか、チェックしてましょう。
また、年齢条件などを付けられるかどうかも重要なポイントです。35歳以上の年齢条件を付けられるのであれば、割引が適用されて保険料がお得になる可能性もあります。
家族で従事している会社もあるでしょう。もし従業員が家族だけで車を運転するのも家族だけなら、運転者の範囲を家族のみと制限すれば保険料は割引されます。
フリート契約で自動車保険に加入する場合、サービス内容で比較してみるといいでしょう。保険会社の中には、フリート契約ならではのサポートをしているところもあります。
例えば、ドライブレコーダーの無料レンタルや従業員管理のためのアプリの提供などです。後者のアプリは、従業員のストレスや睡眠状況なども管理できるようなものも出てきています。
さらに、車両管理台帳の作成を代行する保険会社も見られます。運送業を営んでいる場合、台帳の作成を保険会社に任せられるので自分たちの労力を軽減できるのがメリットです。
このような付帯サービスを見て、利便性の高い保険会社はどこかという視点で比較するのも一考です。
ノンフリート・フリート契約関係なく、補償内容をどうするかはしっかり検討してください。保険料を安くしようとするあまり、肝心の補償が使えなければ元も子もありません。
特に対人賠償保険と対物賠償保険は無制限にしておきましょう。対人と対物は実際に賠償金請求されるとなると、高額になる恐れがあります。
例えば、人をはねて相手が死亡した場合、高額の賠償金を請求されます。また、事故で商店やバスなどの商用の車両に突っ込んで壊してしまった場合、お店を開けられない間の利益補償をしなければなりません。
いずれも、場合によっては賠償金が1億円を超える可能性もあります。そうなると、無制限で補償してもらえたほうが安心です。







