結婚後に苗字が変わると様々な手続きが必要となります。自動車保険における名義人の苗字変更手続きも、その一つです。
この記事では、その手続きの方法や苗字変更をしないとどうなるかなどを詳しく解説していきます。
さらに、結婚後は夫婦で所有する車を減らすもしくは増やすタイミングでもあります。保険料を上手に抑える方法や保険内容を見直すポイントなども紹介するので、参考にしてください。
自動車保険の名義
自動車保険には3つの名義が存在します。どのような名義があるのか理解しておくと、誰を名義人にするか決める際や名義を変更する際などに役立つでしょう。
1つ目は、保険契約者です。自動車保険を契約し、保険料の支払いを行う人のことです。事故で受けた損害を補償してもらうために保険金請求を行う場合は、契約者の同意が必要となります。
2つ目は、記名被保険者です。自動車保険の契約車両を主に運転する人のことです。自動車保険の補償の中心となり、契約内容によっては記名被保険者を中心に、その配偶者や同居の親族などが補償の対象となる場合もあります。記名被保険者は、契約者と同一である必要はありません。
3つ目は、車両所有者です。自動車保険の契約車両を所有している人のことです。車検証の所有者と同一ですが、ローンで車を購入した場合はローン会社などが所有者となり、車を実際に使う人が使用者となっています。
自動車保険の名義変更について

自動車保険を契約中に名義変更の手続きをしなければならないケースがあります。例えば、売買や譲渡などで車の所有者が変わった場合や結婚により苗字が変わった場合などです。
また、保険の契約者や記名被保険者が亡くなった場合、子供が就職して親が払っていた保険料を支払うようになった場合など、保険料を支払う人が変わった場合も含まれます。
他にも、親が使っていた車を免許を取得した子供が運転するようになった場合など、主となる運転者つまり記名被保険者が変更となった場合も名義変更が必要です。
自動車保険で苗字変更の手続きをする場合は、まずは加入している保険会社のコールセンターに電話をして手続きを進めましょう。
連絡先が分からない場合は、保険証券に代理店の連絡先が記載されている場合が多いので確認してみてください。また、保険会社のホームページを検索すれば連絡先がのっています。
通販型自動車保険の場合、ネットから加入や更新の手続きができますが、改性の手続きも可能な場合が多いので試してみましょう。
苗字を変更する際は、保険会社のコールセンターなどに連絡すると後日「自動車保険移動承認請求書」といった必要書類が郵送されてきます。
そして、戸籍抄本や住民票、運転免許証のコピーといった苗字の変更が公的に証明されている書類を準備しましょう。
必要書類に署名捺印し、公的証明書を添付して返送すれば手続きが完了となります。
保険会社によっては、書類への署名や捺印が省略される場合があるなど対応が異なることもあるので、確認しておくと良いでしょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
苗字変更をしない場合のデメリット
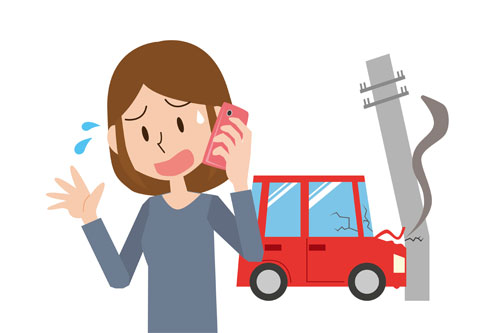
結婚して公的に苗字が変わったのに、自動車保険の苗字変更手続きをしなかったらどうなるのでしょう?
交通事故に遭遇して保険を使うか、保険が満期となって更新するまで苗字変更の必要性に気づかずに忘れていたというケースも少なくありません。
苗字変更せずに保険金請求をした場合、苗字が旧姓のままでも保険の補償対象者だと確認できれば保険金は支払われます。しかし、苗字変更手続きをしていないと確認に手間がかかり、保険金支払いまでに時間が通常よりもかかってしまうことが一般的です。
結婚して車の所有台数が減る場合の自動車保険について

結婚を機に車の所有台数が変わるケースもあります。
例えば、夫婦どちらかが仕事を辞める、引っ越して電車通勤になるなど車が1台不要となることもあります。
車は所有しているだけでも税金などの維持費がかかるため、不便でなければ1台を手放すほうがお得です。車を1台にするということは、自動車保険も1契約解約となるでしょう。
ここで夫婦どちらの保険を解約するかということが、実は保険料を損しないためにも重要になってきます。
夫婦それぞれ1台ずつ所有していた車を結婚後に1台に減らす場合、自動車保険の等級に着目しましょう。等級が高いほうが当然保険料の割引率が高いので、保険料を支払う上でもお得です。
等級は、記名被保険者の配偶者は引き継ぐことができます。
例えば、夫が普通車を、妻が軽自動車を乗っていて妻の軽自動車が不要になるとします。自動車保険の等級は夫のほうが低く、解約すべき妻のほうが高かった場合、妻の保険の等級を夫に引き継ぐことは可能です。
つまり、普通車にかける自動車保険の等級を高くすることで保険料の割引率も高くなるので、結果的に保険料が安く収まり家計の負担も軽くなります。
自動車保険の記名被保険者となるのは、契約車両を主として運転する人でなければなりません。
例えば、妻が電車通勤で夫が車通勤をする場合は、運転頻度が高い夫が記名被保険者となります。
保険料は、記名被保険者の年齢などによって変わってきます。たとえ妻を記名被保険者としたほうが保険料は安くても、夫が運転頻度が高い場合、記名被保険者は夫にしなければなりません。
この内容を偽ると告知義務違反となり、強制解約の対象となる場合もあるので、注意しましょう。
夫婦で車を1台にする場合、自動車保険も1つ解約することになります。等級が高いほうを選んで等級を引き継ぐにしても、どちらもある程度等級が高いケースもあるでしょう。
自動車保険は無事故で保険を使わずに等級を積み重ねていても、一度解約してしまえば等級は消滅します。もし今後もう1台車が必要となり、再度新規で保険に加入したら、6等級からのスタートとなってしまいます。そのため、解約してしまうと積み上げてきた等級は無駄になってしまいます。
そうならないように、「中断証明書」を発行しておくことをおすすめします。中断証明書は、自動車保険を解約しても、解約時の等級を最大で10年間は保存できるというシステムです。
10年以内にもう1台車を所有する可能性があるなら、中断証明書を取得しておけば解約時の等級で再度自動車保険をスタートできるので、保険料の節約にもつながります。
結婚後の自動車保険の内容の見直しについて

結婚後は自動車保険の苗字変更の手続きが必要となります。いい機会なので、一緒に自動車保険の内容を見直してみましょう。
夫婦で車を乗るにしても、夫か妻かどちらかが車を運転するにしても、万一の事故の際に補償できちんとカバーされる設定となっているかチェックすることが大事です。
また、あまり必要のない補償がついていないかなどを確認することで、保険料を抑えられるかもしれません。
家族ができて自動車保険を見直す際に重要となるのが、運転者の範囲です。
夫婦それぞれ1台ずつ車を所有している場合、お互いに普段あまり運転しない車を運転する機会もあるかもしれません。そういった時にもし運転者の範囲が本人限定になっていると、配偶者が運転中に万一交通事故を起こしても保険が使えなくなってしまいます。
結婚後は配偶者限定や家族限定にしておくと、配偶者や同居の家族が運転した場合でも保険が使えるので安心です。
結婚後の自動車保険は、運転者の年齢の条件にも着目しなければなりません。
自動車保険では、若い人は運転歴が浅いため運転技術が未熟だとされています。そのため、事故のリスクが高く、保険料もやや高めに設定されています。
一般的には、年齢区分は4つに分けられていることが多いです。年齢を問わない全年齢補償の保険料が一番高く、次いで21歳以上、26歳以上、そして30歳以上が一番安いです。
また、記名被保険者は26歳以上という年齢区分がさらに6つに分けられています。30歳未満、30歳以上40歳未満、40歳以上50歳未満、50歳以上60歳未満、60歳以上70歳未満、70歳以上と区分があり、保険料にも差が生じます。
例えば、夫が28歳で妻が24歳の場合、年齢条件の区分を26歳以上にしていると妻は補償対象外となってしまうため、年齢条件を21歳以上に変更しなければなりません。
結婚すると、子育てや老後の生活の備えについても考えなければなりません。そこで、万一の事故の際にどの位の保険金を受け取ることができるかも、改めて見直しておく必要があります。
保険の内容によっては損害分を全て補償してもらえない場合もあり、保険でカバーされない分は自己負担となります。
また、大黒柱が交通事故でケガを負って仕事ができなくなると、収入が途絶えて家族を養えなくなるという家庭もあるでしょう。そうなると、日々の暮らしが困ってしまいます。万一の場合に備えて、保険金の設定はやや多めに、保険は手厚くしておく必要もあるでしょう。
交通事故による損害で収入が減っても、どの位の保険金があれば暮らせるかを想定し、補償額を設定することが大事です。
加入している保険の中で補償が重複している場合もあるため、確認しましょう。
例えば、人身傷害保険では、契約車両を運転中のみの事故によるケガなどを補償するタイプと契約車両以外の車を運転中もしくは歩行中の自動車事故によるケガなどを補償するタイプがあります。
夫婦で1台ずつ車を所有する場合、2台とも後者のタイプにすると補償が重複し、補償範囲が広いので保険料も高くつきます。そのため、2台目の車は前者のタイプにしておくと、保険料も抑えられるのでお得です。
また、付帯している特約もチェックしておきましょう。
例えば、日常生活におけるトラブルにより、他者の身体や物に損害を与えた場合の補償となる個人賠償責任特約は、契約者と同居の親族まで補償対象となっています。そのため、1台分の保険のみ付帯させておけば問題ありません。
特約が重複していると、その分保険料が加算されるので、保険内容を見直して無駄になるものは整理しておくことをおすすめします。
夫婦2人の自動車保険だけでなく、それぞれの実家の自動車保険についても見直しておくといいでしょう。それは、実家の両親が加入している自動車保険が、家族限定になっている場合があるからです。
例えば、結婚して実家を離れることになったとします。実家が両親の2人暮らしになる場合、実家の車を運転するのが夫婦2人のみになるなら家族限定から夫婦限定に変更することで、保険料を抑えることも可能です。
ただ、結婚後も実家の車を運転する場合は、家族限定のままで良いと思うかもしれません。しかし、家族限定の補償対象は未婚の子なので、既婚となれば親の車を運転して事故を起こしても補償されなくなります。その点は、気を付けましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
保険会社を同一にするメリット

夫婦でそれぞれ車を1台ずつ所有して使う場合は、自動車保険会社を同じ所にすると、割引の適用などで保険料がお得になる場合が多いです。
例えば、2台以上の自動車保険を1つの保険証券にまとめて契約する「ノンフリート多数割引」が利用できます。この割引を適用している保険会社では、2台で保険料が1~3%、金額でいうと600円~1,000円くらい安くなります。
契約者を夫婦どちらか一人に決める必要はありますが、記名被保険者はそれぞれ夫もしくは妻と違っても問題ありません。契約台数が増えれば、さらに割引率も高くなるのです。
また、保険会社は必ずしも同一でなくても良いですが、2台目の車の等級が通常より1等級上からのスタートとなる「セカンドカー割引」も使えます。
さらに、夫婦で等級を入れ替えることも可能です。そして、保険の更新手続きなども1社にすれば効率よく進められるなどのメリットもあると言えるでしょう。
結婚後に車を夫婦で1台ずつ所有する場合、セカンドカー割引を使うと保険料がお得になります。
例えば、夫の居住地に妻が引っ越し、新たに車を所有して自動車保険に新規加入するとします。本来ならば6等級からスタートする所ですが、セカンドカー割引を使えば1つ高い7等級から保険をスタートできます。
6等級と7等級では割引率が11%も違ってくるので、保険料の節約になるでしょう。
夫が加入している保険会社と同一にすると手続きが効率的ですが、セカンドカー割引は夫と同じ保険会社でなくても適用可能です。
ただし、セカンドカー割引を使うには1台目が11等級以上であることなどの条件があるので、適用できるか確認しておきましょう。
自動車保険では、夫婦間で等級の入れ替えを行うことが可能です。
例えば、夫が使用している1台目の車の自動車保険が15等級で、新たに妻が2台目の車を所有して自動車保険に加入するとします。その場合、2台目はセカンドカー割引を使えば、7等級からのスタートとなります。そして、1台目の自動車保険の15等級と2台目の7等級を入れ替えることも可能です。
つまり、セカンドカー割引と車両入替を同時に行うということです。
年齢が若いと事故のリスクが高いとみなされ、保険料は高くなります。夫が30歳で妻が24歳とすると、妻のほうが自動車保険の年齢条件で見ると保険料が高くなるので、より割引率が高い15等級の保険(夫の等級)にしたほうがお得になります。
夫婦に年齢差があり、等級の高い人が年上の場合は、保険料を抑えるために有効的な方法だと言えます。
自動車保険には様々な割引制度がありますが、その一つが「ゴールド免許割引」です。
ゴールド免許保有者が保険の記名被保険者となると、保険料が10%位割引になります。
また、運転者の年齢によって保険料も異なってくるため、年齢が高い人を記名被保険者にすると保険料を抑えることできます。
保険をまとめる時の手順

夫婦で別々の保険会社に加入していて、それを1つにまとめることは可能ですが、手順があるので確認しておきましょう。
まずは、どちらかの保険の満期日に合わせて、一方の保険の解約手続きをします。この場合、等級の低いほうの保険の満期日に合わせると損が少なくて済むのでおすすめです。
自動車保険は、無事故もしくはノーカウント事故で保険を使わなければ、満期後は1等級上がります。等級が低い保険を満期日で解約すれば、1等級上がった状態で新しい保険に加入することになり、保険料の割引率が高くなります。
等級が高い保険は元から保険料の割引率も高く、1等級上がってもさほど大きな割引にならないかもしれません。そのため、低いほうの等級を上げたほうが全体の保険料が抑えられると言えるでしょう。
1つの保険を解約できたら、加入中の自動車保険の保険会社に連絡して満期日に保険をまとめる旨を伝えれば、手続きしてもらえます。








