自動車保険の保険料は、何等級なのかによって変わってきます。そのため、最高等級になれば最初の契約時よりも割引率が大きくなります。
では、どうすれば最高等級になり、保険料を抑えることができるのでしょう?その等級の仕組みも含めて解説します。
自動車保険の等級

自動車保険での等級は、正式には「ノンフリート等級別料率制度」という名称です。
ノンフリート等級別料率制度とは、契約者の車の所有台数が他社も含めて9台以下の場合に適用されます。
そして、契約者の事故の有無や事故内容によってリスクを1~20等級(22等級までの共済もある)に区分けしています。それによって保険料の割引率が変わるため、保険料が高くなったり低くなったりします。
自動車保険を初めて契約する時は6等級からのスタートです。そこから無事故で1年間を過ごせば等級は上がり、逆に事故により自動車保険を使用した場合は等級が下がることになります。
20等級になると保険料の割引率の上限に達するため、これ以上割引率が高くなることはありません。
無事故か事故ありかによって、同じ等級だったとしても割引率が変わってきます。
事故を起こし、自動車保険を使用すると翌年から「事故有係数適用期間」が適用されます。加算される期間は1等級ダウン事故の場合には1年、3等級ダウン事故の場合には3年です。
等級によって保険料の割引率は変わりますが、さらに事故あり/事故なしかでも割引率は異なります。
最高等級とそれ以外の等級の割引率を知ると、事故を起こさず等級を上げていこうと思えるでしょう。
以下は、各等級の割引率です。
| 等級 | 無事故 | 事故あり |
|---|---|---|
| 20等級 | 63%割引 | 51%割引 |
| 19等級 | 57%割引 | 50%割引 |
| 18等級 | 56%割引 | 46%割引 |
| 17等級 | 55%割引 | 44%割引 |
| 16等級 | 54%割引 | 32%割引 |
| 15等級 | 53%割引 | 28%割引 |
| 14等級 | 52%割引 | 25%割引 |
| 13等級 | 51%割引 | 24%割引 |
| 12等級 | 50%割引 | 22%割引 |
| 11等級 | 48%割引 | 20%割引 |
| 10等級 | 46%割引 | 19%割引 |
| 9等級 | 44%割引 | 18%割引 |
| 8等級 | 38%割引 | 15%割引 |
| 7等級 | 27%割引 | 14%割引 |
| 6等級 契約開始時の等級 | 13%割引 | |
| 5等級 | 2%割引 | |
| 4等級 | 7%割増 | |
| 3等級 | 38%割増 | |
| 2等級 | 63%割増 | |
| 1等級 | 108%割増 | |
6等級以下は無事故と事故ありの区別はありません。また、4等級以下は割引率ではなく割増率となります。
上記で紹介した各等級の割引率については、保険会社によって多少異なることもありますので確認しておきましょう。
最高等級で事故を起こした場合

無事に20等級まで到達したとしても、自分が事故を起こしてしまったり、自分起因ではない事故に遭ってしまったりする可能性もあります。
その場合、等級はどうなるのか以下で詳しく見ていきましょう。
3等級ダウン事故は、相手が死亡したり、負傷したりした場合に使用される対人賠償保険、相手の車や物を破損した場合の対物賠償保険、自分が契約している車が破損した場合に使用する車両保険のどれかを使った場合の事故のことです。
翌年から等級が3つ下がるのに加えて、事故ありでの割引率が3年間適用されます。
最高等級から3等級ダウン事故を起こした翌年からの等級と、保険料の割引率の変動は以下の通りです。
・事故なし20等級から事故あり17等級にダウン
・事故あり17等級の場合は44%割引
(事故なし17等級の場合は55%割引)
・事故あり18等級になり、46%割引
(事故なし18等級の場合は56%割引)
・事故あり19等級になり、50%割引
(事故なし19等級の場合は57%割引)
・事故なし20等級に戻り、63%割引
3等級ダウン事故に該当するのは下記のような場合です。
- 当て逃げに遭う
- 車同士の接触、衝突
- 車庫、電柱、ガードレールなどへの接触や衝突(単独事故)
- 歩行者を轢くなどで負傷させる
- その他転覆、墜落
1等級ダウン事故により車両保険を使用した場合、翌年から等級が1つ下がるのに加えて、事故ありでの割引率が1年間適用されます。
最高等級から1等級ダウン事故を起こした翌年からの等級と、保険料の割引率の変動は以下の通りです。
・事故なし20等級から事故あり19等級にダウン
・事故あり19等級の場合は50%割引
・事故なし20等級に戻り、63%割引
1等級ダウン事故に該当するのは下記のような場合です。
- 盗難
- 落書きやいたずらによる窓ガラスなどの破損
- 車の運行に関係していない火災や爆発
- 台風、洪水、高潮、竜巻などの自然災害
- 落下もしくは飛来したものによる破損(例:飛び石による窓ガラスの破損など)
等級をダウンさせて車両保険を使うのと保険を使わずに実費で修理するの、どちらが良いかを検討する必要があります。
ノーカウント事故は、自分や同乗者がケガをしたとしても、他の人にケガをさせたり、自分の車が損傷したりしていない事故のことです。
保険を使用したとしてもノーカウントのため、翌年に最高等級からダウンすることはなく、まだ最高等級でない時は1つ等級が上がります。
ノーカウント事故に該当するのは以下のような保険または特約を使用した場合です。
記名被保険者、同乗者の車の事故によるケガを補償
示談交渉を弁護士に依頼する場合の費用を補償
原付での事故を補償
自分の飼っている犬が人にケガをさせた場合などの補償
故障時に車をレッカー移動させるための補償
走行している自転車による歩行中のケガ、自分での自転車走行中のケガを補償
保険を使用してもノーカウントなのは、自動車保険が他人への損害、また資産である車の損傷リスクを補うことを目的としているためです。
自分や同乗者のケガの補償は、自動車保険の目的とは別の補足のようなものであることから、等級には影響がありません。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
最高等級に到達するためにできること
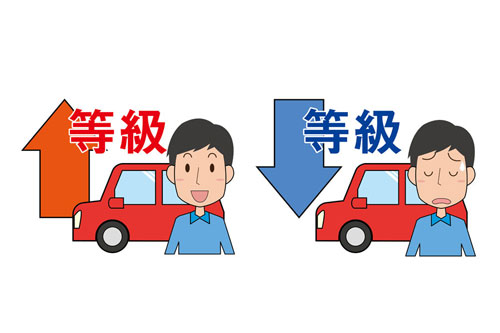
最高等級までは最短で14年かかりますが、どうすれば順調に等級を上げていくことができるのでしょう?
等級を上げるために行える基本的なこと、また特定の場面で気をつけるべきことについて見ていきましょう。
毎年等級を上げて、できる限り早く最高等級に到達するためには、常に安全運転を心がけ、事故を起こさないことが重要です。
警察が定めた安全運転5則、高速運転安全5則を運転の基本として頭に入れておくのも良いでしょう。
①安全速度を必ず守る
②カーブの手前でスピードを落とす
③交差点では必ず安全を確かめる
④一時停止で横断歩行者の安全を守る
⑤飲酒運転は絶対にしない
①安全速度を守る
②十分な車間距離をとる
③割り込みをしない
④わき見運転をしない
⑤路肩走行をしない
等級を上げていくためには、安全運転だけでなく、車を購入する際にASV(先進安全自動車)を選び、車そのものに自分が不安を感じている部分をサポートしてもらうという方法もあります。
下記はサポート機能の例です。
- 自動ブレーキ(衝突被害軽減ブレーキ)
- ぺダル踏み間違い時加速抑制装置
- 車線逸脱警報
- 先進ライト
- バックカメラ(後退時後方視界情報提供装置)
- 後側方接近車両注意喚起装置(リアビークルモニタリングシステム)
- 車間距離制御装置(ACC)
また、車を定期的にメンテナンスし、安全運転ができる状態に整えておくことも大切です。違和感をそのままにしておくと、事故につながる可能性もあるので点検や修理に出すようにしましょう。
どんなに気をつけていても、事故を起こしてしまったり、巻き込まれたりする可能性はあります。しかし、事故に遭ったからといって必ず自動車保険を使わなければいけないわけではありません。
等級が下がるのは事故の有無ではなく、事故によって保険を請求した際の内容です。そのため、保険を使用せずに修理費用を自分で支払うなら、等級には影響がありません。
しかし、最高等級を目指すことだけを考えて高額な修理費用を自分で支払うのは、何のために保険に加入しているのか分からなくなってしまいます。
保険を使うべきかどうかは、修理費用と等級が下がった後の保険料を比較した上で検討しましょう。
これから家族で所有する車を増やす際には、契約する保険会社にセカンドカー割引(複数所有新規割引)が適用されるか確認しましょう。
セカンドカー割引は、条件を満たした場合に2台目以降の車で7等級から契約を開始することができるため、最高等級を目指すのに有利となります。
セカンドカー割引の適用条件は下記の通りです。
・等級が11等級以上
・用途車種が自家用8車種に該当している
・契約開始日が1台目の契約の保険期間内
・記名被保険者が下記に該当
①1台目の契約の記名被保険者、その配偶者
②①の同居親族(6親等以内の血族か3親等以内の姻族)
・車両所有者が個人であり、下記のどれかである
①1台目の契約の記名被保険者もしくはその配偶者
②①の同居親族
③1台目の車の車両所有者
・用途車種が自家用8車種に該当している
保険会社の変更を検討している場合、乗り換えの時期に注意しましょう。
現在契約している保険の満期日に合わせて乗り換える場合には、新しい保険会社での契約での等級は1つ上がります。しかし、保険期間の途中で乗り換えた場合は、今の等級で新たに丸1年の契約が始まるため、その分等級が上がる時期が遅くなってしまいます。
例えば、6等級の場合に保険契約の満期日で乗り換えた場合は新契約の1年は7等級から始まります。しかし、契約期間が半年残っている時に保険会社を変えた場合には、前契約と新契約合計で1年半の間6等級となります。
そのため、保険会社の乗り換えは、慌てずに満期日まで待つのがおすすめです。
自動車保険を使ってしまい等級が下がってしまったからといって、新たに他の保険会社で契約し直しても下がった等級は変わりません。保険乗り換え時の注意でも述べましたが、保険会社を変えても等級は引き継がれます。
そもそも、前の契約での等級や事故の有無は自動車保険の告知義務項目です。また、各保険会社の間でも契約者の等級や事故歴などの情報は、以前の契約の満期日から13ヶ月間は共有し引き継がれます。
最高等級を目指すなら、事故を起こさないよう安全運転を続けていくことが最善であり近道です。
最高等級を維持するための注意点

最高等級の20等級になったら、できる限り維持していきたいものです。
しかし、記名被保険者を変更する場合に等級の引き継ぎは可能なのでしょうか?
また、車にしばらく乗らないような場合にできることについても見ていきましょう。
記名被保険者を変更する場合、条件を満たせば等級を引き継ぐことが可能です。
その対象者は、変更する前の記名被保険者の配偶者もしくは、その同居している親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)です。
注意したいのは、配偶者以外の子どもを含む親族は同居が条件の1つであるということです。別居してしまうと等級の引き継ぎはできません。
さらに、今の保険を解約した翌日から7日以内に手続きをしないと、等級がリセットされてしまい等級の引き継ぎができなくなってしまうので注意しましょう。
車を処分してから別の車を購入するまでに8日以上期間が空いてしまうような場合でも、最高等級がリセットされずに済む方法があります。
それは、保険会社に連絡して「中断証明書」を発行してもらう方法です。そうすれば、最長10年間は等級を維持することが可能です。
最高等級の割引率以外で自動車保険料を抑える方法

最高等級の事故なし20等級の場合は63%割引となります。そうなると、かなり保険料は抑えられているでしょう。
しかし、これ以外にも保険料の見直しの際に検討可能な点があるので、いくつか紹介します。
現在、もし自動車保険の運転者を限定していないのであれば、年齢や範囲を30歳以上の家族や本人だけに限定することで保険料を抑えることができます。
また、卒業や退職などにより、車の使用目的が「通学・通勤用」でなくなった場合には、「日常・レジャー用」に変更することで保険料を安くすることができるでしょう。
車両保険も、一般型からエコノミー型にしたり、免責金額を高くしたりすることで、保険料を低くすることが可能です。
ただし、エコノミー型は一般型より補償範囲が狭く、単独事故や当て逃げなどが対象外となります。また、免責金額を高くすることは、車を修理する時の自分の負担額が大きくなるということです。
保険料を安くするためだけに必要な補償が不足することがないよう、よく検討しましょう。
自動車保険では、先に紹介したセカンドカー割引以外にも様々な割引が用意されています。
下記は例ですが、自分の保険会社の割引を調べて活用できるか検討しましょう。
新規また継続時にインターネットから契約すると適用される割引
自動車保険証券を紙で発行しないことで適用される割引
保険会社を見直すことで、保険料が抑えられる場合もあります。
現在の契約が代理店型の保険会社なら、ダイレクト型(通販型)の保険会社に変更すると、代理店手数料がない分保険料が低くなります。
しかし、代理店であれば担当者と対面で相談しながら決められますが、ダイレクト型は基本的に自分で必要な補償を調べ、決定しなければなりません。
どちらにもメリットとデメリットがあるため、自分に合った保険会社を選ぶことが大切です。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!








