自損事故とは、運転者自身が単独で起こした事故を指します。例えば、ブレーキとアクセルを踏み間違えて電柱に衝突したり、自宅の車庫に車を停める際に操作を誤り、壁や門などの建築物を壊してしまうケースが該当します。
自損事故は、事故の当事者が自分のみで、第三者や他の車両が関与していないのが特徴です。
自動車保険に入っていれば、相手がいる事故の場合は対人賠償などで補償することが可能です。一方、自損事故など相手のいない事故を起こした場合、自動車保険の補償が下りるのか分からない方もいるでしょう。
この記事では、自損事故を起こした場合の自動車保険の補償がどうなっているかについてまとめました。
自損事故を起こした場合の自動車保険の取り扱いについて

自損事故を起こした場合に、自動車保険による補償が受けられるかについて見ていきます。
自動車保険には、自賠責保険と任意保険の2つがあります。自損事故への対応については自賠責保険と任意保険とでは異なるので、注意が必要です。
以下で詳しく説明していきます。
自賠責保険は補償の対象外

自賠責保険の場合、自損事故は補償の対象外です。
自賠責保険は、別名「強制保険」とも呼ばれていて、公道を運転する際には加入が義務付けられています。
自賠責保険は交通事故の被害者を救済するための保険なので、相手のいる事故、特に人的被害が出た場合に保険金が支払われる保険となっています。
自損事故のように被害者のいない事故の場合は、自賠責保険は使えません。また、自損事故で何か物を壊してしまった、自分がけがをしたという場合には保険金が下りないので注意してください。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
任意保険に加入していれば補償を受けられる場合も

任意保険に加入していて自損事故を起こした場合は、補償の対象となります。
自賠責保険と比較して自動車保険と呼ばれる任意保険は補償の範囲が幅広いので、いざという時のために加入しておいたほうがいいでしょう。
自損事故に対しての補償は3つあります。
1つ目は、契約自動車が事故を起こして、乗っている人が死傷した場合の「人身傷害保険」と呼ばれる補償です。
2つ目は、契約自動車に乗っている人が事故でけがをした場合に保険金が支払われる「搭乗者傷害保険」です。人身傷害保険と異なるのは、事故の内容に関係なく、あらかじめ設定されていた保険金が定額で支払われる点です。
3つ目は、自損事故を起こした時に補償される「自損傷害保険」です。これは、相手方に過失のない事故も補償の対象となります。
車両保険はケースバイケース
自損事故で車を壊したとなると車両保険が使えるのではないかと思うかもしれません。しかし、車両保険による補償が受けられるかどうかは、ケースバイケースです。
車両保険には、一般型とエコノミー型の2種類があります。
補償の範囲が広い一般型の保険をつけているのであれば、補償の対象となりますが、エコノミー型の場合は補償の対象外になってしまいます。
エコノミー型とは、車両保険の補償対象を限定することで、一般型よりも保険料が安くなっています。そのため、エコノミー型は相手のいる交通事故のみが補償の対象です。
相手のいない自損事故の場合、エコノミー型では適用外になってしまうので覚えておきましょう。
自損事故保険に加入する方法も
自損事故に関する補償として、自損事故保険があります。これは、自損事故を起こして運転手や同乗者が死亡したり、けがをしたりした場合の保険です。
保険会社の中には、自損事故保険を特約としてつけられる場合もあります。これは人身傷害保険に加入しない人のための特約です。
自損事故保険と人身傷害保険とでは補償範囲が被ります。もし人身傷害保険をつけるのであれば、自損事故保険をつける必要はありません。
ただし、人身傷害保険と自損事故保険を比較して、自損事故保険をつけたほうが保険料が安くなるのであれば、人身傷害保険の代わりに自損事故保険をつけるというのも選択肢の一つです。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自損事故と自動車保険の等級の関係について
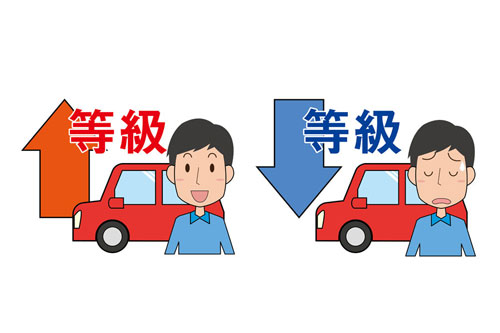
交通事故を起こして自動車保険を使った場合、等級がダウンする恐れがあります。
自家用車の多くが加入しているノンフリート契約では、1~20等級があり、保険料も変わってきます。
自損事故を起こして保険を使うと、翌年度の等級がどうなるか気になる方も多いでしょう。
ここからは、自損事故と自動車保険の等級の関係性について詳しく見ていきます。
自損事故を起こして自動車保険を使う場合、多くのケースで翌年度は3等級ダウンします。
例えば、自損事故を起こしてガードレールや電柱などにぶつかって車を壊し、車両保険で補償を受けた場合などが該当します。
3等級ダウンすれば、翌年度の保険料がぐんとアップしてしまうでしょう。
その上、ノンフリート等級では事故有係数と無事故係数の2種類があります。同じ等級でも事故有のほうが無事故よりも割引率は低く設定されているため、ここでも保険料を余計に支払い続けないといけなくなります。
自損事故を起こして車両保険で車を修理する際には、保険を使った場合の翌年度以降の保険料のことを考えましょう。修理代金よりも保険料の値上がり分のほうが大きければ、保険を使わずに自腹で修理したほうがお得になります。
自損事故の内容によっては、翌年度の自動車保険の等級が下がらない場合もあります。これをノーカウント事故といいます。そのため、ノーカウント事故に該当するのであれば、自動車保険を積極的に使いましょう。
ノーカウント事故は、人身傷害保険や搭乗者傷害保険だけを使った場合です。
自損事故の場合、人身傷害保険や搭乗者傷害保険だけで済む場合も考えられます。
例えば、ハンドルの操作ミスでガードレールや電柱にぶつかりそうになって急ブレーキを踏んだとします。その結果、衝突してしまったけれどもちょっとぶつかっただけでガードレールや電柱に破損がなくて、自分の車もかすり傷程度で済むこともあるでしょう。
しかし、急ブレーキを踏んだ時に同乗者がどこかにぶつけてけがをすることはあります。この場合は、対物賠償保険や車両保険を使わずに人身傷害保険や搭乗者傷害保険だけを使用する形になるため、ノーカウント事故に該当することになります。
一般型の車両保険に加入していれば、自損事故を起こして車を壊した場合に保険金が下ります。しかし、車両保険は、あくまでも自損事故などで契約車両に何らかの損害があった場合に補償される保険です。
例えば、運転中や駐車中に車が故障して動かなくなってしまった場合には、車両保険の適用外です。
純粋に車が故障したというトラブルの場合はロードサービスを活用することになります。ガス欠やバッテリー上がりで車が動かなくなった場合、スタッフが現場に急行して修理します。
現場では対処できない深刻なトラブルの場合は、レッカーで修理工場に移動して修理してもらう流れです。
ロードサービスを利用する場合、それだけで等級がダウンすることはありません。翌年度の保険料が上がることはないので、心配せずに利用しましょう。
自動車保険に加入していれば、自損事故も補償されます。しかし、一部例外もあるので注意しましょう。
まず、運転ミスによる事故ではなく故意に自損事故を起こした場合は補償されません。
また、運転手に重大な過失が認められた場合でも保険金は支払われません。具体的にはお酒を飲んでいて正常な運転ができない状況で起こした事故や盗難車で事故を起こした場合も補償の対象外です。
自損事故を起こした場合の対処法について
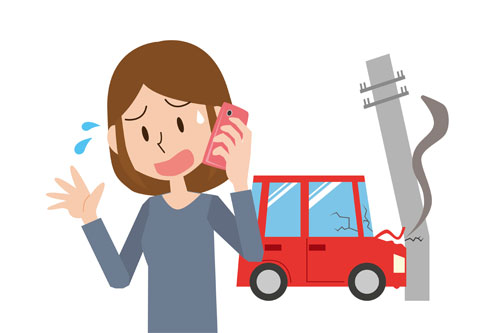
運転ミスによって自損事故を起こした場合、どうしたらいいかパニックになってしまう方もいるかもしれません。そこで、平常時からいざという時のための対処法は頭に入れておきましょう。
ここからは、自損事故を起こした時にやるべきことについて紹介していきます。いざという時のために参考にしてください。
自損事故を起こした場合、何はともあれ警察に通報することを優先してください。運転手には交通事故を起こした場合、警察への報告が法律によって義務付けられています。
警察に連絡する際には事故を起こした日時と場所、死傷者の人数、けが人がいる場合にはけがの程度、物損の場合は損壊したものと程度、事故を起こしてどんな措置を取ったかを報告しなければなりません。
もしこの報告を怠ると道路交通法違反となり、3か月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金が科されます。
また、自動車保険を使う際も警察への通報は必須です。警察に通報すると、交通事故証明書が発行されます。保険会社で保険金請求の手続きをする際に、この交通事故証明書が必要となるので、自損事故を起こしたら、まずは警察に通報しましょう。
自損事故を起こして警察に通報した場合、違反点数をはじめとしたペナルティを受けるのではないかと思っている方もいるでしょう。しかし、警察に適切に報告すれば、違反点数もなければ罰金もありません。
中には警察に通報すると何らかのペナルティを受けてしまうのではないかと思って、通報しない人もいるようです。しかし、通報しないとそのことをとがめられて、罰金の対象になってしまいます。
違反点数や罰金はありませんが、もし自損事故の結果、何か物を壊した場合にはその賠償は発生します。ただし、自動車保険に入っていれば、その保険を使って賠償することは可能です。
また、どこかにぶつけてそのまま逃げてしまうと、当て逃げに該当するかもしれません。こちらもペナルティの対象になるので、警察への連絡は絶対に忘れないようにしましょう。
自損事故を起こして警察に通報したら、次は危険防止措置を取りましょう。危険防止措置も、道路交通法の中で、事故を起こした運転手に対して義務付けられていることです。
自損事故で同乗者がけがをしてしまった場合には、救護措置を取らないといけません。けがの程度にもよりますが、救急車などを呼ぶ必要も出てくるでしょう。
また、けが人がいなくてもどこかにぶつけた場合、車や衝突したものの破片が道路上に散らばることがあります。他の車がその破片を踏むと危険なので、必要に応じてその破片を片付ける、交通量が多く破片の片付けが難しければ他の車を誘導しましょう。
もしこのような義務を怠った場合には、1年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科され、違反点数5点が加算になるので注意しましょう。
自損事故を起こした場合、自分や同乗者は念のため病院に行って診察を受けるようにしましょう。たとえ痛みなどの自覚症状がなかったとしても同様です。
例えば、脳に何らかの損傷を受けた場合、時間をかけて症状が現れる可能性もあります。数日後に症状が顕著になることも考えられます。
すぐに病院で診察を受けるのは、保険金を受け取るためにも必要です。
例えば、自損事故からある程度時間が経過して、何らかの症状が出たとします。そして病院で治療を受けることになっても、保険金が支払われない可能性があります。それは事故とけがとの因果関係の証明が難しくなるからです。そのため、事故を起こしたら、念のため病院を受診しましょう。
自損事故を起こしたら、自動車保険に加入している場合、保険会社への連絡も忘れずにしましょう。警察への届け出など、一連の手続きを済ませた後でも構いません。
保険会社に連絡すれば、保険金が支払われるかなどの案内が行われます。また、自損事故の内容によってはロードサービスが受けられるかもしれません。
もし現場で修理が可能であれば、事故現場にスタッフが駆けつけてくれて必要な作業をしてくれます。もし現場で修理できない場合には、レッカーで近くの提携修理工場に運んでくれます。
自損事故で車が自走できなくなることもあるでしょう。この時、ロードサービスによっては帰宅までの交通費や宿泊費を支給してくれる場合もあるので、保険会社への連絡も忘れないようにしてください。
自損事故のケース別!自動車保険の補償について
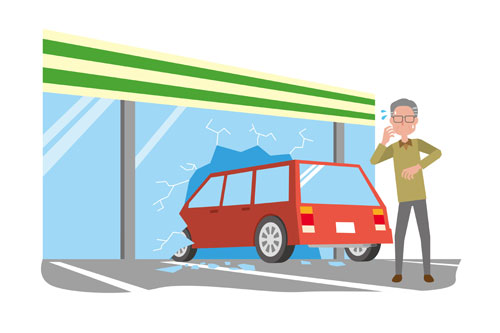
自損事故といっても、いろいろな事例が想定できます。自動車保険を使うといっても、ケースによってどんな補償を使うのかも変わってくるでしょう。
そこでここからは、自損事故の中でも比較的多いとされる事例と、その場合の対処法についてまとめたので見ていきましょう。
ハンドル操作ミスで電柱に衝突してしまった、その上電柱と愛車も壊れている場合には自動車保険の補償が受けられます。
まず電柱に何らかの損害を与えた場合、修繕費は運転手の責任で行わないといけません。自動車保険に加入していれば、対物賠償保険で補償が受けられます。
対物賠償保険は保険金の上限が無制限であることが多いので、保険金で修繕費や賠償金は賄えるでしょう。
もし自分の車も損傷したのであれば、車両保険によって修理できます。ただし、エコノミー型の場合は補償の対象外なので注意しましょう。
もしかすると、自損事故の影響で運転手や同乗者がけがをする可能性もあります。その場合には、治療費などを人身傷害保険から補償を受けられます。
自損事故では、他人の家の塀にぶつかるといった事故も少なくありません。もし家の塀など、他人のものに何らかの損害を与えた場合には対物賠償保険で補償が受けられます。
特に注意しないといけないのは、商店に突っ込んでしまった場合です。この場合、お店の修繕費用だけでは済まない可能性があります。
事故の度合いによっては、お店を閉めないといけない場合も出てきます。その間の逸失利益も賠償の対象になるかもしれません。すると、かなりまとまった賠償金を請求される可能性があります。
その場合、対物賠償保険を無制限で設定していれば、賠償金は保険金ですべて賄えるので安心です。
自損事故でものを壊してしまった場合、自動車保険に加入していれば対物賠償保険で賠償金を賄えます。ただし、駐車しようと思っていたら運転ミスをしてしまい、自宅の車庫を壊してしまったといった場合には例外です。
自宅や自宅の車庫など自分の持ち物を壊してしまった場合、対物賠償保険の適用外となります。そのため、このような場合は「自宅・車庫等修理費用補償特約」をつけておく必要があります。
この特約をつけておけば、自損事故で自宅や車庫を壊してもその修繕費用が一定額補償されます。そして、もし契約自動車も壊してしまったのであれば、一般型の車両保険をつけていれば補償を受けられます。
ただし、自宅・車庫等修理費用補償特約は、一部の保険会社しか取り扱っていません。自分の加入している保険会社にこういった特約があるかどうか、事前に確認しておきましょう。
自損事故で人がケガをした場合の保障
自動車事故は、予期せぬ瞬間に発生し、運転者や同乗者の安全に大きな影響を与えます。自分や同乗者を守るためには、どのような保険でどこまで補償されるのかを理解しておくことが大切です。
ここでは、「人身傷害」「自損事故障害」「搭乗者傷害」という3つの保険について、それぞれの特徴と補償内容を解説します。
人身傷害保険は、自動車事故によって運転者や同乗者が死傷した際に、過失割合に関係なく治療費や逸失利益などが補償される保険です。
通常、交通事故では過失割合に応じて補償額が変わりますが、人身傷害保険では、運転者の過失があっても、定められた補償が適用されるため、安心して治療に専念できるのが特徴です。
自損事故障害保険は、相手方のいない自損事故などで、運転者や同乗者が死傷し、自賠責保険などの補償が適用されない場合に、補償が受けられる保険です。
例えば、運転操作ミスで電柱に衝突してケガをしたケースなどでは、相手方が存在しないために自賠責保険が支払われません。自損事故の場合でも、自損事故障害保険に加入していれば、医療費や治療にかかる費用などの補償が受けられるため、事故後の負担を軽減できます。
搭乗者傷害保険は、ご契約の車に乗車している方が死傷した場合に、契約時に定めた保険金額を定額で支払う「定額払」の保険です。搭乗者傷害保険は事故の状況や治療の進行度合いに関わらず、契約内容にもとづいて一定額が支払われるため、補償が分かりやすい点が特徴です。
同乗者がケガをした場合にも定額で支給されるため、突然の出費に備えられます。
自損事故に備えた保険の選び方
ここでは、自損事故に備えた保険の選び方を紹介します。
自身に合った保険を選ぶために必要な知識を得て、いざというときに備えましょう。
自動車保険に加入する際、まず確認したいのは「保障内容」です。保障内容には、対人・対物の賠償責任保険、搭乗者傷害保険、車両保険など、さまざまな項目が含まれています。
事故による相手への賠償、車の修理費用、自身や同乗者のケガに対する補償など、それぞれの補償項目について確認しておきましょう。
保障内容の確認に加え、もう一つ重要なのが「保障金額」の設定です。保障金額を適切に設定することで、事故の際に十分な補償を受けられるようになります。
例えば、対人賠償の限度額が高く設定されていれば、万が一の大事故でも安心です。とはいえ、保障金額が高すぎると保険料も高額になるため、必要に応じて金額のバランスを見直すことが求められます。
自動車保険には、一般型とエコノミー型という2つの基本的なプランがあります。
一般型は、幅広い保障内容と十分な保障金額を備えており、安心感が高い選択肢です。
一方、エコノミー型は、特定の保障内容を最低限に抑え、保険料を安くすることを重視しています。
エコノミー型は保険料を節約したい方には魅力的ですが、自損事故が対象外といったカバーできる範囲が限られるため、予期せぬリスクが生じたときの備えとしては不安が残るかもしれません。








