引っ越しなどで住所が変わることもあるでしょう。その際に住所変更をしないと、住民票の住所と現住所が異なってしまうことになります。
この記事では、自動車保険における住民票の住所と現住所が異なる場合、注意する点と等級引き継ぎの方法、住所変更での保険の見直しポイントを詳しく解説してきます。今後の転居時にお役立てください。
自動車保険で住所変更が必要な理由について
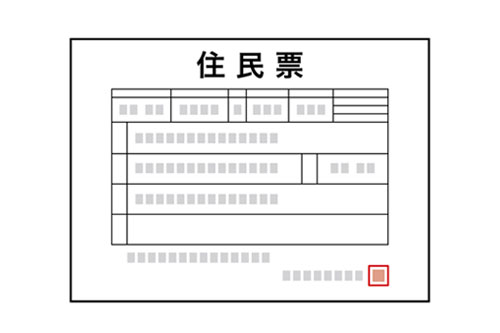
引っ越しや転勤で住所が変わった時は様々な手続きを行う必要があるため、自動車保険まで手が回らないことがあるかもしれません。しかし、自動車保険の契約時に記載した住所は変更時に保険会社に伝える必要があります。
もし運転中にトラブルや事故を起こしてしまった際、保険会社の把握する住所と相違がある場合、事故対応が遅れてしまうケースやロードサービスが迅速に実施できないこともあります。
そのため、住所変更を行った際はできるだけ早く保険会社に連絡することが大切です。契約内容の変更義務を怠ると最悪の場合、通知義務違反で補償が受けられないことがありますので注意しましょう。
自動車保険で同居しているか別居しているかについては、住民票の住所ではなく、生活の本拠によって判断されます。つまり、実際は別居していて住民票を移していない状態は別居扱いになるということです。
例えば、単身赴任で住民票を移さずに生活している場合は、住民票を移していなくても同居ではなく別居扱いになります。
また、お子様が遠隔地の大学に進学して一人暮らしを始めたけれど住民票を移していないということがよくありますが、その場合は同居ではなく別居となるので注意が必要です。
自動車保険の住所変更を行わないとどうなる?

住所変更は自動車保険で必要であることを説明してきました。では、具体的に住所変更をしなかった場合、どのようなことが起こるのでしょう?
ここからは、住所変更を行わなかった場合の弊害について詳しく解説していきます。
住所変更を行わなかった場合の弊害としては、まず保険料が変動する可能性があるということです。
自動車保険の場合、地域によって事故率が異なるため、事故リスクの高い地域は保険料が高く設定されます。そのため、記名被保険者の登録内容に応じて算出されるのが一般的です。
記名被保険者とは、契約した車に対して運転をメインにする人のことで、保険証券などに記された被保険者を指します。
主にどの地域で運転するかによって保険料が変わるケースがあるため、住所変更を行っていないと充分な補償が受けられないこともあると言えます。
また、損害保険料率算出機構が発行している「自動車保険の概況」によると、人口の多い都市を含む都道府県のほうが保険料が高くなりやすいようです。
任意保険については、ダイレクト型と代理店型があります。ネットで申し込みできるダイレクト型は地域差で保険料が変わるケースが多く、代理店型は保険料が全国一律の場合が主流になっている傾向があります。
特にダイレクト型自動車保険に加入している場合、地域によっては保険料が高くなり、差額を支払うケースも考えられるので、注意が必要です。
単身赴任で家族を現住所に残していて別の地域に転勤する場合でも、住所変更が必要になるケースがあります。
それは、自動車保険の対象になる車の記名被保険者が自分になっている場合です。その際は実際に運転する地域が異なりますので、住所変更が必要になります。
また、自分が記名被保険者になっている車に関して配偶者や子供がメインになり、現住所の地域で乗ることになるケースでは、記名被保険者の変更手続きが必要になります。
ただし、別居している家族が補償範囲に含まれる特約を契約している時は変更する必要はありません。例えば、配偶者限定特約や運転者家族限定特約が当てはまります。このような特約をつけているか、保険の内容を再度確認しておきましょう。
住所変更を行わなかった場合、事故後の補償が受けられないケースもあるので注意が必要です。
事故が起こった際、事故内容が保険の補償対象内であった場合、申告内容に不備がないかを保険会社のほうで確認します。正当に補償を受け取ることができるのは、正しい申告を受けている時です。
そのため、住所が変わってから期間があいてしまっていて申告されていない場合には、最悪保険金や補償が受けられないことがあるので注意が必要です。
住所変更をしていないと、自動車保険の継続手続きの案内が届かないこともあります。
保険会社では一般的に自動車保険の契約期間が満期近くになると、次の更新案内をハガキなどで送ってくれます。それを見て契約が満期だと気づく方も多いでしょう。
しかし、住所変更の手続きを行わないと送付しても手元に届かず、最悪の場合、満期を過ぎた状態で自動車保険に加入せずに運転してしまうことが考えられます。そうなってしまうと、もし事故を起こした時に補償されなくなりますので注意が必要です。
保険会社は無保険で運転してしまうことを防ぐために「継続手続特約」を採用しているところもあります。これは、満期日までに継続意思を確認できなかった際の救済措置として、前年の契約に準じた補償で自動継続する方法です。
ただし、所定の払込期間までに保険料が振り込まれない時は始期日に遡っての契約が無効になり、契約解除になってしまうため、その点は覚えておきましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
家族の等級引継ぎのポイントについて

家族で車を利用していると、子供に自動車保険の等級を引き継ごうと考えることがあるかもしれません。等級を引き継ぐことで保険料を抑えられる可能性があるからです。
ただし、家族で等級の引き継ぎを行う場合は同居していることが条件になります。
ここからは、家族で等級の引き継ぎを行うにはどうすればいいのか、そのポイントを詳しく解説していきます。
自動車保険の等級は親族間で引き継ぐことが可能です。しかし、引き継ぎを行うことができる親族の対象には以下の条件があります。
- 契約者の配偶者
- 契約者の同居親族
- 配偶者の同居親族
引継ぎを行う場合に重要なのは「同居」しているかどうかです。同居の確認は住民票で判断することはなく、生活拠点で判断されます。
保険会社によっては、等級の引き継ぎは電話連絡だけで終わるという場合もあるので、住民票の発行は必要ないことを覚えておきましょう。
自動車保険における同居の定義は細かくなっています。例えば、同じ敷地内でも離れである、また玄関が異なる二世帯住宅のようなケースは同居として認められないこともあります。
保険会社によっても同居に関する考え方が異なるため、等級引き継ぎが適用されるか事前に確認を取っておきましょう。
等級の引き継ぎができるタイミングは、限定されるケースもあります。
車の状況は変わらず車の記名被保険者だけを変更する場合はそのまま手続き可能ですが、他の車に引き継ぐ場合には車両入替の手続きが必要になります。
車両入替をする場合の条件は以下の通りです。
- ご家庭で利用する車を増やす場合
- 現在、自動車保険に加入している車を譲渡・廃車・返却して新しい車を購入する場合
等級引き継ぎの多いケースは、同居している子供が車を購入する時です。等級が上がっている親の自動車保険から等級を引き継ぎ、親が新規で自動車保険に加入するパターンが該当します。
この場合は、次のように手続きしていきます。
- 親の契約している自動車保険を車両入替する
- 車両入替した自動車保険の記名被保険者を子供名義に変更する
- 親が使用する車が無保険状態のため、新規契約し記名被保険者を親名義にする
自動車保険の保険料は10代や20代のほうが高く設定されています。それは、年齢別で見たときに事故率が高くなっているからです。
子供が自動車保険に加入する際、年齢条件で保険料を安く設定できないため、どうしても高額の保険料になります。そこで、親の等級を引き継ぐことで保険料を大幅に抑えることができます。
つまり、親が新規加入したとしても子供の保険料が抑えられる分、総額で保険料を抑えることが可能となるのです。
自動車保険の等級を引き継ぐ場合、同居が条件になっています。今後別居する予定があるなら、別居する前に車両入替を実施しておかなければ手続きをすることができませんので、注意しましょう。
先ほどお伝えした通り、住民票を移していない状態であっても、生活拠点が一緒でなければ同居とはみなされません。つまり、就職や結婚、進学などで別居することが決まった場合、転居する前に等級引き継ぎを行っておくことが大切です。
別居後だと引き継ぎの手続きを行うことは難しくなりますので、忘れずに行いましょう。
契約者の同居親族は等級引き継ぎが可能です。しかし、車両入替を行うと、現在契約していた車は自動車保険の新規加入が必要となるため、契約方法によっては保険料が高くなるケースもあります。
その場合、新規加入を自動車保険のセカンドカー割引で利用するのも一つの方法です。
セカンドカー割引とは、2台目以降の車に新規で自動車保険に加入する際、適用条件を満たしていると通常6等級から始まる等級を7等級から契約できる割引です。等級が1つ上がっている分、保険料は安く設定できます。
本来であれば6等級スタートになる自動車保険契約を1等級上がったところからスタートできるため、保険料の割引率が高くなる時期も早まる点はメリットと言えるでしょう。
ただし、セカンドカー割引が適用されるには以下の条件を満たす必要があります。
- 1台目の自動車保険の等級が11等級以上であること
- 1台目の車の用途・車種が「自家用8車種」であること
- 2台目以降の記名被保険者及び車両所有者が個人名義であること
- 2台目以降の記名被保険者の条件
1台目の保険契約の記名被保険者又は記名被保険者の配偶者又はその配偶者の同居の親族 - 2台目以降の車両所有者の条件
1台目の保険契約の車両所有者又は記名被保険者又は記名被保険者の配偶者又はその配偶者の同居の親族
住所変更をした際に自動車保険の見直しをする項目

住所変更を行うと、自動車保険に登録した車の使用目的や条件に変更が出てくる可能性があります。その際、保険内容についてどのような見直しが必要になるのでしょう?
ここからは、住所変更を行った際に自動車保険の補償内容を見直すべき項目を詳しく紹介していきます。
見直すべき項目の1つ目は、運転者の範囲です。転居によって同居する家族構成が変化した時には見直すといいでしょう。
例えば、転居前は単身赴任等で一人暮らしをしていて「運転者限定特約」を本人のみにしていたとします。その場合、転居後に家族で利用するようになった時は、運転限定特約を家族も利用できる状態に変更する必要があります。
そのままにしておくと、万一家族が運転した車が事故を起こしてしまった時に補償を受けることができませんので注意しましょう。
また、運転者の範囲が狭くなる時には条件を変更することで保険料を抑えられる可能性もあります。保険会社と詳細を確認して、手続きを行うことをおすすめします。
運転者限定特約について、保険料の違いは以下の通りです。
2017年5月に損害保険料率算出機構が公表している参考純率の項目で、家族に限定する契約方式が廃止になっています。それによって、家族限定特約を廃止する保険会社も多くなりました。
その背景として、核家族化が進み単身世代が増加傾向にある点が挙げられます。そのため、本人限定特約を扱う保険会社が増えてきているのが現状です。
見直すべき項目の2つ目は、走行距離です。特にダイレクト型自動車保険を利用している方は、確認しておくことをおすすめします。
ダイレクト型自動車保険とは、インターネットなどを利用して自動車保険を契約する方法です。代理店型に比べて中間コストを抑えることが可能なため、割安な保険料になっています。
ダイレクト型は走行距離が細かく区分されていて、走行距離が多くなると保険料が高くなります。使用目的が変わった際は走行距離が変動する可能性も高くなりますので、注意が必要です。
年間走行距離の告知は、オドメーターを利用して申告する「過去1年間の走行距離」と「年間予想走行距離」の2種類があります。
転居によって年間走行距離に変更が生じる時には、保険会社に連絡が必要になります。
もし年間走行距離が大幅に変わり、報告していない状態だと最悪の場合、追加の保険料が請求されたり、補償を受けられなくなったりすることもあります。そのため、適切に告知をしておくことが大切です。
見直すべき項目の3つ目は、電話番号を変更した時です。
携帯電話の番号を登録していて変更がなければ問題ありませんが、固定電話の番号が変わった場合は万一に備えて新しい連絡先を伝えておくことが必要です。
連絡が取れない状態は、保険会社にとってもリスクが大きいので気をつけましょう。
見直すべき項目の4つ目は、ナンバープレートを変更した時です。
住所変更を行い管轄の運輸支局が変わると、ナンバープレートの変更をする場合もあるでしょう。すると、登録番号が変わってしまいますので、変更の際は直ぐに保険会社に連絡しておいてください。
自動車保険では、補償を受ける対象の車両は限定されているため、契約車両として記載された車両である必要があります。ナンバープレートの変更の報告をせずに事故を起こした場合、事故後の手続きに時間が通常よりも長くなってしまう可能性があるので注意してください。
ナンバープレートの変更は住所変更以外にも、中古車の購入や譲渡、ナンバープレートの紛失や盗難、希望ナンバーに変えるケースもあります。
変更の手続きは、ダイレクト型であれば、ネットで変更手続きが行えます。代理店型は電話などで直接担当者と連絡を取り、書類に必要事項を記入して署名(と捺印)を行えば、手続きを終わらせることができるでしょう。








