自動車保険に加入もしくは更新する際、1年契約だと毎年更新しなければならず、少々面倒に思うかもしれません。
長期契約することも可能ですが、それにはメリットもあればデメリットもあるので、ここで詳しく説明していきます。
自動車保険を長期契約にするかどうかご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
自動車保険と契約期間

自動車保険は、事故を起こした際に契約者本人や同乗者、被害者の死亡・ケガ・障害または車や公共物などの物の破損に対して補償してもらえる保険のことです。
保険会社には、代理店型とダイレクト型(通販型)の2種類があり、どちらも基本的な契約期間は1年です。
なお、代理店型とダイレクト型の違いは簡単に以下の通りです。
代理店を通じて保険に加入するため、担当者と対面での手続きが可能です。補償内容がよくわからない場合に相談しやすいのがメリットですが、保険料に手数料が含まれるのでダイレクト型よりやや高くなります。
Webサイトや電話から自分で保険に加入するため、補償内容は基本的に自分で調べて決めることが必要になります。人件費などのコストがかからない分保険料が安いことがメリットになります。
すべての保険会社で長期契約できるわけではない

自動車保険を長期契約することは可能であるとはいえ、すべての保険会社で対応しているわけではありません。
ダイレクト型(通販型)では対応していないことが多いため、代理店型の保険会社に加入する必要があります。
また、代理店型の保険会社でも長期契約の期間はそれぞれ異なります。2年または3年、3年のみ、3年~6年、3年~7年などがあるため、自分が契約したい期間を取り扱っている保険会社を探す必要があります。
自動車保険の1年契約では、翌年の更新ごとに等級が上がったり下がったりします。では、長期契約の場合はどうなるのでしょう?
以下は、1年の契約と3年の長期契約を6等級で開始した場合の等級の変動例です。
1年目
1年契約:6等級
3年契約:6等級
2年目
1年契約:前年が無事故の場合は7等級、事故を起こした場合は3等級もしくは1等級ダウン
3年契約:無事故でも事故を起こしても7等級とみなす
3年目
1年契約:前年が無事故の場合は8等級、事故を起こした場合は現在の等級から3等級もしくは1等級ダウン
3年契約:無事故でも事故を起こしても8等級とみなす
4年目
1年契約:前年が無事故の場合は9等級、事故を起こした場合は現在の等級から3等級もしくは1等級ダウン
3年契約(契約更新):3年間無事故の場合は9等級、事故を起こした場合は事故の回数と内容に応じた等級ダウン+無事故の年数に応じて等級アップ
自動車保険の等級の正式名称は「ノンフリート等級別料率制度」です。契約者が所有している車の台数が、他社での保険も含めて9台以下だと適用されます。
等級は、事故の有無、事故の内容によって1~20等級にリスクが区分けされています。数字が大きくなればなるほど保険料の割引率が上がるため、それに合わせて保険料も安くなります。
初めて自動車保険を契約した際は、6等級からのスタートです。その後、1年間無事故であれば等級が1つ上がります。
最大で20等級まで上がることができますが、逆に事故を起こして自動車保険を使用すれば等級は下がります。どれくらい等級が下がるかは、事故の内容により1等級ダウン事故と3等級ダウン事故の2種類に分かれます。
事故を起こした場合、自動車保険の等級がダウンする他に「事故有係数適用期間」というものもあります。
事故により自動車保険を使った場合、次回の契約更新のタイミングで事故有係数適用期間が適用されます。それは、1等級ダウン事故だと1年間、3等級ダウン事故だと3年間です。
この適用期間中は、同じ等級であっても無事故より割引率が下がるため保険料は高くなります。
事故有係数適用期間の上限は6年、下限は0年です。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
長期契約のメリット

自動車保険を今まで通り1年にするか、それともさらに長期間での契約にするかは、今後誰がどのように車を使っていくかも考えた上で決定する必要があります。
まずは長期契約をすることでどんなメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
自動車保険を長期で契約することの大きなメリットの一つとして、毎年の更新手続きが不要になることが挙げられます。
仕事や育児に追われて多忙である場合などには時間の節約になるだけでなく、忙しさのあまり更新手続きを失念するといった心配を避けることができるでしょう。
長期契約の契約期間中は、保険料や等級が変動しないこともメリットの一つです。
事故を起こして保険を使ってしまった場合であっても、契約期間中であれば保険料は変わりません。そのため、1年ごとの更新で等級が上がり保険料が下がる場合と比べると損をしているのではないかと考えるかもしれません。しかし、長期契約では契約期間中は無事故であるとして計算されており、トータルで考えると長期契約が高くならないよう調整されています。
保険料や等級が変わらないということは、毎年必要な支払いについて計算する時にも分かりやすいので助かるでしょう。
自動車保険の長期契約の場合、保険料を一括で支払うことにより割引が適用されるケースが多いのもメリットです。
3年などの長期契約分を一気に支払うとなると一度の負担は大きいかもしれませんが、長い目で見ればお得と言えます。
割引の有無は保険会社によって異なりますので、契約しようとしている保険会社に確認してみましょう。
長期契約のデメリット

自動車保険を長期契約することでメリットがあるなら、その逆にデメリットも存在します。
ここからは、どのようなデメリットがあるのか詳しく説明していきます。
自動車保険の長期契約でのデメリットは、契約期間中に契約条件を変更し保険料を安くしたいと思っても、できない場合があることです。
契約期間中に免許更新によりブルーからゴールドになったとしても保険料の割引が適用されるのは次回契約更新時からとなり、1年契約よりも割引開始が遅くなるといったケースが挙げられます。
長期契約で保険料が変わらないことはメリットでもありデメリットでもあります。
自動車保険料率は改定によって上がる場合もあれば下がる場合もありますが、もし下がって保険料が安くなったとしても、契約期間中は反映されません。
また、サービスや補償の拡充といった改定があった場合にも、適用されるのは契約更新時なので注意しましょう。
長期契約でのデメリットとして特に気をつけたいのは、契約期間中に何回も事故を起こし保険を使用した場合です。次回の契約更新時に等級が一気にダウンし割引率も下がることから、保険料がかなり高くなってしまいます。
以下は、3年契約で契約期間中無事故の場合と、複数回事故を起こした場合の等級と保険料割引率の変動例です。
3年契約をした時が10等級(46%割引)
1年目:無事故
2年目:無事故
3年目:無事故
4年目の更新時:13等級(51%割引)
3年契約をした時が10等級(46%割引)
1年目:無事故
2年目:3等級ダウン事故
3年目:1等級ダウン事故
4年目の更新時:事故あり7等級(15%割引)
自動車保険の長期契約は基本的に代理店型の保険会社での取り扱いであり、ダイレクト型では対応していません。
契約者が直接保険会社とやり取りをするダイレクト型と異なり、代理店型は代理店が契約者と保険会社の間を繋いでいます。経由がある分、手数料などで基本の保険料がダイレクト型よりも高めの設定です。
そのため、長期契約であってもダイレクト型の1年契約と比べると保険料が高いということが生じる可能性があります。
長期契約にしないほうがいい人とは?

長期契約のメリットやデメリット以外にも、個人の状況から見て長期契約をしないほうがいい場合もあります。
いくつか考えられる状況がありますので、自分がそれに該当する場合には、長期契約をするべきなのかもう一度検討してみましょう。
現在ブルーの免許証の状況で自動車保険の長期契約をしようとする際には、注意が必要です。契約期間中に免許の更新時期がぶつかっており、ブルーからゴールドになる可能性がかなり高いのであれば長期契約を見送ったほうが良いでしょう。
長期契約の契約期間中にゴールド免許になったとしても、途中で条件を変更し保険料を安くすることはできないため、更新時期まで待たないといけなくなるので注意しましょう。
車を手放すことを検討している場合も自動車保険の長期契約には向いていません。
1年契約であれば契約が切れるタイミングでちょうどよく車を手放すこともできますが、長期契約の契約期間中だと中途解約の手続きを行わなければなりません。
そうなっては、手間を省くどころか増えることになります。具体的に車を手放す時期を決めていないとしても、車を持たない生活を考え始めたなら長期契約は不向きと言えるでしょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
長期契約にしてもいい人とは?
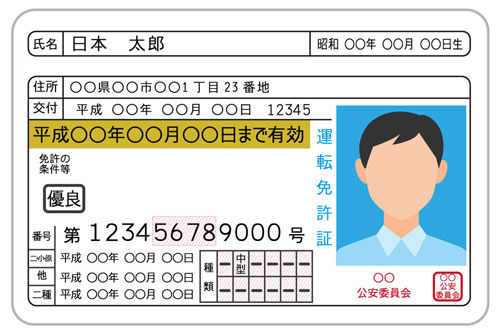
自動車保険の長期契約を行っても差し支えないと思われる状況もいくつかあるので紹介していきます。
こちらに該当する場合には、長期契約の検討を進めて良いでしょう。
長期契約を検討する際には、仕組みをきちんと理解していることが大切です。
これまでに挙げたメリットとデメリットを天秤にかけ、1年契約よりも長期契約が自分の状況に向いていると思われる場合には、長期契約をしても問題ないと言えるでしょう。
現時点ですでにゴールド免許になっているなら、契約期間途中に条件の変更を希望することもないため、自動車保険の長期契約を考えても良いでしょう。
車の主な使用者を変更したり、車を乗り換えたりする予定もなく、現在の状況がこの先何年も続くと思われる場合には、自動車保険を長期契約したほうが手続きがかなり楽になると言えるでしょう。
なお、車の使用者を変更する場合として考えられるのは、以下のようなケースです。
夫が主に運転していたが、単身赴任により妻が運転することになった
親が主に運転していたが、親の代わりに子どもが今後運転することになった
長期契約を途中解約する際の注意点

自動車保険は3年などの長期契約でも途中で解約することが可能です。一般的に違約金は発生しませんが、手続きは保険会社によって異なりますので確認しましょう。
保険を他社に乗り換える場合には、等級や事故有係数は新しい保険に引き継がれます。ただし、保険会社によっては以下のような条件がついていることもあるため、乗り換えを検討する際はよく確かめることが大切です。
「乗り換えでの新しい保険の開始日は解約する保険の満期日」または「乗り換えでの新しい保険の開始日は解約する保険の始期日と同じ日」であること。
例えば、解約する保険を3月1日に開始したのであれば、乗り換える保険も3月1日開始にしなければならないといことです。
また、3年契約の2年目など契約期間の途中で解約すると、それまでの期間無事故だったとしても等級は上がらないため注意が必要です。
例えば、9等級で契約した場合、1年契約なら翌年の更新で10等級、さらに翌年には11等級になりますが、3年契約の期間内で解約した場合、契約開始時の9等級のままとなってしまいます。
なお、一括払いなどで支払い済みの保険料があるなら、保険期間の残りの分に対する返金があります。しかし、短期率によって算出した金額が返金される場合と残期間の保険料を月割の計算で全額返金される場合があるため、自分の保険会社に確かめておきましょう。
短期率は、自動車保険の契約を途中解約する場合、返金する保険料の計算に用いられる係数です。
契約期間の経過日数に応じて係数が設定されており、7日までであれば10%、1ヶ月までであれば25%を差し引いた保険料が返金されることになります。
長期契約とは逆に短期で契約したい場合

自動車保険を長期ではなく短期で契約したいケースもあるかもしれません。
例えば、他人の車を運転する場合や自分の車を1年以内に手放す予定がある場合などです。それぞれに適した短期で契約できる保険があるので紹介していきます。
1日自動車保険:その名の通り、1日から契約できる保険で、1回の申し込みで連続7日間まで契約ができます。
車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車に限定されているため、借りる車が当てはまるかは確認が必要です。
なお、1日自動車保険には等級制度はありません。
ドライバー保険:基本的には1年単位での契約ですが、保険会社によっては1ヶ月での契約が可能です。1年で契約したものの半年で不要になった場合には中途解約となります。
ドライバー保険には等級制度がありますが、通常の自動車保険への等級引き継ぎはありません。
自分の車の場合、1日自動車保険やドライバー保険の契約をすることはできません。通常の自動車保険を1年契約し、中途解約することになります。その際、保険料は年払いではなく必ず月払いにしましょう。年払いだと残期間の保険料が全額返金されない場合があります。








