子供が運転免許証を取得したので、親が使用している自動車保険をそのまま引き継ぎたいと思うことがあるかもしれません。
実際、子供が新規で自動車保険を契約すると、等級や年齢条件などで保険料は割高になるのが一般的です。その際に等級の引き継ぎを行えば、トータルで保険料を抑えられる可能性が高くなります。
この記事では、自動車保険の等級を引き継ぐ際の条件や手続方法、等級制度について詳しく解説していきます。
自動車保険は等級引継ぎが可能

結論から言えば、自動車保険の等級は引き継ぐことができます。そうすれば最初から高い等級で自動車保険に加入することができ、保険料を抑えられるでしょう。
例えば、親が加入していた自動車保険の等級を新規契約する子供に引継げば、通常の新規契約時と比べて保険料を安くすることができます。
等級引継ぎをする際には条件があるため注意が必要です。
ポイントは「記名被保険者との関係」です。
記名被保険者とは、自動車保険をかけている車に対して主に運転する人のことを指します。
等級の引き継ぎができる記名被保険者との関係は、以下の3つです。
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者と同居している家族
- 記名被保険者の配偶者と同居している家族
友人や知り合いから等級の引き継ぎをすることはできません。つまり、親族に対して等級は引き継げるということです。
ここで言う親族の定義は「6親等以内の血族及び3親等以内の姻族」とされています。
また、配偶者に関しては内縁関係でも認められていますが、保険会社に内縁関係を証明する必要があります。
等級の引き継ぎを行う場合の注意点として、記名被保険者または配偶者と同居していることが条件になります。
例えば、車を購入した子供に対して等級の引き継ぎを行う場合、親と同居していれば等級を引き継げますが、子供が就職や進学によって別居している時は引き継ぐことができません。
そのため、子供が就職や進学、結婚などによって別居する可能性があるのであれば、同居中に等級を引き継ぐ手続きを行っておくと良いでしょう。
自動車保険の等級制度について
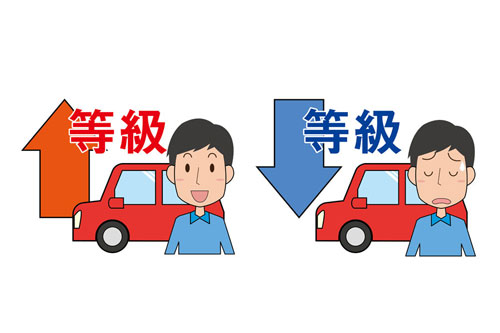
自動車保険の等級制度とはどのようなものでしょう?詳細を知っておくと、今後の役に立つことがあるかもしれません。
ここからは、自動車保険の等級制度について詳しく解説していきます。
自動車保険の等級制度では、等級に応じて割引率が異なります。
簡単に言えば、1等級から4等級までは保険料が割増しになり、5等級から20等級までは保険料が割引かれます。
等級における自動車保険の割引率は、以下の通りです。
| 等級 | 無事故 | 事故有 |
|---|---|---|
| 1等級 | +108% | |
| 2等級 | +63% | |
| 3等級 | +38% | |
| 4等級 | +7% | |
| 5等級 | -2% | |
| 6等級 | -13% | |
| 7等級 | -27% | -14% |
| 8等級 | -38% | -15% |
| 9等級 | -44% | -18% |
| 10等級 | -46% | -19% |
| 11等級 | -48% | -20% |
| 12等級 | -50% | -22% |
| 13等級 | -51% | -24% |
| 14等級 | -52% | -25% |
| 15等級 | -53% | -28% |
| 16等級 | -54% | -32% |
| 17等級 | -55% | -44% |
| 18等級 | -56% | -46% |
| 19等級 | -57% | -50% |
| 20等級 | -63% | -51% |
参照:損害保険料率算出機構(2021年9月28日自動車保険参考純率改定のご案内)
2021年9月に損害保険料算出機構で保険料の見直しがされました。保険会社はこの割増引率を利用して、保険料を算出しています。
今回の改定で無事故の9等級から19等級の割引率が拡大され、それ以外の等級に関しては割引率が縮小、割増率が拡大されています。そして、契約者が多い事故なしの20等級に割引率については、変更がない状態です。
自動車保険の参考純率が平均3.9%引き下げされた背景として、衝突被害軽減ブレーキなど安全運転を支援する車の普及が進み、交通事故が減少している点が挙げられます。
自動車保険を新規契約する時は6等級から始まります。
1年間、事故を起こさずに保険を利用しなければ、翌年度は等級が1つ上がります。そして、等級が上がることで割引率が高くなり、保険料は安くなっていきます。
自動車保険は等級制度により保険料の増減を行うことで、保険料負担の公平性を保っていると言えるでしょう。
また、等級は契約年度ごとに更新されていくので、保険料の反映は翌年度の契約以降になる点は知っておくことが大切です。

事故に遭遇した際に利用する自動車保険ですが、補償の使用状況によって3等級ダウンするか1等級ダウンするかが変わってきます。
具体的には、以下の状況によって区別されています。
- 交通事故によって相手にケガをさせてしまった場合
- 相手の自動車に衝突してしまった場合
- 当て逃げにあった場合
- 単独事故でご自身の車を損傷してしまった場合
3等級ダウンするケースは主に「対人賠償保険」「対物賠償保険」「車両保険」の補償を受けた時になります。
一般的に自分の過失で事故を起こし、自動車保険を使った場合は3等級ダウンになることを知っておきましょう。
また、翌年から3等級ダウンの際は、以後3年間は「事故有」の料率となります。
- 台風、洪水、高潮、竜巻などの自然災害
- 火災や爆発
- 盗難
- 騒擾(集団で起こされた秩序の乱れや騒ぎがあった際の被害)
- 飛び石や落石
- 偶発的な事故によって生じた損害
1等級ダウンする時は「偶発的な原因」がポイントです。自然災害や盗難などは自分の不注意でそのような状況になったわけではないので、ダウンする等級数も低く設定されています。内容としては、車両保険だけを使うケースが当てはまります。
また、翌年から1等級ダウンの際は、以後1年間「事故有」の料率となります。
つまり、等級ダウンするケースでは、過失によって起こった事故は3等級ダウン、偶発的な車両損傷は1等級ダウンするということです。
等級ダウンに関係する事故を起こした時には、先ほどお伝えしたように事故有の料率が使われます。これを事故有係数(じこありけいすう)と言います。
事故有係数は、無事故係数よりも割引率が低く設定されますので、同じ等級であっても保険料が高くなります。また、その保険料が3等級ダウンなら3年間、1等級ダウンなら1年間継続されます。
ただし、3等級ダウンや1等級ダウンの事故ではなく、ノーカウント事故の場合は、事故有係数を使うことがなく無事故係数で料率が適用されます。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自動車保険の等級を引き継ぐ手順について

自動車保険の等級を家族に引き継ぐ場合、どのような手順で行えば良いのでしょう?
ここからは、等級を引き継ぐ方法について、ケース別に詳しく解説していきます。
家族で等級を引き継ぐケースというのは、例えば、同居している子供が車を購入して、親の乗っている車の自動車保険を引き継ぐ場合です。
もし親の等級を引き継がない場合は、子供が自動車保険を新規加入し、6等級からのスタートになります。また、年齢条件の設定をする際に年齢の若い人は保険料がさらに高くなる傾向があります。
そこで、親の自動車保険を引き継ぐことで、等級を6等級より高くした状態で保険に加入できるため、保険料は新規契約よりも抑えることができます。
そのため、親の車と子供の車で自動車保険に加入する場合は、トータルで考えるとお得になると言えます。
自動車保険の等級の引き継ぎ方法は、以下の通りです。
- 納車日を確認して車検証を用意する(可能であれば)
- 保険会社に連絡して「新しい車に車両入替を行いたい」ことを伝える
- 自動車保険の名義と記名被保険者を「子供」に変更
なお、等級を与えた親の車を今後も使用する場合は、親名義で自動車保険を新規加入することが必要になります。
親が同居している子供に車を譲渡する場合は、名義変更を行うことで等級の引き継ぎを行うことができます。
手続方法は、以下の通りです。
- 車の名義を子供に変更する
- 保険契約者(保険料の支払う人)の名義を変更
- 記名被保険者を変更
ここでのポイントは、車の名義変更と自動車保険に関する記名被保険者の変更を行うことです。この2点を変更すれば、等級引継ぎをすることが可能になります。
現在乗っている車を買い替えて新しく購入するケースでも、等級引継ぎはできます。その際は「車両入替」の手続きを行わなければなりません。
手続方法は、以下の通りです。
- 保険会社に「車両入替」をする旨を伝える
- 積算距離、車検証に記載されている情報、納車する日などを記入
- 契約変更後に差額保険料の支払いまたは返金の手続きを行う
車両入替のポイントは、車種によって保険料が異なる点です。車種によって事故率が算出されており、その評価によって保険料が変動します。
他社の保険に切り替える場合についても、等級の引き継ぎが行えます。
手続方法は、以下の通りです。
- 新たに契約する保険会社を選定する
- 新たに契約する保険会社で加入手続きを行う
※契約の際には、運転免許証、車検証、現在加入している自動車保険の保険証券が必要になります。 - 現在契約している保険会社に解約の連絡を入れる
等級の引き継ぎを行う際は、現在契約している保険会社の解約日から「7日以内」に新しい保険会社の契約を開始しなければならないので注意しましょう。
中断証明書について

車を処分したり、一定期間車を乗らなかったりする場合は「中断証明書」の申請をしておくと良いでしょう。そうすることで、等級を保存しておけます。
ここからは、この中断証明書について詳しく解説していきます。
自動車保険は、解約日(満期日)の翌日から7日以内に次の契約の保険を開始させなければ、一般的に等級の引き継ぎができません。
そのため、車を処分したり、海外に渡航するなどの理由で次回の契約をする期間があいてしまう場合は、中断証明書を取得することをおすすめします。
中断証明書を発行すれば、等級を10年間据え置くことが可能になります。
中断証明書を申請すれば等級を維持できるというメリットがありますが、発行するには条件があります。
その条件は、以下の通りです。
もし中断する契約に対して保険期間内に事故を起こしてしまった場合は、等級ダウンする次の等級が7等級以上であることが条件になります。
- 売却や譲渡、廃車が完了している
- リース車の場合はリース会社に返却が完了している
- 車両入替によって他の保険契約の対象になっている
- 盗難によって車が手元にない
- 車検切れの状態である
- 災害によって車が滅失している
これらの条件を満たしていれば、中断証明書の発行が可能です。
ただし、中断日(満期日または解約日)の翌日より13ヶ月以内に中断証明書の発行申請を行わないといけないので注意しましょう。もし解約してから期間があいてしまって車に乗らなくなった場合は、保険会社に連絡して中断証明書が発行できるか問い合わせてみましょう。
等級を引き継ぐメリットとデメリットとは?

等級の引き継ぎについて詳細を解説してきましたが、等級を引き継ぐ際、メリットやデメリットがあります。それは、一体どのような点なのでしょう?
メリットとデメリットを知っておくことで、自動車保険をより効率良く使用できるかもしれません。
ここからは、等級を引き継ぎことのメリットとデメリットについてお伝えしていきます。
等級を引き継ぐ最大のメリットは、保険料を抑えることができる点です。
前述しましたが、子供が自動車免許証を取得した後に車を購入、そして新規で自動車保険に加入するケースであれば、6等級からのスタートになります。また、子供が21歳未満であれば、年齢条件として「全年齢補償」になるため、保険料は高くなるでしょう。
親から子へ等級が引き継げる場合、親の等級が仮に20等級であれば等級割引率が63%なので、保険料を大幅に抑えられます。そして、親が新規で自動車保険を契約しても、トータルで保険料を抑えることが可能です。
このように、若い年齢層の家族が保険料を安くする時には、等級の引き継ぎを行うことのメリットが大きいと言えるでしょう。
等級の引き継ぎを行った際は、変更して契約始期日から1年間無事故であれば等級が1つ上がることになります。
つまり、引き継ぐ前に満期までに6ヶ月あった場合、そのまま使用していれば6ヶ月後に等級が上がりますが、その前に引き継ぎをした場合は、変更した時から1年経過しないと等級が上がらない点は注意が必要です。
また、親が新規契約をすることになれば6等級からスタートになりますので、20等級まで上げるためには最低13年がかかります。それまで割引率も低く設定されているので、その分保険料は高くなります。
そのため、年齢条件の変更や免許証の色など、割引できる項目がないか確認して、できるだけ保険料が安くなるように設定すると良いでしょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!








