キャンピングカーは普通車と大きさが異なるため、運転が難しく感じるかもしれません。運転に慣れていたとしても、不注意から事故を起こすリスクがあります。
ここでは、キャンピングカーの事故の要因と運転時の注意点について見ていきます。また、万一の事故に備えてキャンピングカーの自動車保険に加入する際、何に気を付ければ良いか紹介します。
キャンピングカーは運転が難しい
キャンピングカーは車幅も広く車体が大きくて重量もあり、車高が高いなど普通車とは大きく異なります。
運転者から見える視野も違う上に、車高が高いと重心が不安定になるのでカーブを曲がる際に車体が大きく揺れることもあります。
普段から軽自動車やコンパクトカーなどを運転している方は、特にキャンピングカーの運転が難しいと感じるでしょう。
乗り慣れると恐怖心も和らぎますが、慣れるまでは十分注意が必要です。
キャンピングカーの事故のリスクについて

キャンピングカーを運転する際は、特性を事前に十分理解しておく必要があります。普通車のような感覚で運転すると、思わぬシーンで交通事故を起こしてしまうリスクがあります。
特にスピードの出しすぎや急ハンドル、急ブレーキなどが事故の要因となるので気を付けましょう。
また、タイヤの空気圧にも注意しないと走行中にタイヤがバーストする可能性もあります。
普通車よりも重量が重いキャンピングカーは、ブレーキを踏んでから停止するまでにある程度の距離が必要となります。
速度が出ている場合、ブレーキを早めに踏まないと制動距離が長くなるので、停止線で停止できず前の車に追突するリスクも高まります。
普通車を運転している感覚と同じタイミングでブレーキを急に踏んでも、キャンピングカーは停まれません。重心が不安定なので、衝突のはずみで横転する可能性もあります。
キャンピングカーは車高が高いので、重心が不安定になりやすいという特徴があります。そのため、走行中に急ブレーキを踏むと車体のバランスが崩れて、前に傾きそうになる場合があります。
車内で荷物が床に落下したり、最悪の場合車体が横転したりするかもしれません。普段から急ブレーキを踏まなくても停止できるように、速度を落とし車間距離を保つようにしましょう。
キャンピングカーを運転中に急ハンドルを切るなど、無理なハンドル操作を行うと、車体が左右に大きく揺れて車体の動きを制御できなくなり、横転するリスクが高まります。
車線変更や右折左折など、急ハンドルを切る場面があるかもしれません。そういった時でも、なるべくハンドルをゆっくり切るように意識してください。
道を間違えたとしても焦って急ハンドルを切って右折左折しようとせず、どこかUターンできる場所まで運転してから正しい道に戻るようにしましょう。
普通車よりも車高がかなり高くなるキャンピングカーは、横風の影響をダイレクトに受けやすくなります。
特に風が強い日は、車体が風に煽られて左右に揺れ、ハンドルが取られがちです。思うような運転ができず、横転するのではないかという怖さを感じる方もいるでしょう。
風速毎秒10mを超えるような日に、橋の上や堤防など風を遮るものがない場所や速度が出やすい高速道路などをキャンピングカーで走行するのは、控えたほうが安全です。
バーストとは、走行中にタイヤが突然破裂することです。
キャンピングカーは、バーストを起こすリスクが高いので注意が必要です。その要因は、タイヤの劣化や空気圧が低い、荷物の過積載などです。
普通車でもタイヤのバーストを起こす危険性はありますが、キャンピングカーは車体が重く、空気圧は乗用車の約3倍もあり、強い圧力がタイヤにかかっているためバーストが起こるリスクも高いです。
タイヤがバーストすると、車体が一気に傾き横転する可能性もあります。そのため、普段からタイヤの劣化や空気圧などに注意しておきましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
キャンピングカーでの事故の備えについて

キャンピングカーにおける事故のリスクを軽減させるためには、急ハンドルや急ブレーキといった無理な運転を控えましょう。
車高が高く、重量もあるため、バランスを崩さないよう積載量にも注意が必要です。
また、万一の事故に備えて自動車保険に加入しておくことも大事です。
前述しましたが、キャンピングカーは車高や車体の大きさ、重量も普通車とは大きく違います。普通車のような感覚で運転していると、事故を起こすリスクも高くなります。
キャンピングカーを運転する際は、急ブレーキや急ハンドルを避けて、スピードの出しすぎには十分注意し、慎重に運転することが大事です。
また、乗り始めていきなり遠出するのは危険です。まずは近場を走行することで運転に慣れてから遠出するようにしましょう。
トラックなどの物資を運搬する車は最大積載量が決まっており、車検証にも記載されています。しかし、キャンピングカーは貨物車ではないので、最大積載量に関しては特別な定めはありません。
しかし、積めるだけ積んでも良いと考えるのは危険です。元から車高が高く、重心が不安定にも関わらず、沢山の荷物を積みすぎると走行中に車体が左右に揺れてバランスを崩し、横転する危険性があります。
最大積載量は、車検証に記載がなくても計算して数値をだすことが可能です。
全乗員重量は、車の定員に55㎏をかけた数です。
計算した最大積載量を上限として、積み込む荷物の量に気を付けましょう。
キャンピングカーも一般車両と同様に自動車保険に加入しておくと、万一の事故の際も補償が受けられるので安心です。
車の保険というと、法律で加入が規定されている「自賠責保険」がありますが、これは事故の相手方が死傷した時、つまり被害者の身体の損害に対する補償のみなので補償として不十分だとされています。
キャンピングカー自体も事故で損害を受けると、修理するのにお金がかかってきます。車両価格も高額なため、自己負担となると経済的な負担も大きくなるでしょう。そこで、車両保険に加入しておけば、修理費用を保険でカバーしてもらえるので安心です。
キャンピングカーの自動車保険について
キャンピングカーの自動車保険は、普通車のような一般車両と異なる扱いをしている保険会社が多いです。
その理由は、普通車にはない付属品や特別装備が備わっているため、補償も同じというわけにはいかないからです。
また、キャンピングカーの自動車保険を扱う保険会社も限られているので、加入条件などをきちんと確認しておきましょう。

キャンピングカーは、自動車用途の区分では「特殊用途自動車」に分類されます。
この特殊用途自動車は、以下の車を指します。
- パトカーや救急車などの緊急自動車
- 給水車
- 郵便車などの特定事業車
- 現金輸送車
- ゴミ収集車
- レッカー車
- 移動販売車
特殊用途自動車は、ナンバープレートの右上が8から始まるので「8ナンバー車」とも呼ばれています。
自動車保険では、8ナンバー車を扱う保険会社でしか加入ができないことになっているので注意が必要です。
特殊用途自動車であるキャンピングカーの自動車保険に加入する際は、普通車とは異なり、どこの保険会社でも保険を扱っているというわけではありません。
保険会社では、対象車種を自家用5車種もしくは自家用8車種と定めています。
自家用5車種は以下になります。
- 普通乗用車
- 小型乗用車
- 軽四乗用車
- 小型貨物車
- 軽四貨物車
キャンピングカーは含まれないので、自家用5車種を扱う保険会社で保険を加入することはできません。
自家用8車種は以下になります。
- 普通乗用車
- 小型乗用車
- 軽自動車
- 小型貨物車
- 軽貨物車
- 最大積載量0.5t以下の普通貨物車
- 最大積載量0.5t超2t以下の普通貨物車
- 特殊用途車(キャンピングカーなど)
キャンピングカーが含まれているので、自家用8車種を扱う保険会社なら加入することができます。

キャンピングカーには様々な種類があり、走行方法別に2つに分けることができます。
1つ目は、車両とベッドやキッチンなどの居住スペースが一体化した自走式キャンピングカーです。
2つ目は、一般的な車両と箱型の居住スペースのトレーラーを連結させ、車両が牽引しながら走行するトレーラー式です。このタイプは車両と居住スペースが分離しています。
また、自走式キャンピングカーは、べースとなる車によって種類分けされています。
- バスをベースとした「バスコン」
- ワゴンをベースとした「バンコン」
- トラックをベースとした「キャブコン」
- 軽自動車をベースとした「軽コン」
自走式キャンピングカーとトレーラータイプでは、保険の内容も異なります。また、キャンピングカーの種類によっても保険料に差があるので、注意しましょう。
自動車保険では、車種やグレード、運転者の年齢や範囲など、保険料を決める要素がいくつかあります。その中の1つに車の用途、つまり使用目的があります。
車の使用目的は、以下の3つに分けられます。
- 業務
- 通勤・通学
- 日常・レジャー
それぞれ条件が設定されており、業務使用の保険料は一番高く、次いで通勤・通学、一番安いのが日常・レジャーになります。
乗用車は「通勤・通学」に設定している場合も多いですが、キャンピングカーの場合、用途は「日常・レジャー」のみです。そのため、使用目的だけを見ると、キャンピングカーのほうが保険料が安くなります。

自動車保険は、主に4つの基本補償から成り立っています。
- 対人賠償
- 対物賠償
- 人身傷害
- 車両保険
対人賠償は、事故の相手方が死傷した際の治療費などの補償です。
対物賠償は、事故に相手方の車やガードレールなどの他人の財物に与えた損害に対する補償です。
人身傷害は、運転者や同乗者が死傷した際の治療費などの補償です。
車両保険は、自分の車の損害に対する補償です。
キャンピングカーの自動車保険で特に重要なのが「車両保険」になります。
車両保険は、車の車両価格によって保険料が決まります。キャンピングカーの場合、車体はもちろん設備に費用がかかっています。そのため、車両価格は車体価格に設備価格を加算した金額で設定しなければなりません。
また、補償範囲に設備修理費を含めないと、支払われる保険金額が制限されてしまいます。事故によって車体と設備に損害を受けても、設備修理費が保険でカバーされないと全額自己負担となるので気を付けましょう。
キャンピングカーと普通車の保険料を比較すると、装備がいくつもついているキャンピングカーのほうが高いイメージがあるでしょう。しかし、必ずしもそうではありません。
自動車保険では、事故や盗難の発生率などのリスクに応じて車の型式別に保険料率を数字で区分けした「型式別料率クラス制度」を採用している保険会社が多いです。
キャンピングカーは、スポーツカーなどと比べると事故や盗難率、利用頻度も少ないので、料率クラスは比較的低く設定されています。
改造の程度や装備によって違いはありますが、普通車よりも保険料が安くなる場合もあるので、一概に高いとは言えないのが現状です。
キャンピングカーの自動車保険に加入する際の注意点
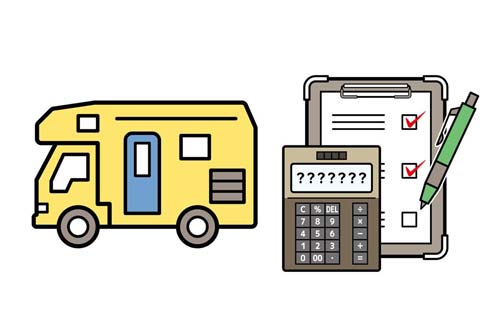
ここまで、キャンピングカーの自動車保険について詳しく解説してきましたが、もし加入する場合はどのようなことに気を付ければいいのでしょう?
ここからは、キャンピングカーの自動車保険に加入する際の注意点をいくつか紹介していきます。
キャンピングカーの車両保険で注意したのが、保険金の上限金額です。
上限金額は、契約車両の車両価格、つまり時価によって異なります。
普通車の場合は基本的に車両本体価格となりますが、キャンピングカーの場合、車によって構造や装備が大きく違う場合が多いです。同じキャンピングカーでも装備の質が高く、改造にかなりの費用がかかっている車もあるでしょう。
そのため、車両本体価格はさほど高くなくても、装備分まで含めると高額になることもあります。
キャンピングカーには一般車両にはない付属品が備わっており、事故などの衝撃でエンジンやボディにはさほどダメージがなくても、装備が破損してしまうケースも多々あります。
そういった場合、車両保険の上限額が少ないと修理費用が全て保険でカバーできず、自己負担となってしまうリスクがあります。
また、車両保険の適用範囲に装備品の故障や破損が含まれていないと、付属品を修理しても保険金が下りない場合もあるので注意しましょう。
免責額というのは、自動車保険において事故による損害額のうち、契約者が自己負担する金額のことです。損害額の中で、保険会社が補償の責任を免除されるということを意味します。
一般的な自動車保険でも車両保険において、免責金額を設定することができます。免責額が高いと保険会社の負担が軽減されることになるので、保険料は安くなります。
また、1回目の事故、2回目に事故で免責額をそれぞれ設定できるようになっています。
キャンピングカーの場合、事故で車体の傷や凹みが軽微であっても、設備が故障するリスクがあります。免責金額を高めに設定すると、免責金額より修理費が安ければ保険金は下りず、全て自己負担となってしまうので注意が必要です。
例えば、免責額が20万円で修理費用が50万円だとすると、20万円は自己負担となり保険金は30万円しか受け取れません。また、修理費用が18万円の場合は保険金は下りず全て実費となってしまいます。
自動車保険の保険料は、車の維持費に関わってくるので、安くするには免責額を高くする必要が出てきます。しかし、キャンピングカーの場合は設備が破損すると高額な修理費用が必要となる可能性も高いので、免責額を高くしすぎると自己負担額が増えることになるでしょう。
免責額をいくらに設定すれば良いかは、慎重に検討することが大事です。
キャンピングカーの目的地というと、山や海など自然豊かな場所であることが多いです。しかし、道が悪い場所に出かけると、バッテリー上がりやタイヤのパンク、脱輪などのトラブルに見舞われるリスクがあります。
その上、周囲に整備工場やガソリンスタンドがない場所であれば、すぐにトラブルを解決してもらえるか分かりません。
こんな時は、自動車保険にロードサービスを付帯させておくと安心です。ロードサービスがあらかじめついている保険もあれば、特約として付帯させなければならない場合もあるので、確認しておきましょう。
自動車保険には、保険料の割増引率を区分けしている「等級制度」が用いられています。等級は1~20等級まであり、新規加入時は6等級からのスタートとなります。
無事故で保険を使わなければ毎年等級が1つずつ上がっていき、保険料の割引率も高くなるという仕組みです。
保険を解約すれば等級はリセットされますが、車の乗りかえの場合は等級をそのまま引き継ぐことができます。そして、キャンピングカーも等級の引き継ぎが可能です。
ただし、加入している自動車保険の加入対象車両が自家用8車種でなければならないので、その点は確認しておきましょう。
自賠責保険の名義変更は必要あるの?手続きの仕方も教えます!
自動車保険の加入前は見積もりをしてもらおう

キャンピングカーは同じ車種や型式でも、改造の仕方や装備などが個々で異なることが多いです。そうなると、車両価格も変わってきます。
一般的な車の自動車保険と違い、加入する保険会社や補償内容によって保険料の金額差も大きくなるでしょう。
キャンピングカーの自動車保険に加入する場合は、保険会社に問い合わせて装備を確認してもらうなど多少手間や時間がかかります。しかし、正確な保険料を算出してもらうためには複数の保険会社に問い合わせて見積もりを取り、比較することが大事です。








