全損事故に遭ったときに相手の過失が認められると賠償を受けられます。賠償で補償される費用は車両代だけではなく、支払い中の税金や廃車費用など、損害と事故の関連性が示せるなら、対象になる可能性があります。
この記事では、全損事故に遭った場合の賠償対象や、保険金の取り扱いについて解説します。万が一の事故に備えたい方は、ぜひ参考にしてください。
車の全損事故では買い替え諸費用の一部が損害賠償の対象になる

全損事故に遭った場合、相手から任意保険を使い買い替えにかかる費用を補償してもらえます。
しかし、賠償されるのは買替諸費用の全額のうち一部であるケースがほとんどで、全額賠償されるかは相手との過失割合や相手の支払い能力によって決まります。
例えば、過失割合が自分と相手で「3:7」の場合、請求した額面から30%がこちらの過失分としてマイナスされます。また、相手の任意保険の補償が十分でなかったり支払い能力がなかったりする場合は満足の行く補償を受けられないことも多くあります。
なお、賠償で請求できる買い替えにかかる諸費用は主に以下の通りです。
- 車両代
- 修理費用(修理できる場合のみ)
- レッカー利用料
- 未経過分の自動車重量税
- 各種登録料
- 休車による機会損失
自動車重量税は、車両の重さに応じてかかる税金です。自動車税は全損で未経過分を還付として受け取れますが、自動車重量税は還付制度が存在しません。したがって、全損事故で賠償を求める場合は未経過の自動車重量税も請求に含めることができます。
また、車両の燃費性能によって異なる税率が課せられる「自動車税環境性能割」という制度が存在します。こちらも買い替えにかかる費用とカウントされるため、請求することが可能です。
損害賠償の対象になるか見極めるポイント

損害賠償として買い替え費用を請求するには、いくつかクリアしなければならない条件があります。
ここからは、損害賠償の対象を見極めるポイントをご紹介します。
賠償で請求できる費用は、事故との関連性を示さなければなりません。
例えば、全損事故で車を新しく買い替える場合は請求できますが、修理できる状態にもかかわらず、新しい車両の購入代金を請求するのは難しいでしょう。
賠償で請求できるのは、あくまで必要が生じた費用に限ります。過度な請求は基本的に認められないため、個人の判断で好きな項目を請求できるわけではありません。
賠償費用を請求する場合、かかった費用の領収書や見積書を提示して、事故との関連性を証明しましょう。
被害車両を処分するためにかかる費用や還付のない既払い費用は、損害賠償の対象になる可能性があります。
例えば、事故現場から車両を移送するのにレッカーを手配した場合、車の処分にかかる費用として認められます。また、廃車手続きにかかる費用も請求の対象です。
車の買い替えに伴う永久抹消登録やスクラップ費用、必要書類の発行手数料など、車両の処分にかかった費用は控えを保管しておきましょう。
全損事故の損害賠償の対象となる買い替え諸費用
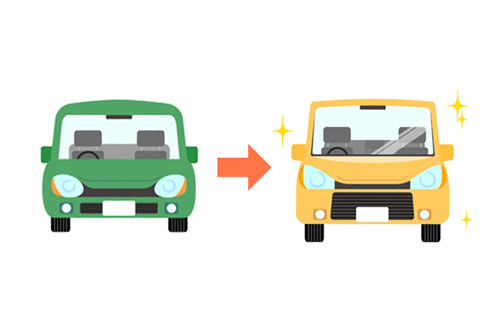
ここからは、任意保険において相手に賠償してもらえる費用項目について紹介します。
自身が事故の被害者の場合、相手の任意保険から車の買い替えにかかる様々な費用を支払ってもらいます。費用の請求は自身で行う他、保険会社や弁護士特約を使って行います。
請求項目に記載していない費用は賠償されないため、どの費用が請求の対象なのか把握する必要があります。
自動車税環境性能割とは、車を取得した際に発生する税金のうち、車の燃費性能に応じて課税されるものです。
自動車税は買替時に発生する費用のため損害賠償の対象です。課税金額は車種やグレード、年式で算出方法が異なります。
例えば、中古車の場合、課税標準基準額に残価率(経過年数に応じた減少価値の割合)をかけた取得価額に税率を当てはめます。
また、自動車税環境性能割は燃費のいい車ほど税金が優遇される制度です。電気自動車の場合は原則非課税です。
車両の購入時に支払う消費税も損害賠償の対象です。また、車両価格に消費税が含まれていない場合は、事故車両と同条件の車を取得する価格の消費税相当額を請求できます。
リサイクル預託金とは、車を購入した際に納めるリサイクルのための費用です。購入者は将来車を廃車するときに備えて、あらかじめリサイクル預託金を支払わなければなりません。
リサイクル預託金は新車購入する場合にかかる費用のため、損害賠償の対象です。
廃車手続きにかかる諸費用は損害賠償で相手に請求できます。廃車にかかる費用は主に以下の通りです。
- 永久抹消登録の登録費用
- レッカー利用料
- リサイクル費用
- 解体費用
- 代行手数料(手続きを代行依頼した場合)
費用相場は個人で手続きするのか業者へ依頼するのかによって異なります。代行業者への依頼も損害賠償の対象なため、基本的に業者に依頼する形で問題ありません。
手続きの際は、かかった費用の領収書や控えを保管しておきましょう。
残存車検費用も損害賠償の対象です。車検費用は事故で返ってこないため、損害賠償の請求項目に加えることで支払われる可能性があります。
残存車検費用の計算式は以下になります。
ただし、残存車検費用は事故車の時価額に反映されていることがあります。この場合は二重請求にあたるため、残存車検費用は請求できません。
また、車検残余期間の保険料の返還を受けている場合は、車検費用から保険料を差し引いた金額を請求しましょう。
全損事故の損害賠償の対象とならない買い替え諸費用

事故と関連性がある出費でも、一部の費用は損害賠償として請求できません。
ここからは、損害賠償の対象ではない買い替え諸費用について紹介します。
自動車税は損害賠償の対象と認められません。
自動車税種別割とは、車両性能に応じて課せられる税金のことで、種別や総排気量など様々な区分で異なる税金がかかります。
また、軽自動車税種別割は軽自動車に対してかかる自動車税です。
自動車税種別割は、廃車手続き後に還付を受けられる可能性が高いため、損害賠償として請求できません。また、軽自動車税種別割は還付を受けられませんが、自動車税であることから賠償の対象外です。
自動車税は賠償されませんが、自動車重量税は請求対象です。混同しないよう注意しましょう。
自賠責保険は解約時に未経過分の還付を受けられるため、損害賠償で請求できません。
また、車両保険も同様で、保険の使用で保険料が上がったとしても、差額分の賠償は不可能です。
車が事故で全損した場合の保険金について

任意の車両保険に加入している場合、適用条件を満たしていれば補償が受けられます。補償金額は加入している保険の内容や事故の程度で決まります。
ここからは、事故で全損した場合の保険料について紹介します。
単独事故の場合、契約時に決めた上限金額内で保険金が支払われます。単独事故にあたる内容は、主に以下の通りです。
- 居眠り運転で電柱に激突した
- 急カーブを曲がりきれずにガードレールにぶつかった
- 崖から転落した
- 運転を誤って川に落ちた
基本的に相手がいない事故は単独事故に該当します。
ただし、地震・津波など災害による全損は保険の適用外となる可能性があります。気になる方は契約内容を確認しておきましょう。
相手がいる事故で車両が全損した場合、全損車両の時価額を目安に保険金を受け取れます。
時価額とは、経過年数に応じた車両の価値のことです。車は経過年数と共に価値が減少するため、適切な価値の計算に時価額が用いられます。
例えば、新車で300万円した車でも現時点の時価額が200万円の場合は保険金の上限額は200万円です。
事故相手がいる場合の賠償は、基本的に相手方の対物賠償保険や自賠責保険が適用されます。相手の対物賠償保険に対物超過特約が付帯している場合は、さらに保険金を請求できます。
ただし、相手がいる事故は過失割合に応じた金額が支払われる点に注意しましょう。相手の過失が10割でない限り、全額補償はされません。こちらの過失が多い場合は、支払額のほうが多くなることもあります。
ただし、受け取れる金額の上限は、車両の時価額か修理にかかる費用のいずれか低いほうです。例えば、時価額が200万円、修理費用が220万円かかる場合、車両保険では200万円のほうが適用されます。
全損した車を廃車にするメリット

事故で車の買い替えをする際、前の車を速やかに処分しなければ余分な出費が発生するでしょう。事故で車が全損した場合、早期に対応することで様々なメリットを享受できます。
ここからは、全損した車両を廃車にするメリットについて紹介します。
廃車手続きで車を処分すると、自動車税を支払う必要がなくなります。自動車税は車検証の登録が続く限り発生するため、廃車手続きで登録を抹消しない限り支払い義務が発生します。
また、廃車手続きよりも買い替えを先に済ませると、新しい自動車と事故車両の2つで支払いが起こる可能性もあります。
自動車税を一括払いしていて、次回の支払時期が近づいているなら、速やかに廃車手続きをする必要があります。
手続きは、お住まいの地域の陸運局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)にて行えますが、混雑するシーズンは手続きが翌日までかかることもあります。業者に代行依頼する場合もある程度日数が必要なため、早めの行動がおすすめです。
自動車税と同様の理由で、廃車手続きで自動車重量税の支払いもストップできます。
自動車重量税は賠償で補填できるため急ぐ必要はありませんが、単独事故かつ無保険の場合は速やかに廃車手続きを行いましょう。
自賠責保険は車両に対して付与されているため、廃車後に支払いをストップできます。
ただし、陸運局の廃車手続きで自賠責保険の解約はできません。自賠責保険を解約するには廃車手続きを済ませた後に保険会社へ連絡し、必要書類を提出することで解約できます。
なお、自賠責保険の解約に必要な書類は以下の通りです。
- 自賠責保険承認請求書
- 運転免許証や健康保険証など本人確認できる書類
- 還付金の振込先口座が記載された通帳
- 廃車手続きを証明できる書類1通
- 印鑑
解約は直接保険会社へ出向くか、電話で受付可能です。書類の郵送で解約手続きを済ませる場合は「自賠責保険承認請求書」の郵送をお願いしましょう。
速やかに廃車手続きを行うことで、各種税金や保険の還付を受けられます。廃車手続きによって返ってくるお金は以下の通りです。
- 自動車税
- 自動車重量税
- 自賠責保険の未経過分
- 車両保険
なお、軽自動車は自動車税の還付がないので注意しましょう。また、還付金は基本的に月割で計算されるため、手続きが月をまたぐと還付金が減少します。もし月末に廃車手続きをするなら、月が変わる前に行動しましょう。
全損した車を廃車にするデメリット

全損した車はそのまま置いていても税金や保険料がかかるため、速やかな廃車手続きがおすすめです。
しかし、廃車手続きは手間と費用がかかるなどのデメリットも存在します。廃車手続きを行動に移す前に、時間的余裕や金銭事情を考えて動き出しましょう。
ここからは、全損した車を廃車にするデメリットについて紹介します。
廃車手続きは個人・代行どちらの手段でも手間がかかります。市役所での必要書類の発行や申請用紙への記入などは、公共施設が稼働している平日にまとまった時間が必要になります。
個人で全損した車を処分するには、以下の書類を用意しなければなりません。
- 車検証
- 自賠責保険証
- ナンバープレート2枚
- 自動車リサイクル券
- 手数料納付書(陸運局にて入手可能)
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 名義人の実印
- 各種申請用紙(陸運局にて入手可能)
- 解体報告記録
- 使用済自動車引取証明書
なお、代行業者に依頼した場合に必要な書類は以下の通りです。
- 車検証
- 自賠保険証
- 運転免許証のコピー
- 印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 名義人の実印がある委任状
どちらの方法でも市役所や区役所にて必要書類を発行する必要があります。マイナンバーカードを持っている方は印鑑証明証をコンビニでも発行できるため、やや労力を軽減できます。
廃車手続きには車両の解体が必要ですが、解体依頼やレッカー車の手配には費用がかかります。また、代行業者に依頼する場合は代行手数料も発生します。
解体を含む手続きを依頼する場合は個人・業者どちらでも2〜5万円程度のお金は用意しておきましょう。
廃車を専門に取り扱う廃車買取業者に限っては、無料で手続きを代行してもらえる場合もあります。できるだけ費用を抑えたい方は、近隣エリアに廃車買取業者がないか調べてみましょう。
例えば、物理的全損は修理を施せないほど車体が損傷しているため、廃車にするしかありません。一方、経済的全損は修理すれば走行が可能です。愛着のある車なら修理するのもよいでしょう。しかし、修理費用が時価額を超えるため、車両保険を適用しても損害のすべては補填できません。また、事故車の修理は修復歴がつくため、車両の売却時に査定額が大幅にマイナスされる可能性がある点には注意しましょう。
全損した車の廃車手続きを行った場合の保険金について

任意の車両保険に加入している場合、全損事故の廃車手続きで保険が使える可能性もあります。
ここからは、廃車手続きを行った場合の保険金について紹介します。
車両保険は車の発生した損害に対して補償が下りる仕組みです。修理や廃車の必要性にかかわらず、損害が生じていれば条件に該当するでしょう。
もしも時間に余裕があるなら、保険金の金額を確認してから買い替えを検討するのも良いでしょう。
加入している車両保険によっては、保険の適用要件に「車両の引き取り」が加わっている場合があります。この場合、既に車両の解体や廃車手続きを済ませていると保険が適用できません。
各種税金や自賠責保険を止めるには廃車手続きを必要としますが、手続きの前に加入している保険の適用要件を確認しておきましょう。
しかし、車両の引き取りは車の所有権を保険会社へ移すため、廃車手続きが必要なくなります。廃車は費用と手間がかかるため、あえて保険を適用するのもよいでしょう。
任意保険は要件を満たしていても、適用の義務はありません。保険を使うかは個人の判断なため、保険料の等級や金額を維持するためにあえて保険を申請しないケースもあります。
例えば、電柱にぶつかる単独事故の場合に保険を使うと3等級のダウンです。保険の内容にもよりますが、無事故状態から3等級ダウンすると、今後数年間負担する保険料が大幅に増加します。
事故の規模によっては保険の適用で実質的な損害を被ることがあるため、保険を適用するかは補償額と等級のバランスを考慮しましょう。





