タイヤ交換
更新日:2022.07.05 / 掲載日:2022.07.04
タイヤ交換でタイヤをローテーションさせるメリットは?タイヤの入れ替えタイミングや方法も解説
車には4本のタイヤが装着されているため、タイヤは定期的にローテーションをしたほうがよいと言われています。しかし、ローテーションの意味が分からない人や必要性を感じていないという人は、意外に多いのではないでしょうか。
そこで今回は、タイヤのローテーションを行うメリットや注意点、依頼先などの情報を詳しく解説します。この記事を読んでローテーションの必要性を理解し、より安全かつ経済的に車を利用しましょう。
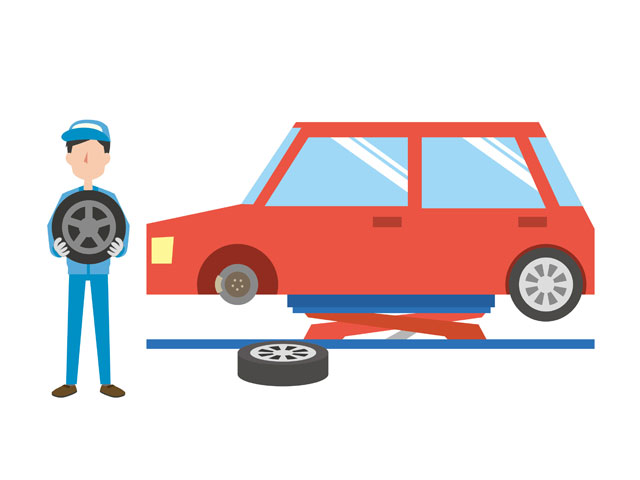
実はトレッド面の摩耗度合いや摩耗する部分は前輪と後輪で違いがあり、ローテーションをしないとタイヤの寿命が短くなってしまうからです。
ローテーションは上記のような状態を防ぐために有効な方法といえますが、ローテーションの仕方は車種やタイヤの種類により異なります。左右や前後だけでなく、場合によっては斜め方向に交換することもあるのです。
なお、スポーツカーなど一部車種では前後で異なるサイズのタイヤを履く場合があり、これらの車種ではローテーションができません。

いずれのメリットも4輪を均等に摩耗させることによるものですが、具体的にどのようなものがあるかを確認しておきましょう。
また、サスペンションのセッティングは前後で異なり、使用するうちに特にタイヤ内側の摩耗が極端に違ってきてしまうのです。しかし、タイヤの位置を入れ替えるローテーションはゴムの減り具合を均一にできるため、タイヤの摩耗による異常な振動や異音の発生を抑えることにつながります。
また、ローテーションしないことで溝の深さが均一でなくなるため、ウエット路面でのグリップ低下により止まりにくくなったり、曲がりにくくなったりすることも。最悪の場合はタイヤの性能が発揮できず、事故の直接的な原因につながることも十分あり得ます。
しかし、ローテーションを行うことでタイヤ本来の性能を発揮できるため、結果として安全な走行にもつながるのです。
タイヤのローテーションを行わずに長く走行し続けると、駆動輪の摩耗だけが早まってしまいます。しかし、定期的にタイヤのローテーションをすることでそれぞれの摩耗度合いを近づけられるため、駆動輪との摩耗差やサスペンションによる前後の摩耗差を最小限に食い止めることが可能です。
また、4本のタイヤが同じくらい摩耗すれば、それだけ長く使用できるため、結果としてタイヤ買い替えの時期を遅らせることができるというメリットもあります。
また、ドライバー本人に対する直接の恩恵ではありませんが、ゴムの消費抑制になるというメリットもあります。つまり、車のタイヤをローテーションさせることは、自分のお財布事情だけでなく地球環境にも優しいカーライフを送れるということです。

ここでは、どんなタイミングや目安でローテーションをすればいいのか、具体的な事例をいくつかご紹介します。
基本的にタイヤは5000km走行するごとに1mm摩耗すると言われているため、5000kmや1万kmなどきりのいいところをローテーションの目安にすれば、覚えやすいのではないでしょうか。
ただし、これはまとまった距離を走行するドライバーにおすすめのタイミングです。そのため、近距離の走行が中心で走行距離が伸びない場合には、これから詳しく説明する定期点検やシーズンタイヤの交換の時期に行うことを検討するとよいでしょう。
シーズンタイヤの交換と一緒にすれば、サマータイヤに加えスタッドレスタイヤもローテーションできるので、ローテーションだけのためにタイヤを外す必要もありません。
タイヤ交換をお店に依頼する際も、「ついでにローテーションも」と一言付け加えれば対応してもらえます。また、お店によっては摩耗具合を見てローテーションしてくれるところがあるので、自分で気をつける機会も少なくて済むでしょう。
点検時にはブレーキパッドの状態を点検したり、サスペンションをチェックしたりとタイヤを外さなければならないため、このときにローテーションするのも目安のひとつになります。
点検を依頼するときに事前にローテーションをお願いしても構いませんし、中には状況に応じてローテーションの必要性を整備士が判断してくれることもあるようです。
できるだけこまめにチェックしたいところですが、給油時に空気圧チェックをお願いするついでに溝の減り具合も確認してもらうと、チェックをする煩わしさを感じないかもしれません。

FFやFRといった駆動方式によっても違いがあり、後輪にスペアタイヤを搭載するクロスカントリーSUVになると、また別のローテーション方法になるからです。さらに、中にはタイヤの銘柄によっては回転方向が指定されているものもあります。このことから、その車に応じたローテーションをしなければなりません。
FFやFR、4WDなど駆動方式により、それぞれ入れ替え方が少し違うので、ここでは具体的にどのようにローテーションするのかを解説します。
右後輪からスタートする場合には、まず右後輪タイヤを左前輪として使うこととなります。そして、次回のローテーションでは左後輪として使い、その次は右前輪に回すというローテーションの方法です。
実際にはひととおりタイヤをローテーションさせる前にタイヤの寿命が来てしまう可能性がありますが、この順序は覚えておくとよいでしょう。
4WD車の場合は基本的にFRと同様と考えていいですが、4WDの方式によっては別の方法がよいこともあります。パートタイム式4WD車やスポーツカーなど常に4輪へ駆動力が伝わるフルタイム4WD車は、FRと同じようなローテーションでよいでしょう。
しかし、FFベースの4WD車の多くは、フルタイム4WDという名称でもいわゆる「スタンバイ式4WD」と言われており、通常は前輪のみを駆動します。この場合はFF車に準じたローテーションが好ましいこともあるので、判断できない人はタイヤのプロに相談するのがおすすめです。
この場合、回転させる方向が指定されているため、左右の摩耗の減り具合を均一にすることはできません。しかし、前後のタイヤを入れ替えるだけでも摩耗の差を少なくさせることが期待できるため、ローテーションによる一定の効果が期待できるでしょう。
この方法は、最後部にスペアタイヤを備えるクロスカントリーSUVなどの車種で有効です。乗用車でも年式が古いものは同サイズのスペアタイヤを装着していればローテーション可能ですが、テンパータイヤと呼ばれる緊急用タイヤは使用できない点に注意してください。
もちろんパンク修理セットしか装備されていない車種は、5本でのローテーションそのものができません。
このことからも、ローテーションする際も左右を入れ替えることはせず、左側右側それぞれで行わなければなりません。
また、方向性タイヤに限らず、実は路面に接するトレッドを触れば摩耗度合いや減っている箇所がわかるので、装着していた位置がわかります。わざわざタイヤに触れて見分ける人はいないかもしれませんが、知識として頭に入れておくのもよいでしょう。
また、ローテーション後の装着位置を間違えたり、作業効率が低かったりと、慣れない人がDIYで対応するのは意外に困難でしょう。
そのため、ローテーション作業に自信がない人は、工賃はかかってしまうもののカー用品店やディーラー、ガソリンスタンドなどのプロに依頼するのが無難です。

いずれの場合も急な対応は難しいですが、事前に予約を入れた上で交換を依頼すればわずかな待ち時間でローテーションをしてくれるため、非常に便利です。作業費用がかかるといっても、作業の手間暇や専用工具の購入経費を考えればむしろリーズナブルかもしれません。
店舗の種類ごとに、実際の費用や依頼するメリットをご紹介します。
作業が始まったら、他のカー用品を探したり、フリースペースで休憩したりして待つことも可能です。わずかな時間で作業が終わるため、気軽に依頼できるでしょう。
依頼するディーラーによって工賃は多少異なることはありますが、1台20~30分の作業で2000円~3000円という相場で対応してもらえます。
作業時間や工賃も他の依頼先と大きく違わず、1台あたり2000円~3000円程度を支払えば作業時間15~30分でローテーションしてくれます。
ローテーション作業を業者に依頼すれば、新しくタイヤを購入した際の組み替えやバランス調整などタイヤに関してトータルなサポートが受けることが可能です。費用はかかりますが、しっかりした作業の工賃が約3000円しかかからないのはむしろお得でしょう。
自分で作業する際は十分なトルクで締め付けないと外れる可能性もあるので、安全面でもローテーション作業は業者に依頼するのがおすすめです。
点検整備などのついでに依頼すれば時間や費用を少しでも減らせるので、ローテーションの依頼は定期メンテナンスの時期を狙いましょう。
そこで今回は、タイヤのローテーションを行うメリットや注意点、依頼先などの情報を詳しく解説します。この記事を読んでローテーションの必要性を理解し、より安全かつ経済的に車を利用しましょう。
この記事の目次
タイヤ交換のローテーションとは?
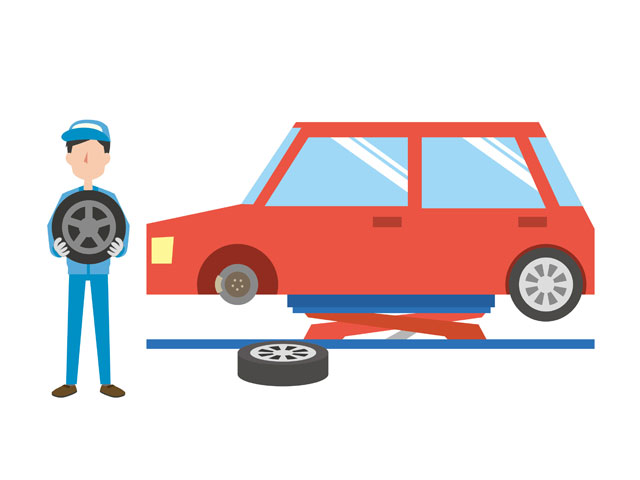
実はトレッド面の摩耗度合いや摩耗する部分は前輪と後輪で違いがあり、ローテーションをしないとタイヤの寿命が短くなってしまうからです。
ローテーションは上記のような状態を防ぐために有効な方法といえますが、ローテーションの仕方は車種やタイヤの種類により異なります。左右や前後だけでなく、場合によっては斜め方向に交換することもあるのです。
なお、スポーツカーなど一部車種では前後で異なるサイズのタイヤを履く場合があり、これらの車種ではローテーションができません。
タイヤをローテーションさせるメリット

いずれのメリットも4輪を均等に摩耗させることによるものですが、具体的にどのようなものがあるかを確認しておきましょう。
タイヤの摩耗を均一にする
タイヤのローテーションを行う最大のメリットは、タイヤの摩耗度合いを均一にできることでしょう。基本的に駆動輪(動力源から駆動トルクが伝えられる車輪のこと)のタイヤは他の2輪よりも摩耗しやすいという特徴があるため、ローテーションをしないと駆動輪とそれ以外の摩耗度合いが極端に変わってしまいます。また、サスペンションのセッティングは前後で異なり、使用するうちに特にタイヤ内側の摩耗が極端に違ってきてしまうのです。しかし、タイヤの位置を入れ替えるローテーションはゴムの減り具合を均一にできるため、タイヤの摩耗による異常な振動や異音の発生を抑えることにつながります。
タイヤの性能が発揮できる
ローテーションすることでタイヤの摩耗を均一にすれば、タイヤ本来の性能を十分に発揮させることが可能です。4本のタイヤ摩耗が異なるままで走行を続けると、偏摩耗による車体の振動や直進安定性の低下といった症状が出る場合があります。また、ローテーションしないことで溝の深さが均一でなくなるため、ウエット路面でのグリップ低下により止まりにくくなったり、曲がりにくくなったりすることも。最悪の場合はタイヤの性能が発揮できず、事故の直接的な原因につながることも十分あり得ます。
しかし、ローテーションを行うことでタイヤ本来の性能を発揮できるため、結果として安全な走行にもつながるのです。
ひとつのタイヤを長く使用できる
タイヤの摩耗を均一にするためにローテーションを行うことで、タイヤの寿命もより長持ちさせることが可能です。タイヤのローテーションを行わずに長く走行し続けると、駆動輪の摩耗だけが早まってしまいます。しかし、定期的にタイヤのローテーションをすることでそれぞれの摩耗度合いを近づけられるため、駆動輪との摩耗差やサスペンションによる前後の摩耗差を最小限に食い止めることが可能です。
また、4本のタイヤが同じくらい摩耗すれば、それだけ長く使用できるため、結果としてタイヤ買い替えの時期を遅らせることができるというメリットもあります。
買い替えの頻度を抑える
タイヤのローテーションを行うメリットとしては、タイヤの買い換えの頻度が減ったり、タイヤ購入に関わる出費を抑えることができたりするという点があります。買い換えの頻度が少なくなれば、それだけ次の購入時期を後ろにずらすことが可能となり、購入費用を減らすことにもつながるため、経済的だからです。また、ドライバー本人に対する直接の恩恵ではありませんが、ゴムの消費抑制になるというメリットもあります。つまり、車のタイヤをローテーションさせることは、自分のお財布事情だけでなく地球環境にも優しいカーライフを送れるということです。
タイヤをローテーションさせるタイミング

ここでは、どんなタイミングや目安でローテーションをすればいいのか、具体的な事例をいくつかご紹介します。
目安は走行距離
ローテーションさせるタイミングがよくわからないという人は、一定の走行距離を目安にしてタイヤを交換することをおすすめします。基本的にタイヤは5000km走行するごとに1mm摩耗すると言われているため、5000kmや1万kmなどきりのいいところをローテーションの目安にすれば、覚えやすいのではないでしょうか。
ただし、これはまとまった距離を走行するドライバーにおすすめのタイミングです。そのため、近距離の走行が中心で走行距離が伸びない場合には、これから詳しく説明する定期点検やシーズンタイヤの交換の時期に行うことを検討するとよいでしょう。
シーズンタイヤの交換時期
雪国のドライバーなどは降雪前と春の年2回タイヤ交換を行うため、このときにローテーションもするというのも交換時期として適当です。シーズンタイヤの交換と一緒にすれば、サマータイヤに加えスタッドレスタイヤもローテーションできるので、ローテーションだけのためにタイヤを外す必要もありません。
タイヤ交換をお店に依頼する際も、「ついでにローテーションも」と一言付け加えれば対応してもらえます。また、お店によっては摩耗具合を見てローテーションしてくれるところがあるので、自分で気をつける機会も少なくて済むでしょう。
定期点検
ローテーションのタイミングとしては、車の定期点検と同時に行うのもおすすめです。車は一定期間ごとの法定点検が義務付けられており、多くのドライバーはディーラーや整備工場に点検整備を依頼することになるでしょう。点検時にはブレーキパッドの状態を点検したり、サスペンションをチェックしたりとタイヤを外さなければならないため、このときにローテーションするのも目安のひとつになります。
点検を依頼するときに事前にローテーションをお願いしても構いませんし、中には状況に応じてローテーションの必要性を整備士が判断してくれることもあるようです。
大切なのは定期的なタイヤのチェック
ローテーション時期のタイミングをご紹介しましたが、これはあくまで目安でしかありません。車種やタイヤの種類、また走行する環境や1回あたりの距離など、タイヤが摩耗する度合いは1台1台違います。そのため、定期的な摩耗チェックをした上で実際にローテーションをするタイミングを図るようにしましょう。できるだけこまめにチェックしたいところですが、給油時に空気圧チェックをお願いするついでに溝の減り具合も確認してもらうと、チェックをする煩わしさを感じないかもしれません。
ローテーションは駆動方式や本数によって異なる

FFやFRといった駆動方式によっても違いがあり、後輪にスペアタイヤを搭載するクロスカントリーSUVになると、また別のローテーション方法になるからです。さらに、中にはタイヤの銘柄によっては回転方向が指定されているものもあります。このことから、その車に応じたローテーションをしなければなりません。
タイヤ4本でローテーションさせる場合
タイヤ4本によるローテーションは、多くの乗用車があてはまる一般的なローテーションの方法と言えます。しかし、4本の場合は2輪同時に外さなければならないため、少し面倒です。FFやFR、4WDなど駆動方式により、それぞれ入れ替え方が少し違うので、ここでは具体的にどのようにローテーションするのかを解説します。
FF車
ローテーションの基本は、駆動輪のタイヤと非駆動輪のタイヤをクロスに使い回すというものです。FF車のタイヤは、後輪から斜めの前輪、同じ側の後輪という順序でローテーションさせていきます。右後輪からスタートする場合には、まず右後輪タイヤを左前輪として使うこととなります。そして、次回のローテーションでは左後輪として使い、その次は右前輪に回すというローテーションの方法です。
実際にはひととおりタイヤをローテーションさせる前にタイヤの寿命が来てしまう可能性がありますが、この順序は覚えておくとよいでしょう。
FR車及び4WD車
FR車及び4WD車の場合は、FF車と違うローテーションを行います。FR車はFF車と逆の流れで行い、右後輪から右前輪、左後輪の次に左前輪という流れです。4WD車の場合は基本的にFRと同様と考えていいですが、4WDの方式によっては別の方法がよいこともあります。パートタイム式4WD車やスポーツカーなど常に4輪へ駆動力が伝わるフルタイム4WD車は、FRと同じようなローテーションでよいでしょう。
しかし、FFベースの4WD車の多くは、フルタイム4WDという名称でもいわゆる「スタンバイ式4WD」と言われており、通常は前輪のみを駆動します。この場合はFF車に準じたローテーションが好ましいこともあるので、判断できない人はタイヤのプロに相談するのがおすすめです。
方向性タイヤ
回転方向が指定されている銘柄の方向性タイヤを履いている車の場合は他の入れ替え方法とは異なり、駆動方式に関係なく前後を入れ替えるだけのローテーションをすることとなります。この場合、回転させる方向が指定されているため、左右の摩耗の減り具合を均一にすることはできません。しかし、前後のタイヤを入れ替えるだけでも摩耗の差を少なくさせることが期待できるため、ローテーションによる一定の効果が期待できるでしょう。
タイヤ5本でローテーションさせる場合
使用している4本のタイヤとスペアタイヤが同じサイズの場合は、5本でローテーションさせることも可能です。この場合前輪に使ったタイヤをスペアに回すという方法になり、右前輪を例にすると「右前輪→スペア→左後輪→左前輪→右後輪→右前輪」とローテーションを行います。この方法は、最後部にスペアタイヤを備えるクロスカントリーSUVなどの車種で有効です。乗用車でも年式が古いものは同サイズのスペアタイヤを装着していればローテーション可能ですが、テンパータイヤと呼ばれる緊急用タイヤは使用できない点に注意してください。
もちろんパンク修理セットしか装備されていない車種は、5本でのローテーションそのものができません。
装着時に注意が必要な方向性タイヤ
いわゆる方向性タイヤの装着時やローテーション時には、タイヤの回転方向にも注意するようにしましょう。方向性タイヤは指定された方向に回転させることで、はじめて本来の性能を発揮します。そのため、回転方向を反対にしてしまうと十分な性能を発揮せず、タイヤの限界が早くなってしまうため、非常に危険です。このことからも、ローテーションする際も左右を入れ替えることはせず、左側右側それぞれで行わなければなりません。
方向性タイヤの見分け方
方向性タイヤは、指定された回転方向を見た目で判別できます。路面に接するトレッドパターンが前後で非対称になっているのがわかるのですが、サイドウォールを見れば回転方向を示す矢印やRotationのマークが確認できるからです。方向性タイヤを装着する際は、矢印の方向にタイヤをセットしましょう。また、方向性タイヤに限らず、実は路面に接するトレッドを触れば摩耗度合いや減っている箇所がわかるので、装着していた位置がわかります。わざわざタイヤに触れて見分ける人はいないかもしれませんが、知識として頭に入れておくのもよいでしょう。
タイヤ交換のローテーションは自分でできる?
タイヤのローテーション作業は自分でも行えますが、タイヤ4本でのローテーションはボディのリフトアップをはじめ工夫をする必要があります。また、ローテーション後の装着位置を間違えたり、作業効率が低かったりと、慣れない人がDIYで対応するのは意外に困難でしょう。
そのため、ローテーション作業に自信がない人は、工賃はかかってしまうもののカー用品店やディーラー、ガソリンスタンドなどのプロに依頼するのが無難です。
プロに依頼した場合の費用やメリット

いずれの場合も急な対応は難しいですが、事前に予約を入れた上で交換を依頼すればわずかな待ち時間でローテーションをしてくれるため、非常に便利です。作業費用がかかるといっても、作業の手間暇や専用工具の購入経費を考えればむしろリーズナブルかもしれません。
店舗の種類ごとに、実際の費用や依頼するメリットをご紹介します。
カー用品店
タイヤのローテーションの依頼先としては、タイヤを購入するカー用品店がまず挙げられるでしょう。購入した店舗に依頼すれば、ローテーション単独でも季節のタイヤ交換でも1台分2000円~3000円程度、作業時間も15~20分程度で対応してもらうことができます。作業が始まったら、他のカー用品を探したり、フリースペースで休憩したりして待つことも可能です。わずかな時間で作業が終わるため、気軽に依頼できるでしょう。
ディーラー
新車や中古車を購入したディーラーにローテーションを依頼すれば、タイヤの交換時に簡単な車両チェックもしてもらえるというメリットがあります。反対に定期メンテナンスと同時に依頼することも可能となっており、この場合は自分でローテーション時期を心配する必要がなくなるでしょう。依頼するディーラーによって工賃は多少異なることはありますが、1台20~30分の作業で2000円~3000円という相場で対応してもらえます。
ガソリンスタンド
ガソリンスタンドであれば、給油ついでにローテーションを依頼したり、作業してもらったりすることも可能なため、わざわざローテーションのために足を運ぶ必要がありません。セルフ給油のスタンドが増えたこともあり、常時作業をしてくれるわけではありませんが、スタッフは常駐しているため、相談や予約は受け付けてもらえるでしょう。作業時間や工賃も他の依頼先と大きく違わず、1台あたり2000円~3000円程度を支払えば作業時間15~30分でローテーションしてくれます。
タイヤ交換のローテーションは業者に依頼
タイヤのローテーションは自分で行うことも可能ですが、効率よく作業するにはちょっとしたコツが必要で、手間もかかります。ローテーション作業を業者に依頼すれば、新しくタイヤを購入した際の組み替えやバランス調整などタイヤに関してトータルなサポートが受けることが可能です。費用はかかりますが、しっかりした作業の工賃が約3000円しかかからないのはむしろお得でしょう。
自分で作業する際は十分なトルクで締め付けないと外れる可能性もあるので、安全面でもローテーション作業は業者に依頼するのがおすすめです。
依頼する時期を見極める
ローテーションを業者にしてもらう場合は、定期点検や季節のタイヤ交換など他のメンテナンスと一緒に依頼するのがよいでしょう。作業時間や工賃はそれほどの負担ではありませんが、ローテーションは緊急を要する作業ではなく、単独で依頼しようとすると連絡を忘れることがあるかもしれません。点検整備などのついでに依頼すれば時間や費用を少しでも減らせるので、ローテーションの依頼は定期メンテナンスの時期を狙いましょう。
まとめ
①タイヤの装着位置をローテーションさせることで、タイヤの摩耗を均一にできる
②ローテーションにより、タイヤを長く使用することができるので買い替え頻度が減る
③ローテーションのタイミングは、走行距離5000kmや1万kmなどがひとつの目安
④定期点検やシーズンタイヤの交換時期に合わせてローテーションさせるのがよい
⑤ローテーションは自分でもできるが、通常の交換と違ったコツが必要なのでプロに依頼するのがおすすめ
この記事の画像を見る
