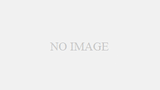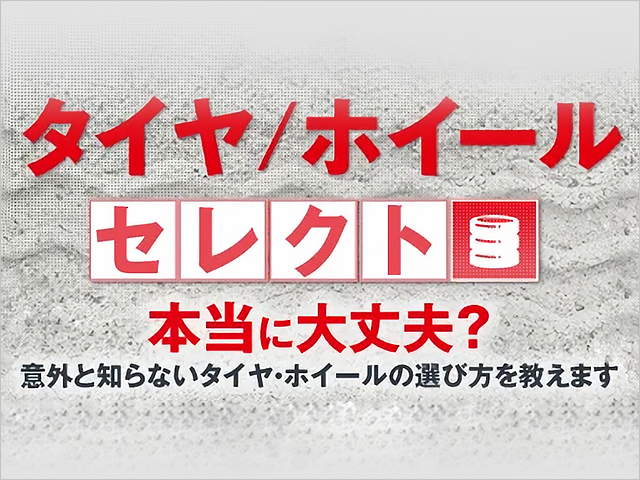タイヤ交換
更新日:2019.12.16 / 掲載日:2019.12.16
インチアップとは?メリット/デメリットやタイヤの選び方を解説!

愛車の足回りをドレスアップする手法の1つであるインチアップ。ホイールを変えるだけでいいので、手軽にできるカスタマイズとして人気があります。
そんなインチアップですが、愛車に適したホイールはどのように選べばいいのでしょうか? また、メリットや注意点などはあるのでしょうか。
今回は、インチアップするメリット・デメリットや、タイヤとホイールの選び方、インチアップする際の注意点について徹底解説します。
インチアップとは

インチアップとは、タイヤの外径を変えずにホイール(リム)を大径化することです。タイヤの扁平率を下げる、つまりタイヤを薄くしてホイールを大きくします。
扁平率はタイヤの高さ(サイドウォール)をタイヤの幅で割った数字をパーセント表示にしたもので、偏平率(%)=タイヤの断面の高さ÷タイヤの断面幅×100で計算できます。低いパーセントのタイヤほど車を横から見たときのタイヤの厚みが薄くなり、タイヤの幅は広くなります。
インチアップのほかに、ホイール径は変えずにタイヤの幅を広げることで相対的に扁平率を下げる「セイムリム扁平化」という手法も存在します。ホイールの買い替えが不要なのでコストは少なくて済みますが、タイヤ幅が広くなるのでホイールハウス内のスペース的な制限から、セイムリム化できる車種は限られています。
インチアップするメリットについて

インチアップは主に、見た目を良くすることを目的に行われるイメージがあると思いますが、ルックス向上だけでなく走行性能にもメリットがあります。それぞれのメリットについて見ていきましょう。
見た目が良くなる
第一に挙げられるメリットとして、インチアップすることでホイールが大きくなり見た目がかっこよくなります。また、単にホイールが大きく見えるだけでなく、ホイールのデザインも自分好みのものに変えることができます。アルミホイールは多種多様な製品があるので、お気に入りの1本を見つければより自分好みのドレスアップが叶います。
ハンドリングのレスポンスが向上する
インチアップを行うとサイドウォールが薄くなり、幅も広がります。その結果タイヤがヨレにくくなるため、操舵に対するレスポンスが良くなります。クイックなハンドリングが好みの人にとってはメリットになるでしょう。
ただし、人によってはクイックすぎて逆にシビアに感じられることもあります。ルーズなハンドリングが好みの人は、あまり極端なインチアップは行わないほうがいいでしょう。
グリップ・ブレーキング性能が上がる
上記でも触れたように、タイヤの扁平率が下がるとタイヤが薄くなり幅が広くなります。タイヤの幅が広くなるとグリップ力が上がり、与えた荷重に対してリニアに反応するようになります。
また、タイヤの厚みが薄くなるとたわみも少なくなるため、コーナリングやブレーキング、発進時のトラクション性能(駆動力)が向上します。
さらに、ホイールが大きくなることでブレーキの大型化が可能となります。ブレーキを大型化した場合、より強力な制動力を得ることができるでしょう。
スポーツカーやスーパーカーなどは、初めから大口径のホイールと扁平率の低いタイヤを装着していますが、それはこのようなメリットがあるからです。
インチアップするデメリットについて

見た目以外にもメリットの多いインチアップですが、全くデメリットがない訳ではありません。では、どのようなデメリットがあるのでしょうか?
車の乗り心地が悪くなる
まず1つめのデメリットとして、乗り心地の悪化が挙げられます。インチアップに伴いタイヤのサイドウォールが薄くなるため、タイヤの空気の層が薄くなり路面から受けるショックがダイレクトに伝わってしまうからです。
また、基本的にホイールが大きくなるとタイヤも含めたバネ下重量が増加し、サスペンションの追従性が下がって乗り心地悪化の原因となります。バネ下重量とは、サスペンションから下についている部品の総重量のことを言い、タイヤやホイールもその一部です。
そのほか、タイヤの幅が広くなることで
・ロードノイズ(騒音)が大きくなる
・ハンドルが重くなる
・わだちにハンドルを取られやすくなる
などのデメリットもあります。
燃費が悪くなる
タイヤの幅が広くなり接地面積が増えると、転がり抵抗が増加するため燃費が悪化します。タイヤ自体も転がり抵抗が大きい銘柄であった場合、よりその傾向は強くなるでしょう。
さらに、ホイールの大径化で重量が増すため、エネルギーのロスによっても燃費が悪化します。単純に車の車重が増加するだけでなく、回転物が重くなると回りだすまでに大きなエネルギーを消費するので、二重にパワーロスが発生します。
インチアップ時は目安として、1Lあたり5~20%ほど燃費が悪化すると考えておきましょう。
車高はどうする?タイヤとフェンダーの間隔
インチアップしてもタイヤの外径は変わらないため、タイヤとフェンダーの間隔が気になるという方もいるかもしれません。その場合は、車高調などで車高を下げるという方法もあります。
ただし、一般的なサスペンションではキャンバー角がついてしまい、タイヤの偏摩耗が発生し交換頻度も上がります。
それを避けるには、キャンバー調整が可能な車高調を使用するか、純正で調整機構があれば偏摩耗しないよう調整にする、またはアライメント調整を行うなどの対応が必要になります。
そもそも、車高調でローダウンすることを検討している方は、そちらを先にやっておくと車体とタイヤ・ホイールとのミスマッチも起こりにくくなるので、あわせて計画的に進めるようにしましょう。
タイヤの選び方

インチアップをする際は、正しいタイヤ選びが重要となります。「サイズが合わない…」といったトラブルを避けるためにも、しっかり確認しておきましょう。
外径サイズを確認する
インチアップ後も同等のタイヤ外径サイズを保つために、まずは今履いている純正タイヤの外径を調べましょう。
タイヤ外径はメジャーなどで測ることもできますが、タイヤメーカーのカタログを参照したほうが正確です。例えば、プリウスのタイヤサイズは195/65R15、外径が約635mmです(グレードによってサイズは変わります)。
純正のタイヤサイズが把握できたら、次はインチアップタイヤで外径が同じものを探しましょう。タイヤメーカーのカタログを参照してもいいですし、メーカーによってはインチアップ早見表があるのでそれを参考にしてもいいです。全く同じ外径のタイヤがない場合は、2,3mmのズレであれば許容範囲内です。
先ほどのプリウスを例にインチアップタイヤを探すと、
・205/55R16
・225/50R16
・215/45R17
・215/50R17
・235/40R17
などのタイヤが適合します。こうしてリストアップした外径が同じタイヤの中から、自分好みのサイズを選びましょう。見た目の好みもあると思いますが、先ほど述べたようなデメリットもあるので、あまり極端なインチアップは控えたほうが無難です。
なお、タイヤの外径が合っていないとスピードメーターが狂ってしまうので注意してください。タイヤが小さいと実速度よりスピードが速く表示され、タイヤが大きいとその逆になります。車検でも多少のズレは許容されていますが、ズレが許容範囲を超えると車検に通らなくなってしまいます。
荷重指数を確認する
荷重指数とは、タイヤが支えることのできる最大負荷能力を示す指数で、ロードインデックス(LI)と表記されることもあります。荷重指数は大きいほど耐えられる負荷が大きく、小さいほど耐えられる負荷が小さくなります。
ここでは、荷重指数と負荷能力の関係をまとめた表を以下で紹介します。
| 荷重指数 | 負荷能力 | 荷重指数 | 負荷能力 | 荷重指数 | 負荷能力 | 荷重指数 | 負荷能力 |
| (LI) | (kg) | (LI) | (kg) | (LI) | (kg) | (LI) | (kg) |
| 60 | 250 | 76 | 400 | 92 | 630 | 108 | 1000 |
| 61 | 257 | 77 | 412 | 93 | 650 | 109 | 1030 |
| 62 | 265 | 78 | 425 | 94 | 670 | 110 | 1060 |
| 63 | 272 | 79 | 437 | 95 | 690 | 111 | 1090 |
| 64 | 280 | 80 | 450 | 96 | 710 | 112 | 1120 |
| 65 | 290 | 81 | 462 | 97 | 730 | 113 | 1150 |
| 66 | 300 | 82 | 475 | 98 | 750 | 114 | 1180 |
| 67 | 307 | 83 | 487 | 99 | 775 | 115 | 1215 |
| 68 | 315 | 84 | 500 | 100 | 800 | 116 | 1250 |
| 69 | 325 | 85 | 515 | 101 | 825 | 117 | 1285 |
| 70 | 335 | 86 | 530 | 102 | 850 | 118 | 1320 |
| 71 | 345 | 87 | 545 | 103 | 875 | 119 | 1360 |
| 72 | 355 | 88 | 560 | 104 | 900 | 120 | 1400 |
| 73 | 365 | 89 | 580 | 105 | 925 | 121 | 1450 |
| 74 | 375 | 90 | 600 | 106 | 950 | 122 | 1500 |
| 75 | 387 | 91 | 615 | 107 | 975 | 123 | 1550 |
インチアップをする際は標準タイヤと同等、もしくはそれ以上の荷重指数を持つタイヤを選ぶようにしましょう。荷重指数が標準以下だとタイヤが負荷に耐えられず、バーストするなどの危険があります。
ホイールの選び方

タイヤ選びができたら、次はホイールを選んでいきましょう。ホイールは大きさ(径)さえ合っていればどれでもいい訳ではありません。ハブの穴数や間隔が合っていなければ、装着できないからです。買ったホイールが装着できないという悲劇に遭わないためにも、以下のポイントを確認しておきましょう。
ハブの穴数を確認する
ハブというのはホイールを車軸に連結させる部分のことを言います。ホイールハブとホイールはボルトナットで結合されますが、車両によって穴の数が異なります。
ホイールの中心に4本のボルトが留まっていれば4穴のホイール、ボルトが5本なら5穴のホイールです。穴の数はホイールのサイズによって変わり、基本的には16インチ以上のホイールから5穴、それ以下は4穴のものが多く、軽自動車は4穴のホイールが主流となっています。
当然ながら、穴の数が合っていないとホイールを装着することはできません。タイヤをインチアップする際は、必ず同じ穴数のホイールを購入するようにしてください。
ちなみに、大幅な加工や専用のハブスペーサーを噛ませれば穴数を変換することも不可能ではありません。しかし、強度が弱くなる上にコストがかかるのであまりおすすめしません。
ハブの間隔を確認する
ハブの穴数は意識しても、間隔の違いは見落としがちなポイントです。そもそも、ホイールによってハブの間隔が違うこと自体を知らない人も少なくないでしょう。
ハブの間隔とは、ホイールを留めているボルトの間隔のことを指します。ハブの間隔は“PCD”という規格で決まっており、例えば国産車だとPCD114.3mmや100mmが一般的です。PCDが合っていないとホイールを取り付けることができないため、必ず愛車のPCDと同じホイールを選びましょう。
もし愛車のPCDがよく分からない場合は、カー用品店やタイヤ専門店などでスタッフに相談することをおすすめします。
インチアップする際の注意点

インチアップする際は、サイズの合ったホイールとタイヤを組み合わせる以外にも、注意しなければならない点がいくつかあります。これらの点に注意せずにインチアップを行うと、思わぬトラブルが起きたり道路交通法違反で切符を切られたりする可能性があるので、必ず確認しましょう。
タイヤが車体に接触しないか
前述の通り、タイヤを低扁平化すると幅が広くなります。多少幅広くなる程度であれば問題にはなりにくいですが、あまり大幅にサイズアップすると車体のタイヤハウス(フェンダー)と干渉することがあります。
タイヤが真っすぐな状態では大丈夫そうに見えても、ハンドルを切った際に車体と干渉する可能性もあるのでチェックは入念に行いましょう。タイヤが車体に干渉すると、急に挙動が乱れるなど事故の原因になり大変危険です。そのような場合は、接触しないタイヤと早急に交換してください。
ホイールのインセット・アウトセット(オフセット)に気を付ける
また、タイヤの幅だけでなく、ホイールのインセット・アウトセットによっても干渉する可能性があります。インセット・アウトセットとは、リム幅の中心を基準に、取り付け面(ハブ)が内側(イン)か外側(アウト)かをmmで表したものです。
以前はオフセットという呼称が使われていましたが、2008年7月1日からインセット・アウトセットに変わっています。
・ゼロセットよりもホイールが車体の外に出っ張る=アウトセット
・ゼロセットよりもホイールが車体の内側に引っ込む=インセット
・ハブがリム幅の中心=ゼロセット
知らぬ間にアウトセットのホイールを購入すると、タイヤが車体からはみ出してフェンダーに干渉する恐れがあるので注意してください。
また、インセットの場合でも内側のサスアームなどに干渉することがあります。基本的には標準ホイールと同じサイズにするのが主流ですが、タイヤの幅が広くなった分、少しだけインセットにして帳尻を合わせる裏ワザもあります。
ただ、このような合わせ込みはプロでないと難しいので、タイヤショップなどで相談することをおすすめします。
ホイールが車体よりはみ出さないようにする
ホイールの幅やインセット・アウトセットの組み合わせを間違えると、車体からホイールがはみ出してしまうことがあります。車体からホイールがはみ出している状態は法律で認められておらず、その状態で走行していると整備不良で切符を切られてしまいます。
余談ですが、平成29年6月22日以降にタイヤのはみ出しに関する法改正が行われました。かなり複雑な内容ですが、簡単に言えば「タイヤのみ、車体から10mm以内であれば、はみ出してもOK」というものです。これにより、タイヤのリムガードやラベル(銘柄の表記)の厚みについてはタイヤの突出禁止規定の対象外になりました。
この法改正以降、「ホイールのはみ出し解禁!」と勘違いする人が増えていますが、ホイールやナットのはみ出しは今まで通り禁止されているので注意しましょう。
タイヤは正しい空気圧で使用する
タイヤが低扁平になるとタイヤ内部の空気量が減ってしまうため、タイヤが支えられる負荷(荷重指数)が減ってしまいます。そのため、低扁平なタイヤは通常よりも高い空気圧を必要としますが、むやみに空気圧を上げるとタイヤがバーストする危険があります。
そこで登場するのが、エクストラロードタイヤ(XL)やレインフォースドタイヤ(RF)です。XL(RF)規格のタイヤは高い空気圧に耐えられるため、空気量が少ない低扁平タイヤでも高い負荷に耐えることが可能です。普通のタイヤと同じ空気圧に設定しても高い負荷能力は発揮できないので、空気圧の管理を怠らないようにしましょう。
空気圧はタイヤメーカーの指定に合わせれば問題ありませんが、不安な方はカー用品店などに相談してください。
まとめ
今回は、インチアップするメリット・デメリットや、タイヤとホイールの選び方、注意点について解説しました。
タイヤをインチアップするメリットには、ドレスアップ効果やハンドリングの向上、グリップ・ブレーキング性能の向上が挙げられます。しかし、メリットだけではなく、乗り心地や燃費の悪化がデメリットとして存在します。
タイヤを選ぶ際の注意点としては、外径サイズや荷重指数をよく確認することです。また、ホイールを選ぶ際は、ハブの穴数やハブの間隔も忘れずに確認するようにしましょう。
タイヤをインチアップする際の注意点は、タイヤが車体と接触せず、車体よりはみ出さないように気を付ける、また正しい空気圧で使用することが挙げられます。
正しい知識がないままタイヤをインチアップしてしまうと、車検時に通らないだけでなく、重大な事故を引き起こす恐れもあります。メリットやデメリットを理解した上で、自分好みのインチアップホイールを装着し、愛車をカッコよく仕上げてください!
【合わせて読みたい】車の車高を下げる意味・メリット・デメリットについてはこちらの記事をチェック!