中古車購入チェックポイント
更新日:2022.07.28 / 掲載日:2022.07.28
中古車の購入は経費で計上可能?経費処理方法のポイントを詳しく解説
中古車に限らず、車を事業用に購入した時は、エアコンや社内備品と同様、固定資産になります。
固定資産の場合、経費処理をどのように行えばよいのか分からない点もあるかもしれません。そこで、この記事では中古車や新車を含めた購入時の経費処理における方法と注意点やポイントを詳しく解説していきます。
今後、事業用として車を購入する際の参考にしてください。

車は使用していくと価値が減少していく減価償却資産です。車の購入費は数年に分けて計上することになるため、耐用年数や取得価額が影響してきます。
しかし、要件を満たす場合には全額経費計上を行うことも可能です。これは、「少額減価償却資産」の適用が認められることが関係しています。
青色申告を行っている中小企業などが、年度内において30万円未満の減価償却資産を購入した場合は、一括経費計上ができます。そのため、中古車の購入額が30万円未満であれば、節税に繋がります。
さらに、複数車を購入した際には特例を受けることができる取得価額合計限度額があり、300万円を上限として認められています。
もし年式・車種・走行距離にこだわらないのであれば、販売価格の安い車を複数購入すると、経費計上を早期に実施することが可能です。

一般的に会社員であれば、車を購入しても経費処理を行うことは稀です。しかし、個人事業主であれば経費処理を行うことは必須となるでしょう。
個人事業主が実施する確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。
先ほどお伝えした少額減価償却資産として一括計上するのであれば、青色申告を行っている必要があります。
それでは、理解しておきたい経費計上の基礎知識について、解説していきます。
これは、不動産や会社の備品についても同様です。長期に渡って利用できるものは、国税庁が定めている耐用年数で償却をすることになります。
大規模な設備や機器の費用をまとめて計上しないようにすることで、損益が赤字になったり利益の減少を防いだりすることが可能です。
経理上の扱いとして行うので、本来は購入した費用については販売先に支払うことになります。減価償却費は経費扱いになるので、損金になります。したがって、経理上は利益の減少になりますが、その分法人税の支払いも減少することになります。
つまり、減価償却費が大きくなれば節税効果が高まるということです。そして、耐用年数によって計上する年数が決定し、経費計上するので、その年数分を節税することも可能となります。
しかし、経営状況によっては減価償却費を数年行うことによって、負担が増えて深刻な赤字になってしまうケースもありますので、注意が必要です。
計算式は、以下の通りです。
・自動車の取得価額×償却率
例えば、耐用年数4年で、取得価額が100万円の中古車を購入した場合は次のようになります。
・償却率=1÷4=0.250
<1年間の減価償却費>
100万円×0.250=25万円
25万円を4年かけて減価償却していくことになります。
メリットとして、年間同じ額を計上するため、経理処理が簡単であることが挙げられます。それほど経理が得意でない場合でも、利用しやすい方法と言えるでしょう。
定額法に比べて経理処理が複雑ですが、初年度の経費計上を多くすることが可能なので、購入時に費用を多く計上したいときには利用価値が高いやり方です。
例えば、耐用年数4年で取得価額が100万円の中古車を購入して定率法で償却する際は、以下のように行います。
耐用年数4年における定率法の償却率=0.400
1年目:100万円×0.400=40万円
2年目:(100万円−40万円)×0.400=24万円
3年目:(100万円−40万円−24万円)×0.400=14.4万円
このように手間はかかりますが、経費計上については初年度に大きくすることができるので、節税効果も期待できるでしょう。
個人事業主の場合は、事前に経費計上を定率法で行う旨を税務署に申請する必要がありますので、注意しましょう。
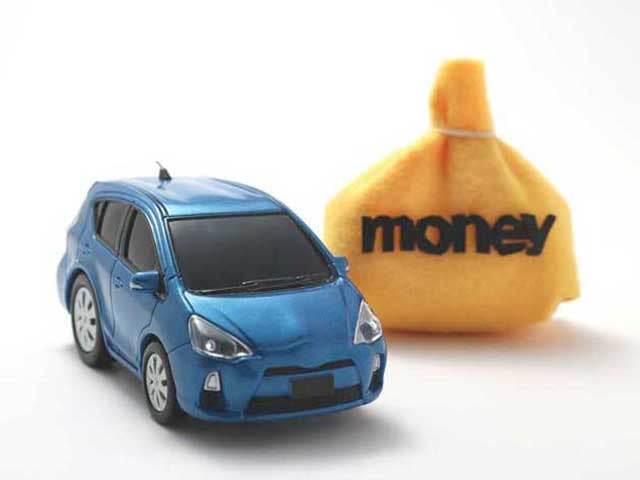
車の購入金額は大きいため、経費として多く計上することで税金対策にも繋がります。
ここからは、経費を大きく計上するポイントについて詳しく解説していきます。
以下が、その法定耐用年数になります。
・普通乗用車:6年
・軽自動車:4年
・バイク:3年
・自転車:2年
上記のようにあと何年間業務で使用できるかを明確にしているので、その期間を減価償却して経費計上を行います。
普通自動車で6年、軽自動車で4年になっており、新車の場合はこれを適用することになります。
減価償却で考えると、新車購入は法定耐用年数が決まっているため、早期に経費計上を行いたい場合は定率法で償却するのが良いでしょう。
ただし、法定耐用年数を「経過していない場合」と「経過している場合」では、計算式が異なるので注意しましょう。
以下は、計算式となりますので、確認してみてください。
例として、2年落ちの普通自動車を購入したケースで計算してみます。普通自動車の法定耐用年数は6年ですので、次のような計算式になります。
(6年−2年)+2年×0.2=4年+0.4年=4.4年
ただし、1年未満は切り捨てになるため、耐用年数は4年として算出されます。
普通自動車は6年、軽自動車4年を経過していると上記の計算式になります。つまり、法定耐用年数を超えている時は、一律同じ耐用年数になります。
例えば、7年落ちの普通自動車を購入した際の耐用年数の計算式は以下の通りです。
6年×0.2=1.2年
2年未満は2年と数えます。つまり、法定耐用年数を超える場合は、耐用年数は2年として、減価償却を行います。そのことを考えると、経過年数によって減価償却が早期に行えることになるでしょう。
新車に比べて中古車は経過年数が異なっているので、ある程度年数が経った中古車は節税効果が大きくなると言えます。

定額法や定率法で実施することになりますが、やり方を知っておけば確定申告などで役立ちます。
それでは、減価償却の方法について「新車」「中古車」「リース」の場合でどうなるのか、具体的な計算式を利用して行っていきます。
例)200万円の軽自動車を新車で購入したケース
年間50万円が減価償却費です。それを4年かけて償却していきます。
1年目:200万円×0.500=100万円
2年目:(200万円−100万円)×0.500=50万円
3年目:(200万円ー100万円−50万円)×0.500=25万円
4年目は1円を備忘価格(耐用年数が過ぎても価値が残るもの)として残して償却します。定額法よりも初年度に大きく計上できることが理解できるでしょう。
例)200万円の普通自動車を2年落ちで購入したケース
耐用年数=(6年−2年)+2年×0.2=4年+0.4年=4.4年
2年以上は1年未満は切り捨てですので、耐用年数は4年となります。
年間50万円を4年かけて償却します。
1年目:200万円×0.500=100万円
2年目:(200万円−100万円)×0.500=50万円
3年目:(200万円−100万円−50万円)×0.500=25万円
中古車も新車と同様の計算ですが、耐用年数の算出が必要になります。
社用車としてカーリースを利用するのであれば、会社の固定資産にはなりません。そのため、面倒な経費処理も必要なく、月々のリース料を計上するだけで行えます。
また、車検やメンテナンス、自動車税などもリース料に含まれるケースが多い点もメリットです。
ただし、リース料として経費計上できる条件は、「リース期間が1年以内」や「リース料の総額が300万円以下」である場合などです。
条件を満たさない時は、リース期間は定額法を用いて減価償却を行うこともありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
例えば、普通自動車で4年落ちの中古車を200万円で購入したとすると、耐用年数は2年で計算されます。
定額法であれば、年間100万円ずつを2年かけて減価償却します。
しかし、定率法であれば、2年の償却率が「1.000」になりますので、一度に200万円を経費計上することが可能です。そのため、4年落ちの中古車は経費計上する点で有利だと言えます。
税金面であれば、損金が多くなることによって収益は低くなってしまいますので、税金も低く抑えることが可能です。中古車を購入する際、普通自動車であれば4年が良いと言われているのはそのためです。
また、軽自動車の場合は2年落ちであれば2年で減価償却することができるので、知っておくと良いでしょう。

経費として計上するときには、耐用年数だけではなく、それ以外にもポイントがあります。それを知った上で行えば、より計上することが可能になるでしょう。
ここからは、中古車を経費計上する際の注意点について、詳しく解説していきます。
経費処理を行う際は、車の利用目的がプライベートの使用だと経費計上ができません。これは、個人事業主や法人でも一緒です。
基本的に法人であれば個人的に使用するケースは稀ですが、個人事業主の場合だと仕事とプライベート兼用で車を利用する機会も多いでしょう。その際は、家事按分で計上することが必要です。
家事按分とは、仕事とプライベートで使用する際に按分率を算出し、仕事で使用した分を経費計上する方法です。
例えば、100万円の中古車を購入して、仕事とプライベートの使用が「6:4」だったとします。その際、中古車の経費計上できる金額は60万円になります。
家事按分における按分率は、その根拠を税務署から求められることもありますので、使用記録簿などを用意して確認しながら按分率を決めると良いでしょう。
節税対策として、4年落ちの中古車を購入して定率法で償却年数を1年にしたとしても、一括計上できるは事業年度初月のみです。
なぜかというと、減価償却費は年度計上ではなく、月ごとの計上になります。そのため、購入時期には気をつけましょう。
事業年度の初めに購入すれば、経費計上を最大限にすることが可能です。しかし、当年の事業年度が赤字になる可能性があれば、あえて決算期末に購入をして減価償却費を少なく計上することもできます。
基本的に取得日は実際に使用した日になりますので、その点は注意しておきましょう。
車のオプション品は、カーナビやドライブレコーダー、ホイールなどが挙げられます。
納車の際に装着した状態であれば、オプション品も一緒に経費計上を行えます。また、オプション品を納車後に装着することで、一括償却することも可能です。
中小企業や個人事業主で青色申告を行う場合、オプション品は少額減価償却資産として適用され、30万円未満の固定資産を一括償却できる特例を受けられます。
ただし、特例を受けるためには条件があり、取得価額の合計が300万円までとなっているので注意しましょう。
どうしても購入費に目がいきがちになってしまいますが、車はメンテナンスや車検、ガソリン代、任意保険、自賠責保険といった費用が必ずかかります。
これらの費用は、基本的に経費として計上することが可能です。ただし、減価償却では行わずに通常の経費処理を行います。
家事按分で計上しているときには、その比率分で計上することになりますので、間違わないように行いましょう。
固定資産の場合、経費処理をどのように行えばよいのか分からない点もあるかもしれません。そこで、この記事では中古車や新車を含めた購入時の経費処理における方法と注意点やポイントを詳しく解説していきます。
今後、事業用として車を購入する際の参考にしてください。
この記事の目次
中古車を購入したら全額を経費計上することは可能?

車は使用していくと価値が減少していく減価償却資産です。車の購入費は数年に分けて計上することになるため、耐用年数や取得価額が影響してきます。
しかし、要件を満たす場合には全額経費計上を行うことも可能です。これは、「少額減価償却資産」の適用が認められることが関係しています。
青色申告を行っている中小企業などが、年度内において30万円未満の減価償却資産を購入した場合は、一括経費計上ができます。そのため、中古車の購入額が30万円未満であれば、節税に繋がります。
さらに、複数車を購入した際には特例を受けることができる取得価額合計限度額があり、300万円を上限として認められています。
もし年式・車種・走行距離にこだわらないのであれば、販売価格の安い車を複数購入すると、経費計上を早期に実施することが可能です。
中古車購入における経費計上の基礎知識

一般的に会社員であれば、車を購入しても経費処理を行うことは稀です。しかし、個人事業主であれば経費処理を行うことは必須となるでしょう。
個人事業主が実施する確定申告は「青色申告」と「白色申告」の2種類の方法があります。
先ほどお伝えした少額減価償却資産として一括計上するのであれば、青色申告を行っている必要があります。
それでは、理解しておきたい経費計上の基礎知識について、解説していきます。
車は減価償却で経費計上する
先程もお伝えした通り、車は固定資産として位置づけられています。そのため、耐用年数から算出した年数で減価償却を行います。これは、不動産や会社の備品についても同様です。長期に渡って利用できるものは、国税庁が定めている耐用年数で償却をすることになります。
大規模な設備や機器の費用をまとめて計上しないようにすることで、損益が赤字になったり利益の減少を防いだりすることが可能です。
経理上の扱いとして行うので、本来は購入した費用については販売先に支払うことになります。減価償却費は経費扱いになるので、損金になります。したがって、経理上は利益の減少になりますが、その分法人税の支払いも減少することになります。
つまり、減価償却費が大きくなれば節税効果が高まるということです。そして、耐用年数によって計上する年数が決定し、経費計上するので、その年数分を節税することも可能となります。
しかし、経営状況によっては減価償却費を数年行うことによって、負担が増えて深刻な赤字になってしまうケースもありますので、注意が必要です。
定額法
定額法とは、毎年決まった金額で経費計上する方法です。個人事業主が行う減価償却の主なやり方になります。計算式は、以下の通りです。
・自動車の取得価額×償却率
例えば、耐用年数4年で、取得価額が100万円の中古車を購入した場合は次のようになります。
・償却率=1÷4=0.250
<1年間の減価償却費>
100万円×0.250=25万円
25万円を4年かけて減価償却していくことになります。
メリットとして、年間同じ額を計上するため、経理処理が簡単であることが挙げられます。それほど経理が得意でない場合でも、利用しやすい方法と言えるでしょう。
定率法
定率法とは、毎年減価償却累計額に一定割合の償却率をかけて減価償却していく方法になります。定額法に比べて経理処理が複雑ですが、初年度の経費計上を多くすることが可能なので、購入時に費用を多く計上したいときには利用価値が高いやり方です。
例えば、耐用年数4年で取得価額が100万円の中古車を購入して定率法で償却する際は、以下のように行います。
耐用年数4年における定率法の償却率=0.400
1年目:100万円×0.400=40万円
2年目:(100万円−40万円)×0.400=24万円
3年目:(100万円−40万円−24万円)×0.400=14.4万円
このように手間はかかりますが、経費計上については初年度に大きくすることができるので、節税効果も期待できるでしょう。
個人事業主の場合は、事前に経費計上を定率法で行う旨を税務署に申請する必要がありますので、注意しましょう。
経費を大きく計上するポイントとは?
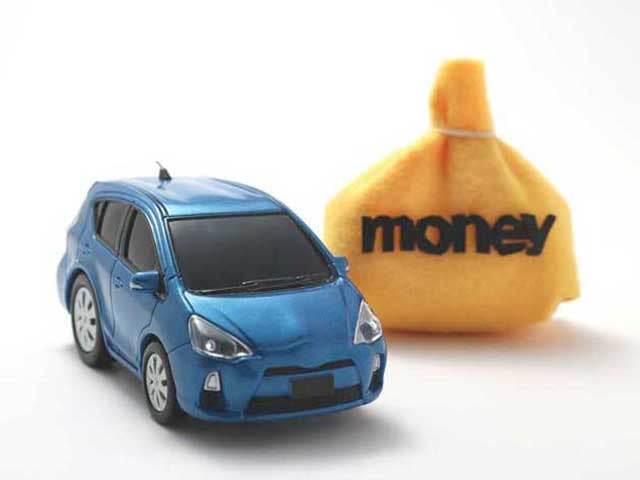
車の購入金額は大きいため、経費として多く計上することで税金対策にも繋がります。
ここからは、経費を大きく計上するポイントについて詳しく解説していきます。
新車の法定耐用年数
新車の法定耐用年数は、国税庁で詳細に定められており、それに基づいて減価償却を行うことになります。以下が、その法定耐用年数になります。
・普通乗用車:6年
・軽自動車:4年
・バイク:3年
・自転車:2年
上記のようにあと何年間業務で使用できるかを明確にしているので、その期間を減価償却して経費計上を行います。
普通自動車で6年、軽自動車で4年になっており、新車の場合はこれを適用することになります。
減価償却で考えると、新車購入は法定耐用年数が決まっているため、早期に経費計上を行いたい場合は定率法で償却するのが良いでしょう。
中古車の耐用年数は計算式がある
中古車の場合は新車と違い、使用年数も個々に異なっているため、耐用年数は経過期間に応じて計上期間が変わります。その際、計算式があるので、それを利用して算出します。ただし、法定耐用年数を「経過していない場合」と「経過している場合」では、計算式が異なるので注意しましょう。
以下は、計算式となりますので、確認してみてください。
法定耐用年数を経過していない場合
(新車法定耐用年数−経過年数)+経過年数×0.2例として、2年落ちの普通自動車を購入したケースで計算してみます。普通自動車の法定耐用年数は6年ですので、次のような計算式になります。
(6年−2年)+2年×0.2=4年+0.4年=4.4年
ただし、1年未満は切り捨てになるため、耐用年数は4年として算出されます。
法定耐用年数を経過している場合
新車法定耐用年数×0.2普通自動車は6年、軽自動車4年を経過していると上記の計算式になります。つまり、法定耐用年数を超えている時は、一律同じ耐用年数になります。
例えば、7年落ちの普通自動車を購入した際の耐用年数の計算式は以下の通りです。
6年×0.2=1.2年
2年未満は2年と数えます。つまり、法定耐用年数を超える場合は、耐用年数は2年として、減価償却を行います。そのことを考えると、経過年数によって減価償却が早期に行えることになるでしょう。
新車に比べて中古車は経過年数が異なっているので、ある程度年数が経った中古車は節税効果が大きくなると言えます。
具体的な減価償却の計算方法

定額法や定率法で実施することになりますが、やり方を知っておけば確定申告などで役立ちます。
それでは、減価償却の方法について「新車」「中古車」「リース」の場合でどうなるのか、具体的な計算式を利用して行っていきます。
新車の減価償却
新車の場合は、法定耐用年数が決まっているので、考慮して償却を行いましょう。例)200万円の軽自動車を新車で購入したケース
定額法で減価償却した場合
200万円×0.250(法定耐用年数4年)=50万円年間50万円が減価償却費です。それを4年かけて償却していきます。
定率法で減価償却した場合
(耐用年数4年の償却率は0.500)1年目:200万円×0.500=100万円
2年目:(200万円−100万円)×0.500=50万円
3年目:(200万円ー100万円−50万円)×0.500=25万円
4年目は1円を備忘価格(耐用年数が過ぎても価値が残るもの)として残して償却します。定額法よりも初年度に大きく計上できることが理解できるでしょう。
中古車の減価償却
中古車の場合は、経過年数で耐用年数が異なりますので、先に耐用年数を計算してから減価償却費を算出するのがポイントです。例)200万円の普通自動車を2年落ちで購入したケース
耐用年数=(6年−2年)+2年×0.2=4年+0.4年=4.4年
2年以上は1年未満は切り捨てですので、耐用年数は4年となります。
定額法で減価償却した場合
200万円×0.250(耐用年数4年)=50万円年間50万円を4年かけて償却します。
定率法で減価償却した場合
(耐用年数4年の償却率は0.500)1年目:200万円×0.500=100万円
2年目:(200万円−100万円)×0.500=50万円
3年目:(200万円−100万円−50万円)×0.500=25万円
中古車も新車と同様の計算ですが、耐用年数の算出が必要になります。
リースの場合の経費計上
車をリース契約した場合の経費計上は、「リース料」として経費計上することが可能です。社用車としてカーリースを利用するのであれば、会社の固定資産にはなりません。そのため、面倒な経費処理も必要なく、月々のリース料を計上するだけで行えます。
また、車検やメンテナンス、自動車税などもリース料に含まれるケースが多い点もメリットです。
ただし、リース料として経費計上できる条件は、「リース期間が1年以内」や「リース料の総額が300万円以下」である場合などです。
条件を満たさない時は、リース期間は定額法を用いて減価償却を行うこともありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。
4年落ちの中古車が経費計上で有利な理由
「4年落ちの中古車が税金対策になる」ということを、聞いたことがあるかもしれません。しかし、どうして経費計上で有利に働くのか知らない方も多いでしょう。例えば、普通自動車で4年落ちの中古車を200万円で購入したとすると、耐用年数は2年で計算されます。
定額法であれば、年間100万円ずつを2年かけて減価償却します。
しかし、定率法であれば、2年の償却率が「1.000」になりますので、一度に200万円を経費計上することが可能です。そのため、4年落ちの中古車は経費計上する点で有利だと言えます。
税金面であれば、損金が多くなることによって収益は低くなってしまいますので、税金も低く抑えることが可能です。中古車を購入する際、普通自動車であれば4年が良いと言われているのはそのためです。
また、軽自動車の場合は2年落ちであれば2年で減価償却することができるので、知っておくと良いでしょう。
中古車を経費計上する際の注意点

経費として計上するときには、耐用年数だけではなく、それ以外にもポイントがあります。それを知った上で行えば、より計上することが可能になるでしょう。
ここからは、中古車を経費計上する際の注意点について、詳しく解説していきます。
事業目的で購入する
1つ目は、事業目的で車を購入することです。経費処理を行う際は、車の利用目的がプライベートの使用だと経費計上ができません。これは、個人事業主や法人でも一緒です。
基本的に法人であれば個人的に使用するケースは稀ですが、個人事業主の場合だと仕事とプライベート兼用で車を利用する機会も多いでしょう。その際は、家事按分で計上することが必要です。
家事按分とは、仕事とプライベートで使用する際に按分率を算出し、仕事で使用した分を経費計上する方法です。
例えば、100万円の中古車を購入して、仕事とプライベートの使用が「6:4」だったとします。その際、中古車の経費計上できる金額は60万円になります。
家事按分における按分率は、その根拠を税務署から求められることもありますので、使用記録簿などを用意して確認しながら按分率を決めると良いでしょう。
決算期末は車を購入しないのが無難
2つ目は、決算期末には車を購入しないことです。節税対策として、4年落ちの中古車を購入して定率法で償却年数を1年にしたとしても、一括計上できるは事業年度初月のみです。
なぜかというと、減価償却費は年度計上ではなく、月ごとの計上になります。そのため、購入時期には気をつけましょう。
事業年度の初めに購入すれば、経費計上を最大限にすることが可能です。しかし、当年の事業年度が赤字になる可能性があれば、あえて決算期末に購入をして減価償却費を少なく計上することもできます。
基本的に取得日は実際に使用した日になりますので、その点は注意しておきましょう。
車のオプション品も経費計上が可能
3つ目は、車のオプション品も経費計上ができることです。車のオプション品は、カーナビやドライブレコーダー、ホイールなどが挙げられます。
納車の際に装着した状態であれば、オプション品も一緒に経費計上を行えます。また、オプション品を納車後に装着することで、一括償却することも可能です。
中小企業や個人事業主で青色申告を行う場合、オプション品は少額減価償却資産として適用され、30万円未満の固定資産を一括償却できる特例を受けられます。
ただし、特例を受けるためには条件があり、取得価額の合計が300万円までとなっているので注意しましょう。
車は維持費が掛かる点にも注意
4つ目は、車には維持費がかかることです。どうしても購入費に目がいきがちになってしまいますが、車はメンテナンスや車検、ガソリン代、任意保険、自賠責保険といった費用が必ずかかります。
これらの費用は、基本的に経費として計上することが可能です。ただし、減価償却では行わずに通常の経費処理を行います。
家事按分で計上しているときには、その比率分で計上することになりますので、間違わないように行いましょう。
まとめ
①中古車は購入年度の減価償却費が多く、4年落ち以上の車は一括経費計上が可能
②購入年度に多くの減価償却を行いたい場合、定率法を利用すると良い
③決算期末に購入してしまうと節税効果は薄いので、決算後の初月に購入する
④事業目的での購入しか経費として処理されないため、個人使用も含まれる場合は、家事按分を行う
⑤税金・保険料・メンテナンス費なども経費計上が可能
この記事の画像を見る
