中古車購入チェックポイント
更新日:2022.08.29 / 掲載日:2022.08.29
中古車の譲渡には贈与税がかかる?贈与税の要件について解説
親が車を使わなくなったため、子供に受け渡すことがあるでしょう。中古車に限らず、車を人に譲渡すると「贈与税」が関わってくるケースがあります。そのため、どのような状態であれば贈与税がかかるのか、知っておくことが必要です。
この記事では、中古車を含めた譲渡に関して、贈与税の課税対象する要件について詳しく解説していきます。
これから車を譲渡する予定がある、譲渡される予定がある方はぜひ参考にしてみてください。
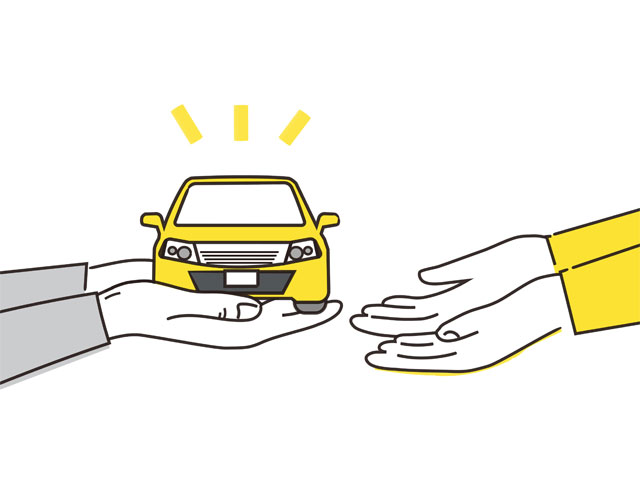
車に限らず財産を贈与すれば、贈与税を負担しなければなりません。
贈与税の計算方法は、贈与された財産を個々に行うのではなく、1年間に贈与された合計金額に応じて翌年に納税を行います。
それに加えて、年間贈与された財産合計から基礎控除(110万円)の金額を差し引いた金額に税率をかけて贈与税額を算出します。

例えば、譲渡してもらった車が110万円以下であれば贈与税はかかりません。ただし、それ以外に財産をもらっていて110万円を超えてしまう時には贈与税がかかります。
年間で110万円を超えるか超えないかがポイントです。
ここからは、譲渡の具体的なケースについて詳しく解説していきます。
子供が地方の大学に進学することになり、日常生活における資金や車が必要になることもあるでしょう。この場合、例えば車を子供に買って譲渡しても贈与税がかかることはありません。
国税庁で定められている法令では「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と示されています。
ここで言われている生活費とは、日常生活に必要な費用のことを指し、養育費や治療費、その他子育てに関する費用が含まれます。そして教育費は、学費や文具費、教材費などが当てはまります。
ただし、生活費や教育費として必要な時に直接充当することがポイントです。そのため、生活費や教育費として受け取り、そのお金を預金したり不動産や投資の資金に充てたりすると贈与税がかかるので、注意しましょう。
結論から言えば、前述したケースと同じように、日常生活に必要とされた状態であれば贈与税はかからないこととなっています。
夫婦だとお互い扶養する義務があるため、生活に必要なお金や車を通常必要と認められる範囲であれば、対象になることはありません。
しかし、車が高級車であれば嗜好品として贈与されると考えられ、贈与税がかかる可能性もあります。生活費であれば贈与税はかかりませんが、生活費と嗜好品の判断が難しいところです。
例えば、普通車であれば、生活に必要なものとして考えられます。しかし、既に車が1台あるのにも関わらず、夫が全額出して高級車を購入して妻の名義にした場合、贈与とみなされる可能性が高くなります。
夫婦間における高額なプレゼントとして捉えられる譲渡は、贈与税の対象になるケースが高いことを知っておきましょう。
これは父母・祖父母・兄弟姉妹・友人など、どんな間柄であったとしても贈与とみなされます。そのため、受け取った車の価格に基づいて税率が定められ、贈与税が課せられることになるでしょう。
例えば、親から子供へ車の贈与が行われた場合は、子供が贈与税を支払うことになります。
意外と見落とされがちなのが、税金は現金で納めることになるという点です。親から子供へ車を贈与したケースだと、車を譲渡されているので車を受け取ってはいますが、現金が増えた状態ではありません。
つまり、贈与税が発生したとしても、税額が高い状態であれば簡単に支払いができないことも考えられます。そのため、現金以外の財産贈与は、贈与された人が自分で保有をしている現金で納税することになります。
車に限らず不動産などの固定資産に関しても直接現金を渡すわけではないので、贈与する際には税金面も考慮しておくことが必要です。

計算するポイントは、車の評価額と税率です。特に祖父母や親から譲り受けた場合は、他の人から譲渡されるよりも税率が低くなります。
算出方法を知っておけば、どのぐらいの贈与税がかかるか理解することができるでしょう。
ここからは、車の価額と適用される税率について詳しく解説していきます。
売買実例価格とは、現在売買されている価額のことです。
財産の評価は、時価によるものとされていています。そのため、課税時期の財産の現状によって不特定多数の当事者間による自由取引が行われる状態が、通常成立する価額です。
つまり、一般市場に売買されるものは、売買実例価格に基づいて評価されることを原則とします。
精通者意見価格とは、贈与税の財産評価する際に専門的な知見を利用しないと財産評価が難しい場合に、各種の専門家の査定や鑑定結果を用いた財産価格のことです。
車でいえば、中古車買取業者などの査定額がこれに当てはまります。車の精通者で考えると、中古車買取業者は専門家として位置づけされますので、査定額等が基準になります。
通常の贈与税の課税方法は、「暦年課税」を利用します。これは基礎控除の110万円を差し引いた額に対して、税率がかかるというものです。
一方、特例贈与財産は、贈与による財産を取得した者が、父母や祖父母などから贈与によって取得した財産にかかる贈与税の計算に利用されます。例えば、父から子への贈与や祖父から孫への贈与などです。
ちなみに贈与により財産を取得した者の条件として、贈与を受けた年の1月1日に、20歳以上の者となっています。(令和4月1日以後の贈与については18歳以上に変更)
以下、税率一覧になりますのでご確認ください。
<特例贈与財産の税率一覧>
先述した「相続時精算課税」とは、60歳以上の祖父母や父母と、20歳以上(令和4年4月1日以降の贈与は18歳)の子や孫との間で行われる贈与に適用されます。
これは、贈与財産の種類・金額・回数に制限がなく、複数年に渡り2,500万円を限度として特別控除を受けることができる制度です。
相続時精算課税を選択した時の税率は、特別控除額を差し引いた残りの額に対して一律20%になっています。
一度、相続時精算課税を選択してしまうと、暦年課税に戻すことができない点に注意が必要です。しかし、相続時精算課税を選択していない贈与者から贈与を受ける時には、暦年課税を適用できます。
以下、税率一覧になりますのでご確認ください。
<一般贈与財産の税率一覧>
一般贈与財産は、特例贈与財産に比べると税率が高くなっています。
・課税価格=車の評価額-基礎控除額
・贈与税額=課税価格×税率-控除額
実際に例を挙げて算出してみましょう。
例)車の評価額450万円で、父から子供(成人)への贈与を行った場合(特例贈与財産)
・課税価格=車の評価額-基礎控除額
・課税価格=450万円-110万円=340万円
・贈与税額=課税価格×税率-控除額
・贈与税額=340万円×0.15-10万円=41万円
例)車の評価額450万円で、夫から妻への贈与を行った場合(一般贈与財産)
・課税価格=車の評価額-基礎控除額
・課税価格=450万円-110万円=340万円
・贈与税額=課税価格×税率-控除額
・贈与税額=340万円×0.20-25万円=43万円

その方法を知っておくことで、贈与された人は税金の負担をかけることなく車を使用してもらうことができます。
ポイントは4つありますので、今後の参考にしてみてください。それでは、贈与税がかからない方法について詳しく解説していきます。
新車の場合だと売買実例価格が採用され、実際に購入した金額が贈与税の対象額になります。
しかし、年数の経過に伴って車の価値はどんどん下がっていきます。中古車になればその分査定額も引き下がるため、基礎控除の110万円を下回れば贈与税がかからずに済むということです。
また、中古車を購入して贈与する方法もあります。その方法とは、中古車購入価格を110万円以下にすることです。新車では難しい価格でありますが、高年式で質の良い中古車なら基礎控除の範囲内で購入できる可能性もあります。
査定額や購入額を視野に入れて譲渡することが、税金対策になると言えるでしょう。
車の名義変更を行わない状態であれば、車を借りて乗っているだけとなるため、贈与税はかからないことになります。
例えば、車の名義は親の状態で、子供がその車を使用するケースが当てはまります。その際は借りて車に乗っていることになりますので、贈与にはなりません。
現状、そのように利用している方は多いでしょう。贈与税を回避する方法としては一般的な方法と言えます。
しかし、車の所有者と使用者が異なるため、任意保険などの手続きで子供が適用できる状態にする必要はあります。また、所有者が行わなければならない手続きなどは使用者で行えない場合もあるため、注意しておきましょう。
車を譲渡すると購入代金や査定額に応じていっぺんに贈与したことになりますので、贈与税が大きくかかるケースもあります。そのため、車を購入する時に複数年で現金を贈与してもらうようにする方法があります。
贈与額が年間110万円以内であれば贈与税は発生しませんので、車の購入資金を現金で贈与してもらうことが可能です。
しかし、気をつけなければならないのは、事前に購入価格を合計して贈与することが決まっていると判断されれば、合計額で贈与税を算出しなければならなくなる点です。
そのようなことにならないためにも、毎年現金を贈与する時に贈与契約書を作成して、その時に必要である現金を贈与していることを証明する状態を作っておくことが大切になります。
名義変更を行えば贈与税がかかってしまうことは先ほどお伝えしましたが、複数の中古車買取業者に依頼しておくことで、査定額も差が出てきます。
一般的に、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)が公表している査定基準に基づいて、中古車買取業者は査定額を算出しています。その価格をベースに中古車市場の需要を織り交ぜて、最終的な査定額を出したいるのです。
業者によって車種の得意・不得意も存在するため、査定価格の変動があります。その際、低い査定額を出してくれた業者の価格を参考にすると良いでしょう。
売却する際には、査定額が高いほうがお得ですが、贈与税の時はその逆が良いと言えます。
評価額が基礎控除110万円近い車であれば、それを下回っているほうが税金面ではお得になります。
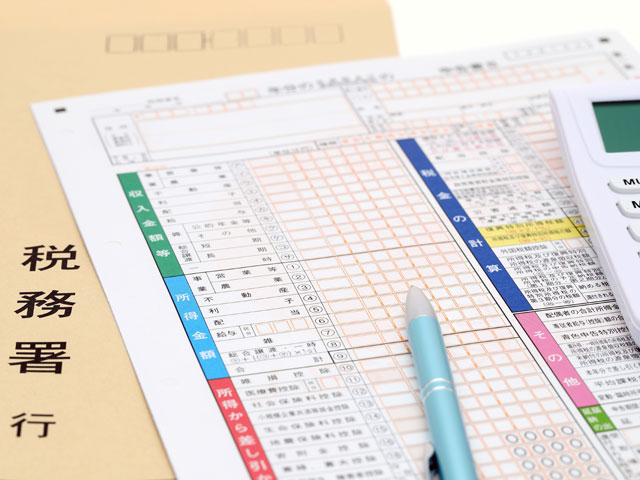
作成方法は、税務署の窓口や国税庁のホームページで申告用紙を入手して手書きで記入する方法と、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使う方法の2種類です。
贈与税の申告は、贈与を受けた人が自分の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。また、e-Taxを利用して電子申告を行うことも可能です。
申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までとなり、納付期限も翌年3月15日までです。
申告書は、「贈与税申告表第一表」を提出する必要があります。第一表には、申告する人(受贈者)と財産を贈与した人(贈与者)の情報、贈与財産の内容と税額等を記入することになります。
その他、必要な添付書類として「本人確認書類」「贈与財産の価額を証明する書類」が必要です。
本人確認書類は番号確認書類としてマイナンバーの通知カード又はマイナンバーが記載されている住民票の写しが必要となります。それに加えて、身元確認書類として運転免許書やパスポート、保険証などのいずれかが必要となりますので、準備しておきましょう。
この記事では、中古車を含めた譲渡に関して、贈与税の課税対象する要件について詳しく解説していきます。
これから車を譲渡する予定がある、譲渡される予定がある方はぜひ参考にしてみてください。
車の譲渡で税金はかかる?
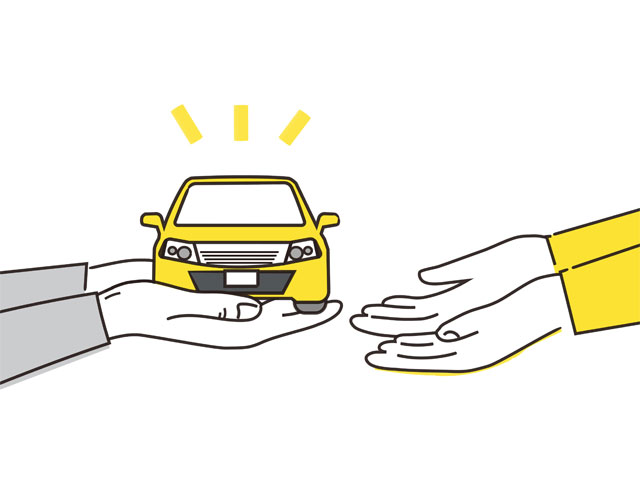
車に限らず財産を贈与すれば、贈与税を負担しなければなりません。
贈与税の計算方法は、贈与された財産を個々に行うのではなく、1年間に贈与された合計金額に応じて翌年に納税を行います。
それに加えて、年間贈与された財産合計から基礎控除(110万円)の金額を差し引いた金額に税率をかけて贈与税額を算出します。
課税対象になる要件

例えば、譲渡してもらった車が110万円以下であれば贈与税はかかりません。ただし、それ以外に財産をもらっていて110万円を超えてしまう時には贈与税がかかります。
年間で110万円を超えるか超えないかがポイントです。
ここからは、譲渡の具体的なケースについて詳しく解説していきます。
1:子供や孫に購入・譲渡するケース
子供や孫に、生活や教育に必要であるお金や車を譲渡するケースがあります。子供が地方の大学に進学することになり、日常生活における資金や車が必要になることもあるでしょう。この場合、例えば車を子供に買って譲渡しても贈与税がかかることはありません。
国税庁で定められている法令では「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と示されています。
ここで言われている生活費とは、日常生活に必要な費用のことを指し、養育費や治療費、その他子育てに関する費用が含まれます。そして教育費は、学費や文具費、教材費などが当てはまります。
ただし、生活費や教育費として必要な時に直接充当することがポイントです。そのため、生活費や教育費として受け取り、そのお金を預金したり不動産や投資の資金に充てたりすると贈与税がかかるので、注意しましょう。
2:夫婦で購入・譲渡するケース
夫婦で車を購入したり、譲渡するケースはどのようになるのでしょう?結論から言えば、前述したケースと同じように、日常生活に必要とされた状態であれば贈与税はかからないこととなっています。
夫婦だとお互い扶養する義務があるため、生活に必要なお金や車を通常必要と認められる範囲であれば、対象になることはありません。
しかし、車が高級車であれば嗜好品として贈与されると考えられ、贈与税がかかる可能性もあります。生活費であれば贈与税はかかりませんが、生活費と嗜好品の判断が難しいところです。
例えば、普通車であれば、生活に必要なものとして考えられます。しかし、既に車が1台あるのにも関わらず、夫が全額出して高級車を購入して妻の名義にした場合、贈与とみなされる可能性が高くなります。
夫婦間における高額なプレゼントとして捉えられる譲渡は、贈与税の対象になるケースが高いことを知っておきましょう。
名義変更しても課税対象になる
対価を支払わずに譲渡された車を自分名義にした場合も贈与に該当されます。これは父母・祖父母・兄弟姉妹・友人など、どんな間柄であったとしても贈与とみなされます。そのため、受け取った車の価格に基づいて税率が定められ、贈与税が課せられることになるでしょう。
贈与税は誰が納税するのか
贈与税を納税する対象者は、財産贈与を受けた人になります。例えば、親から子供へ車の贈与が行われた場合は、子供が贈与税を支払うことになります。
意外と見落とされがちなのが、税金は現金で納めることになるという点です。親から子供へ車を贈与したケースだと、車を譲渡されているので車を受け取ってはいますが、現金が増えた状態ではありません。
つまり、贈与税が発生したとしても、税額が高い状態であれば簡単に支払いができないことも考えられます。そのため、現金以外の財産贈与は、贈与された人が自分で保有をしている現金で納税することになります。
車に限らず不動産などの固定資産に関しても直接現金を渡すわけではないので、贈与する際には税金面も考慮しておくことが必要です。
贈与税の算出方法はどのように行うか

計算するポイントは、車の評価額と税率です。特に祖父母や親から譲り受けた場合は、他の人から譲渡されるよりも税率が低くなります。
算出方法を知っておけば、どのぐらいの贈与税がかかるか理解することができるでしょう。
ここからは、車の価額と適用される税率について詳しく解説していきます。
贈与税の評価額は「売買実例価格」「精通者意見価格」が基準
贈与税の評価額の決め方として、車を含む一般動産は「売買実例価格」と「精通者意見価格」の2種類あります。売買実例価格とは、現在売買されている価額のことです。
財産の評価は、時価によるものとされていています。そのため、課税時期の財産の現状によって不特定多数の当事者間による自由取引が行われる状態が、通常成立する価額です。
つまり、一般市場に売買されるものは、売買実例価格に基づいて評価されることを原則とします。
精通者意見価格とは、贈与税の財産評価する際に専門的な知見を利用しないと財産評価が難しい場合に、各種の専門家の査定や鑑定結果を用いた財産価格のことです。
車でいえば、中古車買取業者などの査定額がこれに当てはまります。車の精通者で考えると、中古車買取業者は専門家として位置づけされますので、査定額等が基準になります。
特例贈与財産による税率一覧
贈与税の税率は、贈与方法によって「暦年課税」「相続時精算課税」の2種類に分かれています。通常の贈与税の課税方法は、「暦年課税」を利用します。これは基礎控除の110万円を差し引いた額に対して、税率がかかるというものです。
一方、特例贈与財産は、贈与による財産を取得した者が、父母や祖父母などから贈与によって取得した財産にかかる贈与税の計算に利用されます。例えば、父から子への贈与や祖父から孫への贈与などです。
ちなみに贈与により財産を取得した者の条件として、贈与を受けた年の1月1日に、20歳以上の者となっています。(令和4月1日以後の贈与については18歳以上に変更)
以下、税率一覧になりますのでご確認ください。
<特例贈与財産の税率一覧>
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
これは、贈与財産の種類・金額・回数に制限がなく、複数年に渡り2,500万円を限度として特別控除を受けることができる制度です。
相続時精算課税を選択した時の税率は、特別控除額を差し引いた残りの額に対して一律20%になっています。
一度、相続時精算課税を選択してしまうと、暦年課税に戻すことができない点に注意が必要です。しかし、相続時精算課税を選択していない贈与者から贈与を受ける時には、暦年課税を適用できます。
一般贈与財産による税率一覧
特例贈与財産に該当しない場合は、一般贈与財産を利用します。具体的には、夫婦間の贈与や兄弟姉妹の贈与、親から子供への贈与で子供が未成年のケースなどで使われます。以下、税率一覧になりますのでご確認ください。
<一般贈与財産の税率一覧>
| 基礎控除後の課税価 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | - |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
具体的な車に関する贈与税の計算方法
車に関する贈与税の計算方法は、以下の通りです。・課税価格=車の評価額-基礎控除額
・贈与税額=課税価格×税率-控除額
実際に例を挙げて算出してみましょう。
例)車の評価額450万円で、父から子供(成人)への贈与を行った場合(特例贈与財産)
・課税価格=車の評価額-基礎控除額
・課税価格=450万円-110万円=340万円
・贈与税額=課税価格×税率-控除額
・贈与税額=340万円×0.15-10万円=41万円
例)車の評価額450万円で、夫から妻への贈与を行った場合(一般贈与財産)
・課税価格=車の評価額-基礎控除額
・課税価格=450万円-110万円=340万円
・贈与税額=課税価格×税率-控除額
・贈与税額=340万円×0.20-25万円=43万円
贈与税がかからない要件とは?

その方法を知っておくことで、贈与された人は税金の負担をかけることなく車を使用してもらうことができます。
ポイントは4つありますので、今後の参考にしてみてください。それでは、贈与税がかからない方法について詳しく解説していきます。
1:中古車になってから譲り受ける
1つ目は、中古車になってから譲渡してもらうことです。新車の場合だと売買実例価格が採用され、実際に購入した金額が贈与税の対象額になります。
しかし、年数の経過に伴って車の価値はどんどん下がっていきます。中古車になればその分査定額も引き下がるため、基礎控除の110万円を下回れば贈与税がかからずに済むということです。
また、中古車を購入して贈与する方法もあります。その方法とは、中古車購入価格を110万円以下にすることです。新車では難しい価格でありますが、高年式で質の良い中古車なら基礎控除の範囲内で購入できる可能性もあります。
査定額や購入額を視野に入れて譲渡することが、税金対策になると言えるでしょう。
2:車の名義変更をしないで使用する
2つ目は、車の名義変更を行わないで使用させることです。車の名義変更を行わない状態であれば、車を借りて乗っているだけとなるため、贈与税はかからないことになります。
例えば、車の名義は親の状態で、子供がその車を使用するケースが当てはまります。その際は借りて車に乗っていることになりますので、贈与にはなりません。
現状、そのように利用している方は多いでしょう。贈与税を回避する方法としては一般的な方法と言えます。
しかし、車の所有者と使用者が異なるため、任意保険などの手続きで子供が適用できる状態にする必要はあります。また、所有者が行わなければならない手続きなどは使用者で行えない場合もあるため、注意しておきましょう。
3:購入資金を控除額以下で少しずつ贈与する
3つ目は、購入資金を控除額以下にして少しずつ贈与することです。車を譲渡すると購入代金や査定額に応じていっぺんに贈与したことになりますので、贈与税が大きくかかるケースもあります。そのため、車を購入する時に複数年で現金を贈与してもらうようにする方法があります。
贈与額が年間110万円以内であれば贈与税は発生しませんので、車の購入資金を現金で贈与してもらうことが可能です。
しかし、気をつけなければならないのは、事前に購入価格を合計して贈与することが決まっていると判断されれば、合計額で贈与税を算出しなければならなくなる点です。
そのようなことにならないためにも、毎年現金を贈与する時に贈与契約書を作成して、その時に必要である現金を贈与していることを証明する状態を作っておくことが大切になります。
4:車の評価額が低い査定を利用する
4つ目は、複数の買取業者に依頼し、低い査定価格を算出することです。名義変更を行えば贈与税がかかってしまうことは先ほどお伝えしましたが、複数の中古車買取業者に依頼しておくことで、査定額も差が出てきます。
一般的に、一般財団法人日本自動車査定協会(JAAI)が公表している査定基準に基づいて、中古車買取業者は査定額を算出しています。その価格をベースに中古車市場の需要を織り交ぜて、最終的な査定額を出したいるのです。
業者によって車種の得意・不得意も存在するため、査定価格の変動があります。その際、低い査定額を出してくれた業者の価格を参考にすると良いでしょう。
売却する際には、査定額が高いほうがお得ですが、贈与税の時はその逆が良いと言えます。
評価額が基礎控除110万円近い車であれば、それを下回っているほうが税金面ではお得になります。
贈与税の申告方法は?
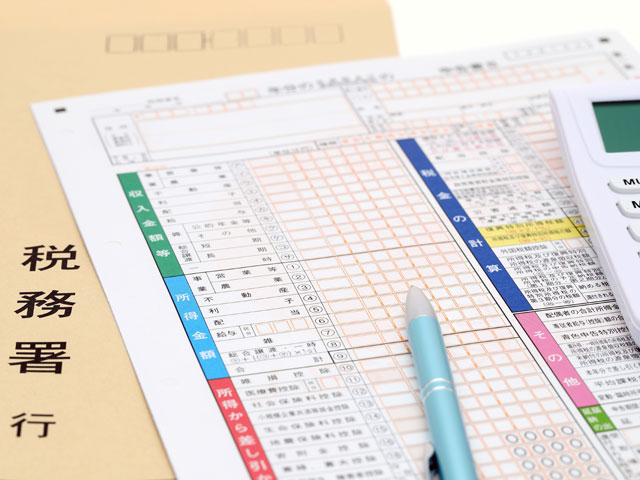
作成方法は、税務署の窓口や国税庁のホームページで申告用紙を入手して手書きで記入する方法と、国税庁の確定申告書等作成コーナーを使う方法の2種類です。
贈与税の申告は、贈与を受けた人が自分の住所を管轄する税務署に申告書を提出します。また、e-Taxを利用して電子申告を行うことも可能です。
申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までとなり、納付期限も翌年3月15日までです。
申告書は、「贈与税申告表第一表」を提出する必要があります。第一表には、申告する人(受贈者)と財産を贈与した人(贈与者)の情報、贈与財産の内容と税額等を記入することになります。
その他、必要な添付書類として「本人確認書類」「贈与財産の価額を証明する書類」が必要です。
本人確認書類は番号確認書類としてマイナンバーの通知カード又はマイナンバーが記載されている住民票の写しが必要となります。それに加えて、身元確認書類として運転免許書やパスポート、保険証などのいずれかが必要となりますので、準備しておきましょう。
まとめ
①車を贈与された場合、金額が110万円以下であれば贈与税はかからない
②贈与税は、譲渡された人が納税する
③贈与税の評価額基準は、「売買実例価格」や「精通者意見価格」で決定される
④贈与税の税率は、贈与方法によって「暦年課税」もしくは「相続時精算課税」の2種類から算出される
④税率は対象となる関係性によって、「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分かれる
⑤購入者の名義変更を行わなければ、使用者が異なっていても贈与税はかからない
この記事の画像を見る
