中古車購入チェックポイント
更新日:2022.09.27 / 掲載日:2022.09.27
中古車の故障に関する責任はどこにある?車の売買における契約不適合責任について詳しく解説
中古車を購入したらすぐに故障してしまい、トラブルになることがあります。事前に販売店で整備していたとしても、不具合が出てしまう可能性はゼロではありません。
そういった場合、責任は売主と買主のどちらにあるのでしょうか。車を買った側としては、売主に責任を取ってほしいと思う方も多いかもしれません。
そこで今回は、車の売買における契約不適合責任について詳しく解説していきます。万一トラブルがあった際に対処できるよう、知っておくと良いでしょう。
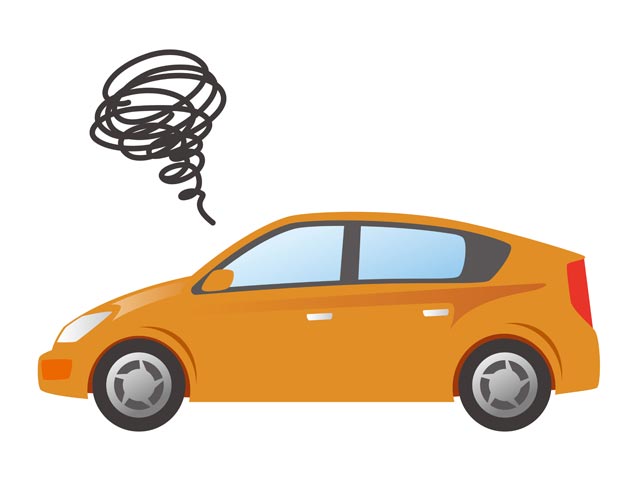
以前は「瑕疵担保責任」が制定されていましたが、2020年4月に民法が改正されて契約不適合責任に変わりました。
ここからは、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて詳しく解説していきます。
しかし、特定物の売買において、売主は「契約で定められたその特定のものを引渡せばよい」と考えられていました。そのため、契約で定めたものが、いくらボロボロのものであっても、売主は引渡しさえすれば、その後は責任を負わなくてよいものと理解されていました。
しかし、買主の立場から考えると、不利益を被ることにも繋がります。そういった理由があり、民法を改正し契約不適合責任に変更したと言えます。売主の責任を多くすることで、買主がより保護される法律になっています。
また、契約不適合責任には瑕疵担保責任では認められていなかった、「追完請求権」や「代金減額請求権」も認められるようになりました。
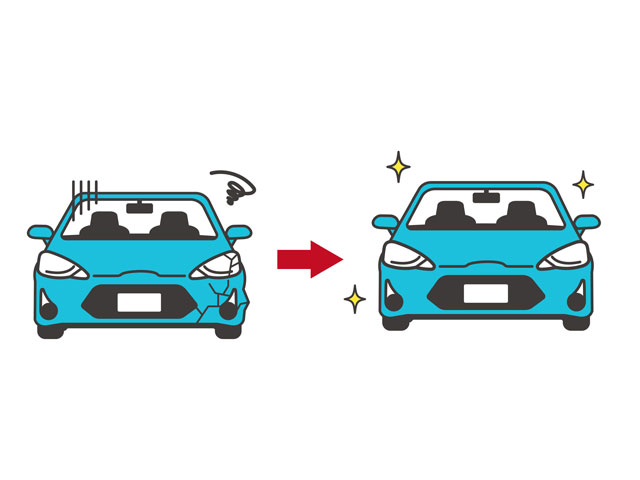
具体的には「追完請求権」「代金減額請求権」「損害賠償請求権」「契約解除権」です。
この内容を理解しておけば、今後故障した際に役立つこともあるでしょう。
これから契約不適合責任によって、買主が請求できる権利を詳しく解説していきます。
つまり、不完全な状態で引き渡されたケースでは、完全なものを渡すよう請求ができるということです。
具体例として、中古車を購入した数日後にエンジンが故障してしまい動かなくなったとします。原因が購入前からエンジンに不具合があった場合であれば、買主は売主に対してエンジン交換やエンジン修理など追完の請求を行うことができます。
しかし、買主の帰責事由(責められる理由や落ち度、過失)がある場合には、買主は売主に対して追完請求権は行えません。売主の負う追完すべき事項が履行不能になる可能性があるため、買主の追完請求権は受け入れられないことになります。
つまり、購入後の所有者が無理な運転を行ったために、故障を引き起こしたと判定されると、追完請求権を行使することはできないことを指しています。
あくまでも購入前に故障を引き起こす要因があった場合に適用される権利である点を知っておくことが必要です。
・買主が追完請求を行ったが、一定期間内に追完が行われない
・そもそも追完することが不可能なケース
・定期売買のケースで追完がされず、一定時期を経過した状態
・売主が追完を拒絶している
・追完の催告を行っているのにも関わらず、追完を受ける見込みがないケース
具体的に例を挙げれば、中古車は新車と異なり、経過年数や車の性能状況が個々異なっています。新車であれば代替物として同型式の別の車を用意することもできますが、中古車では代替しづらいでしょう。
性能や車の状況が一律ではない点で、追完を実施することが難しいケースがあります。したがって代金の減額を求め、対応することになります。
その際、代金減額請求権に関しても、買主の帰責事由があった時は、売主に対して代金減額請求権は受諾されないので注意が必要です。そして、履行の追完が不能のケースでなければ、すぐに代金減額請求を行うことはできません。
つまり、中古車を購入した後、通常使用していた状態であれば当然利用できた利益を失うことになった際も、損害賠償請求をすることができるということです。
以前の瑕疵担保責任であれば契約内容の瑕疵によって損失を受けた場合のみの適用でしたが、加えて購入者の権利を拡大した内容に変更されている点は、買主にとってメリットになるでしょう。
ただし、契約不適合責任に関して売主の帰責事由がない時、買主は損害賠償請求を認められないことになっています。違う言い方をすると免責事由と呼ばれるものになり、売主が免責事由を契約時に明記しているかが重要です。
追完請求権や代金減額請求権には免責事由の規定はないので、注意しましょう。
催告解除とは、契約不適合責任で買主が売主に相当期間を設定し追完するようにしたのにも関わらず、相当期間内に追完されないケースであれば認められます。(しかし、契約不適合責任が軽微である時は受け入れられません。)
無催告解除とは、追完不能の場合や売主が追完を拒絶している時、追完を催告しているのにも関わらず、履行される見込みがないことが明らかなケースで適用されます。

以前の瑕疵担保責任に基づく損害賠償と契約解除では、買主が瑕疵の存在を知ってから1年以内に権利行使をしなければならないことになっていました。
つまり、民法改正により1年以内に通知すれば権利行使をすることが可能になったため、買主の権利行使期間が延びたと言えるでしょう。
買主は1年以内に目的物の種類、品質が契約内容と異なることを通知することで、いつどのような請求をするかは自由に選択できることになります。
ただし、目的物の数量や権利は見れば明確に分かるものなので一般の消滅時効が有効です。その場合、権利を行使できることを知った時から5年(主観的起算点)か、権利を行使できる時から10年(客観的起算点)の早い方が時効となります。
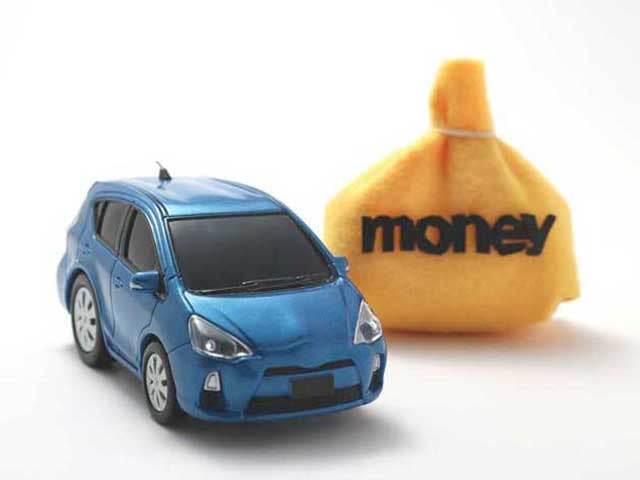
まず、従来の買主における権利が一層保護されるようになりました。以前であれば、損害賠償請求や契約解除を実施することが可能でしたが、さらに契約不適合責任により追完請求権と代金減額請求権も増えました。
そして、侵害賠償の範囲においても変わった点があります。買主の契約が有効であると信頼した状態で失った利益(信頼利益)のみの適用であったのに対し、さらに契約が有効であった際に得られた利益(履行利益)も適用範囲に含まれるようになっています。
しかし、故意ではない無過失であった場合は、今回の契約不適合責任では問われなくなった点には注意が必要です。
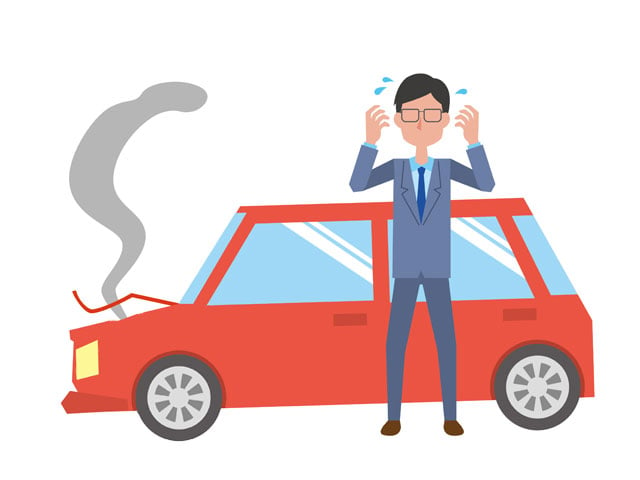
中古車の売買に関しては、JPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)や消費者センターなどで相談事例が公表されています。実際に注意していなければ自分がトラブルに巻き込まれる可能性も十分あります。
ここからは、実際に起こったトラブル事例について詳しく解説していきましょう。
こういった内容は一部の悪徳業者の可能性がありますが、瑕疵担保責任の故意でない無過失責任を問うことができる点を利用しています。
しかし、先述した通り契約不適合責任に改正され、無過失責任を問われることはないため、こういったトラブルは回避できるようになっています。
もしこのようなケースがあった時には、消費者センターや弁護士に相談するのが賢明です。
契約の目的を達成できない時や本来の品質・性能が劣っており、契約内容と相違がある場合については、買主が契約不適合責任を適用することができます。
しかし、車のボディのへこみや傷は車を販売店と買主で相互確認した際に簡単に見つけることができます。そのため、こういったケースでは売主が不適合責任に問われることは少ないと言えるでしょう。

また、中古車の売買はクーリングオフの適用外になっているため、法律上も難しいとされています。
しかし、契約内容や購入後の不具合によっては返品ができるケースもあります。ここからは、その例を4つ紹介します。
修復歴の有無については、売主がはっきりと表示することが義務化されています。これは、自動車公正取引協議会における自動車公正競争規約集第3章10項目に提示されています。
そのため、中古車販売店が修復歴がある車を説明や表示をせずに販売することは契約内容に不備があると言えるため、返品の対象です。
一般的に「事故車」と「修復歴車」は一緒に考えられがちですが、中古車販売業者では明確に区別されています。
修復歴車は、交通事故やその他の災害において、自動車の骨格部分の交換や修理をした状態の車です。
骨格部分と言われる箇所は8か所あり、車の強度を保つために重要な役割を果たしています。修理をしていても走行する際に不具合が生じる可能性が高まるため、提示する必要があるのです。
事故車は、実際に事故を起こして修理をした箇所が骨格部分以外の車のことです。例えば、バンパーをぶつけてしまい交換したとしても、バンパーは骨格部分ではないので修復歴車にはなりません。
つまり「修復歴車」だと明記されていなければ、安全に走行することが困難だということが分からなくなります。伝えられていなければ契約と相違があることから、契約解除を行える可能性は高いと言えます。
基本的に、通常の状況下で使用していた時に起こり得ない不具合が発生したケースであれば、契約不適合責任に該当する可能性があります。
これは現状渡しで購入した時にも当てはまりますので、弁護士や消費者センターに相談してみると良いでしょう。
2017年以降、車検証に走行距離の最大値を記載することが義務化されました。そのため、車検証に記載されている走行距離が実際のメーターより多くなっていることは、現実としてあり得ないことになります。
これは中古車を購入する際にも確認できることなので、チェックを怠らないようにしましょう。
ちなみに民法や消費者契約法により、事実と異なることを伝えられ誤解して契約した際は、契約の取り消しが可能であると規定されています。
しかし、消費者契約法第7条1項では適用可能期間について説明が間違っていると気付いてから6か月以内、購入契約後5年以内になっていますので気をつけましょう。
中古車販売店によっては、返品保証をつけている業者もあります。業者との契約内容にもよりますが、車両本体価格は返金され、それ以外にかかった諸経費は購入者負担になるケースが一般的のようです。
しかし、返品保証があるといっても返品できる条件がありますので、契約書や直接販売店に確認することをおすすめします。
具体的には、走行距離や納車後の日数など販売店が定める条件があります。そのため、ある程度走行している状態であれば、返品保証があったとしても適用対象外になることが考えられます。
また、購入後に改造していたり、傷やへこみ、車内の汚れがひどいなど購入前より大幅に状態が変化していたりする場合は、一般的に返品は厳しいでしょう。
そういった場合、責任は売主と買主のどちらにあるのでしょうか。車を買った側としては、売主に責任を取ってほしいと思う方も多いかもしれません。
そこで今回は、車の売買における契約不適合責任について詳しく解説していきます。万一トラブルがあった際に対処できるよう、知っておくと良いでしょう。
この記事の目次
車の売買による契約不適合責任とは?
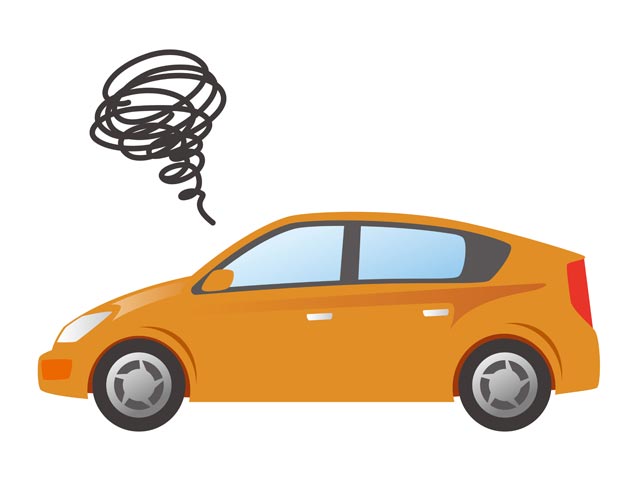
以前は「瑕疵担保責任」が制定されていましたが、2020年4月に民法が改正されて契約不適合責任に変わりました。
ここからは、瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについて詳しく解説していきます。
瑕疵担保責任が民法改正によって廃止された理由
まず瑕疵担保責任では、売買の目的物に隠れた瑕疵があった時に売主が買主に対して責任を負うことになっていました。しかし、特定物の売買において、売主は「契約で定められたその特定のものを引渡せばよい」と考えられていました。そのため、契約で定めたものが、いくらボロボロのものであっても、売主は引渡しさえすれば、その後は責任を負わなくてよいものと理解されていました。
しかし、買主の立場から考えると、不利益を被ることにも繋がります。そういった理由があり、民法を改正し契約不適合責任に変更したと言えます。売主の責任を多くすることで、買主がより保護される法律になっています。
また、契約不適合責任には瑕疵担保責任では認められていなかった、「追完請求権」や「代金減額請求権」も認められるようになりました。
契約不適合責任で買主が請求できる権利は?
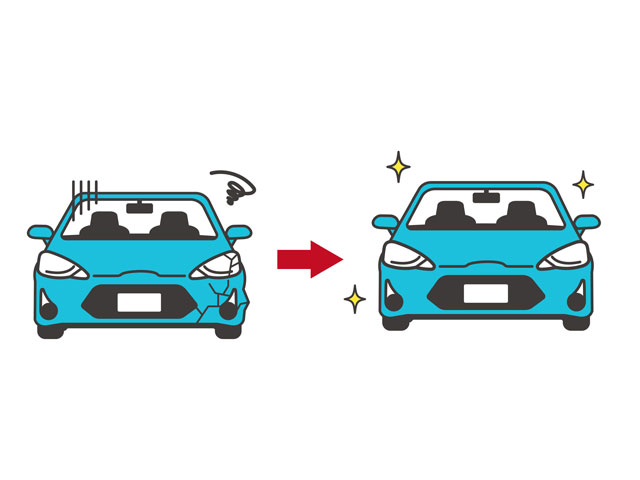
具体的には「追完請求権」「代金減額請求権」「損害賠償請求権」「契約解除権」です。
この内容を理解しておけば、今後故障した際に役立つこともあるでしょう。
これから契約不適合責任によって、買主が請求できる権利を詳しく解説していきます。
①追完請求権(補修請求権)
民法改正562条1項では、買主は売主に対して、目的物の補修、代替物の引き渡しまたは不足分の引き渡しなど「追完請求」を行うことができるようになっています。つまり、不完全な状態で引き渡されたケースでは、完全なものを渡すよう請求ができるということです。
具体例として、中古車を購入した数日後にエンジンが故障してしまい動かなくなったとします。原因が購入前からエンジンに不具合があった場合であれば、買主は売主に対してエンジン交換やエンジン修理など追完の請求を行うことができます。
しかし、買主の帰責事由(責められる理由や落ち度、過失)がある場合には、買主は売主に対して追完請求権は行えません。売主の負う追完すべき事項が履行不能になる可能性があるため、買主の追完請求権は受け入れられないことになります。
つまり、購入後の所有者が無理な運転を行ったために、故障を引き起こしたと判定されると、追完請求権を行使することはできないことを指しています。
あくまでも購入前に故障を引き起こす要因があった場合に適用される権利である点を知っておくことが必要です。
②代金減額請求権
民法の改正により、代金減額請求権を行う前に、まずは追完をメインで行うことになります。そして、代金減額請求できるのは以下のような状況だった場合です。・買主が追完請求を行ったが、一定期間内に追完が行われない
・そもそも追完することが不可能なケース
・定期売買のケースで追完がされず、一定時期を経過した状態
・売主が追完を拒絶している
・追完の催告を行っているのにも関わらず、追完を受ける見込みがないケース
具体的に例を挙げれば、中古車は新車と異なり、経過年数や車の性能状況が個々異なっています。新車であれば代替物として同型式の別の車を用意することもできますが、中古車では代替しづらいでしょう。
性能や車の状況が一律ではない点で、追完を実施することが難しいケースがあります。したがって代金の減額を求め、対応することになります。
その際、代金減額請求権に関しても、買主の帰責事由があった時は、売主に対して代金減額請求権は受諾されないので注意が必要です。そして、履行の追完が不能のケースでなければ、すぐに代金減額請求を行うことはできません。
③損害賠償請求権
契約不適合責任は、民法改正により債務不履行を中心に据えて考えるようになっています。そのため、買主は債務不履行に関して、売主に損害賠償請求を行うことが可能になりました。つまり、中古車を購入した後、通常使用していた状態であれば当然利用できた利益を失うことになった際も、損害賠償請求をすることができるということです。
以前の瑕疵担保責任であれば契約内容の瑕疵によって損失を受けた場合のみの適用でしたが、加えて購入者の権利を拡大した内容に変更されている点は、買主にとってメリットになるでしょう。
ただし、契約不適合責任に関して売主の帰責事由がない時、買主は損害賠償請求を認められないことになっています。違う言い方をすると免責事由と呼ばれるものになり、売主が免責事由を契約時に明記しているかが重要です。
追完請求権や代金減額請求権には免責事由の規定はないので、注意しましょう。
④契約解除権
契約不適合責任について、買主の契約解除権があります。これは法定解除の一般ルールに基づいて行うことになり、「催告解除」と「無催告解除」の2つがあります。催告解除とは、契約不適合責任で買主が売主に相当期間を設定し追完するようにしたのにも関わらず、相当期間内に追完されないケースであれば認められます。(しかし、契約不適合責任が軽微である時は受け入れられません。)
無催告解除とは、追完不能の場合や売主が追完を拒絶している時、追完を催告しているのにも関わらず、履行される見込みがないことが明らかなケースで適用されます。
契約不適合責任の期間制限について

以前の瑕疵担保責任に基づく損害賠償と契約解除では、買主が瑕疵の存在を知ってから1年以内に権利行使をしなければならないことになっていました。
つまり、民法改正により1年以内に通知すれば権利行使をすることが可能になったため、買主の権利行使期間が延びたと言えるでしょう。
買主は1年以内に目的物の種類、品質が契約内容と異なることを通知することで、いつどのような請求をするかは自由に選択できることになります。
ただし、目的物の数量や権利は見れば明確に分かるものなので一般の消滅時効が有効です。その場合、権利を行使できることを知った時から5年(主観的起算点)か、権利を行使できる時から10年(客観的起算点)の早い方が時効となります。
契約不適合責任と瑕疵担保責任の相違点
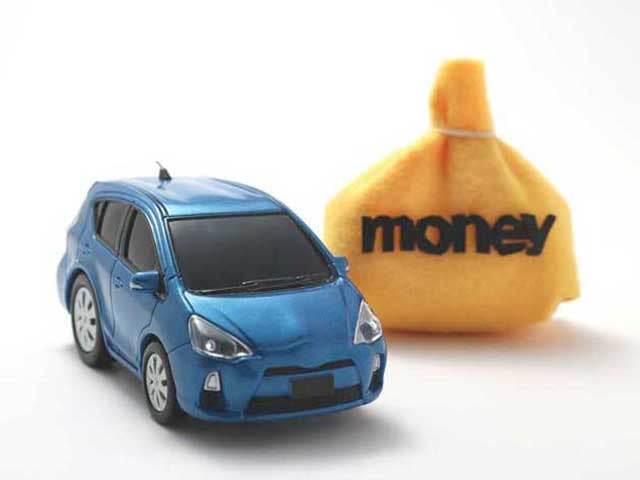
まず、従来の買主における権利が一層保護されるようになりました。以前であれば、損害賠償請求や契約解除を実施することが可能でしたが、さらに契約不適合責任により追完請求権と代金減額請求権も増えました。
そして、侵害賠償の範囲においても変わった点があります。買主の契約が有効であると信頼した状態で失った利益(信頼利益)のみの適用であったのに対し、さらに契約が有効であった際に得られた利益(履行利益)も適用範囲に含まれるようになっています。
しかし、故意ではない無過失であった場合は、今回の契約不適合責任では問われなくなった点には注意が必要です。
中古車の売買におけるトラブルとは?
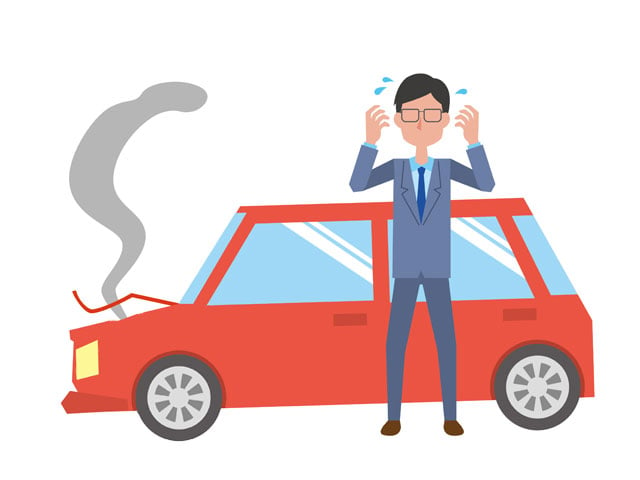
中古車の売買に関しては、JPUC(一般社団法人日本自動車購入協会)や消費者センターなどで相談事例が公表されています。実際に注意していなければ自分がトラブルに巻き込まれる可能性も十分あります。
ここからは、実際に起こったトラブル事例について詳しく解説していきましょう。
中古車の売却後におきたトラブル事例
中古車の買取業者に査定をして買い取ってもらった後に「事故車だったため査定額を減額したい」「査定時に申告されていないメーター改ざんが見つかった」と連絡があり、損害賠償請求や契約解除を求められる事例が挙げられています。こういった内容は一部の悪徳業者の可能性がありますが、瑕疵担保責任の故意でない無過失責任を問うことができる点を利用しています。
しかし、先述した通り契約不適合責任に改正され、無過失責任を問われることはないため、こういったトラブルは回避できるようになっています。
もしこのようなケースがあった時には、消費者センターや弁護士に相談するのが賢明です。
中古車の購入後におきたトラブル事例
中古車の購入後に多いトラブルが、「エンジンの調子が悪く何度も修理が必要なケース」や「実際購入した車が当初契約した種類や内容と異なっていた場合」などです。契約の目的を達成できない時や本来の品質・性能が劣っており、契約内容と相違がある場合については、買主が契約不適合責任を適用することができます。
しかし、車のボディのへこみや傷は車を販売店と買主で相互確認した際に簡単に見つけることができます。そのため、こういったケースでは売主が不適合責任に問われることは少ないと言えるでしょう。
中古車の購入後に返品が可能なケース

また、中古車の売買はクーリングオフの適用外になっているため、法律上も難しいとされています。
しかし、契約内容や購入後の不具合によっては返品ができるケースもあります。ここからは、その例を4つ紹介します。
①修復歴が伝えられていない
返品が可能なケースの1つ目は、修復歴が買主に伝えられていない場合です。修復歴の有無については、売主がはっきりと表示することが義務化されています。これは、自動車公正取引協議会における自動車公正競争規約集第3章10項目に提示されています。
そのため、中古車販売店が修復歴がある車を説明や表示をせずに販売することは契約内容に不備があると言えるため、返品の対象です。
一般的に「事故車」と「修復歴車」は一緒に考えられがちですが、中古車販売業者では明確に区別されています。
修復歴車は、交通事故やその他の災害において、自動車の骨格部分の交換や修理をした状態の車です。
骨格部分と言われる箇所は8か所あり、車の強度を保つために重要な役割を果たしています。修理をしていても走行する際に不具合が生じる可能性が高まるため、提示する必要があるのです。
事故車は、実際に事故を起こして修理をした箇所が骨格部分以外の車のことです。例えば、バンパーをぶつけてしまい交換したとしても、バンパーは骨格部分ではないので修復歴車にはなりません。
つまり「修復歴車」だと明記されていなければ、安全に走行することが困難だということが分からなくなります。伝えられていなければ契約と相違があることから、契約解除を行える可能性は高いと言えます。
②契約不適合責任に該当する
返品が可能なケースの2つ目は、契約不適合責任に該当する場合です。基本的に、通常の状況下で使用していた時に起こり得ない不具合が発生したケースであれば、契約不適合責任に該当する可能性があります。
これは現状渡しで購入した時にも当てはまりますので、弁護士や消費者センターに相談してみると良いでしょう。
③改ざんが行われていた
返品が可能なケースの3つ目は、改ざんが行われていた場合です。例えば、走行距離のメーターの巻き戻しが挙げられます。2017年以降、車検証に走行距離の最大値を記載することが義務化されました。そのため、車検証に記載されている走行距離が実際のメーターより多くなっていることは、現実としてあり得ないことになります。
これは中古車を購入する際にも確認できることなので、チェックを怠らないようにしましょう。
ちなみに民法や消費者契約法により、事実と異なることを伝えられ誤解して契約した際は、契約の取り消しが可能であると規定されています。
しかし、消費者契約法第7条1項では適用可能期間について説明が間違っていると気付いてから6か月以内、購入契約後5年以内になっていますので気をつけましょう。
④返品保証がついている
返品が可能なケースの4つ目は、中古車の返品保証がついている場合です。中古車販売店によっては、返品保証をつけている業者もあります。業者との契約内容にもよりますが、車両本体価格は返金され、それ以外にかかった諸経費は購入者負担になるケースが一般的のようです。
しかし、返品保証があるといっても返品できる条件がありますので、契約書や直接販売店に確認することをおすすめします。
具体的には、走行距離や納車後の日数など販売店が定める条件があります。そのため、ある程度走行している状態であれば、返品保証があったとしても適用対象外になることが考えられます。
また、購入後に改造していたり、傷やへこみ、車内の汚れがひどいなど購入前より大幅に状態が変化していたりする場合は、一般的に返品は厳しいでしょう。
まとめ
①契約不適合責任は、契約内容に適合しない場合に債務不履行責任として定められている
②契約不適合責任で買主が請求できる権利は「追完請求権」「代金減額請求権」「損害賠償請求権」「契約解除権」の4つがある
③契約不適合責任における目的物の種類や品質が契約に適合しなければ、1年以内に通知すれば権利行使ができる
④契約不適合責任と瑕疵担保責任の相違点は、買主の権利が強くなり、瑕疵ではなく契約内容に適合しないものに変化したことが挙げられる
⑤中古車購入後の返品は原則できないが、契約上の不履行がある場合と返品保証がある時は、状況によって可能な場合がある
この記事の画像を見る
