中古車購入チェックポイント
更新日:2023.01.25 / 掲載日:2023.01.25
車は10年たつと故障しやすい?多い故障の症状や長持ちさせる秘訣などを解説
車は決して安い買い物ではなく、維持費もかかるため、できるだけ長く乗っていたいと思っている方も多いかもしれません。
しかし、年数を重ねるにつれて、どうしてもエンジンや備品が次第に劣化していきます。特に「10年」を超えると故障しやすくなるため、「10年が寿命」と言われることもあります。
そこで、この記事では10年経過した車に故障が増えてくる理由や具体的な故障例、かかってくる維持費などを解説していきます。
10年経過した車が故障しやすくなるのは紛れもない事実ですが、きちんと対策をとれば10年を超えても乗り続けることができるとされています。

例えば、タイミングベルトやミッション、ステアリング機構やサスペンションといった部品は、故障すると走行に大きな支障が出てくる上、修理や交換に費用がかさみます。
そういった重要な構成部品の多くは、10万kmの走行には耐えられるように設計されています。
一方、用途やライフスタイルによって様々ですが、車の年間走行距離は平均1万kmだと言われています。単純に計算すると、10年間同じ車に乗り続けた場合、多くの部品が寿命を迎える10万kmに達するでしょう。
つまり、目安として10年経過すると、これらの重要な構成部品に故障が増え、修理コストも高くなるため、「車の寿命は10年」とよく言われているのです。
しかし、車はたとえ走行していなくても長い間、雨・風・日光などにさらされています。そのため、鉄やゴムなどでできている各部品がサビや紫外線などで劣化し、10年以上経過すると正常に作動しなくなることがあります。
特に、屋根がない場所に青空駐車している場合や潮風が吹き付ける海に近いところに駐車している場合は、劣化が早い傾向にあります。

今回は、安全性や修理にかかる費用の面から、車の寿命に大きく関わってくると考えられるものをいくつかピックアップしていきます。
このタイミングベルトが経年劣化によって伸びたり、切れたりしてしまうと、吸気・排気・点火のタイミングがずれ、エンジンがかからなくなります。
車が走行する上で欠かすことのできない重要な部品であるため、ゴム製ながら高い耐久性を持っていますが、10年または走行距離10万kmが寿命とされています。
問題は、その交換に多額の費用がかかることです。部品代は数千円と高くありませんが、交換するには車種によってエンジンを下ろしたり、分解したりする工程が増えるため、工賃が数万円~10万円程度かかります。
ただし、最近の車は原則交換する必要がなく、伸びたり切れたりして走行不能になることもない金属製のタイミングチェーンに代わってきています。
しかし、年数が経過するとそれが劣化したり、振動によって継ぎ目の隙間が広がったりして、内封されているエンジンオイルが漏れ出てくる可能性があります。
オイル漏れ自体は、10年以内の経過年数が少ない車でも起きる故障ですが、10年経過している車のオイル漏れは同時多発的に発生したり、1箇所修理しても同じように劣化している他の部位から連続してオイルが漏れたりすることがあるので厄介です。
また、車にはエンジンオイルだけでなく、パワステやミッション、ブレーキなどにもオイルが用いられています。10年も経つとそれらも漏れ出してくる可能性があります。
ミッションが故障した場合、オーバーホールで15万~30万円、ミッションそのものを丸ごと載せ替える場合は40万~80万円近く修理費用がかかってしまいます。
そのため、ミッションが故障した場合は「車の寿命」と判断され、買い替えをすすめられることも多いです。
これらのパーツは、タイヤやブレーキパットなどの消耗品と呼ばれる箇所と異なり、定期的な交換を前提としていないため、部品代も工賃も割高です。
また、不具合箇所の見極めが困難なため、単一箇所を部品交換しても症状が改善しない場合や再発することもあります。

しかし、10年を超えた車にかかるお金は故障した際の修理費用だけではありません。ここからは、修理費用以外にかかってくる維持費について説明していきます。
・ワイパー
・タイヤ
・バッテリー
・ブレーキパット など
これらの寿命は比較的短いため、10年その車を乗っていれば何度も交換することになるでしょう。
しかし、以下のような10年を寿命の目途とする消耗品も多いです。
・燃料フィルター
・オルタネーターのブラシ
・サーモスタット
・ラジエター
・ブレーキホース
・エンジンマウント
・ウォーターポンプ
これらの交換コストは高額な上、いっぺんに寿命を迎える可能性もあるため、10年を超えて乗り続けようとするとどうしても維持費が高くなってきます。
そして、新規登録から13年経過したガソリン車と11年経過したディーゼル車は、下記の通り自動車税が約15%上乗せされます。
軽自動車
10,800円(10,800円)→12,900円
1,000cc以下
29,500円(25,000円)→33,900円
1,000cc超1,500cc以下
34,500円(30,500円)→39,600円
1,500cc超2,000cc以下
39,500円(36,000円)→45,500円
2,000cc超2,500cc以下
45,000円(43,500円)→51,700円
2,500cc超3,000cc以下
51,000円(50,000円)→58,600円
3,000cc超3,500cc以下
58,000円(57,000円)→66,700円
3,500cc超4,000cc以下
66,500円(65,500円)→76,400円
4,000cc超4,500cc以下
76,500円(75,500円)→87,900円
4,500cc超6,000cc以下
88,000円(87,000円)→101,200円
6,000cc超
111,000円(110,000円)→127,600円
※()内は2019年10月以降に購入(新車登録)した場合の税額
また、2年に1度やってくる車検の際に支払う自動車重量税に関しても、新規登録から13年経過すると約39%も増税されます。
軽自動車
15,57年(2021年度)
普通車
13.84年(2022年3月末)
いずれも、一般的に言われている「10年」よりも3~5年は長く、技術進歩やエコを重要視する社会情勢に合わせ、年々伸びています。
また、丈夫で長持ちと評判の国産車は、国内での役目を終えると海外に飛び出し、20年・30年を超えても現役で活躍しています。
もちろん、文化や用途の違いはありますが、故障が増えるという理由だけで車の寿命が「10年」と決めつけることはできないでしょう。
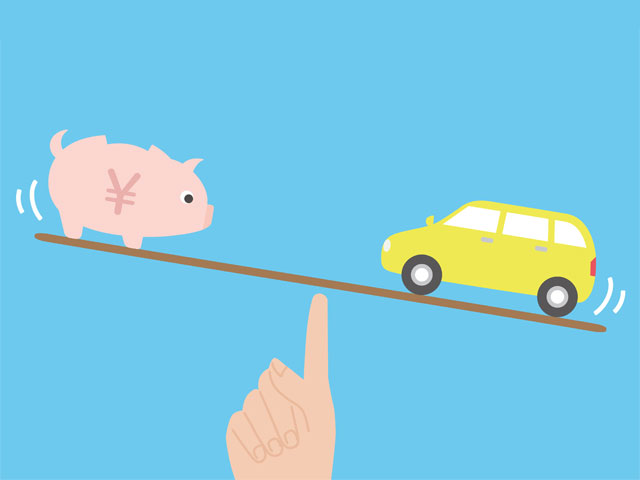
しかし、車は10年を超えると故障が増えるのは確かです。そして、修理費用だけでなく、消耗品代・税金などを加えた維持費や管理コストが年々かさんできます。
そこでここからは、維持コストと車の寿命との関係を中心に、修理するか買い替えるかを決めるポイントを挙げて見ていきます。
例えば、合計10万円の費用がかかったとしても、その他の部分に目立った故障や不具合がなくてその後5年・10年乗り続けられるのであれば、修理や交換をする価値は十分あります。
反対に、その時は1万円で済んだとしても、近い将来さらに大きな故障の種を抱えているのであれば、乗り換えも視野に入れたほうがいいでしょう。
具体的に言うと、不具合箇所が駆動系や足回り系だけであれば、一度修理や交換すればその後長く乗り続けることも可能です。
一方、オイル漏れや電機系の不具合は、一旦修理や交換しても関連する他の箇所が不具合を起こす可能性もあります。
修理や交換をする前に、修理すればどれぐらい車に乗れそうか、依頼業者に問い合わせておきましょう。そして修理するか買い替えるか決めるといいでしょう。
例えば、10年11ヶ月目のタイミングで、修理に大きな出費を伴う故障が発生したとしましょう。この場合は、翌月すぐに車検がやってくるので、買い替えを視野に入れたほうがいいかもしれません。
特に12年目は、自動車税などが上がるタイミング(13年目)も控えています。このタイミングで大きな故障が発生するとさらに維持費が高くなってくるため、より慎重に判断しましょう。
もしデザインなどが気に入って乗りたいと思える車があれば、思い切って乗り換えるのも一つの手です。
燃費・安全性能に優れる現在の車は、燃料代などの維持費が安上がりな上に故障しにくく、10年前の車より長持ちする可能性も高くなってきます。また、HVやEVなどのエコカーであれば、減税や購入補助金の恩恵も受けられます。
もちろん、費用をかけることができるなら、愛着のある今の車を維持することも可能です。ただし、総合的に見ると車を買い替えたほうがお金がかからない可能性もあります。

そこで最後に、車を長持ちさせるための秘訣を紹介していきます。
エンジンオイルには、潤滑・冷却・密封・洗浄という4つの働きがありますが、古くなったオイルはこの全ての能力が低下します。
そして、長期間古いオイルを使い続けた場合、以下の内容が同時に起こります。
・潤滑不足による金属摩耗の進行
・冷却不足による過熱での部品劣化
・密封力低下によるオイル漏れ
・洗浄力低下による目詰まり
この結果、エンジン並びにその周辺の部品が故障したり、最悪の場合はエンジン自体が焼き付き、使い物にならなくなったりする可能性もあります。
1度や2度オイル交換のタイミングが遅れたからと言って、すぐ上記のような不具合が出てくるわけではありません。しかし、10年間きちんと定期的にオイル交換をしてきた車とそうでない車とでは、エンジンの状態に雲泥の差が出てきます。
特に10年を超えた車がよく起こす故障の代表格である、オイル漏れは、定期的なオイル交換の実施によってその発生を遅らせたり、症状を軽くしたりすることが可能です。
一方、法定点検は車が本来の走行性能を維持しており、故障や不具合がないかを確かめる検査で、12ヶ月ごとに受けることが法律で義務付けられています。
ただし、点検を受けなくても公道を走行でき、罰金や罰則を科せられることもないため、受けていないという方もいるかもしれません。
しかし、法定点検では細分化された点検項目に沿って、各部品・消耗品の状態や劣化度合いを確認するため、故障の早期発見はもちろん、その悪化を食い止めることも可能です。
また、ユーザー自身がタイヤや各種オイルなどといった消耗品を点検する日常点検も、法定点検を補助するものとして実施すれば、より車の寿命を延ばすことにつながるでしょう。
そして、急発進はエンジンに、急停車はブレーキに、急ハンドルはステリング関係に、急加速・急減速はミッション系に、それぞれ強い負荷をかけるため、劣化を早めてしまいます。
反対に、「急」のつかない運転、つまり車にやさしい運転を心がければ各種パーツにかかる負担が軽減され、結果的に車の寿命を延ばすことも期待できます。
また、エコ走法(燃費向上)や安全運転にもつながるため、実践してみましょう。
しかし、年数を重ねるにつれて、どうしてもエンジンや備品が次第に劣化していきます。特に「10年」を超えると故障しやすくなるため、「10年が寿命」と言われることもあります。
そこで、この記事では10年経過した車に故障が増えてくる理由や具体的な故障例、かかってくる維持費などを解説していきます。
この記事の目次
車は10年が寿命って本当?車の寿命について徹底検証
結論から言ってしまうと「車は10年が寿命」という定説は、半分本当で半分嘘です。10年経過した車が故障しやすくなるのは紛れもない事実ですが、きちんと対策をとれば10年を超えても乗り続けることができるとされています。
車はなぜ10年を超えると故障が増えてくるのか

走行距離が10万kmに近づいてくるため
車は常に走っていることが前提の精密機械です。例えば、タイミングベルトやミッション、ステアリング機構やサスペンションといった部品は、故障すると走行に大きな支障が出てくる上、修理や交換に費用がかさみます。
そういった重要な構成部品の多くは、10万kmの走行には耐えられるように設計されています。
一方、用途やライフスタイルによって様々ですが、車の年間走行距離は平均1万kmだと言われています。単純に計算すると、10年間同じ車に乗り続けた場合、多くの部品が寿命を迎える10万kmに達するでしょう。
つまり、目安として10年経過すると、これらの重要な構成部品に故障が増え、修理コストも高くなるため、「車の寿命は10年」とよく言われているのです。
各パーツの経年劣化が進むため
前項で走行距離から車の寿命を算出しましたが、「1年に1万kmも走らなければ、10年以上持つのでは?」と思う方もいるでしょう。しかし、車はたとえ走行していなくても長い間、雨・風・日光などにさらされています。そのため、鉄やゴムなどでできている各部品がサビや紫外線などで劣化し、10年以上経過すると正常に作動しなくなることがあります。
特に、屋根がない場所に青空駐車している場合や潮風が吹き付ける海に近いところに駐車している場合は、劣化が早い傾向にあります。
10年経過した車に多い故障事例

今回は、安全性や修理にかかる費用の面から、車の寿命に大きく関わってくると考えられるものをいくつかピックアップしていきます。
①タイミングベルトの劣化・断絶
タイミングベルトとは、クランクシャフトとカムシャフトを結んでいるベルト状の部品です。エンジンの吸気・排気・点火が、適切なタイミングで行われるように調整する役割があります。このタイミングベルトが経年劣化によって伸びたり、切れたりしてしまうと、吸気・排気・点火のタイミングがずれ、エンジンがかからなくなります。
車が走行する上で欠かすことのできない重要な部品であるため、ゴム製ながら高い耐久性を持っていますが、10年または走行距離10万kmが寿命とされています。
問題は、その交換に多額の費用がかかることです。部品代は数千円と高くありませんが、交換するには車種によってエンジンを下ろしたり、分解したりする工程が増えるため、工賃が数万円~10万円程度かかります。
ただし、最近の車は原則交換する必要がなく、伸びたり切れたりして走行不能になることもない金属製のタイミングチェーンに代わってきています。
②各種オイルの漏れ
車のエンジンには継ぎ目があるため、パッキンやシールなどでエンジンオイルが漏れるのを食い止めています。しかし、年数が経過するとそれが劣化したり、振動によって継ぎ目の隙間が広がったりして、内封されているエンジンオイルが漏れ出てくる可能性があります。
オイル漏れ自体は、10年以内の経過年数が少ない車でも起きる故障ですが、10年経過している車のオイル漏れは同時多発的に発生したり、1箇所修理しても同じように劣化している他の部位から連続してオイルが漏れたりすることがあるので厄介です。
また、車にはエンジンオイルだけでなく、パワステやミッション、ブレーキなどにもオイルが用いられています。10年も経つとそれらも漏れ出してくる可能性があります。
③ミッション関係の故障・不具合
手動で切り替えるMT車だけでなく、AT車でも走行中は常にミッションのギアは切り替えられています。そして、10年もたつと度重なる切り替えでギアが摩耗・破損し、切り替え不良などの症状が出ることもあります。ミッションが故障した場合、オーバーホールで15万~30万円、ミッションそのものを丸ごと載せ替える場合は40万~80万円近く修理費用がかかってしまいます。
そのため、ミッションが故障した場合は「車の寿命」と判断され、買い替えをすすめられることも多いです。
④足回りのガタつき・エンジンからの異音など
その他、ステアリング関連、サスペンションやブレーキ関連、エンジンの振動や異音を抑制するパーツなど、10年を超えると金属疲労や素材劣化などを原因とする故障が頻発します。これらのパーツは、タイヤやブレーキパットなどの消耗品と呼ばれる箇所と異なり、定期的な交換を前提としていないため、部品代も工賃も割高です。
また、不具合箇所の見極めが困難なため、単一箇所を部品交換しても症状が改善しない場合や再発することもあります。
寿命に影響?車は10年を超えると何かとお金がかかる

しかし、10年を超えた車にかかるお金は故障した際の修理費用だけではありません。ここからは、修理費用以外にかかってくる維持費について説明していきます。
交換コストの高い消耗品の相次ぐ寿命
車には数多くの消耗品が用いられています。その代表格は以下になります。・ワイパー
・タイヤ
・バッテリー
・ブレーキパット など
これらの寿命は比較的短いため、10年その車を乗っていれば何度も交換することになるでしょう。
しかし、以下のような10年を寿命の目途とする消耗品も多いです。
・燃料フィルター
・オルタネーターのブラシ
・サーモスタット
・ラジエター
・ブレーキホース
・エンジンマウント
・ウォーターポンプ
これらの交換コストは高額な上、いっぺんに寿命を迎える可能性もあるため、10年を超えて乗り続けようとするとどうしても維持費が高くなってきます。
自動車税の割り増しも見過ごせない
車を所有している限り、毎年課税されることになる自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に支払いの義務が生じます。そして、新規登録から13年経過したガソリン車と11年経過したディーゼル車は、下記の通り自動車税が約15%上乗せされます。
軽自動車
10,800円(10,800円)→12,900円
1,000cc以下
29,500円(25,000円)→33,900円
1,000cc超1,500cc以下
34,500円(30,500円)→39,600円
1,500cc超2,000cc以下
39,500円(36,000円)→45,500円
2,000cc超2,500cc以下
45,000円(43,500円)→51,700円
2,500cc超3,000cc以下
51,000円(50,000円)→58,600円
3,000cc超3,500cc以下
58,000円(57,000円)→66,700円
3,500cc超4,000cc以下
66,500円(65,500円)→76,400円
4,000cc超4,500cc以下
76,500円(75,500円)→87,900円
4,500cc超6,000cc以下
88,000円(87,000円)→101,200円
6,000cc超
111,000円(110,000円)→127,600円
※()内は2019年10月以降に購入(新車登録)した場合の税額
また、2年に1度やってくる車検の際に支払う自動車重量税に関しても、新規登録から13年経過すると約39%も増税されます。
データから見る車の平均寿命について
軽自動車検査協会および自動車検査登録情報協会の調べによれば、日本国内における「乗用車」の平均使用年数は以下の通りです。軽自動車
15,57年(2021年度)
普通車
13.84年(2022年3月末)
いずれも、一般的に言われている「10年」よりも3~5年は長く、技術進歩やエコを重要視する社会情勢に合わせ、年々伸びています。
また、丈夫で長持ちと評判の国産車は、国内での役目を終えると海外に飛び出し、20年・30年を超えても現役で活躍しています。
もちろん、文化や用途の違いはありますが、故障が増えるという理由だけで車の寿命が「10年」と決めつけることはできないでしょう。
修理するか買い替えるかを決めるポイント
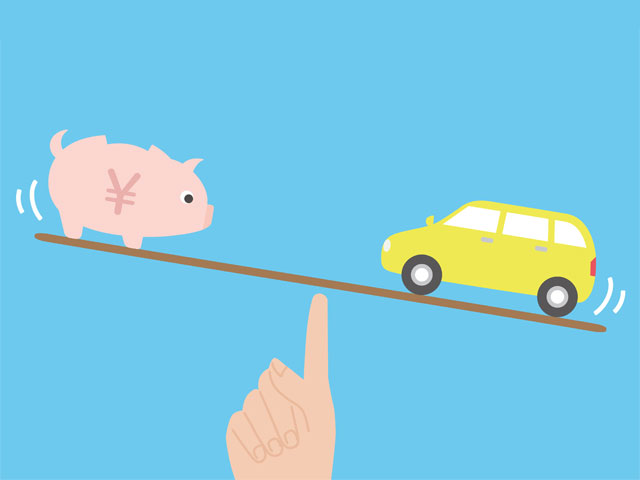
しかし、車は10年を超えると故障が増えるのは確かです。そして、修理費用だけでなく、消耗品代・税金などを加えた維持費や管理コストが年々かさんできます。
そこでここからは、維持コストと車の寿命との関係を中心に、修理するか買い替えるかを決めるポイントを挙げて見ていきます。
修理や交換のコストだけでなく「効果」も考慮する
車は沢山の部品で構成されており、それぞれ役目も違えば、修理や交換にかかる費用も大きく異なります。そして、部品ごと故障の原因も違えば、修理交換後の「効果」も変わってきます。例えば、合計10万円の費用がかかったとしても、その他の部分に目立った故障や不具合がなくてその後5年・10年乗り続けられるのであれば、修理や交換をする価値は十分あります。
反対に、その時は1万円で済んだとしても、近い将来さらに大きな故障の種を抱えているのであれば、乗り換えも視野に入れたほうがいいでしょう。
具体的に言うと、不具合箇所が駆動系や足回り系だけであれば、一度修理や交換すればその後長く乗り続けることも可能です。
一方、オイル漏れや電機系の不具合は、一旦修理や交換しても関連する他の箇所が不具合を起こす可能性もあります。
修理や交換をする前に、修理すればどれぐらい車に乗れそうか、依頼業者に問い合わせておきましょう。そして修理するか買い替えるか決めるといいでしょう。
車検がやってくるタイミングをチェックする
一般的に、車は3年、5年、7年、9年、11年、13年…と、初回以降は2年に1度大きな出費の機会である車検が必ずやってきます。そして、どれだけ修理や交換に費用を費やしたとしても、次にやってくる車検を受けないことには公道を走ることができません。例えば、10年11ヶ月目のタイミングで、修理に大きな出費を伴う故障が発生したとしましょう。この場合は、翌月すぐに車検がやってくるので、買い替えを視野に入れたほうがいいかもしれません。
特に12年目は、自動車税などが上がるタイミング(13年目)も控えています。このタイミングで大きな故障が発生するとさらに維持費が高くなってくるため、より慎重に判断しましょう。
乗りたい車があるかどうかも大切
車の技術は年々進歩しているため、今乗っている車が10年を超えている場合は、今の車より燃費・安全性能で数段優れる新車がリリースされています。もしデザインなどが気に入って乗りたいと思える車があれば、思い切って乗り換えるのも一つの手です。
燃費・安全性能に優れる現在の車は、燃料代などの維持費が安上がりな上に故障しにくく、10年前の車より長持ちする可能性も高くなってきます。また、HVやEVなどのエコカーであれば、減税や購入補助金の恩恵も受けられます。
もちろん、費用をかけることができるなら、愛着のある今の車を維持することも可能です。ただし、総合的に見ると車を買い替えたほうがお金がかからない可能性もあります。
車を長持ちさせるための秘訣とは?

そこで最後に、車を長持ちさせるための秘訣を紹介していきます。
エンジンオイルのこまめな管理と交換
エンジンは車にとっての心臓であり、その寿命を大きく左右するのはエンジン内部を流れる血液と呼ぶべきエンジンオイルです。エンジンオイルには、潤滑・冷却・密封・洗浄という4つの働きがありますが、古くなったオイルはこの全ての能力が低下します。
そして、長期間古いオイルを使い続けた場合、以下の内容が同時に起こります。
・潤滑不足による金属摩耗の進行
・冷却不足による過熱での部品劣化
・密封力低下によるオイル漏れ
・洗浄力低下による目詰まり
この結果、エンジン並びにその周辺の部品が故障したり、最悪の場合はエンジン自体が焼き付き、使い物にならなくなったりする可能性もあります。
1度や2度オイル交換のタイミングが遅れたからと言って、すぐ上記のような不具合が出てくるわけではありません。しかし、10年間きちんと定期的にオイル交換をしてきた車とそうでない車とでは、エンジンの状態に雲泥の差が出てきます。
特に10年を超えた車がよく起こす故障の代表格である、オイル漏れは、定期的なオイル交換の実施によってその発生を遅らせたり、症状を軽くしたりすることが可能です。
法定点検や日常点検の実施
車検を受けないと車は公道を走れませんが、車検はあくまでも車が保安基準を満たしているかを確かめる検査に過ぎません。そのため、車検の検査項目に関係ない部分が故障、例えば軽いオイル漏れが発生していたとしても、保安基準さえ満たしていれば車検を通過できることもあります。一方、法定点検は車が本来の走行性能を維持しており、故障や不具合がないかを確かめる検査で、12ヶ月ごとに受けることが法律で義務付けられています。
ただし、点検を受けなくても公道を走行でき、罰金や罰則を科せられることもないため、受けていないという方もいるかもしれません。
しかし、法定点検では細分化された点検項目に沿って、各部品・消耗品の状態や劣化度合いを確認するため、故障の早期発見はもちろん、その悪化を食い止めることも可能です。
また、ユーザー自身がタイヤや各種オイルなどといった消耗品を点検する日常点検も、法定点検を補助するものとして実施すれば、より車の寿命を延ばすことにつながるでしょう。
「急」がつく運転を極力避ける
10年を超えた車の故障が増えてくる最大の理由は、経年使用による各種部品の劣化です。そして、急発進はエンジンに、急停車はブレーキに、急ハンドルはステリング関係に、急加速・急減速はミッション系に、それぞれ強い負荷をかけるため、劣化を早めてしまいます。
反対に、「急」のつかない運転、つまり車にやさしい運転を心がければ各種パーツにかかる負担が軽減され、結果的に車の寿命を延ばすことも期待できます。
また、エコ走法(燃費向上)や安全運転にもつながるため、実践してみましょう。
まとめ
- ①車の寿命が10年と言われている理由の背景には、「走行距離が10万kmに近づくこと」「各部品が経年劣化すること」「車自体の耐久性が低くなること」などが挙げられる
- ②10年を超えた車に多い故障は、「タイミングベルトの劣化・断絶」「各種オイルの漏れ」「ミッションの故障」「足回りのガタつき」「エンジンからの異音」などがある
- ③車は10年を超えると出費がかさむので寿命と言われるが、現実には10年を超えて使用されていることもある
- ④修理するか買い替えるかを決める際は、「修理の費用対効果」「車検のタイミング」「乗りたい車の有無」などを考慮すべき
- ⑤車を10年以上長持ちさせたいなら、エンジンオイルのこまめな管理と交換が最重要
- ⑥定期健診にあたる法定点検と日常点検の実施も大切
この記事の画像を見る
