中古車購入チェックポイント
更新日:2023.01.26 / 掲載日:2023.01.26
電気自動車の急速充電器が故障してたらどうする?故障発生時の対処法を解説
最近の電気自動車は、課題と言われていた航続可能距離も随分伸びてきたため、「次はEVもいいかな?」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、充電設備がまだ少ないのも事実です。また、短時間での充電を可能とする急速充電器が故障していて充電できないと、走行不可という事態になりかねません。
そこで今回は、電気自動車(EV)の急速充電器が故障した場合、どのように対処したらいいか、充電設備設置の現状などを踏まえつつ詳しく解説していきます。
・スターターやライト類、エアコンやカーナビなどを動かすための「補機用バッテリー」
・走行用モーターに電力を供給する「モーター駆動用バッテリー」
ここで注意したいのが、補機用バッテリーに電気が残っていたとしても、モーター駆動用バッテリーの電気が空っぽだと、ガソリン車におけるガス欠と同じ状態、つまり「電欠」で走行不能になってしまうことです。
この電欠を防ぐため、各所に設置されているのが「急速充電器」です。しかし、急速充電器は管理の難しい精密機器のため、故障やメンテナンス中で充電できないケースもあります。
しかも、電気はガソリンのように携行缶などで持ち運んで補充することもできません。だからこそ、電気自動車をトラブルなく便利に使うためには、急速充電器の仕組みや設置状況について詳しく知っておくことが大切です。

まずは、その仕組みや設置状況、主な設置場所などを詳しく説明していきます。
一方、普通充電器は充電器で受け取った交流をそのまま車に送り、車の中で直流に変えてからバッテリーに充電しています。
つまり、外野から直接バックホームしているのが急速充電器で、内野手が一旦中継プレイを挟みバックホームするのが普通充電器とイメージすると分かりやすいかもしれません。
アウトかセーフかはともかく、どちらのほうが早くボールをバックホームできるか(バッテリーに電気を届けられるか)は想像できるでしょう。交流より直流のほうが送電効率がいいため、大容量の電気を短時間でバッテリーに貯められます。
しかし、外野から直接バックホームするには強肩が必要なように、充電器内部で交流から直流に変換している分、充電器自体の設備は大掛かりになります。
2021年3月末の登録ベースで29,005店舗存在するガソリンスタンドに比べると、その設置は進んでいません。
急速充電器は、普通充電器より1台当たりの充電時間が短くて済むのが利点ですが、普通充電器は同時点で13508基設置されています。
つまり、急いで充電したくて充電スタンドを見つけても、そこには普通充電器しかなかったというケースが多いということです。
さらに、同サイトでの掲載データを詳しく見ていくと北海道全域における急速充電器の設置台数が358基なのに対し、東京都内の設置台数は486基でした。
つまり、車での移動距離が長くなりやすく、公共交通機関の整備状況から生活における必要性も高い、地方での設置が進んでいないとされています。
急速充電器の普及は、電気自動車の利便性を上げ、環境保護・脱炭素社会の実現につながるという公共性の高さから、市町村役場・公園など地方自治体の施設などに設置されているケースもあります。
さらに、国内では早い段階から電気自動車を発売している日産や三菱などのカーディーラーや、企業を上げて温室効果ガスを総量でゼロにする取り組みを進めているイオンなど、全国チェーンの商業施設にも設置されています。
また、地方自治体単位で充電施設の誘致を進めているところもあるほか、個人住宅レベルでの設置も進みつつあります。
なお、充電設備がある場所(不特定多数の方が利用できる場所・会員になれば誰でも利用できる場合を含む)には、「CHARGING POINT」と記された標識が掲げられています。
また、一目で充電器の種類が分かるよう、以下のように表記がされているため、用途に応じて目印にすると良いでしょう。
・普通充電器の場合
「EV・PHV 100V」または「EV・PHV 200V」
・急速充電器の場合
「EV・PHV QUICK」

歴然としたその違いを具体的に示すため、今国内で最も台数が多い電気自動車である日産リーフのベースグレード(バッテリー容量40kWh)を例に挙げて、電欠状態からフル充電までの所要時間を比較してみましょう。
普通充電器には100Vと200Vの2タイプがあります。100Vの充電能力は約3kWh、200Vは約6kWhです。
つまり、100Vタイプの普通充電器の場合(40kWh÷3kWh)で約13時間18分、200Vの場合は(40kWh÷6kWh)で6時間36分、充電に時間がかかる計算になります。
一方、急速充電器の充電能力は「50kWh以上」であるため、約30分もあれば充電が完了してしまいます。
さすがに数分で終わるガソリン給油スピードには及びませんが、急速充電器の増設が電気自動車の利便性アップに大きく関わることが分かります。
しかし、実際は普通充電より急速充電のほうが充電にかかる時間当たりの費用はかなり割高になります。
例えば、リーフをリリースしている日産は、EVユーザー向けに「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3(ZESP3)」という会員制の充電サービスを展開しています。
以下のように、EVの使用状況に合わせた4つのプランが用意されています。
・プレミアム40
40回・400分相当の急速充電付き。以降の急速充電は275円/10分で普通充電は無料
・プレミアム20
20回・200分相当の急速充電付き。以降の急速充電は330円/10分で普通充電は無料
・プレミアム10
10回・100分相当の急速充電付き。以降の急速充電は385円/10分で普通充電は無料
・シンプル
充電ごとに清算。急速充電は550円/10分で普通充電は1.65円/分
いずれを選んだ場合も、急速充電のほうが普通充電よりコストがかかります。
これはあくまでも一例ですが、他社の充電サービスを利用しようと充電スポットでその都度清算しようと、普通充電より急速充電のほうが充電にかかる時間当たりの費用が高いのは現状変わりません。
また、充電器を必要とする電気自動車の普及率は、日本自動車販売協会連合会が発表しているデータによると、普通車全体のわずか0.8%程度です。
つまり、設置・維持・管理にお金がかかるにも関わらず、電気自動車の利用数がまだまだ少ないため、ガソリンスタンドのようにビジネスとして成り立たないということになります。
いくら「地球環境のため」と言っても、儲からない事業に手を出す企業はそうそう出てきません。そのため、EVをリリースしている日産やテスラのような自動車メーカーや地方自治体などが、採算を度外視してユーザー・住民サービスの一環として設置しないかぎり、設置は進まないでしょう。
また、元々エネルギー源に乏しい日本では、短時間で代用力の電力を消費する急速充電器の設置にやや消極的なのも、システムがなかなか確立しないことに影響していると考えられます。

しかし、急速充電は高電圧の電流で従来の充電方法よりも充電時間を短縮できる一方、普通充電より車載バッテリー(リチウムイオンバッテリー)に負荷がかかります。
その結果、漏電までには至らなくとも、電気系統に不具合が生じたり、バッテリー自体の寿命が短くなったりする可能性があります。
事実、メーカーには急速充電でトラブルが発生したという報告が多数寄せられており、日産では「できるだけ急速充電を控え、普通充電かV2H(充放電機)を使い、充電してほしい」と注意喚起しているほどです。
これは、急速充電するには費用がかかるので電気自動車に乗り換えるのをためらってしまうという方が増えてしまい、それ故に充電システムが整わず、急速充電器もなかなか普及しない…という悪循環の元凶にもなっています。
例えば、普通充電器は100V(3kW)タイプなら数万円、200V(6kW)タイプでも20万円程度で設置が可能です。
一方、急速充電器は本体だけで200~300万円かかり、設置場所によっては工事費用を含めると1,000万円以上必要なケースもあります。
また、一般家庭で使う最大容量の40倍以上の契約容量が必要なため、基本料金だけで月に20万円以上かかってきます。さらに、高圧電力を新たに利用するにはキュービクル(変圧器)の設置と電気主任技術者の選定も必要になります。
一方、普通充電器の利用で一番多かったのは60分です。60分超は少なく60分以下が大半を占めていました。
もちろん、このデータには「急速充電器を使いたかったが仕方なく普通充電をした」もしくは「普通充電でも良かったが、たまたま空いていたので急速充電をした」という方も含まれているでしょう。
しかし、いずれにしても1時間以上充電しているEVユーザーは少ないという事実が浮かび上がってきます。
つまり、EVユーザーは充電スタンドが少ない現状をしっかり把握していて、電欠しないようこまめに充電を行っているということです。そのため、普通充電器の数が増えさえすれば、そもそも急速充電器は必要ないのかもしれません。
ただでさえ少ない急速充電器にようやく到達しても、故障や整備中で使えず、電欠してしまったというトラブルが頻発しているようです。
また、ガソリンスタンドには通常複数台の給油機(給油ノズル)があり、数台への給油を一気にこなせますが、充電スタンドは1基につき1台しか充電できません。
そのため、EVユーザー数が多い都市部や充電スタンドの絶対数が少ない地方などでは、長時間にわたる「充電の順番待ち」が発生する場合があります。
また、車の中で仮眠をしていて、充電は終わっているのに車を充電場所から移動してくれないというケースも見られます。
充電時間が長く、設置されている場所での滞在時間も長い普通充電スタンドでよくあるトラブルですが、充電できないのはもちろん、他のユーザーとの言い争いに発展するリスクもあるため注意しましょう。

政府も充電インフラの整備に力を入れていますが、電欠やトラブルに遭遇する心配がないほど充電スタンドの数が増えるのは、まだまだ先の話になるでしょう。
それでは、現状電欠や充電トラブルを回避するためには、一体どうすればいいのでしょうか?
以下では考えられる対処法を紹介していきます。
そのため、電気自動車の購入を検討する場合は、自分の行動範囲のどこに充電スタンドがあるのか、設置状況や設置場所を事前に確認しておく必要があります。
また、充電器が故障やメンテナンス中で使えないことや順番待ちが発生していたり、放置車両があったりする場合を考え、第2・第3候補となる充電スタンドの設置場所も一緒に把握しておくことが大切です。
なお、 一般道なら充電スタンド位置情報アプリを利用すると便利なので活用してみましょう。
ただし、充電スタンドの数や電欠した時のデメリットを考慮すると、ガソリン車と同じような感覚では少々危ないかもしれません。
目安としては、電池残量が30%を切ったら、80%を超える程度まで充電するのが電気自動車の良い運用方法だと考えられます。
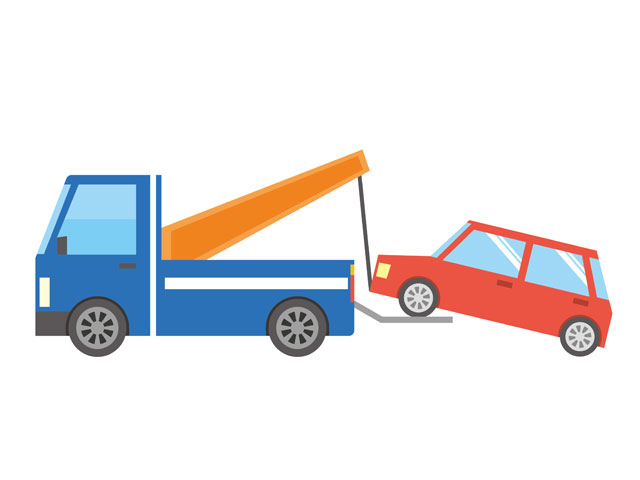
ただし、ガソリンは携行缶などで持ち運びができるため、その場での復旧も可能ですが、電欠の場合はそうもいきません。
ガソリン車の給油ランプと同様に、電気自動車のモーター駆動用バッテリー残量が乏しくなってくると、「リチウムイオンバッテリー残量警告灯」が黄色く点灯します。これが点灯したら、速やかに最寄りの充電施設で充電するようにしましょう。
もし付近に充電施設がないようであれば、完全に電気が無くなる前に安全な場所に停車し、その存在を周囲に知らせた上でJAFやロードサービスの救援を依頼しましょう。
ただ、プロでも電欠をその場で普及することは難しいため、基本的には最寄りのディーラーなどの充電施設が使えるところまでレッカー車で移動してもらうことになります。
なお、電気自動車の電気系統には高圧電流が流れているおり、感電・やけど・火災発生の危険があるため、むやみに触らないようにしましょう。
しかし、充電設備がまだ少ないのも事実です。また、短時間での充電を可能とする急速充電器が故障していて充電できないと、走行不可という事態になりかねません。
そこで今回は、電気自動車(EV)の急速充電器が故障した場合、どのように対処したらいいか、充電設備設置の現状などを踏まえつつ詳しく解説していきます。
この記事の目次
ガス欠ならぬ「電欠」の危機!?急速充電器の故障に備えて知っておくべきこと
電気自動車には通常、以下の2つのバッテリーが備わっています。・スターターやライト類、エアコンやカーナビなどを動かすための「補機用バッテリー」
・走行用モーターに電力を供給する「モーター駆動用バッテリー」
ここで注意したいのが、補機用バッテリーに電気が残っていたとしても、モーター駆動用バッテリーの電気が空っぽだと、ガソリン車におけるガス欠と同じ状態、つまり「電欠」で走行不能になってしまうことです。
この電欠を防ぐため、各所に設置されているのが「急速充電器」です。しかし、急速充電器は管理の難しい精密機器のため、故障やメンテナンス中で充電できないケースもあります。
しかも、電気はガソリンのように携行缶などで持ち運んで補充することもできません。だからこそ、電気自動車をトラブルなく便利に使うためには、急速充電器の仕組みや設置状況について詳しく知っておくことが大切です。
電気自動車の急速充電器とは?

まずは、その仕組みや設置状況、主な設置場所などを詳しく説明していきます。
急速充電器の仕組み
電気自動車のモーター駆動用バッテリーには、潮流電気が貯められていますが、急速充電器は外部から「交流」を取り入れ、充電器の中で高電圧の「直流」に変換して車に送り、直接バッテリーに充電しています。一方、普通充電器は充電器で受け取った交流をそのまま車に送り、車の中で直流に変えてからバッテリーに充電しています。
つまり、外野から直接バックホームしているのが急速充電器で、内野手が一旦中継プレイを挟みバックホームするのが普通充電器とイメージすると分かりやすいかもしれません。
アウトかセーフかはともかく、どちらのほうが早くボールをバックホームできるか(バッテリーに電気を届けられるか)は想像できるでしょう。交流より直流のほうが送電効率がいいため、大容量の電気を短時間でバッテリーに貯められます。
しかし、外野から直接バックホームするには強肩が必要なように、充電器内部で交流から直流に変換している分、充電器自体の設備は大掛かりになります。
急速充電器の普及状況はどれぐらい?
電気自動車(EV)充電スタンド情報サイトである「GoGoEV」によると、国内独自規格「CHAdeMO(チャデモ)」に即した急速充電器の設置台数は、2022年12月23日時点で8088基でした。2021年3月末の登録ベースで29,005店舗存在するガソリンスタンドに比べると、その設置は進んでいません。
急速充電器は、普通充電器より1台当たりの充電時間が短くて済むのが利点ですが、普通充電器は同時点で13508基設置されています。
つまり、急いで充電したくて充電スタンドを見つけても、そこには普通充電器しかなかったというケースが多いということです。
さらに、同サイトでの掲載データを詳しく見ていくと北海道全域における急速充電器の設置台数が358基なのに対し、東京都内の設置台数は486基でした。
つまり、車での移動距離が長くなりやすく、公共交通機関の整備状況から生活における必要性も高い、地方での設置が進んでいないとされています。
急速充電器が設置されている主な場所
短時間での充電が可能な急速充電器は、高速道路のSAやPA、幹線道路沿いの道の駅、コンビニなど、比較的滞在時間が短い場所での設置が進んでいます。急速充電器の普及は、電気自動車の利便性を上げ、環境保護・脱炭素社会の実現につながるという公共性の高さから、市町村役場・公園など地方自治体の施設などに設置されているケースもあります。
さらに、国内では早い段階から電気自動車を発売している日産や三菱などのカーディーラーや、企業を上げて温室効果ガスを総量でゼロにする取り組みを進めているイオンなど、全国チェーンの商業施設にも設置されています。
普通充電器が設置されている主な場所
1回当たりの充電時間が長くなる普通充電器は、滞在時間が長くなると思われる宿泊施設・商業施設・オフィスビルの駐車場などによく設置されています。また、地方自治体単位で充電施設の誘致を進めているところもあるほか、個人住宅レベルでの設置も進みつつあります。
なお、充電設備がある場所(不特定多数の方が利用できる場所・会員になれば誰でも利用できる場合を含む)には、「CHARGING POINT」と記された標識が掲げられています。
また、一目で充電器の種類が分かるよう、以下のように表記がされているため、用途に応じて目印にすると良いでしょう。
・普通充電器の場合
「EV・PHV 100V」または「EV・PHV 200V」
・急速充電器の場合
「EV・PHV QUICK」
普通充電と急速充電の違い

フル充電までに要する時間
普通充電器と急速充電器の最大の違いは、「フル充電までに要する時間」にほかなりません。歴然としたその違いを具体的に示すため、今国内で最も台数が多い電気自動車である日産リーフのベースグレード(バッテリー容量40kWh)を例に挙げて、電欠状態からフル充電までの所要時間を比較してみましょう。
普通充電器には100Vと200Vの2タイプがあります。100Vの充電能力は約3kWh、200Vは約6kWhです。
つまり、100Vタイプの普通充電器の場合(40kWh÷3kWh)で約13時間18分、200Vの場合は(40kWh÷6kWh)で6時間36分、充電に時間がかかる計算になります。
一方、急速充電器の充電能力は「50kWh以上」であるため、約30分もあれば充電が完了してしまいます。
さすがに数分で終わるガソリン給油スピードには及びませんが、急速充電器の増設が電気自動車の利便性アップに大きく関わることが分かります。
充電費用は急速充電のほうが割高
ハイオクとレギュラーで値段が異なるガソリンと違い、急いで充電しようがゆっくり充電しようが同じ電気なので費用も変わらないと思うかもしれません。しかし、実際は普通充電より急速充電のほうが充電にかかる時間当たりの費用はかなり割高になります。
例えば、リーフをリリースしている日産は、EVユーザー向けに「日産ゼロ・エミッションサポートプログラム3(ZESP3)」という会員制の充電サービスを展開しています。
以下のように、EVの使用状況に合わせた4つのプランが用意されています。
・プレミアム40
40回・400分相当の急速充電付き。以降の急速充電は275円/10分で普通充電は無料
・プレミアム20
20回・200分相当の急速充電付き。以降の急速充電は330円/10分で普通充電は無料
・プレミアム10
10回・100分相当の急速充電付き。以降の急速充電は385円/10分で普通充電は無料
・シンプル
充電ごとに清算。急速充電は550円/10分で普通充電は1.65円/分
いずれを選んだ場合も、急速充電のほうが普通充電よりコストがかかります。
これはあくまでも一例ですが、他社の充電サービスを利用しようと充電スポットでその都度清算しようと、普通充電より急速充電のほうが充電にかかる時間当たりの費用が高いのは現状変わりません。
普通充電に比べて急速充電はシステムが確立していない
前述したように、急速充電の充電費用が高いのは、その設置メンテナンスにコストがかさむからです。また、充電器を必要とする電気自動車の普及率は、日本自動車販売協会連合会が発表しているデータによると、普通車全体のわずか0.8%程度です。
つまり、設置・維持・管理にお金がかかるにも関わらず、電気自動車の利用数がまだまだ少ないため、ガソリンスタンドのようにビジネスとして成り立たないということになります。
いくら「地球環境のため」と言っても、儲からない事業に手を出す企業はそうそう出てきません。そのため、EVをリリースしている日産やテスラのような自動車メーカーや地方自治体などが、採算を度外視してユーザー・住民サービスの一環として設置しないかぎり、設置は進まないでしょう。
また、元々エネルギー源に乏しい日本では、短時間で代用力の電力を消費する急速充電器の設置にやや消極的なのも、システムがなかなか確立しないことに影響していると考えられます。
急速充電器がなかなか普及しない理由

過充電によるトラブル発生のリスク
過充電によるトラブル防止のため、ほとんどの急速充電器は充電制御によって80%や90%で充電が終了されるようになっています。しかし、急速充電は高電圧の電流で従来の充電方法よりも充電時間を短縮できる一方、普通充電より車載バッテリー(リチウムイオンバッテリー)に負荷がかかります。
その結果、漏電までには至らなくとも、電気系統に不具合が生じたり、バッテリー自体の寿命が短くなったりする可能性があります。
事実、メーカーには急速充電でトラブルが発生したという報告が多数寄せられており、日産では「できるだけ急速充電を控え、普通充電かV2H(充放電機)を使い、充電してほしい」と注意喚起しているほどです。
設置・メンテナンスコストが高い
急速充電器の設置やメンテナンスコストは、普通充電器より圧倒的に高いです。これは、急速充電するには費用がかかるので電気自動車に乗り換えるのをためらってしまうという方が増えてしまい、それ故に充電システムが整わず、急速充電器もなかなか普及しない…という悪循環の元凶にもなっています。
例えば、普通充電器は100V(3kW)タイプなら数万円、200V(6kW)タイプでも20万円程度で設置が可能です。
一方、急速充電器は本体だけで200~300万円かかり、設置場所によっては工事費用を含めると1,000万円以上必要なケースもあります。
また、一般家庭で使う最大容量の40倍以上の契約容量が必要なため、基本料金だけで月に20万円以上かかってきます。さらに、高圧電力を新たに利用するにはキュービクル(変圧器)の設置と電気主任技術者の選定も必要になります。
そもそも急速充電器は必要ない?
先ほどのデータ元として紹介した「GoGoEV」によると、急速充電器の1回の充電時間の傾向で一番多かったのは30分でした。一方、普通充電器の利用で一番多かったのは60分です。60分超は少なく60分以下が大半を占めていました。
もちろん、このデータには「急速充電器を使いたかったが仕方なく普通充電をした」もしくは「普通充電でも良かったが、たまたま空いていたので急速充電をした」という方も含まれているでしょう。
しかし、いずれにしても1時間以上充電しているEVユーザーは少ないという事実が浮かび上がってきます。
つまり、EVユーザーは充電スタンドが少ない現状をしっかり把握していて、電欠しないようこまめに充電を行っているということです。そのため、普通充電器の数が増えさえすれば、そもそも急速充電器は必要ないのかもしれません。
急速充電器の使用でよく起こるトラブル
続いて、現在急速充電器の使用でよく起こっているトラブルについてまとめてみました。急速充電器の故障や不具合がなかなか改善されない
急速充電器は仕組みが大掛かりな上、保守・点検・整備に高圧電流を取り扱う専門知識が不可欠です。そのため、故障や不具合がなかなか改善されないことがあります。ただでさえ少ない急速充電器にようやく到達しても、故障や整備中で使えず、電欠してしまったというトラブルが頻発しているようです。
順番待ちが発生して充電できない
急速充電にしろ普通充電にしろ、充電スタンドの数はガソリンスタンドよりかなり少ないです。その上、いずれの場合も数分あれば終了する燃料給油より1回の充電に時間がかかります。また、ガソリンスタンドには通常複数台の給油機(給油ノズル)があり、数台への給油を一気にこなせますが、充電スタンドは1基につき1台しか充電できません。
そのため、EVユーザー数が多い都市部や充電スタンドの絶対数が少ない地方などでは、長時間にわたる「充電の順番待ち」が発生する場合があります。
充電したまま放置されている車がある
充電スタンドでの充電は時間がかかる上、充電完了後に車の移動を促すスタッフが常駐していないことがほとんどです。そのため、充電したまま放置している車があり、充電できないというトラブルの報告もあります。また、車の中で仮眠をしていて、充電は終わっているのに車を充電場所から移動してくれないというケースも見られます。
充電時間が長く、設置されている場所での滞在時間も長い普通充電スタンドでよくあるトラブルですが、充電できないのはもちろん、他のユーザーとの言い争いに発展するリスクもあるため注意しましょう。
電欠&充電トラブルを回避するための対処法

政府も充電インフラの整備に力を入れていますが、電欠やトラブルに遭遇する心配がないほど充電スタンドの数が増えるのは、まだまだ先の話になるでしょう。
それでは、現状電欠や充電トラブルを回避するためには、一体どうすればいいのでしょうか?
以下では考えられる対処法を紹介していきます。
充電スタンドのある場所を日ごろから把握しておく
自動車メーカーのたゆまぬ努力の結果、電気自動車の航続可能距離は格段に伸びましたが、ガソリン車には及びません。そのため、電気自動車の購入を検討する場合は、自分の行動範囲のどこに充電スタンドがあるのか、設置状況や設置場所を事前に確認しておく必要があります。
また、充電器が故障やメンテナンス中で使えないことや順番待ちが発生していたり、放置車両があったりする場合を考え、第2・第3候補となる充電スタンドの設置場所も一緒に把握しておくことが大切です。
なお、 一般道なら充電スタンド位置情報アプリを利用すると便利なので活用してみましょう。
余裕のある充電を心掛ける
電気自動車の場合、満タンにするとバッテリーへの負担が増すとされています。そのため、日常的には急速充電器がストップする80~90%くらいの充電量で使い続けるのが車を長持ちさせるコツと言えるでしょう。ただし、充電スタンドの数や電欠した時のデメリットを考慮すると、ガソリン車と同じような感覚では少々危ないかもしれません。
目安としては、電池残量が30%を切ったら、80%を超える程度まで充電するのが電気自動車の良い運用方法だと考えられます。
電欠してしまったらどうする?
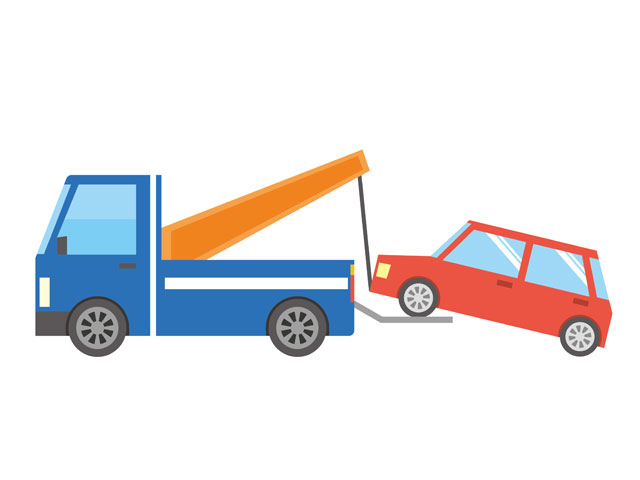
ただし、ガソリンは携行缶などで持ち運びができるため、その場での復旧も可能ですが、電欠の場合はそうもいきません。
ガソリン車の給油ランプと同様に、電気自動車のモーター駆動用バッテリー残量が乏しくなってくると、「リチウムイオンバッテリー残量警告灯」が黄色く点灯します。これが点灯したら、速やかに最寄りの充電施設で充電するようにしましょう。
もし付近に充電施設がないようであれば、完全に電気が無くなる前に安全な場所に停車し、その存在を周囲に知らせた上でJAFやロードサービスの救援を依頼しましょう。
ただ、プロでも電欠をその場で普及することは難しいため、基本的には最寄りのディーラーなどの充電施設が使えるところまでレッカー車で移動してもらうことになります。
なお、電気自動車の電気系統には高圧電流が流れているおり、感電・やけど・火災発生の危険があるため、むやみに触らないようにしましょう。
まとめ
- ①電気自動車の急速充電器は、交流電圧を直流変換することで車両に大電力を供給することで、短時間での充電を可能にしている
- ②急速充電器は、高速道路SA・道の駅・コンビニ・ガソリンスタンド・カーディーラーなどに設置されている
- ③急速充電器には、充電時間を短縮できるメリットがあるが、充電にかかる費用が高いなどのデメリットもある
- ④急速充電器は、過充電によるリスクがあったり、設置やメンテナンスに高額のコストがかかったりするといった弱点も存在する。そのため、設置が容易かつ安価な普通充電より普及台数が少ない
- ⑤充電スタンドがあるところに行ったとしても、故障していたり、長時間の充電待ち、放置車両などのトラブルが発生している
- ⑥電気自動車の電欠やトラブル回避のため、充電スタンドの設置場所の把握や、こまめな充電を心掛ける
- ⑦電欠した場合は、JAFやロードサービスなどの救援を依頼する
この記事の画像を見る
