中古車購入チェックポイント
更新日:2023.04.17 / 掲載日:2023.04.17
軽自動車の自動車税とはどんな税金?税額や納付方法などについて解説
軽自動車に関する税金のうち、毎年課税されるのが軽自動車税(種別割)です。
今回は、この軽自動車税についてあまりよく知らない方のために、どのような税金なのか、税額はいくら位かかるのか、どのように納付するのか詳しく解説していきます。
また、軽自動車税の納付通知書が郵送されてきても、未納のまま放置するとどのようになるのかについても知っておいたほうがいいでしょう。
普段は軽自動車税に関してあまり意識したことがない方も、これから軽自動車を購入予定という方も目を通してみてください。

税額は車の総排気量に応じて変わるのが特徴です。排気量1ℓ以下~6ℓ超えまで区分されており、0.5ℓ大きくなるごとに税額が高くなるという仕組みです。
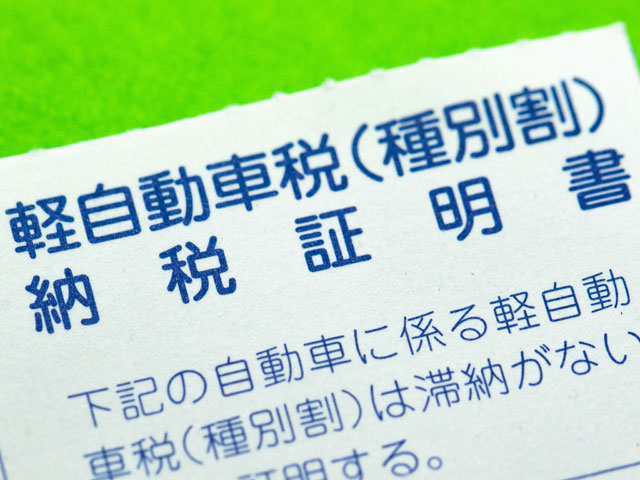
毎年4月1日時点での軽自動車の所有者宛てに、納税通知書が5月上旬頃に郵送で届きますので納付期限までに支払いましょう。
軽自動車税の課税対象は、軽自動車以外にもバイクや原付などの二輪車、トラクターやフォークリフト、農耕車などの小型特殊車も含まれます。

具体的には2015年3月31日までに新規検査を受けた軽自動車は、旧税率での税額となります。
2015年4月1日以降に新規検査を受けた軽自動車は、新税率に基づく税額でその後の軽自動車税(種別割)を納めていくことになります。
新税率は、旧税率よりも税額が高いです。今後も税率が変わる可能性はあるので注意しておきましょう。
軽自動車税は一律なので、自家用車が7,200円、事業用車は5,500円です。また、軽貨物車に関しては自家用車は4,000円、事業用車は3,000円となっています。
少し古い中古車を購入した場合、車検証などで確認してみるといいでしょう。
これから新車を購入予定の方も、新税率で軽自動車税(種別割)が課税されます。
税額は自家用車が10,800円、事業車は6,900円、自家用貨物車は5,000円、事業用貨物車は3,800円となります。
車が排出する排気ガスは、地球温暖化を加速させる要因の一つだと国は考えています。古い車は環境への負荷が重いため、税金を高くすることで買い替えを促している一面もあるでしょう。
新車登録から13年経過すると、軽自動車は税額が約20%増の12,900円となります。
環境に優しい電気自動車やハイブリッド車の場合は、増税の対象外となっているので、新車登録から13年経過しても税金は変わりません。
ガソリン車とLPガス車が増税の対象となります。
対象となるのは、身体障害者本人が使用する車もしくは身体障害者のために使用されている車になります。運転者は本人だけでなく、同居や別居の家族、常時介護をする方なども対象です。
また、障害の区分や級別によって減免となる範囲も決められています。各自治体によって条件などが細かく規定されているので、確認してみましょう。
軽自動車税は月割りで請求されることはないので、4月2日以降に購入してもその年の分は税金を納める必要はありません。つまり、4月2日以降に車を購入し、新規登録をすることでその年1年分の軽自動車税(種別割)を節約することができるのです。
グリーン化特例とは、排気ガスの排出量が少ない、燃費性能の良い、環境性能に優れた車に対して減税される制度です。
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド車が対象です。
それぞれ条件に応じて税額の軽減率が異なり、標準税額の25%から最大で75%まで減税となります。
ただし、グリーン化特例に適用には期限が設けられています。2023年3月現在において、2023年3月31日までに新規登録した車両はその翌年に限り適用されることになっています。
今後、グリーン化特例の期間が延長される可能性もありますが、期限については注意しましょう。

納付期限はほとんどの地域で5月31日までとなっています。5月31日が土日の場合は6月上旬です。
また、一部地域では納付期限が6月30日となっているところもあります。こういった地域では、納税通知書の到着が6月までずれ込む可能性もあります。
遅延金の加算率は各自治体によって異なるので一概には言えませんが、大体は納付期限から1ヶ月までは納付額の約3%、1ヶ月以上経過すると納付額の約9%の遅延金が加算されます。
遅延金は計算上、1,000円未満だと切り捨てになるので、1,000円以上となった段階で加算されることになっています。
納付期限が経過すると、後日遅延金が発生した段階で遅延金分が加算された納税通知書が届くので、そちらを使って支払う必要があります。
期限が切れていたとしても、あまり日数が経過していなければ納税通知書が使える場合もあるので、できるだけ早めに軽自動車税を支払うようにしましょう。
財産の差し押さえまでの流れは、まず督促状、催告状が届き、差押予告通知書がきて差し押さえとなります。
納付期限からどの位経過したら差し押さえが行われるかは各自治体によって異なるため明確には決まっていません。ただし、法律では納付期限から1ヶ月程度経過すれば差押可能となっています。
この場合の差押対象の財産は給与や銀行口座などが当てはまり、強制的に税額分を徴収されます。
もし車検を受けないまま車検期限が過ぎると、無車検車となり公道を走行できなくなります。走行すれば、法律違反で罰せられてしまうので注意しましょう。

しかし、直接窓口に出向かなくても、ネットからクレジットカードを使って決済を行ったり、ネットバンキングによるペイジーを使ったりする方法もあります。
さらに、現金払いでなくても電子マネーなどのキャッシュレス決済にも対応しています。
便利な納付方法がいくつもあるので、忙しい方でも効率よく期限までに納付できるでしょう。
納付場所はコンビニや銀行、信用金庫など金融機関が主です。他にも、郵便局や市区町村の役所の納税を担当する課でも納付できます。
納付の際は、窓口に納税通知書と現金を提出すれば手続きしてもらえます。
納税通知書には領収印を押すことで「納税証明書」になる半券がついています。窓口で納付すると、この納税証明書が渡されますので、きちんと保管しておきましょう。
給与の振込口座を、電気やガスなどの光熱費の引き落としと同じ口座にしている方もいるでしょう。その口座を軽自動車税の納付口座にすれば効率的です。
納付期限を忘れていたとしても勝手に引き落とされるので、納付し忘れて知らないうちに滞納になっていたという心配はありません。
ただし、口座振替を利用する場合は、あらかじめ銀行などの金融機関に出向いて手続きをする必要があります。
引き落とし日までにクレジットカードに紐づけした口座に入金しておけばよいので、持ち合わせがなくてもすぐに納付できます。また、時間や場所を選ばずに納付できるのもメリットの一つです。
各市区町村の支払いサイトにアクセスし、クレジットカード情報などを入力して決済を行います。
ただし、決済手数料がかかります。それに加えて、クレジットカードは決済が反映されるまでに数週間かかる場合もあるので注意してください。
ペイジーというのは、ネットバンキングやATMを使って支払いができるサービスのことです。
導入されていない自治体もありますが、届いた納税通知書にペイジーのマークが書かれていれば使えますので確認してみましょう。
ネットバンキングなら、パソコンやスマホからでも利用可能です。納付書に記載された番号を入力するなどして、決済手続きをします。
自動読み取りが機能がついたATMなら、納付書を差し込むだけで入力が不要です。ただし、コンビニのATMは使えないので注意しましょう。
納付書に記載されているバーコードを読み取るだけで、キャッシュレス決済が可能です。また、電子マネーを導入している自治体も増えています。
自宅や外出先などからスマホで簡単に決済ができるので、時間がない方には効率的でしょう。決済手数料も無料となっている自治体が多いです。
ただし、決済が反映されるまで他の納付方法よりも時間をかかるので気を付けましょう。
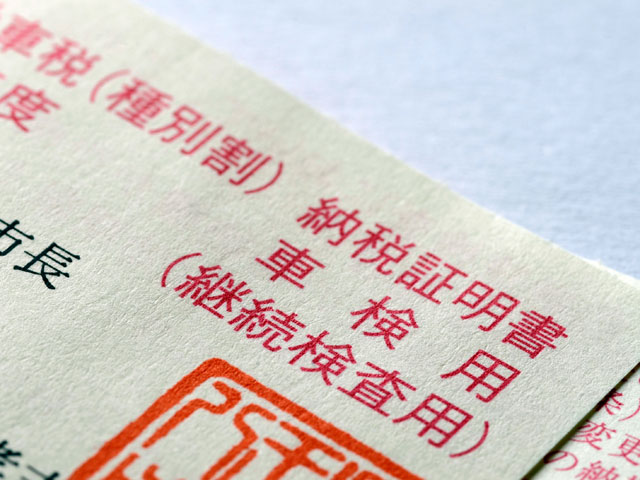
しかし、2023年1月よりオンラインで納税の有無を確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入されました。車検を請け負うディーラーや整備工場などの業者は、オンラインシステムに必要事項を入力し、検索することで該当車両が納税済みか未納かを簡単に確認することができます。
このシステムの導入前は、納税証明書がない場合は交付手続きが必要でしたが、現在では車検時に納税証明書がなくても、オンラインシステムで納税済みが確認できれば車検が受けられるようになっています。
軽自動車税納付確認システムに納税情報が反映されるまでには、相当な日数がかかるとされています。そのため、納付後すぐに車検を受ける場合は、システムで納税の有無が確認できないので納税証明書の提示が求められるでしょう。
さらに中古車を購入後、同じ年度内に車検を受ける場合も、納税者が前の所有者になるのでシステムでの確認が難しくなります。また、他の市区町村から転居し、その年度内で車検を受ける場合も当てはまります。
過去に未納がある場合も、納税証明書の提示が求められるでしょう。
もし納税証明書が必要であれば、交付請求をすることで発行されます。その申請方法は、ネット、窓口、郵送の3つがあります。
窓口の場合は、市税事務所や区役所の出張所、市役所のサービスコーナーや連絡所などです。
窓口で受け取りができない場合は郵送も可能です。その際は送料がかかるので注意しましょう。

廃車にした場合、自動車税は残りの期間に応じて月割りで還付されますが、軽自動車税は金額が少額なので残念ながら還付はされません。間違えないようにしましょう。
今回は、この軽自動車税についてあまりよく知らない方のために、どのような税金なのか、税額はいくら位かかるのか、どのように納付するのか詳しく解説していきます。
また、軽自動車税の納付通知書が郵送されてきても、未納のまま放置するとどのようになるのかについても知っておいたほうがいいでしょう。
普段は軽自動車税に関してあまり意識したことがない方も、これから軽自動車を購入予定という方も目を通してみてください。
この記事の目次
自動車税(種別割)とは?

税額は車の総排気量に応じて変わるのが特徴です。排気量1ℓ以下~6ℓ超えまで区分されており、0.5ℓ大きくなるごとに税額が高くなるという仕組みです。
軽自動車税(種別割)とは?
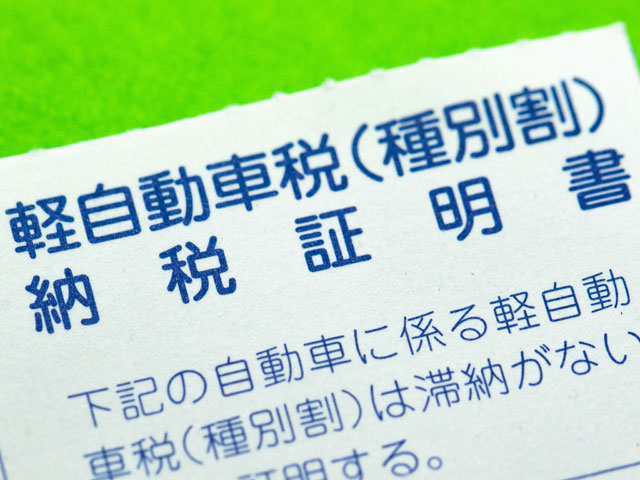
毎年4月1日時点での軽自動車の所有者宛てに、納税通知書が5月上旬頃に郵送で届きますので納付期限までに支払いましょう。
軽自動車税の課税対象は、軽自動車以外にもバイクや原付などの二輪車、トラクターやフォークリフト、農耕車などの小型特殊車も含まれます。
軽自動車税の税額について

具体的には2015年3月31日までに新規検査を受けた軽自動車は、旧税率での税額となります。
2015年4月1日以降に新規検査を受けた軽自動車は、新税率に基づく税額でその後の軽自動車税(種別割)を納めていくことになります。
新税率は、旧税率よりも税額が高いです。今後も税率が変わる可能性はあるので注意しておきましょう。
旧税率の税額
所有している軽自動車が2015年3月31日までに初回の検査を受けた場合は、旧税率が適用されます。軽自動車税は一律なので、自家用車が7,200円、事業用車は5,500円です。また、軽貨物車に関しては自家用車は4,000円、事業用車は3,000円となっています。
少し古い中古車を購入した場合、車検証などで確認してみるといいでしょう。
新税率の税額
所有している軽自動車が2015年4月1日以降に初回の新規検査を受けた場合は、2016年度から改定された新税率が適用されます。これから新車を購入予定の方も、新税率で軽自動車税(種別割)が課税されます。
税額は自家用車が10,800円、事業車は6,900円、自家用貨物車は5,000円、事業用貨物車は3,800円となります。
新車登録から13年経過すると重税対象
新車登録から13年経過した車に関しては、軽自動車税が増税されるので注意しましょう。車が排出する排気ガスは、地球温暖化を加速させる要因の一つだと国は考えています。古い車は環境への負荷が重いため、税金を高くすることで買い替えを促している一面もあるでしょう。
新車登録から13年経過すると、軽自動車は税額が約20%増の12,900円となります。
環境に優しい電気自動車やハイブリッド車の場合は、増税の対象外となっているので、新車登録から13年経過しても税金は変わりません。
ガソリン車とLPガス車が増税の対象となります。
身体障害者などの減免制度
軽自動車税(種別割)では、身体障害者の方を対象に減税もしくは免税される制度があります。対象となるのは、身体障害者本人が使用する車もしくは身体障害者のために使用されている車になります。運転者は本人だけでなく、同居や別居の家族、常時介護をする方なども対象です。
また、障害の区分や級別によって減免となる範囲も決められています。各自治体によって条件などが細かく規定されているので、確認してみましょう。
年度途中で車を購入すると税金がお得になる
軽自動車税は、毎年4月1日時点での軽自動車の所有者に対して課税されます。つまり、新車を購入する予定であっても4月1日の時点でまだ所有者となっていなければ、納税通知書も届かないので課税されないことになります。軽自動車税は月割りで請求されることはないので、4月2日以降に購入してもその年の分は税金を納める必要はありません。つまり、4月2日以降に車を購入し、新規登録をすることでその年1年分の軽自動車税(種別割)を節約することができるのです。
エコカーは減税対象
「エコカー減税制度」というものがありますが、これは自動車重量税に適用される制度なので軽自動車税は対象となっていません。その代わりに「グリーン化特例」という減税制度が適用されます。グリーン化特例とは、排気ガスの排出量が少ない、燃費性能の良い、環境性能に優れた車に対して減税される制度です。
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド車が対象です。
それぞれ条件に応じて税額の軽減率が異なり、標準税額の25%から最大で75%まで減税となります。
ただし、グリーン化特例に適用には期限が設けられています。2023年3月現在において、2023年3月31日までに新規登録した車両はその翌年に限り適用されることになっています。
今後、グリーン化特例の期間が延長される可能性もありますが、期限については注意しましょう。
軽自動車税の納付期限

納付期限はほとんどの地域で5月31日までとなっています。5月31日が土日の場合は6月上旬です。
また、一部地域では納付期限が6月30日となっているところもあります。こういった地域では、納税通知書の到着が6月までずれ込む可能性もあります。
納付期限を過ぎても支払わなかったらどうなる?
納付期限までに軽自動車税を納付しなかった場合、期限後大体20日以内に督促状が届きます。そして、納付期限の経過日数によっては遅延金が加算されます。遅延金の加算率は各自治体によって異なるので一概には言えませんが、大体は納付期限から1ヶ月までは納付額の約3%、1ヶ月以上経過すると納付額の約9%の遅延金が加算されます。
遅延金は計算上、1,000円未満だと切り捨てになるので、1,000円以上となった段階で加算されることになっています。
納付期限が経過すると、後日遅延金が発生した段階で遅延金分が加算された納税通知書が届くので、そちらを使って支払う必要があります。
期限が切れていたとしても、あまり日数が経過していなければ納税通知書が使える場合もあるので、できるだけ早めに軽自動車税を支払うようにしましょう。
財産を差し押さえられる可能性も
遅延金が加算された後も納付しないで軽自動車税を滞納し続けたとしても、未納のまま許されるわけではありません。その場合、財産の差し押さえが行われることもあります。財産の差し押さえまでの流れは、まず督促状、催告状が届き、差押予告通知書がきて差し押さえとなります。
納付期限からどの位経過したら差し押さえが行われるかは各自治体によって異なるため明確には決まっていません。ただし、法律では納付期限から1ヶ月程度経過すれば差押可能となっています。
この場合の差押対象の財産は給与や銀行口座などが当てはまり、強制的に税額分を徴収されます。
未納のままだと車検を受けられない
車検を受けるためには、軽自動車税を納めていることが条件となっています。もし車検を受けないまま車検期限が過ぎると、無車検車となり公道を走行できなくなります。走行すれば、法律違反で罰せられてしまうので注意しましょう。
軽自動車税の納付方法

しかし、直接窓口に出向かなくても、ネットからクレジットカードを使って決済を行ったり、ネットバンキングによるペイジーを使ったりする方法もあります。
さらに、現金払いでなくても電子マネーなどのキャッシュレス決済にも対応しています。
便利な納付方法がいくつもあるので、忙しい方でも効率よく期限までに納付できるでしょう。
コンビニなどの窓口納付
自動車税の納付方法は、郵送されてくる納税通知書を持参して納付場所に出向く、窓口納付が一般的です。納付場所はコンビニや銀行、信用金庫など金融機関が主です。他にも、郵便局や市区町村の役所の納税を担当する課でも納付できます。
納付の際は、窓口に納税通知書と現金を提出すれば手続きしてもらえます。
納税通知書には領収印を押すことで「納税証明書」になる半券がついています。窓口で納付すると、この納税証明書が渡されますので、きちんと保管しておきましょう。
口座振替による納付
自分名義の銀行口座を指定し、自動的に引き落としになる口座振替という納付方法もあります。給与の振込口座を、電気やガスなどの光熱費の引き落としと同じ口座にしている方もいるでしょう。その口座を軽自動車税の納付口座にすれば効率的です。
納付期限を忘れていたとしても勝手に引き落とされるので、納付し忘れて知らないうちに滞納になっていたという心配はありません。
ただし、口座振替を利用する場合は、あらかじめ銀行などの金融機関に出向いて手続きをする必要があります。
クレジットカードからの納付
コンビニや金融機関などの窓口に出向かなくても、いつでもネットからクレジットカードを使って納付することも可能です。引き落とし日までにクレジットカードに紐づけした口座に入金しておけばよいので、持ち合わせがなくてもすぐに納付できます。また、時間や場所を選ばずに納付できるのもメリットの一つです。
各市区町村の支払いサイトにアクセスし、クレジットカード情報などを入力して決済を行います。
ただし、決済手数料がかかります。それに加えて、クレジットカードは決済が反映されるまでに数週間かかる場合もあるので注意してください。
ペイジーを使った納付
ネットからの納付方法の一つに、ペイジー(Pay-easy)を使った支払方法もあります。ペイジーというのは、ネットバンキングやATMを使って支払いができるサービスのことです。
導入されていない自治体もありますが、届いた納税通知書にペイジーのマークが書かれていれば使えますので確認してみましょう。
ネットバンキングなら、パソコンやスマホからでも利用可能です。納付書に記載された番号を入力するなどして、決済手続きをします。
自動読み取りが機能がついたATMなら、納付書を差し込むだけで入力が不要です。ただし、コンビニのATMは使えないので注意しましょう。
キャッシュレス決済での納付
スマホやタブレットの決済アプリ、請求書支払いサービスも軽自動車税の納付に使えます。納付書に記載されているバーコードを読み取るだけで、キャッシュレス決済が可能です。また、電子マネーを導入している自治体も増えています。
自宅や外出先などからスマホで簡単に決済ができるので、時間がない方には効率的でしょう。決済手数料も無料となっている自治体が多いです。
ただし、決済が反映されるまで他の納付方法よりも時間をかかるので気を付けましょう。
車検時に軽自動車税の納税証明書の提示は必要?
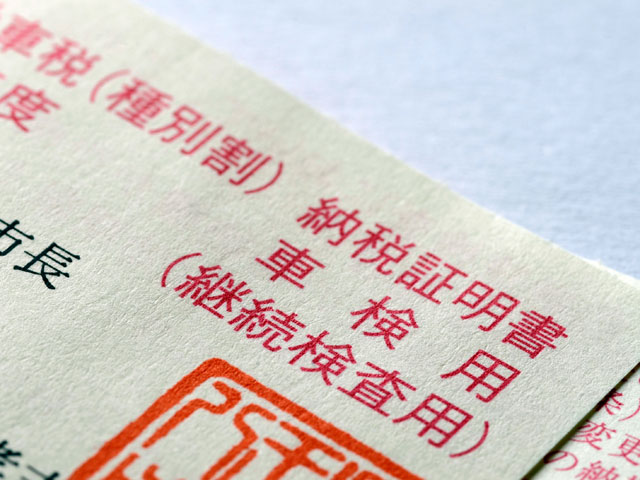
しかし、2023年1月よりオンラインで納税の有無を確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入されました。車検を請け負うディーラーや整備工場などの業者は、オンラインシステムに必要事項を入力し、検索することで該当車両が納税済みか未納かを簡単に確認することができます。
このシステムの導入前は、納税証明書がない場合は交付手続きが必要でしたが、現在では車検時に納税証明書がなくても、オンラインシステムで納税済みが確認できれば車検が受けられるようになっています。
納税証明書の提示が必要な場合もある
基本的には車検時に納税証明書の提示は不要ですが、例外もあるので注意してください。軽自動車税納付確認システムに納税情報が反映されるまでには、相当な日数がかかるとされています。そのため、納付後すぐに車検を受ける場合は、システムで納税の有無が確認できないので納税証明書の提示が求められるでしょう。
さらに中古車を購入後、同じ年度内に車検を受ける場合も、納税者が前の所有者になるのでシステムでの確認が難しくなります。また、他の市区町村から転居し、その年度内で車検を受ける場合も当てはまります。
過去に未納がある場合も、納税証明書の提示が求められるでしょう。
納税証明書がなければ交付してもらう
納税証明書は、窓口で納付した時に受け取ることができます。しかし、スマホ決済やクレジットカードの納付などの場合は発行されません。もし納税証明書が必要であれば、交付請求をすることで発行されます。その申請方法は、ネット、窓口、郵送の3つがあります。
窓口の場合は、市税事務所や区役所の出張所、市役所のサービスコーナーや連絡所などです。
窓口で受け取りができない場合は郵送も可能です。その際は送料がかかるので注意しましょう。
車を手放す際に軽自動車税の返還はされない

廃車にした場合、自動車税は残りの期間に応じて月割りで還付されますが、軽自動車税は金額が少額なので残念ながら還付はされません。間違えないようにしましょう。
まとめ
①自動車税は車の排気量によって税額が決まるが、軽自動車の場合は一律の金額となる ②毎年4月1日時点で車を所有している人の住所地に納付書が届き、期限までに納付する ③軽自動車税の税額は、初めて新規検査を受けた時期によって異なり、新規登録から13年以上経過すると増税となる ④軽自動車税の納付は、クレジットカードやキャッシュレス決済などネットからもできる ⑤オンラインで納税が確認できる場合、車検時に納税証明書の提示は不要この記事の画像を見る
